穢れが多く煩悩にまみれたこの世の中、心を惑わすものばかりの火宅から誰が逃れられるというのだろうか。
祇園精舎の鐘の音には諸行無常の響きがあるが、人を愛する者は、恋人との後朝の別れを惜しむがために、時間が経過することを嫌う。
沙羅双樹の花の色は盛者必衰の理(ことわり)を顕すが、その香りを愛でる者は、年月が過ぎて花が散ることを嫌がるが故に、一重に長く続く春を望もうとする。
思い巡れば夢の世、思いを巡らせなくても夢の世、一体どちらが幻なのだろうか。
心のうちに思いのある者は龍華の三会、弥勒菩薩が龍華樹の下で釈迦入滅の後五十六億七千万年過ぎてから衆生を救うために行う法会に臨めるというが、我々凡人は解脱する方法が良く分からない。
惑いから覚めて悟った者は、虎穴や龍の巣にいても、心の平安をきっと得ることができるのだろう。
かくしてこの世を捨てて、伏姫は富山の奥に二年の春と秋を送ったのである。
里見治部大輔義実の娘、伏姫は、親のため、また国のために、言葉の真実を民衆に失わせる訳にはいかないとその身を捨てて、犬の八房に伴われて、山奥の日の落ちるところに隠れてしまった後は、誰とも会うことがなかった。
川岸の埴生の小さい丘の洞に菅で作った筵を敷き、寝床を決めて冬籠りをして、春が去りまた春が来て、朝鳥が友を呼ぶころには、霞が八重にも立ち込めて、滝田での暮らしを懐かしく思う。
弥生のころは里の雛祭り、着飾った少女が二人並んで、今朝摘んできたばかりのその名も懐かしい母子草。
夏の夜には衣服のたもとにまで涼しい松風が吹き、風は髪を乱し、また夕立の雨に洗われて髪が乱れていく。
秋となれば、いろいろな虫の鳴く音とともに、谷の紅葉が織った様に美しく、錦の床がかりそめの宿とは知らずに鹿も鳴く。
山の沢はいつも時雨が降っていて晴れ間が見えず、果てには白雪も積もり、樹木も蔦も春になればまた花を咲かす。
四季の眺望はあるが、侘しく過ごしているので敷物を敷いて外には立たず、後世のためとばかりに、経文を音読し、筆写をしていた。日数も経つうちに、心配ごとにも慣れて、心配ごととしなくなっていった。いつしか浮世のことは忘れ、鳥の音と獣の声さえ、姫は一念探求の友としていた。その心構えこそ見事なものであった。
これより先、八房は伏姫を背に乗せてこの山に入った時、川の幅が広い山間に洞窟があった。石門は以前から彫刻された様であり、松や柏が西北にそびえて壁となっていた。この洞は南に向いていて、中は暗くはないのだ。
犬が入口に留まって前足を折って伏せたので、伏姫はその意を悟って、静かに背中から降りて中に入った。
中を見渡すと、ちぎれた敷物と焼き捨てられた灰がわずかに残っていた。
「世を捨てて、世に捨てられて、この山に山籠もりしたものは、私だけではなかったのだ」
と独り言を言って中に入り、そのまま座ると、犬は姫の傍らに伏せた。
滝田の館を出発した際、法華経八巻と和紙、硯を身から離さず、ここまで持ってきた。この夜は月下で読経し、何とか一日を明かすことができた。
思いがけず手に入れた水晶の数珠は、今なお襟に掛けてある。頼むところは神仏のご加護のみなのだ。
人の言葉を大体聞き分けているはずだが、もし八房が自分を騙して、山の奥に伴ったのだろうか。あるいは、犬が不覚にも情欲を起こして、最後には最初の誓いを忘れてしまったとしたら。
浅ましい心で我が身に近づくのならば、主をあざむく罪は八房にあり。
ただ一刀に刺し殺そう、と思い詰めて、胸騒ぎを鎮めて、ただ密かに護身刀の袋の紐を解いて右手に持ったまま、伏姫は読経を続けた。
姫の心を悟ったのか、八房は近くにも寄らず、ただほれぼれと主人である伏姫の顔を伏せながら眺め、また起きては見ていた。舌を出して時にはよだれを垂らすものの、自分の毛と鼻を舐め、静かに息を吸っていた。
こうして八房は伏姫を守りながら、夜を明かした。
翌朝八房は早起きして谷を下り、木の実とわらびの根を取っては、姫君の元に運ぶのだった。
この様に一日も怠らず、今日、明日と暮らして百日あまり経つほどに、八房はいつしか、姫の読経の声に耳を傾ける様になり、心を澄ましているかの様に見えた。また息を乱して、姫上を見ることもなくなった。
伏姫は思った。
栄花物語の第二十五巻峯(みね)の月に載っている関寺の牛仏の話である。関寺の造営に携わっていた牛が、ある日仏の化身であると夢のお告げがあり、噂を信じた関白藤原道長たちが次々と参拝する様になった。この牛を牛仏と呼んだ逸話を思い出したのだ。
他にも犬が読経の声を喜ぶ話は、古い物語に良く見ることができる。御仏の慈悲は現世の我々をお救い下さる。空を飛ぶ鳥、地を走る獣、草葉の虫、川や海を泳ぐ魚まで、すべてのものを成仏して下さるのだ。
今、この犬が欲を忘れて、読経を聞くことを楽しみ、徐々に仏道修行の友となっていくのは、すべて経文のお力による。しかしながら、私が幼かった時、宿世をお示しなさった役行者のお力こそ大事なものだとありがたく思って、いよいよ読経に励むのだった。
明日には例の数珠を押し揉んで遥かに洲崎の方角に祈念し、ある時は父母のために経文の仏の功徳をほめたたえる詩を書き写して、前の川に流していく。春には花を摘んでは仏に手向け、秋には沈む月に向かって口ずさみ、気の向くまま西の空を西方浄土と思って眺めるのである。
山の恵みである木の実が膝に落ちて変わり映えのしない朝の食事は、心変わりの秋風で飽きてしまう。
しかしたき火は常に燃えていて、ほのかな月の晩を過ごす暖かい夜衣となって、寒さを防ぐ。山は険しいが、伯夷叔斉の兄弟が首陽山でわらびや山菜だけを食べて遂には餓死した様なことはなく、洞に梅が咲くのは遅くはあったが、匈奴に嫁いだ王昭君の様に異国の言葉を学ぶ悲しみはここにはない。
姫は二十歳にならず、容貌は玉の様に美しく、古代中国の巫山の神女が雲となった逸話の夢の面影を伝えていた。小野小町が花にたとえた歌、「花の色は移りにけりな、いたづらにわが身世にふるながめせしまに」の風情を残していた。
滝田の立派な御殿の中で過ごした日々はともかく、今の山籠もり生活が長くなっていくに連れて、衣装は汚れ、破れたところも出てきた。しかし肌は残雪よりも白くなり、黒髪は櫛で整えてはいないが春の花より良い匂いがした。細かった腰はさらにやせて風に吹かれる柳の様である。指先も細くなっていた。
その素性は安房の国主たる里見氏の息女なのだ。
姫の心映えは、横佩大臣(よこはぎのおとど)と呼ばれた右大臣藤原豊成の息女である中将姫(ちゅうじょうひめ)にも等しい。
中将姫は、継母に憎まれ、虐待を受けてしまう。ある日、父がいない時に継母が家臣に中将姫の殺害を命じてしまうが、命乞いをせず亡き母の供養を続け、極楽浄土へ渡るために読経する姫の殺害ができず、部下はこれを逃がしてしまった。父によって見つけられた中将姫は、十六歳の時に淳仁天皇の後宮に入ることを望まれるがこれを辞退し、二上山の当麻寺に入って尼となった。
その後は仏道に励み、仏の助力を得て、当麻曼荼羅を短期間で織ったとされる。その後二十九歳で入滅、阿弥陀如来に導かれ、生きたまま西方極楽浄土に向かったとされる。
伏姫は、字の読み書きは父の才を受けて、道理と正義に賢しく育った。裁縫や管弦は母に習っており、特に音楽の調べは上手だった。この様に愛されるべき乙女が、どうして月下氷人たる仲人に憎まれたのか、犬の八房に伴われて悲しい有様になっていくのか。今後もなお細かく描写していくが、作者の筆は渋り心は痛む。読者にはどうかこの光景をご想像いただきたい。
こうして年は暮れて、翌春に岸辺の草も萌え出て、谷の木の芽も緑を増すころ、ある日伏姫は硯の水を汲もうと外に出た時、近くの水たまりに映った自分の影を見て驚いた。
その姿は身体は人であったが、頭部はまさしく犬になっていたのだ。
思いがけず、堪えきれず、ああっと叫んで後退った。また近づいて水面を覗くと、今度は面影は自分とは違わなかった。先に見た幻こそ自分の心の惑いである、と姫は思った。
幻に驚いた姫は念仏を唱えながら、この日は経文を書写していたが、胸の辺りが急に苦しくなった。次の日も苦しかった。
実はこのころから月のさわりが絶えていた。日数が経つと、腹が張って我慢できなくなりつつあった。
早く死んでしまいたいと思うものの、春は暮れ、夏が過ぎて、とうとう悲しい秋になってしまった。指折り数えてみれば、去年のこの月に滝田の館を出たのだ。自分の病に比べて、ただいたましいのが母上のことだ。泣きながら見送られ、母の面影だけが眼に残っていた。忘れようにも忘れられないのが母君、母上もきっと同じ思いでいるだろう。
娘が滝田に帰れないことを思い続け、悩んで、病み患いなさった母君。父上、弟の義成、皆懐かしく思えてしまう。同じ国、同じ郡にいながら、今は遠ざかってしまった親や弟、家臣たち、山を隔てて面影すら見れない愛する者との別れ、人の命はは蜻蛉の様にはかなく再会はかなわないことだろう。
胸が詰まって、伏姫は岩に額を押し当てて声を押し殺して泣いた。しばらくして眼を拭い、ああ、間違えた、愚痴を吐いてしまったと思った。
恩愛の情を捨て、世俗の執着を断ち切って悟りの道に入ると仏は説きなされた。家族との別れの悲しみも仏道の心構えと思うべきなのだ。
家族を懐かしんで嘆くことは、罪深いことだ。この世の仏よ、どうかお許し下さい。
八房は食べ物を探しに先に出て行って、まだ帰ってこない。私のために食べ物を求めて、見つからない時はなかなか帰って来ない。
私もまた御仏に仕える心を怠らない様にしよう。露に濡れるころ、深山には草の花も稀だったが、探し求めて仏に手向けよう。
独り言を言いながらようやく重い身を起こして、川の流れに沿って林が生い茂ったところで菊の花を手折ろうと、二三町(約220メートル~330メートル)を裾を濡らしながら進んだ。
そこへ乾、西北の八重山の方角から、笛の音がかすかに聞こえてきた。伏姫は耳を澄まして不思議に思った。
この山には木こりも入って来ず、山に住む者たちも住んでいない。自分がここへ来た時から、今日まで人に逢うことはなかった。
思いがけず聞こえてきた笛の音は、草を刈る者でも迷い込んだのだろうか。そうでなければ、魔物か山の精霊が修行の邪魔をして、自分の仏心を試そうとしているに違いない。いずれにしろこの身は世間から捨てられたも同然、何があっても逃げ隠れるべきだ。
しかしまずは笛の音の正体を見ようと、乾の方角へ向かった。
澄んだ笛の音はますます近づいていく。ふと見れば、一人の子供がいた。年のころは十二三と見えた。腰には草を刈る鎌と土を掘る道具を挿し、鞍には二つの籠を掛け、手に笛を持っている。そして子牛に尻を乗せて、林の奥から出て来るのだった。
伏姫を尻目に子牛に掛けたまま、笛を止めなかった。そのまま川の中に子牛を進めて渡ろうとするので、思わず姫はこう言った。
【草花を探して伏姫、神童に遇う】

ああ、伏姫の一張羅が酷く傷んでおります。やっぱり替えの服が必要ですよ、姫様~
「これこれ、そなたはどちらの里の子か。滅多に人の来ないこの山奥に一人で入って来るのも大変なのに、山道を知っているの様に見える。そなたは」
伏姫は一旦言葉を切って、
「私を知っているか」
と尋ねると、童子はにっこりと笑って、静かに笛を襟に差し、
「知らない訳がありませんよ。姫様は僕を知らないでしょう。それでは不公平ですから、申し上げましょう」
なかなか大人びた口を利く童子である。
「そもそもこの山は、木こり、狩人はもちろんのこと、旅のものですら通ることはほとんどありません。父君の里見義実殿が姫が他人に見られることを恥とお思いになって、去年からこの山に人の入ることを禁止されたのです。これで人の足が途絶えました。でも母君は姫のことを心配になられて、ご無事かどうか調べるために侍女を何人か遣わしたのです。でも尼崎十郎殿が殿の仰せを受けて、富山に入った時に川で溺れて亡くなってしまったのです。それ以来皆恐れて、川を渡れず、使いの者たちは岸から帰ってしまうのです、だから姫の安否は誰も知らないのですよ。これも運命であり、またご時世ですね」
伏姫は黙って聞いていた。
「僕の身の上をそろそろ申し上げましょう。牛や馬の世話のために草を刈る者ではありません。僕の師匠はこの山の麓におり、またある時は洲崎におります。年齢は何百歳なるのか、もはや分かりません。常に人の病を治療し、また占いをして生活しているのです。もし薬を与える時は、死から救い、寿命を保ち、万病を治すのですよ。また占い用の筮竹を手に取った時は未然に運命を察知して、本人も忘れている様な過去を明らかにするのです。師匠の占いは必ず当たります」
童子の言い分は本当だろうかと伏姫は首を傾げた。
「今日、僕は師匠の言いつけで薬を採るために来たのです。この山は今は人が通ってはいけないのですが、近々元の様に出入りが許されるでしょう。師匠はこれを悟って薬を採ることをお命じになったのです」
伏姫はため息を吐いて、
「両親の慈悲は月日と共にありがたく照らしてくれる。私は身を汚さず清く修行をしていることをご存じないから、その様にお取り計らったのだろう。しかし私のために尼崎輝武殿を溺死させ、木こりたちの生活の妨げになるだけではなく、旅行く者の足さえ止めてしまうとは、罪深いこと。どうかお許し下さい」
伏姫は涙ぐんだ。
しばらくしてから、伏姫は気になっていたことを童子に聞いてみた。
「そなたは名医に仕えているというのなら、人の病を診ることも大人の様に多いのでしょう。試しに聞いてみたいことがあります。私はこの春ごろから絶えて月のさわりがなく、胸が苦しくて煩わしい上に、月々に身体が重くなるのです。これは何という病気か分かりますか」
と聞けば、童子は微笑んだ。
「婦人の月経が滞って、一月二月、吐き気がして酸っぱいものを好む様になる、俗にこれを悪阻と言います。三四か月後、腹はすでに大きくなり、五か月になると子供がやや動くことがあるのです。女性なら皆ご存じで、医師に聞くまでもありません」
あまりのことに伏姫は驚いて何も言えない。
「あなた様はすでにご懐妊されており、五六か月になっています。何のお疑いがありますか」
伏姫は思わず、
「ませたことを言う子供だこと、私に夫はおりません。去年のこの月、この山に入った日から他に人を見ていません。一念込めて仏道修行と読経の他に何もしていないのです。どうして身籠るというのです、おかしなことを言うのですね」
堪えかねて、ほほと笑うしかなかった。
しかし童子は姫を見て冷たく笑った。
「あなた様に夫はいるではありませんか、すでに親から許された八房は何者なんです」
と問い詰めると、伏姫は顔つきを変えて、
「そなたは物ごとを知っている様に見えるが、実は何も知らない。父も母も涙を飲んで、飼い犬と世にも浅ましいと思われるかもしれないが、私は共に深山で月日を送っています。しかしお経のご加護によって、幸いにも身を穢されることがなく、八房もまたお経を聞くことを喜んでいます。例え証拠はなくても、私の身は清らかで潔白です。神様こそご存じで、なぜ八房に孕まされるとは、聞くも愚かで汚らわしい。私は変な子供に話し掛けてしまったのだろう」
馬鹿にされて悔しいと伏姫は腹を立てて、泣いた。
童子はますます笑い、
「僕には分かりますよ、良く分かるのです。姫様こそ一を知ってはいますが、二を知らないのです。それでは迷いを解いて差し上げましょう。すべてのものは互いに感じ合い、響き合うのですが、その神髄は平凡な者には分かりゃしません」
伏姫は童子の言葉を聞くしかない。
「例えば、石と金を叩くと火を起こせます。また檜などは同じ木が擦れあうことで火が起きますよ。鳩の糞は、長い間たくさん積まれていると勝手に燃え出します。こういったことは普通の道理や常識では説明のできない、不思議なことなんです」
童子は尚も説明する。
「物は陰と陽が互いに感じ合わず、響き合わなければ、子を産みません。ただ草木は感情がなく、松と竹には雌花と雄花があるけれども交わったりはしませんが、良く子供を実らせます。他にも鶴は千歳になっても交わりはしませんが、お互いに見つめ合って子を孕むのですよ」
話はまだまだ続くのである。
「秋に悲しむ男性は妻を娶らずに魂を通わせて、春の華やぐ女性は嫁ぐことなく孕んだりするのですよ。聞けば古代中国の楚の国のお妃様は、いつも鉄の柱にもたれかかることを好んでいたので、とうとう鉄の玉を産んだそうです。それを干将と莫邪(かんしょうとばくや)が剣にしたんですって。我が国でも」
今度は本邦での例を説明し始めた。
「源平合戦の時代、近江にいた身分の低い女が人にお腹を押してもらうことを喜んでいたら、その挙句に生の腕を産んだという話もありますよ。手孕村という名前も残っています」
もはや得意気な口調なのである。
「みーんなこれ、すべてのものは互いに感じ合い、響き合った結果なんです。目の前のことだけ見ていても駄目なんです。あなた様が妊娠なさったのも、この類いです、何をお疑いになるのです。姫様は確かに乙女のままですし、八房もまた今はその欲をなくしています。でも姫様は、お身体もお心もすでに彼に許して、この山中に伴われて、犬もまた姫様を得て、自分の妻と思っています。彼はあなた様を愛するが故に、姫様の読経を聞くことを喜びました。姫様もまた、彼が帰依したことを自分のことの様に思われていたでしょう。この感情はすでに感じ合い、響き合っているのです。身体を重ねなくても、身重になることがあるんですよ。僕が見るところ、胎内にいるのは八人の、そう八子ですね。しかし感じるところ、子供は実体ではなく、言わば虚のもの同士が胎内で巡り合って生まれるので、子供達には形がありません。形を作らずしてここに生まれ、生まれて後にまた別の形に生まれるのです」
伏姫は身体を震わせた。
「これはすべて宿命のせいなんです、善行の報いなのです。原因は何でしょうか。例えば八房の前身は、その性が歪んだ女の人です。父君の里見義実殿を恨むことがあって、その恨みの残った魂が一匹の犬となり、姫様親子に祟るのです。その結果はどうでしょうか。八房は姫様を得ましたが、とうとう犯すことなく、法華経読経の功徳によって、ようやくその宿怨を晴らしました。更に悟りを得ようと、今、八つの子供を残した訳なんです。八は即ち八房の八を意味しており、また法華経の巻の数でもあります」
平凡な人はいっぱいいるけれども、優れた人にはなかなか巡り合えないでしょう、と童子は言い、更に、その子たちは皆、智勇に秀でて、その忠信節操は里見の家を助けて、関八州に里見の名を輝かすでしょうと予言めいたことを口走るのである。
「すべて伏姫様の賜物です。誰がそんな子供たちの母を愚かなどと言いますでしょうか。これが善い報いの結果なんです。そもそも禍福はあざなえる縄の如し、って言いますでしょ。良いことも悪いことも公平にやって来るんですよ。今の災いを見て、誰が後の幸せを知ることができますか。世の中の悪口というものは愛憎から起きますし、物の汚れは潔白だからこそ分かるのです。ですから誹謗中傷も嫌がることなんかないのですし、恥辱もただ良く忍んで堪えた方が良いのです。秘密はかえって世間に知られやすいというものです。それに隠そうとしても必ず現れてしまいますからね、これもまた自然の摂理です」
大人びた口を利く童子である。
「犬は六十日、人は十月で出産します」
その声に伏姫は現実に引き戻された。
「人間と犬に差はありますが、合わせて考えますと、姫様は妊娠六か月、今月その子供たちは生まれます。お産の時には思いがけず、親御さんと旦那さんにお会いになれますよ。えーと、ここから先のことはまだ定まっておりません」
童子は笑ってみせた。
「ああいけない。細かく喋ってしまうと、天の秘密を洩らしてしまいます。また誰か詳しい人がいて、その子たちの身上を話してくれるかもしれませんよ、今はここまでにしておきましょう」
と童子は牛の背中を叩いた。
「秋の日は短いというのに、長話をしてしまっていけませんねえ。さぞかし師匠がお待ちになっていることでしょう、急ぐとしましょう」
そう言って童子は牛の鼻を引いて、元の方向へ返して進むのだった。
伏姫が何か話す前に、童子と牛は川に入り、あっという間に影は霧に隠れていく。かき消す様に姿が見えなくなり、行方知れずになってしまった。
(続く……かも)










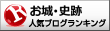

















火打石なんて昔もあったと思うのですが、これも不思議なことだったんでしょうか?
分からないですけど(笑)
と、話の展開はわかりましたが、ぜんぜん納得できないであります。
見つめあうだけで、、、おおごとになりますぞ!
ただ
見ているだけで満足♪
という気持ちはわかります。
今回は、考えさせられます。
(またコメントする…かも)