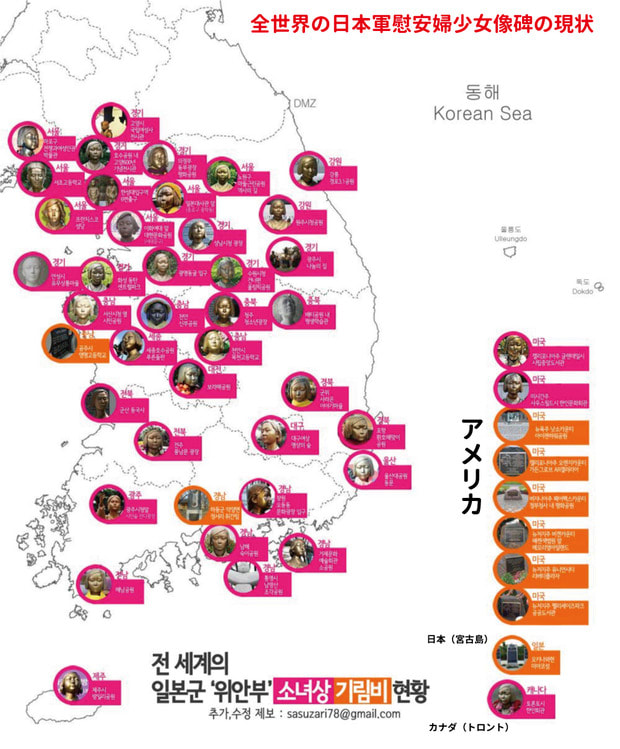pop***** | たった今
被害者が特定できない出来事に何の意味があるんだろうね
はっきり言っておくよ
どんな事件も加害者だけでは成り立たない
これがセクハラならば被害者がいるはず
で、どこにその被害者はいるのですか?
0
0
返信0
lio***** | たった今
マスコミは人間のクズがなるもんだ。
人の不幸で飯を食っている輩がグダグダぬかすな。
0
0
返信0
chi***** | たった今
ハニートラップを仕掛けて、失敗したら録音データを編集して、セクハラだと訴えるか。
特ダネのためにすり減った私。記者たちの #MeToo
4/21(土) 16:06配信 BuzzFeed Japan
特ダネのためにすり減った私。記者たちの #MeToo
財務省事務次官セクハラ問題でテレビ朝日の会見に集まった記者やカメラマン(4月19日未明)
テレビ朝日が、女性社員がセクハラを受けていたと公表した会見。情報がほしい、もっと近づきたいという思惑が負い目となり、取材活動を通して記者が受けてきたセクハラは表面化してきませんでした。でも、変えなければ。6人の記者が、実態を話してくれました。【BuzzFeed Japan / 小林明子、伊吹早織、貫洞欣寛、籏智広太】
こんな処世術、なくなるといいなあ
凶器に使われた刃物の柄は、どんな状態だったのか。
絶対に他社に特ダネを抜かれたくない。そのために、女性は深夜のホテル街にいた。ほどよく酔っ払った警察幹部の男性と、ホテルに入る入らないで腕を引っ張り合い、押し問答をしていた。

「こんなネタのために、私、何やってるんだろう...」
財務省の福田淳一事務次官から女性社員がセクハラを受けたと、4月19日未明にテレビ朝日が記者会見で発表した。ある民放局の女性記者Aさんは、ふたをしていたはずの数年前の体験が脳裏に蘇り、会見を冷静に見られなくなった。
過去と向き合い、後輩記者たちが自分と同じ目に遭わないよう、報道の現場を変えたい。そんな思いから、BuzzFeed Newsに経験を話してくれた。
「見えない女子枠」があった
当時、配属されたのは、社内でも花形である警視庁記者クラブ。配属後の「1カ月ルール」というものがあり、1カ月以内に特ダネが取れなければ「飛ばされる」と聞いていた。
担当チームで、女性記者は1人だけ。Aさんは女性記者から引き継ぎを受け、女性記者に引き継いだ。そこにはきっと「見えない女子枠」があったのだ。
Aさんは、事件取材をしたいわけでも、特ダネを取りたいわけでもなかった。テレビ局に入社したのは、ドキュメンタリーを制作したかったから。事件取材で頑張って実績を出せば、次のチャンスがもらえるはずだと信じていた。
実際、独自ネタをとったら、それを元に番組の企画枠を担当させてもらえた。目の前にぶら下げられた小さなごほうびが、Aさんをプライベートがほとんどない取材活動に駆り立てていった。
「もうレース感覚ですね。その日その日の運動会で、1位を取ろうと必死でした」
同時に、もう一人の自分が常にささやいていた。
「このレースのルールは、本当に公正なの?」
セクハラを笑って流せる娘キャラ
特ダネをとるためには、他社の記者がいないところで、警察幹部と2人きりで話す機会をつくらなければならなかった。
警察幹部を自社のハイヤーに乗せ、自宅まで送り届ける間、車内の後部座席で捜査情報を聞き出すことが多かった。普通に話をしていたのに、暗がりにさしかかった途端、手を握ろうとしたり胸を触ろうとしたりする人もいた。運転手に昼食をおごり、不審に感じたら急に道を曲がったりカーラジオの音量を大きくしたりして雰囲気を変えてほしい、と頼んだ。
Aさんは、特ダネをとるためにどこまでするか、自分なりのルールを決めていた。
・男性と2人で話すのは、OK。
・2人きりでゴルフに行くのは、OK。
・2人きりで飲みに行くのは、OK。
・飲食店の個室に入るのも、OK。
・手を握られるのは、NG。
・キスをされるのは、NG。
・ホテルに行くのも、NG。
NGラインに入りそうになったときは、「笑って流せるキャラ」を演じてかわしてきた。まさに、元日経新聞記者でジャーナリストの中野円佳さんが名付けた「コイツには何言ってもいい系女子」。下ネタやセクハラも冗談にして受け流すキャラのことだ。
万一、相手を不快にさせて、先輩記者から脈々と受け継いできた取材先との関係、つまりネタのパイプラインを絶つようなことは、あってはならなかった。
「最初は、とにかく特ダネがほしくて、どのラインまで許容するかを決める余裕すらありませんでした。女としてではなく、男キャラや娘キャラとして接すると、身を守りながらもガンガンネタがとれることがわかってきて、ここまでならOKというラインが見えてきました」
「ただ、それまでの自分とはまったく違うキャラに変わらなきゃと真剣に考えたのは、記者クラブの飲み会に出たことがきっかけです」
きれいごとではない現実
その飲み会でAさんは、思い出すだけで吐き気がするような酷い集団セクハラを、先輩や同僚から受けた。女性記者だけでなく若手の男性記者もいじられ、笑いながら耐えていた。このレベルのセクハラを笑って乗り切れないと、この世界にはいられないんだ。そう悟った。
「なぜ私はそこで、この世界で生き延びなきゃいけない、と信じ込んでいたんでしょうね...。就職を喜んでくれた親の顔や、ドキュメンタリーを撮りたいという夢、いろいろなことが頭に浮かんでいました。記者になってまだ何も成し遂げていないのに負けてたまるか! という気持ちも大きかったんだと思います」
2年半後。異動する自分の後任となる女性記者を同伴した飲み会で、Aさんは服を脱がされた男性記者を笑い、ひたすら盛り上げ役に徹していた。もうすっかり「この世界」に染まっていた。ふと気づくと、後任の女性が店から姿を消していた。
「いたたまれなくなったんでしょうね。今ならわかります。でもそのときに私が思ったのは『ヤバい。早く戻ってきてよ。相手を怒らせたらどうするつもりなの』でした。今となっては顔から火が出るほど恥ずかしく、申し訳ない気持ちでいっぱいです」
テレビ朝日が、女性社員がセクハラを受けていたと公表した会見は、Aさんに当時の不快感と罪悪感の両方を思い出させるものだった。生き延びるために、セクハラの被害者にも加害者にもなった。どんな場面であろうとセクハラは許されない、というのは正論だが、現実はきれいごとでは済まなかった。
「記者にも下心がある」
全国紙で警察を担当している20代の女性記者Bさんは、取材先との微妙な距離の取り方に、常に気をつけているという。
「記者としては、ネタがほしいという下心があって取材先に近づいています。性的な関係になりたいわけじゃないけど、仲良くなって情報を得たいという微妙な思惑がある。だから自衛するしかないと思うんです」
スカートは絶対に履かないし、胸元があいた服も絶対に着ない。お酒を飲む量にも気をつけている。面倒なことになりそうだったら、トイレに駆け込んで先輩に『電話してもらえますか』と連絡し、呼び出されたことにして消える。
記者の仕事は、取材とプライベートの線引きが難しい。だからこそ、いざというときはネタ元を切ってでも、自分で自分の身を守るしかないと思っている。
女性記者は約2割
日本新聞協会の2017年4月の調査によると、加盟している新聞・通信社の記者数は1万9327人。そのうち女性記者は3741人で、全体の19.4%だ。管理職となると、女性の割合はますます少ない。
「この業界はどこまでいっても男社会で、上司も取材先も男性です」
10年ほど前、取材先の男性からセクハラを受けたという全国紙の女性記者Cさんは言う。セクハラ行為だけでなく、被害を新聞社の上司に訴えたときの対応に、深く傷ついた。
セクハラの加害者は、担当する行政機関の幹部だった。態度は常に紳士的で、いつも妻の話をする「愛妻家」。娘は自分と同い年だとも聞いていた。
この幹部と別の記者と3人で飲むはずの席で、もうひとりの記者が急に来られなくなり、2人きりになった。「珍しいビールがある。二次会はうちで」と自宅に誘われた。
家族がいると思って幹部宅に向かうと、家族は旅行中で無人だった。突然、幹部に後ろから羽交い締めにされた。突き飛ばしてなんとか逃れた。自宅に戻りドアを閉めた途端、涙が溢れた。
「その気にさせたお前が悪い」
翌日、職場の上司に相談した。「とにかくこの話は誰にも言うな。絶対に週刊誌にも言うな」。慰めるどころか、高圧的な態度だった。考えてもいなかった週刊誌へのリークの話までされて、呆然とした。
後日、上司から「幹部と直接会って、話をつけてきた。『両想いだと思っていた。勘違いだとすると申し訳ない』と頭を下げてきた」と伝えられた。具体的に何をどう話をつけたのか、それ以上の説明はなかった。
次の春、この幹部は定年退職した。「無事退職できたのはあなたのおかげです」というメールを送ってきた。自分の行動に罪の意識があり、もしCさんが告発していたら懲戒処分は免れなかったということが分かっていたのだ。
合わせてCさんも転勤になった。職場の送別会の二次会で、上司は冗談めかして言ってきた。
「その気にさせたお前が悪い。そういうところは気をつけろ」
「上司に言ってもダメだったのだから」と社内で訴えることも諦め、すべてを心の中に封じ込めてきたが、今でも思い出すと、悔しさに体が震えることがある。
元毎日新聞記者の上谷さくら弁護士によると、セクハラの裁判では、加害者の責任はもとより、会社の対応のまずさが問われることが多い。使用者責任や安全配慮義務違反として、上司の対応などが厳しく判断される。
それはつまり、報道現場でセクハラが起こる構造的な背景が問われているということだ。
地方紙が自治体と全面対決
BuzzFeed Newsは現在、大手新聞社、放送局、通信社、BuzzFeed Japanを含めたネットメディアの計15社に、社員がセクハラを受けた場合の対応や、性犯罪の報道指針についてアンケート調査を依頼している。回答をまとめ、記事化する予定だ。
セクハラの対応として注目されたのは、2017年12月、岩手県の地方紙「岩手日報」の報道だ。自社の女性記者が岩泉町長からわいせつな行為をされた、と自ら報じた。
その日の紙面では「岩手日報社は問題発生直後から、町長に対し厳重に抗議し、代理人を通して事実関係を認めるとともに謝罪するよう求めている」とも記している。地元に密着した地方紙でありながら、ひとりの記者を守るために町のトップと全面対決の姿勢を表明した。町長はその後、辞職した。
テレビ朝日は4月19日の会見で、セクハラ発言をされた女性社員が「セクハラの事実を報じるべきではないか」と相談したが、上司が「本人が特定され、二次被害が予想される」との理由で報道しなかったという一連の対応を明らかにした。同日、財務省に抗議文を提出している。
記者の #MeToo を会社は守れるか
セクハラを許さない組織をつくるために、労働組合による実態調査を提案するなど社内で問題提起を始めたのは、20代の女性記者、Dさんだ。
「警察官や政治家が悪びれずに女性記者に対してセクハラ発言ができるのは、長々と続いてきた環境、習慣によるもので、それを再生産してきたのはマスコミ業界だと思います」
テレ朝の女性社員は、セクハラを自社で報じることを止められたため、週刊新潮に連絡を取り、告発記事が掲載された。記者の#MeToo だ。テレ朝は会見で対応のまずさを認め、「女性社員の人権を徹底的に守っていく」と述べた。
#MeToo と声を上げることは、被害者に負担がかかることだ。実際、声を上げたことによる二次被害に苦しむ人もいる。それでもDさんは「被害者が声を上げ、追及することが、今の状況を変える一番効果的な方法だと思います」と訴える。
「悲しいけれど、ハラスメントをしたら社会的制裁を受けるということを痛感してもらうしかないからです。そういう意味で、個々の記者対加害者ではなく、所属している組織が記者を守っていく姿勢が必要です」
一つひとつのセクハラが記者をすり減らす
記者へのセクハラは、警察や政治家など、権力と情報を持った取材先によるものだけではない。事件取材で現場周辺の住民に話を聞いていたときに、名刺を渡しただけの相手から執拗に連絡が来たり、災害取材で性的な言葉を投げかけられたりすることもある。社内や、同業他社の記者たちが集まる記者クラブでも起こりうる。
Dさんは続ける。
「一つひとつ声を上げていったらキリがない。費用対効果が悪すぎます。その場で受け流せば済んでしまうセクハラがいっぱいある。でもそういうものが、少しずつ自分たちをすり減らしているんです」
声を上げづらい背景には、そのリスクとコスト以外に、女性記者ならではの”負い目”もあるという。
「実際、若い女性記者を相手にするとガードが緩くなる取材先がいるのも確かです。その経験って、女性記者はみんな少なからずある。だから『女を使ったことは一度もありません』と言えなくなっちゃうというか、変な負い目になってもいるんですよね」
男性記者と対等に戦いたいがために、あえて被害を口にしない女性記者もいる。
「でもそれってセクハラの免罪符にはならないですよね。改めるべきは女性のほうではなくて、加害するほう。Twitterに『セクハラされてでもネタを取ってこいと言われるとしても、相手がセクハラしなければ、セクハラされずにネタを取ってこれるはずだ』と投稿している人がいて、その通りだと思いました」
弁護士の上谷さんは、こうも指摘する。
「どんなにセクハラやパワハラをされようが、記者は取材先との関係構築のため、明日も明後日も取材に行かなければならない。取材先は、ハラスメントをしても記者が何度も来るから、自分のやっていることは嫌がられていないし許されている、と本気で思っていることがあります」
男性記者に替えれば解決するのか
全国紙の20代の女性記者Eさんは、警察幹部から無理やりキスをされたことがある。耐えられないと感じ、すぐに会社の上司に報告した。上司もすぐに動き、女性を担当から外して、代わりに男性記者をあてたという。
「上司が理解があったので担当を外してもらいました。セクハラを受けても続けなければいけなかったテレビ朝日の彼女は、精神的に相当キツかったんじゃないでしょうか」
30代の全国紙記者Fさんは、度重なるセクハラに会社が対応してくれたと感謝する一方で、過度な警戒心を抱かれることの息苦しさも感じている。
取材先を信頼して、フェアな関係を築いてきたつもりだった。それなのに「誤解を与えるから」と、先輩の男性記者と同じように夜回りをさせてくれない取材先がいたことに、もどかしさを覚えた。
「信頼関係ではなく性別で区切られてしまうのは、たとえ配慮であったとしても悲しくなります。性別関係なく、記者として見てもらいたいだけなのに…」
取材活動の制限がもたらすこと
4月19日発売の週刊新潮によると、麻生太郎財務大臣は「セクハラされるのが嫌なら、男性記者に替えればいい」という趣旨の発言をしたという。
セクハラを防ごうとすると、このような議論になりがちだ。
女性記者を取材先と1対1で会わせない、特ダネをとるような取材はさせない、そもそも配属しないーーそれは「スカート姿で夜道を歩かない」と同様、女性記者の活動の幅を狭めることにつながる。同時に、加害者となりうる側は何も変わらないでいいということになる。
取材先と信頼関係を築くために絶妙なバランスで距離を縮めようと努力している記者に「嫌なら2人きりにならなければいい」「呼び出されても行かなければいい」といった言葉を投げかけるのは、記者倫理を捨てろと言っているのと同じだ。そもそも、2人きりになったからといって、セクハラが起きても仕方がないと言えるはずがない。
それに、ネタ元となる取材相手が女性のこともあれば、男性記者が被害に遭うこともある。性別に関する被害に矮小化していては、抜本的な解決にはならない。
冒頭の民放局の女性記者Aさんは、多くの警察幹部と話す中で、社会正義を目指すスタンスなどに共感することが多かった。記者と警察官、職種は違うとはいえ「熱くて純粋で、青臭い気持ち」で通じ合える人にたくさん出会えた。その信頼関係は、宝だ。
「取材相手と記者は、そうした漠然とした思いを、事件や事故といったネタをフックにして共有しているのではないでしょうか。逆に言うと、ネタをとるための取材活動は、よりよい社会に向かって一歩ずつ進んでいると信じて、やり続けることだと思うんです」
取材は、取材相手と記者との共同作業だ。そこに必要なのは、目先だけの単純な規制ではない。互いの立場を尊重した、対等な関係性だろう。
-------
BuzzFeed Japanはこれまでも、性暴力に関する国内外の記事を多く発信してきました。Twitterのハッシュタグで「#metoo(私も)」と名乗りをあげる当事者の動きに賛同します。性暴力に関する記事を「#metoo」のバッジをつけて発信し、必要な情報を提供し、ともに考え、つながりをサポートします。
新規記事・過去記事はこちらにまとめています。
https://www.buzzfeed.com/jp/metoojp
ご意見、情報提供はこちらまで。 japan-metoo@buzzfeed.com

fum***** | 4時間前
一番マスコミがセクハラパワハラの多い職場だろう。
3150
91
返信28
vir***** | 4時間前
セクハラは良くない。
これは当たり前。
ただ、くノ一取材はどうなのか?
一歩間違えば、ハニートラップ。
3515
252
返信73
mod***** | 4時間前
これはいずめメディアに大きなブーメランになるよ。女子アナという言葉も差別だし、テレビやラジオで日々セクハラは起きてる。ケンコバがAKBの子に生ゴミを出す出さないとかでエロいワードを言わそうとする企画とか三村は乳を揉んでたこともあるし。
2266
104
返信23
na***** | 3時間前
これは取材方法に問題があるということですよね?
女性を利用してセクハラをさせてる感はある。
1058
51
返信9
jdu***** | 4時間前
ハニートラップとセクハラは紙一重?
記事が事実とすれば、思わせ振りの女性記者や会社にも問題があると思います。
1116
78
返信11
お大事さん | 3時間前
セクハラはアウト。しかし、女性記者が女性アナウンサー以上のハニートラップをかけて、特ダネや玉の輿など、会社と一緒に画策するのもアウト。相撲協会やサッカー協会やレスリング協会と内容は変わらないですね。お互いの利権構造を変えないと。ジャーナリズムとは、何なのでしょうかね。
962
37
返信1
cur***** | 3時間前
女性議員に若い男あてがう事もあるし、やっぱり取材側の問題が大きいよ。本人はそのつもり無くても、そもそも配属する方は明らかにそこ狙って配属してる。同性同士で取材するのが一番だよ。
935
35
返信12
lin***** | 4時間前
もう、同性にしか取材しないようにしたらいいんじゃない無いですかね。
現在のように、高齢化が進み、国が衰退している中で、大局的な視点での対応が十分に話されないのは、将来必ず大きな打撃になります。
780
53
返信9
土風鈍介 | 3時間前
生々しい話だが、この記事の結論
「取材は、取材相手と記者との共同作業だ。そこに必要なのは、目先だけの単純な規制ではない。互いの立場を尊重した、対等な関係性だろう。」
にはもっともだと思う反面、違和感を覚える。
訴えられるべき相手は、記者が所属する業界だろう。
この記事が本当なら、福田次官はむしろ被害者に見えてくる。
取材されるような社会的地位が高い男は、大体においてテストステロン値が高い傾向にあり、「女」を出す記者にに対してはオス本能が出るのは自然現象。
だからと言ってそれが良いとは言わないが、少なくとも「女」を出す取材は「しない」「させない」ことが必要なのではないか。
786
73
返信6
okn***** | 3時間前
セクハラはよくないが、若い女を武器にして仕事を得てることも確か
取材対象が男性ということも大きい
例えば小池百合子が取材対象なら若いイケメン男性なら口が軽くなるかというとどうだろうか?
kzm***** | 1分前
小娘じゃあるまいし。リスク承知での取材だろう。それが被害者?なんでも有りの取材なら、これからは取材無視で良いんじゃない。
0
0
返信0
人生”番外地 | 1分前
何でセクハラ情報を雑誌社に持ち込むのか。警察か弁護士に訴えろ~。
0
0
返信0
vbn***** | 1分前
誘導尋問のような質問取材と言葉尻を切り取った報道
いったい日本のマスコミは正義を報道したいのか/日本を潰したいのか
日本はどこへ向かうのか、心配だ