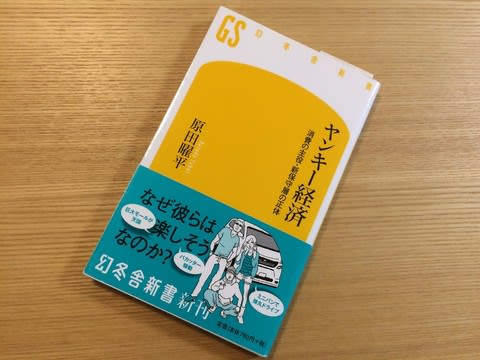 自分の悪いクセで、流行の本をとりあえず購入はしてみるものの、何せ全体的に読書スピードが遅いので結局本棚の肥やしになってしまい、挙げ句数年後にやっと手に取り読み始めるというパターンが少なからず。一時流行語にさえなった感のある本書もそのひとつです(しかも読み終わったのも1年以上前です)。数年前、この本から飛び出した「マイルドヤンキー」という言葉だけが独り歩きした結果、この本には何となくヤンキーの皆さんをdisるというか、小ばかにしたような漠然としたイメージを持っていたので、まさに「ヤンキー」がわんさかいた埼玉県北部で育った自分としても正直あまりよい印象は持っていませんでした。 自分の悪いクセで、流行の本をとりあえず購入はしてみるものの、何せ全体的に読書スピードが遅いので結局本棚の肥やしになってしまい、挙げ句数年後にやっと手に取り読み始めるというパターンが少なからず。一時流行語にさえなった感のある本書もそのひとつです(しかも読み終わったのも1年以上前です)。数年前、この本から飛び出した「マイルドヤンキー」という言葉だけが独り歩きした結果、この本には何となくヤンキーの皆さんをdisるというか、小ばかにしたような漠然としたイメージを持っていたので、まさに「ヤンキー」がわんさかいた埼玉県北部で育った自分としても正直あまりよい印象は持っていませんでした。
ただ、あらためてページをぱらぱらとめくって読んでみるとそのようなことはなくて、著者の原田燿平さん(日テレ「ZIP!」に出てくる(た?)謎のスキンヘッドのおじさん、と言った方がわかりやすい?)が大手広告代理店・博報堂の社員であること、また副題からもわかるとおり、本書はマイルドヤンキーを小ばかにするどころか、大真面目にマーケティングの対象として、一般的な若者に比べるとやや特徴的なライフスタイル、行動原理及び消費に対する考え方を調査・分析し、「顧客」としてどのようにアプローチするべきかを提案するものです。もちろん、本を売るために話題を呼ぼうと「マイルドヤンキー」というキャッチ―な言葉で釣った部分があるにせよ、純粋にマーケティングにあたっての参考書と理解してよいのではないでしょうか。
さて、本書ではその「マイルドヤンキー」とされた皆さん135名にインタビューを行い分析を行っています。本書で言う「マイルドヤンキー」というのは、かつてのヤンキーに比して文字通りやさしくマイルドになった存在です。具体的にどうマイルドなのかと言うと、かつてのヤンキーに比べると、犯罪に手を染める割合も減り、社会や大人への反抗心をむき出しにする者もめったにいなくなった、といった点。そして、一般的な若者層、あるいは「意識高い系」と呼ばれる若者たちが、よく「若者の○○離れ」と言われるとおり(その手の報道をそのまま受け入れるかどうかは大いに議論はありそうですが)、「モノ」を買わなくなっている。そういう中にあって、このマイルドヤンキー層はクルマ、タバコ、ショッピングモールでの買い物などにより消費をしているなどの点で一般的な若者とは異なるようです。そうした皆さんを「かつての『ヤンキー』が変容した形としての新保守層」として、大真面目に研究対象としています。
この「マイルドヤンキー」は大きくふたつのタイプに分かれると著者は言います。ひとつは(1)「残存ヤンキー」で、要は昔のままの姿で今も残っているヤンキーで、そういう意味では絶滅危惧種とも言えるカテゴリ。ただ、それでもやはり昔に比べれば、随分とマイルドな人々が多く、見た目もかなりおとなしく、むしろEXILEのようにオシャレになっていると指摘しています。
もうひとつが(2)「地元族」、昔であればヤンキーカテゴリだった人も一部いるものの、見た目は全くヤンキーではない。人間関係が狭く、地元友達とつるむ。地元のファミレスや居酒屋、仲間の家でダラダラ過ごすのが好き。一方で多少のヤンキー性には憧れがある、といった点で特徴づけられます(地元志向は(1)も同様)。前述のとおり、若者のパチンコ離れ、やたばこ離れなどが叫ばれる中、パチンコやスロットをやっている人や喫煙者が多く、お酒や車やバイクに興味を残っている人も多いと言います。
こうしたことをもって、そもそも全体的に人口が急激に減少しつつある中で、消費意欲が減っていると言われる「さとり世代」(こういうレッテル貼りも個人的にはあまり好きになれません)の若者たちの中で、このマイルドヤンキー層は、少なくとも同世代の若者たちに比べると企業にとっては実に優良な消費者である、と整理されています。
そんな彼らの特徴として本書で指摘されている内容をあらためて箇条書きに落としてみると、
◆何があっても地元を離れたくない
⇒地元友達と、昔のまま居心地のよい生活をずっとキープし続けたい。ライフステージが変わったからと言って、ライフスタイルや人間関係を変えるのは面倒。地方に限った現象ではなく都内でもこうした例あり。激安居酒屋、ROUND1などデフレカルチャーの象徴のようなお店に出入り。地元に一軒家を持って初めて一人前。
◆現状への高い満足度(上昇志向のなさと表裏一体)
⇒大きな夢があるわけではないが、かといって将来に絶望しているわけでもない。このまま地元で仲間と過ごす生活が続くことを願っている(ただし、「失われた20年」と言われる我が国の経済情勢を踏まえれば、現状維持だけでも御の字と言えるか)。
◆メンツや見栄という感覚をわずかに残しており、それが消費行動にも反映される
⇒ブランド物を好む等。
◆地元で仲間と遊ぶにあたり自動車は必須アイテム。
⇒電車には乗らず自動車で移動。その自動車の車種については、ホスピタリティ重視ゆえ大きければ大きいほどよい、セダンやスポーツカーではなくミニバンを選択。
◆EXILEが鉄板の人気(仲間・家族主義、オラオラ系ファッションに共感)。その他、西野カナ、浜崎あゆみ、安室奈美恵など。
◆消費の選択にあたっては、地元の仲間のお墨付きを重視。
◆ITへの関心が全体的に低い。
⇒連絡手段としてのSNSのためにスマホにはするものの使いこなしていない。そもそも知的好奇心には乏しく、選択肢が多いことは苦痛。調べてまで買わない。閉じた人間関係がいわゆる「バカッター」現象を引き起こしている?
◆旅行は「パッケージ化された日常」、「息抜き」を望む
⇒決して刺激や冒険を望むものではなく、知っているところで仲間と親睦を深めて息抜きしたい。旅行にあたり事前に調べたりせず、知っているもののなかから選ぼうとする。TDR(ディズニーリゾート)への圧倒的ともいえる支持。
といったところでしょうか。
ポイントとも言える消費行動については、総じてかつてのような「今の自分を変革し高いステージに上るための消費」ではなく「現状維持を続けるための消費」としています。ただ、本書は「マイルドヤンキー」と著者たちが見做した135名にインタビューを行い、その内容を根拠に導かれた「仮説」くらいに理解しておいた方がよいのでしょう。というのも、全体的に、因果関係について「のだと思います」といった記述が割りと目立つこと、また、個人的には、最初から「マイルドヤンキー的な消費者層がいる」という前提で論理が組み立てられているのではないか、という疑念が最後まで消えることがなかったからです(加えて、そもそも「数年前の本」という前提でこの書評もお読みいただければ幸いです)。
| Trackback ( 0 )
|
|