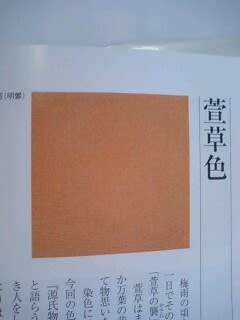

『紅の黄ばみたる気添ひたる袴、
萱草(くわんぞう)色の単(ひとえ)、いと濃き鈍色』 (幻)
萱草(くわんぞう)色の単(ひとえ)、いと濃き鈍色』 (幻)
他にも喪服と一緒に[かんぞうの袴]とあったので、
「かんぞう」を調べてみました。
「かんぞう」を調べてみました。
萱草(くわんぞう)はユリ科で、橙色のユリに似た小さな花を咲かせる。
赤味のある黄色。1日でその花がしぼんでしまう所か、
この花色に染めた襲を喪に服す時の色とした。
赤味のある黄色。1日でその花がしぼんでしまう所か、
この花色に染めた襲を喪に服す時の色とした。
別名に「諼(けん)草」ともあり、「けん」は忘れるという意味。
万葉集では、忘れ草と呼ばれ衣を染めるのではなく
花そのものを身につけて物思いを忘れるとも。(吉岡幸雄日本の色辞典)
万葉集では、忘れ草と呼ばれ衣を染めるのではなく
花そのものを身につけて物思いを忘れるとも。(吉岡幸雄日本の色辞典)
画像の色は光線で少し暗い感じになりましたが、
もう少し薄い色です。
もう少し薄い色です。
長崎盛輝 日本の伝統色 では、
古くは、くわぞう色とも。
柑子・蜜柑の色にちなんで、柑子(こうじ)色とも呼ばれるが、実物の色からみると
赤味が強いとも。
古くは、くわぞう色とも。
柑子・蜜柑の色にちなんで、柑子(こうじ)色とも呼ばれるが、実物の色からみると
赤味が強いとも。
植物のかんぞうはこれを植えて玩味すれば、憂を忘れるという中国の言い伝えから、
忘れな草ともよばれ、また「醜の醜草」すなわち、いやな草ともされ、
喪服着用の凶色とも。
忘れな草ともよばれ、また「醜の醜草」すなわち、いやな草ともされ、
喪服着用の凶色とも。

















