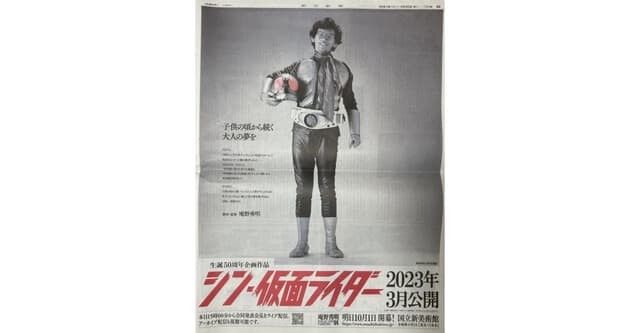さて、『うる星やつら』に引き続き、当時はそのライバル的立ち位置だった作品について。
実は動画でも本作が言及されており、その補足みたいな意味も含まれますので、どうぞお読みください!
風流間唯人の女災対策的読書・第46回「フィクトセクシャル――オタクは現実の女に興味がないのか」
* * *
さて、正直そんなにメジャーな作品でもない本作ですが、読んだこと、観たことのない方も『アオイホノオ』で言及されていたのを読んだことがあるかも知れません。
1980年から『月刊サンデー』に連載開始された、乱暴に言えば『うる星』エピゴーネン的漫画。エピゴーネンというのは、あまり誉めた表現ではないですが、少なくとも受け止められ方はそのような感じだったはずですし、また作者の細野不二彦、ぼくもこの人の作品、一時期いろいろと読んでいたのですが、どうも作家性の強い方というよりは、計算で仕上げていくタイプの人ではないかという気がするので、恐らくご当人もそうした意識を持って描いていた作品なのではないでしょうか(何しろ、他にも露骨に『オバQ』、『めぞん一刻』を意識した作品のある作家さんです)。
さて、そんなこんなで基本設定は、忍者学校を舞台にした美少女とデブ少年とのラブコメ。デブ少年の肉丸は一応、忍術の使い手としては一流なのですが、人間離れしたデブが主人公という辺り、『うる星』の時も言及した、当時の「男性」が像を結びにくくなっていた時代性を象徴しています。
そんな時代性を持った本作、先にもエピゴーネンと言ったように、『うる星』の二匹目のドジョウを狙って1982年、アニメ化されました。とっとと二匹目をとっ捕まえねばと大慌てだったからかどうか、月刊誌連載であるがためエピソードのストックがなかったところのアニメ化で、たちまちのうちにネタが底を突きます。
そのため、苦肉の策の「番外編」が連発されることになりました。今もキャラのスピンオフだの学園漫画でもないものを学園漫画化だの、近いパターンはよく見かけますが、当時は「あくまでその漫画連載(アニメ放映)内で番外編をやる」ということがよくありました。中でも多かったのは「舞台を変える」というもの。いきなりキャラクターたちが江戸時代の住人になったり、スペースオペラの主人公になったり。『うる星』でもよくあったパターンで、「日常系」でネタが尽きた時の定番企画でした。中でも本作は本当にそれが多く、三回に一回くらい番外編だったんじゃないかなあ、という感じ(……ウィキペデアを観たら、三分の一以上と書かれていました)。
この辺りについては懐かしのアニメ(しかしなかなかスポットライトの当たらないものを絶妙にチョイスしている)サイト、「記憶のかさぶた」の「№50 さすがの猿飛」でも言及されているところで、詳しくはそちらをご覧いただきたいところなのですが……この時にパロディの「元ネタ」として選ばれていたのは、一つには当時上映中の話題作、そしてもう一つは往年の名作。『第三の男』とか。
80年代当時は、オタクのためにアニメが作られ出した時代でした。例えば『超時空要塞マクロス』などはオタク世代が作り手に回った、オタクのオタクによるオタクのためのアニメ第一号と言っていいと思うのですが、まだまだ「おっさん世代の作り手」が多かった。一方では華々しい若者文化でありながら、一方ではおっさんが若者に向けて作っている面があったわけです。そこには時おり、「おい若いの、アニメばかりじゃダメだぞ。おじさんの若い頃にはこんな名画があってだな……」と言わんばかりのパロディが登場し、少々鼻についたものでした。
そして、もちろんそれはそれで仕方のないことではあるのだけれども、アニメ誌などでは「おっさんの、オタクへの悪意」がさらに凝り固まった形で発露されている……といったことは以前、動画(風流間唯人の女災対策的読書・第37回「オタク差別最終解答」)でもお伝えしたことがありますね。
『うる星』がそうであったように、この頃のアニメは作品自体が「何でもアリの、スタッフが好き勝手に遊べる遊び場」であり、そこがアニメ文化、オタク文化という「新しい若者文化」を形作っていった面も、多いにあったわけですが、そうした世代間ギャップが露わになる場でもあったわけですね。
さて、それともう一つ。
本作のオリジナル展開はそのような番外編に限りません。
ヒロインである魔子ちゃんは基本、肉丸の庇護下にあるのですが、やがて自立した女を目指すようになるのです。その「魔子の自立編」、たまに挟まっては、ヒロインがつまらぬ苦悩を延々し出してうっとおしい、という印象でした(このテーマ、Wikiによると決着を見ず、なし崩し的に終わるようです)。
乱暴に言えば、オタクの誕生とは「男の子が初めて自分の遊び場を持った」という人類史上、記念すべき事件なのですが、その最初期から実のところ、その遊び場にはおぢさん(この「ぢ」が当時風)と女の子の邪魔が入っていたわけです。
Wikiなどを見ても、「魔子の自立編」が女性スタッフによるものかどうかは判断がつきかねますが、まさに『水星の魔女』的な、そして『トクサツガガガ』的な、「少女漫画」感が濃厚なんですよね。
まあ、近年もエロゲなどでいかにも女性ライターがプロデュースしたんだなあというような歪な作品のお手伝いをさせていただくことがあり、もうちょっと自分たちが男の子向けを作ってるって自覚を持ってくださってもいいんでは……と思うこともしばしばですが、どうもあの人たち、端っから「男の子向け」をテンで理解しておらず、しかし自分は男性的な志向を持っていると、どうもあどけなく信じているようなんですよね。
さて、ではその最終回は……?
当然、原作アニメと異なるオリジナル展開であり、主人公たちの通う忍ノ者高校が悪の巨大組織と戦うという話。日本政府は忍ノ者高校の生徒たちに出動命令を下し、宇宙戦艦大和(だいわ)で決死の特攻作戦を敢行! 何でお気楽ラブコメが急にこんな話になるのかわかりませんが、ともかく決戦前夜のキャラクターたちが死を覚悟し、また恋人が運命を共にしたいと闘いに同行しようとする様が丁寧に描かれます。
しかし「愛する者を守って死ね」との命令に対し、主人公たちは「愛する者は隣にいるじゃないか」とはたと気づく。
主人公たちは愛する者と共に戦線から離脱。悪の組織の総統はモテないがために女の子に怨嗟の念を抱くメカの天才少年で、そのため日本を滅ぼそうとしていたというオチがつきます(先の「記憶のかさぶた」では「受験に失敗し続けた浪人生、アニメと特撮が大好きなオタクで、外見のせいでを女にふられた」という設定が語られていますが、これは記憶違いと思しい)。
女に怨嗟の念を吐くことに加え、兵器としてペギラやゴジラを繰り出す、メカフェチで人間よりもメカに愛着を持つ、また防衛軍側にも嘲笑される幼稚で子供っぽい敵として描かれ、「オタク」といった言葉はさすがに出てこないものの、明らかにそれを意識したキャラクター造型がなされています。
日本は焼け野原になりましたが、忍法でリセット、破壊される前の日本が復元され、平和な光景のまま、終劇。
何というか、サブカル君の薄っぺらな平和思想と醜いオタクへのへの憎悪がありありと現れた最終回ですねw
この辺、ギャグ作品とは言えあまりにも破天荒ですが、この種のオタクを悪役に仕立て上げてドヤる、というのは当時、たまに見たパターンです。翻って例えば時期の近い『スケバン刑事Ⅱ 少女鉄仮面伝説』(1985)では(バックに日本を牛耳るジジイがいるとは言え)天才少年が高校生たちをオルグし、「十代の若者のみによる革命」を企みます。
当時は丁度、学生運動が挫折し、オタクは政治を「ダサい」こととして上の世代をからかっていましたが、同時に校内暴力の吹き荒れた時期でもありました。つまり「正義」が失われたがため、若者たちの中で「DQN」はただ暴れ回り、「オタク」はおとなしくいじけていた。上の世代はそれぞれに自らの願望を仮託し、前者は反体制的スーパーヒロインであるスケバン刑事やその敵役(悪とは言え義を持った存在)に、後者は『猿飛』のラスボス(否定されるべき、ただ惨めな悪)に仕立て上げられたのです。
最終回の脚本は本作のシリーズ構成を務めた首藤剛志。『ミンキーモモ』などの傑作で知られ、80年代的ニヒリズムというか、物語の定番を常に外す作家であり、ぼくも尊敬する作家さんの一人ではあるのですが……『モモ』や、他にも『ようこそようこ』など少女を主人公にしたアニメでは保たれているさわやかさが、ことマニア向けアニメになると受け手への憎悪へと取って代わってしまったわけです。
受け手もまた、そうした憎悪を上の世代に植えつけられ、自らの周囲の、「俺よりも格が下(だと本人が信じる)オタク」へと向けた。
男性というものが像を結びにくい時代、肉丸という戯画的に描かれた少年が美少女とラブコメを演じる本作は、外部に皮肉にもそうした「負の連鎖」を生み出し、エンディングを迎えたのです。
さて、しかしさらにもう一つ、本作は期せずしてだと思いますが、先に述べたようにヒロインの「自立」をテーマにしつつ、それが「愛する者は隣にいる」という結論を導き、結果、主人公たちに「敵からの逃亡」という結論を導き出させました。
ここには「女性の社会進出」「男女共同参画」が戦いを忌避させるのだとの、ある種の平和論が成立しています。『ガンダム』とかイキって女をいっぱい出してるけど、女が銃後にいないんだから、逃げちゃえばいいじゃん、という80年代的考えです。
しかし、そうなると敵と戦う者がいなくなる。そこをごまかすために作り手はオタクに悪役を演じさせ、焼け野原もギャグでごまかして一瞬で「復興」させた。
これはまさに、悪に挑むフリをしながら弱い者イジメしかできず、もちろん国を守ることもできない当時の左派の思想的終焉をも、描いてしまったように思えます。
というわけで、何というか、終わり。