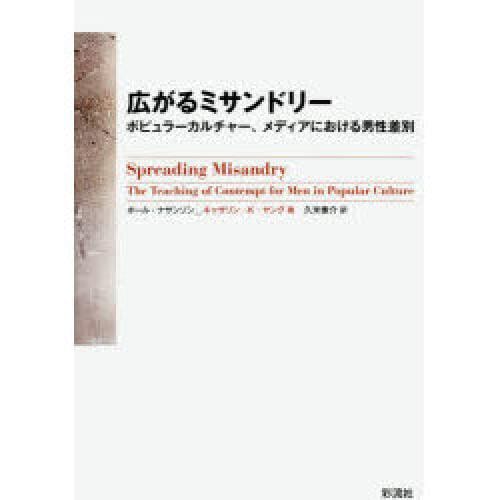
前回記事の続きです。
未読の方はまず、そちらを読んでいただくことを強く推奨します。
さて、いよいよ最終章、九章の「結論」です(ホントに「結論」っていうタイトルです)。
が、読みだすや「ジェンダー両極化を覆さねばならない(大意)」などと言っていて(355p)、早速どんよりさせられます。
どうしてミソジニーの存在が、ミサンドリーを正当化するだろう?
(368p)
ミソジニー(女性蔑視)とそれを作り出している男性中心的世界観に反対することは重要である。しかしミサンドリー(男性蔑視)とそれを作り出している女性中心的世界観に反対することも平等に重要である。
(376-377p)
(368p)
ミソジニー(女性蔑視)とそれを作り出している男性中心的世界観に反対することは重要である。しかしミサンドリー(男性蔑視)とそれを作り出している女性中心的世界観に反対することも平等に重要である。
(376-377p)
著者たち、及び翻訳者の「わかってなさ」を象徴する名フレーズです。
この著者たちの「ミソジニー」に対する温度はわかりません。が、こうある以上、「ミソジニーがあるのだ」というフェミニズムの主張を、ある程度受け入れていると考える他はないでしょう。
フェミニストの欺瞞について批判しつつも、ジェンダーフリーなどのフェミの成果に対しては盲信を抱いている。「男性差別クラスタ」にたまにいる層であり、また「表現の自由クラスタ」ともそっくりです。
しかし本ブログの愛読者の方にはとっくにおわかりでしょう。
男女には絶対的究極的根源的な「愛され格差」がある。
基本的に、男性は「殺していい性」として設定されている。
過労死者の、ホームレスの95%が男性なのはそれ故です。
そんな中、「ミサンドリー」と言われても、困る。
ぼくたちの棲むこの宇宙それ自体が「巨大なミサンドリーそのもの」としか、言いようがないのですから。
「ミサンドリー」は神羅万象全てに宿っているが、「ミソジニー」は、そもそも、ない。
いや、全くないわけではないぞと言いたい方もいるかもしれないが、だとしてもそれはニホンオオカミや二ホンカワウソの分布図くらいに局所的なものです。
しかしそういった認識が本書の著者たちや翻訳者にあるかとなると、疑問と言わざるを得ない。
もっともよい着眼点もあります。ミサンドリーの理解されにくい点として、
ミサンドリーが最も露骨な形態をとって現れたときも、事実として、男性蔑視はしばしば女性蔑視にすり替えて解釈されてしまう。
(358p。アンダーライン部は原典では傍点)
(358p。アンダーライン部は原典では傍点)
としていることです。
その例として、著者たちはまた一つ、「絶対悪としての男性が被害者としての女性に加害する」映画を例に挙げます。この映画、『イン・ザ・カンパニー・オブ・メン』の主人公であるチャドはマッチョで、女性ばかりかあらゆる男性をも憎み蔑ろにしている、にもかかわらずこれはミソジニーを告発する映画として解釈され、場合によってはミソジニーそのものと解釈されると著者たちは言います。
しかし何としたこと、著者たちはこの慧眼の直前で、こんなことを言っています。
男性も女性もしばしばミサンドリーを問題として見ることができないのは、性差別がミソジニーの点からに限って定義されているからだ。
(中略)
あらゆるミソジニーの痕跡の何十年もの執拗な追跡のあとでは、ミサンドリーがミソジニーの重要なカウンター概念であることが受け入れられるのはとても難しくなり得る。
(357-358p)
(中略)
あらゆるミソジニーの痕跡の何十年もの執拗な追跡のあとでは、ミサンドリーがミソジニーの重要なカウンター概念であることが受け入れられるのはとても難しくなり得る。
(357-358p)
まさしく「わかってないなあ」です。
確かに、フェミニズムはミサンドリーの限りを尽くしてきました。上の映画もその影響を、受けていないわけがありません。
しかしもし今ここでフェミニストを全員殲滅すれば――それでは足りないかもしれません、歴史を改変し、フェミニズムという思想の出現を完全に阻止すれば――「ミサンドリー」は地上に出現しなかったのでしょうか。
そんなはずはありません。「ミサンドリー」は「ジェンダー」が地上に出現した時点で、そこに内包される形で生まれていたのです。
そこを、まるで「ミサンドリー」が「ミソジニー」の二次概念ででもあるかのようによいしょと持ち出して来て、「ミソジニーがけしからぬならば同様にミサンドリーもけしからぬぞ、さあどうだ」などとイキったところで、解決する問題は何一つ、ない。
ぼくたちは、ミサンドリーが正当なこととして存在している「凡ミサンドリー社会」に生きている。そのことをまず、認識しなければ何も始まらない。
上の映画にしても、基本的にはチャドが女性へと悪さをする部分がメインの話なのだから、「チャドのミサンドリーについても言及がないとは許せぬ」という言い方はいささかパンチ不足です。例えばですが、チャドが男は平然と殺し、女には殴打で済ませているのに「ミソジニーだ」と言われている、とでもいった描写があるのならわかるのですが、そうでないのであれば、「映画のテーマ外のことを持ち出して、無理にインネンをつけている」に過ぎません(実際の映画を見てみないと断言はできませんが、少なくとも本書の筆致自体が、そうしたことに言及していない以上、彼らの見方に問題があると判断せざるを得ません)。
これこそ、著者たちがミソジニーとミサンドリーをただ対照的な概念とだけ捉えていることの証拠であり、「わかってない」ことの証明です。
「男性蔑視はしばしば女性蔑視にすり替えて解釈されてしまう。」との指摘は、例えばですが以下のような事例を指してなされるべきでした。
「女性だけの街」問題というのがありました*1。フェミニストたちが「(安全のために)男を排除した女性だけの街が欲しい」と主張し、しかし平然と「しかしインフラは男たちが外部から通ってきて、整備せよ」などと言って呆れられたというのが経緯です。
また、「フェミニスト男性」を自称する者が「ネットにはいつ女性が殺されてもおかしくないほどのミソジニーをはらんだ女叩きで溢れている」との主張をしたこともありました*2。しかし彼は「AEDで女性を救助すると訴えられるかも」との「真っ当な懸念」をも、「女叩き」にカウントしていました。
これらは根を一にしています。
「男は邪悪だから、女性だけの街を作り、排除せよ」。
「男は邪悪だから、女性が倒れても、その汚らわしい手で助けるなど許さぬ」。
もし、そうした意見があったのであれば、それは確かに「ミサンドリー」でしょう。
しかし彼ら彼女らが言っているのは、そうしたことではありません。
「排除するが、インフラだけは整えよ」。
「その汚らわしい手で助け、女性の任意で罪人扱いされても文句を言うな」。
それが彼ら彼女らの言い分です。
この意見に異を唱えることが、絶対に許されるべきでない「ミソジニー」であるというのが、彼ら彼女らのホンキの考えです。
彼ら彼女らは、ミサンドることは「空気のように当たり前な前提」とし、「その上でさらに女へと夥しいコストを投じないこと」を「ミソジニー」であると定義づけているのです。「ミサンドらないこと」が「ミソジニー」なのではありません。「ミサンドること」は大前提で、その上であれもしてこれもしてそれもしてが当然、それをしないことが「ミソジニー」なのです。それは「ミサンドリー」を遥かに上回る、本物の悪魔ですら震え上がるであろう吐き気を催すほどの邪悪な「何か」でした。
それこそが「男性蔑視はしばしば女性蔑視にすり替えて解釈されてしまう。」ことの、本当の理由だったのです。
フェミニズムは、「ミサンドリー」という「元から山のようにあった女性側の負債」を完全にスルーするという蛮行に、まず、出ました。その、しかる後に「ミソジニー」という仮想通貨による借金を捏造して、ぼくたちに「金返せ」と『ナニワ金融道』のような取り立てを始めました。そこが彼女らの悪質さであり、彼女らは「ミサンドリー」の発明者などではなかったのです。
*1『女性だけの街』ヲ作ろう
*2 男性が描いた「男性がフェミニストにならなきゃいけないワケ」の漫画が話題
前回もちらっと触れましたが、あとがきでは久米師匠がこれからのマスキュリズムの展望について、
要するに男女平等を目指す上で過去フェミニズムが男性に対して主張し行ってきたことを女性に対して主張し行うのである。
(444p)
(引用者註・離婚時の男親の不利な法的状態を例に挙げ)厳しく批判、監視していく必要がある。(まさにフェミニズムがやってきたことと同じことを性別を入れ替えてやるだけだが)。
(445p)
(444p)
(引用者註・離婚時の男親の不利な法的状態を例に挙げ)厳しく批判、監視していく必要がある。(まさにフェミニズムがやってきたことと同じことを性別を入れ替えてやるだけだが)。
(445p)
などと言っています。
彼のかかわっている、「男親にも親権を認めよ」という運動自体には賛成なのですが、女親に有利な現状だって、ある意味では「母親により子供が懐くから」であり、それを無視したジェンダーフリーに賛成はできません。
いや、それよりも、そもそも、ここまでフェミニズムの欺瞞を暴露しておきながら、その方法論だけはパクろうという久米師匠の感覚はさっぱり理解できません。上の監視すべき対象としては「マスメディア」も挙げられており、この調子だと「男性差別的漫画」とかに文句をつけそうですよね。
つまり彼の言うマスキュリニズムも、フェミニズムの「功績」を頂戴しての「よし、俺も」でしかないことがここで明言されているわけです。しかしそれではダメなことは、ここまで読んできた方にはもうおわかりのことでしょう。
先に「男性差別的漫画」と書きましたが、師匠は『巨人の星』、手塚治虫、宮崎駿、また『ワンピース』などをミサンドリー作品、作家であると位置づけます。しかしこれら作家、作品がミサンドリックであるとは、ぼくにはあまり思えません。これら作家、作品においては男親は悪、女親は善という図式が透徹されていてけしからぬそうですが、それって単純に昔の作品では主人公が「旧世代の男」を乗り越えることがドラマツルギーとして普遍的だったというだけのことです。『ワンピース』について、ぼくは全く知らないのですが、師匠の指摘を見る限り旧世代の作品と同様のようで、そうなるとこうした図式はやはり、時代を超えて普遍的なものなのかもしれません。
師匠の『ワンピース』への憎悪はものすごく(戦闘員であっても女性は守られ続けるという図式が露骨だそうで、それに憤るのはわかるのですが)、
まず、男性差別、ミサンドリーの代表的作品といえるのが、少年(?)漫画である『ワンピース』である。この作品は、極めて強く男性嫌悪、女性中心的作品でありつつ、さらに非常に知名度が高く、そしてメディアで人気(誰に人気なのかはおいておくが)なため、総合点において必ず、触れておくべきだと思ったため、あげた。
(448-449p)
(448-449p)
何だか見ていて笑ってしまいます。
師匠の腐女子への憎悪が(括弧の中から)窺われます。もっとも、師匠は「女性向けには少女漫画というジャンルがあるのに、何故少年漫画が女性に媚びるのだ(大意・452p)」とも言っており、「男女共生」というポリコレに盲目的に操られて「ガンダム事変」を引き起こした連中*3に比べれば、フラットなジェンダー感を持っていることもまた、窺われるのですが。
……などと思いながら読み進めていくと、本当に最後の最後というところまで来て、ものすごい爆弾が控えていました。
またこれらの男性差別作品とし(原文ママ)挙げているものは、男性の作者であるが、男性の読者に自然発生的に人気が出て、横に広まっていったというよりも、ある一定の(フェミニズムを大いに含む)メディア政治勢力によって政治的な意図をもってプロパガンダされている気配がある。この手の作品が才能がないのに無理やり押されているというのではない、才能がある作品のうち男性差別的(言い換えるとミサンドリーフェミニズム)に都合のよいものが選んで政治的にプッシュされていると思っている。
(452p)
(452p)
え~と、すみません、師匠は既に遠い世界に行っていらっしゃるようです。
手塚の時代からフェミニズムはメディアを牛耳り、手塚を(本来人気などなかったのに)表舞台に押し上げたのだそうです。まあ、ジブリ作品は母親受けがいい、くらいのことは言えるかとは思うのですが、それだってフェミとは関係ないでしょう(フェミを延命したくてならない自称フェミ批判者が、ママさん世論的なものをフェミと混同してスケープゴートにしがちなのをふと、連想します)。
まあ、こんなわけですから師匠に対しては遠目にそっと、(『巨人の星』の)明子姉ちゃんくらいの感じで見守るに留めておいた方がよさそうです。
(後一つ、本書については訳文の拙さについて延々愚痴ってきましたが、こうして見ると師匠自身の文章もアレだとわかります。確か千田由紀師匠が「日本語ネイティブではないのでは」と評していた記憶があるのですが、それも道理です)。
*3「ホモソーシャル」というヘンな概念にしがみつく人たち (兵頭新児)
さて、では、これからぼくたちはどうすればいいのだ、と言われても困るのですが、しかしぼくたちが考えるべきことは、もう自明であるかのように思われます。
例えば上の映画『イン・ザ・カンパニー・オブ・メン』には当初、チャドと協力状態にあるものの、次第に被害者女性を真剣に愛するようになるハワードという男性も登場します。言わば、今一頼りない男という、90年代を象徴する人物です。前回挙げた『愛がこわれるとき』のベンも、そんな感じでしたね。が、しかしそこを考えるとこの映画もまた「女性に加害する男性、誠実に愛する男性」の二者の登場するジェップスなのです。
先に、こうしたジェップスを「ジェンダー規範に忠実」と書きましたが、正確にはちょっと違う。古典的な、ジェンダー規範に忠実な物語であれば、ハワードはヒロインを助けに来る正義の味方として描かれていたであろうからです。
ひと昔、90年代より前ならば正義の男性と悪の男性が物語のメインとして描かれていたはずです(本書は専ら90年代の作品について語られています)。男性は能動的に動くというジェンダー規範が求められるため、かつての物語において、「ヒーローであると共にヒールであった」。つまり女性は無力なピーチ姫(或いはオリーブでも何でもいいのですが)という役割のみを与えられていたが、男性はマリオかクッパ(ないし、ポパイかブルート)に分かれていた。ところがマリオやポパイが失われてしまった、それが90年代に起きた変化だったのです。両者が共にブルーカラーなのは実に示唆的です。
『セーラームーン』はまさにこの時期に誕生した「女の時代」の寵児であり、そうした「男を蹴散らす」的なミサンドリーの念をもって描かれ、しかしアニメスタッフによってそうしたノイズが取り除かれた良作であることは以前指摘した通りです*4。とは言え、このセーラームーンにおいても、彼女の彼氏であるタキシード仮面は活躍すると「男のくせに出しゃばるな」と言われ、しくじると「男のくせに情けない」と言われた存在でした。
かつてより、「男は悪者」でした。その代わり、かつては「男は正義の味方」でもあり、「女はお姫様」役を演ずるのみでした。それは丁度、手柄を立てるのも悪いことをするのも男の方が多いという、現実世界のジェンダー規範の、忠実な反映です。
男性解放論者の古典的名著『正しいオトコのやり方』において、フレドリック・ヘイワードは
女の子はお砂糖とスパイスと、すてきなものばかりでできていた。そのかわり弱くて、おばかさんで、パンクしたタイヤも取り換えられない。そして男の子は強くて自信に満ち、有能だった。そのかわり無法者で信用がおけず、セックスに目がなくて、卵もゆでられない連中なのだ。両性の闘いは続き、そして現在、主役と悪役は決定された。女の子は以前両性で分けあっていた良い性質を全部独占してしまった。男の子はただもう、悪いだけだ。
(191p)
(191p)
と極めて鋭い指摘をしています。
本書の分析の全てが無意味だとは全く思いません。しかしそれを実りあるものにするならば、近年の物語(否、言説のレベル)において「ヒーロー」が不在になっていることをこそ、問題とすべきなのです(久米師匠は「ヒーロー」の存在そのものを「男性差別」だとい言い募りそうですが、まあ、彼のことはどうでもよろしい)。
言わば「ミサンドリー」はあってもいい、しかしよりそれ以上の「オトコスキー」がかつてはあったし、あってしかるべきなのにそれが失われた、何故なのか、というのが設問であるべきだったのです*5。
その理由は、何か……? 大情況的には産業のサービス業への移行に伴う男性性の価値の減退みたいことは、先進国に必ず起こる必然だったでしょう。ヴィジュアル文化時代には、見栄えのする女性が有利ということもあります(これはテレビ普及が大きいでしょう)。
むろん、フェミニズムだけが原因ではないとはいえ、彼女らがそこに乗っかり、男性のネガティビティを喧伝し続けてきたということは言えます。本書の諸々の指摘は、そうしたフェミの蛮行の記録にもなっており、そこはもちろん、大変に有意義です。
本書を見ていくと、ポリティカルコレクトに対する鋭い批判、左派が雑に黒人と女性とを混同して「聖なる弱者」に仕立て上げている点についての批判もあり、それぞれ至極もっともな話です。
端々には
ほとんどの人はもし完全な平等が達成されたら、もし私たちが文化システムとしてのジェンダーの名残を全滅したとき、何が実際に起こるのか考えようとしない。私たちが、“脱ジェンダー化”と呼ぶものは全ての男女の文化的違いを解消し、生物学的違いさえ緩和するだろう。ではどうやって男性も女性もアイデンティティを形成するのだろう?
(140p)
(140p)
といった記述もあり、これなどジェンダーフリーへの鋭いカウンターになっています。
しかし、同時に別な箇所ではジェンダーフリー肯定と思える記述があるなど、全体を通してみると本書がぶれないはっきりとしたビジョンを提示し得ているとは、言い難い。
ましてや久米師匠には、批判する漫画がむしろ古典的ジェンダー観に則ったものであることが象徴するように、ジェンダーフリーへの強烈な志向がある。
それともう一つ、彼は「男性差別解消を目指す人は人文系の学問を納めるべき」と主張し、また本書を学者、学生に読まれることを期待しているなど(445p)、どこか権威主義の匂いのする御仁です。また、上の腐女子への視線や先のポルノ批判の記事*6を見ても、オタクに対しての憎悪を持っていることが窺い知れる。仮にブログ「独り言 女権主義」の主が久米師匠であるとの顔面核爆弾さんの考えを正しいとすると、そのオタク憎悪の強烈さは疑い得ないものとなりましょう。つまり彼自身が今の左派の特徴である「とにもかくにも弱者と見るや、本能的に激烈な憎悪を燃え立たせる」という特徴を十全にお持ちの方であると評価せざるを得なくなるのです。
ぼくが「女災」問題と「オタク」問題を並列させて語ってきたわけは、当ブログの愛読者の方にはおわかりでしょう。「オタク」は「弱者男性」と「≒」で結べる存在であり、従来のポリティカルコレクトネスの穴を突く存在(アメリカで言えば「プア・ファット・ホワイトマン」に当たる存在)であるからです。
そのオタクを呪う久米師匠こそ、この世で一番の「ミサンドリスト」と言えましょう。
左派が女性でありセクシャルマイノリティであり特定の外国人でありを理解する素振りを見せるのは、言うまでもなく彼ら彼女らの人権を慮っているからでは全くなく、最初から持っていた「社会一般」に対する強烈な憎悪を、「正義」に偽装するためでした。
フェミニズムの本質は「箱舟」です。「甚だしく勘違いした、幼稚なナルシシズムを根底に置いたエリーティズム」です。
自らのエリーティズムを満たすため、箱舟に搭乗したが、しかしその箱舟すらもアララト山に辿り着くことができないと知った者がいたとしたら……?
今までの久米師匠の主張は、彼が彼なりに考えて提示したアンサーでした。
弱者男性を深く憎悪する久米師匠(及び、田中俊之師匠)は「男性解放」を小銭稼ぎのネタにすると同時に、実のところ自分たちと歩調をあわせる「選ばれし者」のみを正義とすることで、男性一般は見下すというウルトラCを開発した方でした。
一方、数年前まで「世界ミサンドリストナンバー1」の地位にあった「オタク界のトップ」は、しかしながら、目下のところオタクの味方のふりをしている。彼らは専ら「表現の自由」問題というワンイシュー()に論点を特化することで、今までの方法論のまま、オタクの味方として振る舞おうとした人たちでした。
久米師匠の、フェミの方法論をパクろうという施政方針演説を見ればわかるように、彼らはフェミニストを憎みつつ、同時に彼女らの持つ資産、つまり論理の構築であり(これこそ非実在の仮想通貨なのですが)アカデミズムやマスコミにおける権力に魅力を感じているように思われます。
彼らはフェミニストのトップを殺して、首だけを挿げ替え、そのリソースを利用しようという野望に憑りつかれてしまったのではないでしょうか。彼らが勝利した時、きっとバカ殿としてピル神みたいな人が椅子に座らされることになるのでしょう。
*4 セーラームーン世代の社会論
*5 さらに言えばフェミニズムとは「オンナスキー」が(専ら彼女らの責任で)失われ、もう、しょうかたなしに、ほとほと根を上げて、男がホンの僅かばかり露呈させた「ミソジニー」を手に取り、大袈裟に誇張して騒ぎ立てるという現象そのものでしたが、まあ、それは置きましょう。
*6 男性に対する性の商品化の学問上の批判










