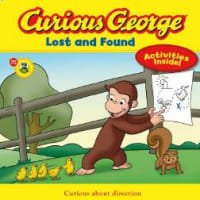タイトルの「半暮刻」は「はんぐれどき」と読むそうだ。この言葉を本書で知った。手許の2冊の大辞典を引いたがこの語句は載っていない。著者の造語なのだろうか。
本作の末尾は次の一文で終わる。
「夕暮れが闇に呑まれる半暮刻に、波が嗤うようにざわめき始めた」(p461)
本書のタイトルはここに由来するようだ。
本書は2023年10月に単行本が刊行されている。
『カタラ』は新宿にある表向き会員制クラブということになっている別世界。そこが最初の舞台となる。「カタラ」はギリシャ語で「呪い」という意味だという。「カタラは決してホストクラブなどではない」(p8)というが、女達を若くて見栄えがよい男達(スタッフ)が相手をするという点ではホストクラブと似ていると思う。カタラグループの創立者は城有。城有は「カタラ」に若い女をスタッフが連れ込む為の<マニュアル>を整備していた。マニュアルを熟読して、それに沿って実行する。何を実行するのか。若い女をスタッフ達がコール(カタラの隠語)する。つまりナンパして、クラブ「カタラ」の客として引き込み、マニュアルに沿った対応する。スマートで甘い言葉と態度により、高価な酒を飲ませて金を使わせる。借金を背負わせることにより、その返済のための手段にF(風俗)を紹介して、金を回収する。ホストクラブではないという意味は、女を嵌めてFに売ることに主眼があるという点なのだろう。スタッフになっている大半は見栄えのよい普通の大学生たち。
「カタラ」は毎月、スタッフの中での売上高トップ・テンを公表している。つまり、女を嵌めて、酒を飲み楽しませ、借財を多くさせて、Fを紹介する形で返済させる。Fに行くことを納得させる言葉も、<マニュアル>には準備されている・・・という次第。
勿論、これはフィクションだが、似たような別世界が現実に存在する気にさせるところがある。そう思わせるところにリアル感が・・・・。
ここで登場するのが、山科翔太と辻井海人。二人は対照的な環境で育ってきた。
山科翔太はシングルマザーに育児放棄された。家裁の判断で強制的に児童養護施設行きとなり、施設で育ち、定時制高校を中退。不良になった。地元の先輩に呼びだされて、カタラのスタッフになった。<マニュアル>を熟知し、それを元に行動するのは、生きる為だった。彼にとって<マニュアル>は己の行動を律する手段。
辻井海人は、世田谷に豪勢な実家があり、G大の学生。父親は経産省のキャリア官僚である。海人はカタラのスタッフになっているのを人生勉強だと考えている。<マニュアル>の実践が大学での講義などよりはるかに人生経験の場になると判断している。<マニュアル>には、「意識の高さ」「自分磨き」「価値観」「向上心」「人生は勝ち負け」・・・などの言葉が散りばめられている。海人はこの<マニュアル>を有益で、その実践が人生経験になり己の成長につながると。若い女をコールし、カタラに連れ込み、Fに送り込むことに罪悪感のかけらもない。成果を挙げ、トップ・テンになることは、自分磨きの実証という観点しか捉えてないのだ。海人の自己中心性である。
城有は「オレらは法に触れることは何もやってないわけ」「オレらの目的はあくまで自分磨き」(p31)を翔太や海人に強調していた。
海人に誘われて翔太は海人とペアになって<マニュアル>の実践を行う。街中でこれはと思う若い女へのコールを効率的に実行していく。その結果は、たちまち二人を「タカラ」のトップ・テンに引き上げる。
このプロセスがこのストーリーの「起」(第一ステージ)となる。ここから翔太と海人の人生が岐路に向かう。
本作は二部構成。「第一部 翔太の罪」、「第二部 海人の罰」である。
「承」(第二ステージ)は、カタラ・グループの城有はじめスタッフに職業安定法違反容疑で逮捕状が執行されることから始まる。翔太にとっては城有の言を信じていた故に、全く想定外の事態だった。この事態にどのように対処するか。逮捕者それぞれの対応の有り様が描き込まれていく。現実の法執行の状況でありそうな対応がリアルに描き込まれているように感じる。そこには法律の適用手続きの限界点すら感じる。
第一部において、翔太は何も語らず、法律違反の「罪」を判決として宣告されて服役する。一方、海人は結果的に容疑者としての逮捕対象者にも入らなかった。実名でスタッフをしていたにも関わらずである。カタラの壊滅後、海人は素知らぬ顔でその後G大学の学生生活に戻っていく。翔太と海人のそれぞれの人生の岐路の始まり。
第一部はまず翔太に焦点を当てる。刑期を満了した翔太が、出所し社会復帰していく人生の有り様が「転」(第三ステージ)として、第一部の後半で進展していく。お定まりの転落となり、そこから翔太は人生再生への道のりに歩み出す。あることが契機で読書することが翔太にとり人生再生への一つのトリガーになっていく。この設定が興味深い。
第二部は、海人の人生の「転」(第三ステージ)の状況を主体に描き出していく。大学卒業後、海人は念願の広告代理店最大手、株式会社アドルーラーに入社していた。営業企画部戦略企画室という花形部署に所属。海人の欲望は、アドルーラーでの勝者となること。そために出世のチャンスを狙っていた。海人にとり、他人は踏み台にしかすぎない。だが、その意識の自覚すら海人は持ち合わせていない・・・・。
仮称「東京ワールドシティ・フェスティバル」を2028年に開催することを目的とした「シティ・フェス推進準備室」に海人は課長待遇の室長補佐として、29才で出向することになる。
アドルーラーのビジネス・センスを体現した海人は、かつて学んだカタラ・グループの<マニュアル>を融合させた意識と思考で、己に課された業務活動を推進する。そこにアドルーラーの企業倫理と企業風土、さらにビジネスの舞台裏が活写されていく展開となる。ビジネス行動の歪みが実に具体的で生々しいリアル感を漂わせて描き込まれていく。
政財界の癒着。政治家と反社会的勢力との結び付き。都政の舞台裏。裏金作りと資金還流。業務の下請け構造とピンハネ構造。過酷労働。パワハラ。セクハラ。情報操作 ・・・・・。
現代の日本における社会経済構造に潜むブラックな側面の実態が、アドルーラーとこの「シティ・フェス推進準備室」で室長補佐として行動する海人の行動に凝縮される形で、ストーリーが進展していく。海人が室長補佐で出向した頃に、海人の結婚生活もまた始まっていく。そこには海人の結婚観が反映している。
海人を軸としたストーリの展開が、本作では読ませどころになっている。
どこかで伝聞したような・・・・という事例が数々フィクションという形で織り込まれているように感じる。このあたり、社会諷刺小説の局面を内包しているとも言えよう。
海人が準備室長補佐として、シティ・フェス開催PRの前面に顔を出す様になる。これが「転」の段階から「結」(第四ステージ)の段階に展開する契機になるのではないかと思う。顔を曝すことが墓穴を掘る契機になると言えようか。
本作がどのような進展を経るかは、本書を開いて楽しんでいただきたい。
辻井海人は、カタラの件でも、アドルーラーでのビジネス行動においても、法律の執行による「罪」を課されることなくすり抜けた。だが、社会的客観的視点では「罰」を受ける状況に落ちる結果となる。だが、海人自身がそれを「罰」と自覚し認識するかである。
「結」の段階で、最後の最後に、翔太は海人と再会する。
二人の会話がこの「半暮刻」の落とし所になっている。
そして、冒頭に引用した本作最後の一行に帰着する。
本作を読み終えて、「半暮刻」は、「半グレ」をダブル・ミーニングとして内包しているのではないか・・・・ 辻井海人が「半グレ」への道を歩み始める「刻」を暗示しているのではないかと。そんな印象を抱いた。
本書の目次裏に、フョードル・ドストエフスキー『地下室の手記』安岡治子訳の一節が引用されている。本作を読み終えてから、この引用文を再読すると、実に巧みに照応しているように感じる。最後に引用しておきたい。
「この手記の作者も、『手記』そのものも、むろん虚構である。にもかかわらず、こうした手記の作者のような人物は、そもそも我々の社会が形成された事情を考慮すれば、我々の社会に存在する可能性は大いにある。いや、それどころか、むしろ必ずや存在するにちがいない」
ご一読ありがとうございます。
著者の作品について、以下の読後印象を以前に『遊心逍遙記』の方に載せています。
併せてご一読いただけるとうれしいです。
『土漠の花』 幻冬舎
『脱北航路』 幻冬舎
本作の末尾は次の一文で終わる。
「夕暮れが闇に呑まれる半暮刻に、波が嗤うようにざわめき始めた」(p461)
本書のタイトルはここに由来するようだ。
本書は2023年10月に単行本が刊行されている。
『カタラ』は新宿にある表向き会員制クラブということになっている別世界。そこが最初の舞台となる。「カタラ」はギリシャ語で「呪い」という意味だという。「カタラは決してホストクラブなどではない」(p8)というが、女達を若くて見栄えがよい男達(スタッフ)が相手をするという点ではホストクラブと似ていると思う。カタラグループの創立者は城有。城有は「カタラ」に若い女をスタッフが連れ込む為の<マニュアル>を整備していた。マニュアルを熟読して、それに沿って実行する。何を実行するのか。若い女をスタッフ達がコール(カタラの隠語)する。つまりナンパして、クラブ「カタラ」の客として引き込み、マニュアルに沿った対応する。スマートで甘い言葉と態度により、高価な酒を飲ませて金を使わせる。借金を背負わせることにより、その返済のための手段にF(風俗)を紹介して、金を回収する。ホストクラブではないという意味は、女を嵌めてFに売ることに主眼があるという点なのだろう。スタッフになっている大半は見栄えのよい普通の大学生たち。
「カタラ」は毎月、スタッフの中での売上高トップ・テンを公表している。つまり、女を嵌めて、酒を飲み楽しませ、借財を多くさせて、Fを紹介する形で返済させる。Fに行くことを納得させる言葉も、<マニュアル>には準備されている・・・という次第。
勿論、これはフィクションだが、似たような別世界が現実に存在する気にさせるところがある。そう思わせるところにリアル感が・・・・。
ここで登場するのが、山科翔太と辻井海人。二人は対照的な環境で育ってきた。
山科翔太はシングルマザーに育児放棄された。家裁の判断で強制的に児童養護施設行きとなり、施設で育ち、定時制高校を中退。不良になった。地元の先輩に呼びだされて、カタラのスタッフになった。<マニュアル>を熟知し、それを元に行動するのは、生きる為だった。彼にとって<マニュアル>は己の行動を律する手段。
辻井海人は、世田谷に豪勢な実家があり、G大の学生。父親は経産省のキャリア官僚である。海人はカタラのスタッフになっているのを人生勉強だと考えている。<マニュアル>の実践が大学での講義などよりはるかに人生経験の場になると判断している。<マニュアル>には、「意識の高さ」「自分磨き」「価値観」「向上心」「人生は勝ち負け」・・・などの言葉が散りばめられている。海人はこの<マニュアル>を有益で、その実践が人生経験になり己の成長につながると。若い女をコールし、カタラに連れ込み、Fに送り込むことに罪悪感のかけらもない。成果を挙げ、トップ・テンになることは、自分磨きの実証という観点しか捉えてないのだ。海人の自己中心性である。
城有は「オレらは法に触れることは何もやってないわけ」「オレらの目的はあくまで自分磨き」(p31)を翔太や海人に強調していた。
海人に誘われて翔太は海人とペアになって<マニュアル>の実践を行う。街中でこれはと思う若い女へのコールを効率的に実行していく。その結果は、たちまち二人を「タカラ」のトップ・テンに引き上げる。
このプロセスがこのストーリーの「起」(第一ステージ)となる。ここから翔太と海人の人生が岐路に向かう。
本作は二部構成。「第一部 翔太の罪」、「第二部 海人の罰」である。
「承」(第二ステージ)は、カタラ・グループの城有はじめスタッフに職業安定法違反容疑で逮捕状が執行されることから始まる。翔太にとっては城有の言を信じていた故に、全く想定外の事態だった。この事態にどのように対処するか。逮捕者それぞれの対応の有り様が描き込まれていく。現実の法執行の状況でありそうな対応がリアルに描き込まれているように感じる。そこには法律の適用手続きの限界点すら感じる。
第一部において、翔太は何も語らず、法律違反の「罪」を判決として宣告されて服役する。一方、海人は結果的に容疑者としての逮捕対象者にも入らなかった。実名でスタッフをしていたにも関わらずである。カタラの壊滅後、海人は素知らぬ顔でその後G大学の学生生活に戻っていく。翔太と海人のそれぞれの人生の岐路の始まり。
第一部はまず翔太に焦点を当てる。刑期を満了した翔太が、出所し社会復帰していく人生の有り様が「転」(第三ステージ)として、第一部の後半で進展していく。お定まりの転落となり、そこから翔太は人生再生への道のりに歩み出す。あることが契機で読書することが翔太にとり人生再生への一つのトリガーになっていく。この設定が興味深い。
第二部は、海人の人生の「転」(第三ステージ)の状況を主体に描き出していく。大学卒業後、海人は念願の広告代理店最大手、株式会社アドルーラーに入社していた。営業企画部戦略企画室という花形部署に所属。海人の欲望は、アドルーラーでの勝者となること。そために出世のチャンスを狙っていた。海人にとり、他人は踏み台にしかすぎない。だが、その意識の自覚すら海人は持ち合わせていない・・・・。
仮称「東京ワールドシティ・フェスティバル」を2028年に開催することを目的とした「シティ・フェス推進準備室」に海人は課長待遇の室長補佐として、29才で出向することになる。
アドルーラーのビジネス・センスを体現した海人は、かつて学んだカタラ・グループの<マニュアル>を融合させた意識と思考で、己に課された業務活動を推進する。そこにアドルーラーの企業倫理と企業風土、さらにビジネスの舞台裏が活写されていく展開となる。ビジネス行動の歪みが実に具体的で生々しいリアル感を漂わせて描き込まれていく。
政財界の癒着。政治家と反社会的勢力との結び付き。都政の舞台裏。裏金作りと資金還流。業務の下請け構造とピンハネ構造。過酷労働。パワハラ。セクハラ。情報操作 ・・・・・。
現代の日本における社会経済構造に潜むブラックな側面の実態が、アドルーラーとこの「シティ・フェス推進準備室」で室長補佐として行動する海人の行動に凝縮される形で、ストーリーが進展していく。海人が室長補佐で出向した頃に、海人の結婚生活もまた始まっていく。そこには海人の結婚観が反映している。
海人を軸としたストーリの展開が、本作では読ませどころになっている。
どこかで伝聞したような・・・・という事例が数々フィクションという形で織り込まれているように感じる。このあたり、社会諷刺小説の局面を内包しているとも言えよう。
海人が準備室長補佐として、シティ・フェス開催PRの前面に顔を出す様になる。これが「転」の段階から「結」(第四ステージ)の段階に展開する契機になるのではないかと思う。顔を曝すことが墓穴を掘る契機になると言えようか。
本作がどのような進展を経るかは、本書を開いて楽しんでいただきたい。
辻井海人は、カタラの件でも、アドルーラーでのビジネス行動においても、法律の執行による「罪」を課されることなくすり抜けた。だが、社会的客観的視点では「罰」を受ける状況に落ちる結果となる。だが、海人自身がそれを「罰」と自覚し認識するかである。
「結」の段階で、最後の最後に、翔太は海人と再会する。
二人の会話がこの「半暮刻」の落とし所になっている。
そして、冒頭に引用した本作最後の一行に帰着する。
本作を読み終えて、「半暮刻」は、「半グレ」をダブル・ミーニングとして内包しているのではないか・・・・ 辻井海人が「半グレ」への道を歩み始める「刻」を暗示しているのではないかと。そんな印象を抱いた。
本書の目次裏に、フョードル・ドストエフスキー『地下室の手記』安岡治子訳の一節が引用されている。本作を読み終えてから、この引用文を再読すると、実に巧みに照応しているように感じる。最後に引用しておきたい。
「この手記の作者も、『手記』そのものも、むろん虚構である。にもかかわらず、こうした手記の作者のような人物は、そもそも我々の社会が形成された事情を考慮すれば、我々の社会に存在する可能性は大いにある。いや、それどころか、むしろ必ずや存在するにちがいない」
ご一読ありがとうございます。
著者の作品について、以下の読後印象を以前に『遊心逍遙記』の方に載せています。
併せてご一読いただけるとうれしいです。
『土漠の花』 幻冬舎
『脱北航路』 幻冬舎