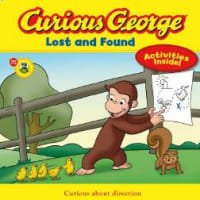著者のアート小説を主体にしながら読み継いできた。リーチ先生とは、イギリス人陶芸家バーナード・リーチのことである。本作は学芸通信社配信により全国の7新聞各紙に、2013年10月20日~2015年11月10日に順次配信され、2016年10月に単行本が刊行された。第36回新田次郎文学賞受賞作。2019年6月に文庫化されている。
私は京都近代国立美術館で、河井寛次郎、富本憲吉、濱田庄司の作品を幾度も見ている間に、バーナード・リーチの作品も見る機会があり、その名を記憶した。陶芸家の彼らの間に交流があったことを知ったが、それ以上の人間関係などについて意識しなかった。
私にとっては、彼ら相互間の人間関係や親交の経緯、さらに柳宗悦や白樺派との交流関係などを、本作で具体的にで知る機会となった。これはうれしい副産物である。バーナード・リーチのことは、美術館で作品を観た以上のことはほとんど知らなかった。本書を通じて、彼の人柄や彼の人生の一端、日本との関わりを具体的にイメージできるようになった。伝記風アート小説の醍醐味といえる。
本書のタイトルは「リーチ先生」。先生と付くので、バーナード・リーチに対し先生と敬称で呼ぶ人が存在することになる。バーナード・リーチとその人もしくは人々との関係がタイトルそのものに現れている。バーナード・リーチ中心の伝記風小説というよりも、バーナード・リーチと人々との関係の中で、バーナード・リーチ像を浮き彫りにしていくアプローチである。
一方、私は著者は、バーナード・リーチを一方の極にして、他方の極に次のメーッセージにあたる人を共に描き出したいのではないかと受け止めた。
それは、エピローグに出てくる次の文:
「----- 名もなき花。
それは、まさしく父のことだった。
ひっそりとつぼみをつけ、せいいっぱい咲いて、靜かに散っていった野辺の花。
けれど、父は種をまいたのだ。東と西の、それぞれの大地に。
そして、自分は、その種から芽を出したのだ」(p584)
が表象している人と受け止めた。
「名もなき花」と題されたこのエピローグ、涙無しには読み通せなかった。ストーリーの流れに感情移入を深めさせる著者の作品構成と筆致は巧みだなと思う。受賞作になったのもうなずける。
本作のプロローグとエピローグは普通の小説からすると、いわばそれぞれ一章分に近いと思えるボリュームがある。それによって、本作は時間軸の展開が入れ子構造のストーリーとなっている。さらに、その入れ子構造の時間経過に、本作のモチーフの巧みさが組み込まれている。読者を感動させる要因がそこにあり、かつバーナード・リーチの最晩年の一コマを描き出してもいる。
ストーリーの入れ子構造の時間軸の経緯と、最小限の経緯をご紹介する。
<プロローグ 春がきた>
1954年(昭和29年)4月時点。バーナード・リーチが大分県の小鹿田(オンダ)という陶芸を生業とする集落を訪れる。受け入れを坂上一郎が代表として行い、小石原の出自で、坂上一郎を師匠として修行に入り、まだ日の浅い高市(コウイチ)がリーチ先生の世話係となる。リーチ先生は小鹿田に3週間ほど滞在し、陶工の指導と己の作品づくりをする。最初の2日間だけ、河井寛次郎と濱田庄司が同行してきた。
窯の焚き口の近くで、高市はリーチ先生から、父親の名は沖亀乃介かと質問される。
第1章から第5章は、時間軸が明治末近くを起点に始まっていく。
<第1章 僕の先生>
1909年(明治42年)4月時点。横浜の食堂で給仕をしていた14歳の亀乃介が、高村光太郎より差し出された住所を記した紙片をきっかけに、17歳で東京の彫刻家・高村光雲邸の住み込み書生になっているところから始まる。そこに、英国で高村光太郎と知り合ったバーナード・リーチが高村光雲邸を訪ねてくる。リーチと亀乃介の出会い。リーチは芸術において英国と日本の架け橋となりたいという大志を抱いて来日した。確たる方針はないままに。リーチはまずはエッチング教室を始める。亀乃介はこの時点からリーチ先生の弟子となる。
<第2章 白樺の梢、炎の土>
1910年(明治43年)6月時点。リーチのロンドンでの美術学校時代の親友、レジナルド・ターヴィーが、母国へ帰る途中に、来日する。その折り、富本憲吉が帰国途中でターヴィーと交流。それで光雲邸にターヴィーを導くことになる。そこから濱田とリーチならびに亀乃介との交流が始まる。
エッチング教室開催を契機にし、リーチと白樺派を結成した人々との交流が始まる。亀之介は横浜で耳から修得した英語力でリーチ先生の通訳を担当し、白樺派の人々とも知り合う。同人誌「白樺」の編集長を柳宗悦が担当したことで、リーチと柳との交流が始まり、リーチと柳が生涯の友になって行く。その親交の経緯が明らかになる。
リーチと亀乃介は富本憲吉に誘われて芸術家下村某の主催する会で絵付けを体験する。この陶芸初体験が、リーチを陶芸の世界に導く。勿論亀乃介も同席するので、亀之介自身もまた陶芸の魅力に引きこまれていく。
<第3章 太陽と月のはざまで>
1911年(明治44年)7月時点。尾形乾山の6代目を名乗る浦野光山のもとに通い、陶芸を始める。それがろくろの神秘を知る契機に。リーチは七代尾形乾山を襲名するまでに至る。が、その後、リーチは北京に引っ越すという決意に至り、亀乃介に告げる。リーチが日本に戻るまでの顛末が、一つのエピソードとなる。
我孫子の手賀沼を望む高台にある柳宗悦邸に、柳の支援のもとでリーチが工房を構え、庭に窯を完成させる。初めて窯に火を入れた時の状況。濱田庄司がリーチに会いに来る顛末。第11回目の窯焚きで工房が火事となる事態。と、ストーリーは進展していく。
リーチは陶芸の世界に深く入って行くことに。火災の原因となった窯からの作品の取り出し場面が感動的である。
<第4章 どこかに、どこにでも>
1920年(大正9年)6月時点。リーチの滞日11年目。「我孫子窯」の全焼後、黒田清輝子爵の好意を受け、麻布の邸内に、リーチは新たに工房と窯を造り、再スタートする。この頃、柳宗悦は陶器の持つ「用の美」に着目し「民陶」の美を主唱し始めていた。
濱田は「アーツ・アンド・クラフツ」の実践をリーチ先生が実践していると理解していた。「無名」の職人としてではなく「有名」な芸術家として陶芸に取り組んでいるのだと。濱田と亀乃介にとり、リーチは理想の陶芸家だった。
リーチはイギリスに帰国し、イギリスのセント・アイヴスで工房を開くという決断にたどり着く。濱田と亀乃介はリーチに同行し、工房の開設への協力という役割を担うことに。亀乃介はどこまでもリーチ先生の弟子として随行する決意を示す。
セント・アイヴスの西、ランズ・エンドで陶芸創作の根幹となる土を発見するまでの経緯が描かれていく。この陶土発見がやはり感動的な場面である。
<第5章 大きな手>
1920年(大正9年)12月時点。セント・アイヴスでの工房と登り窯の建設から工房での作陶が一応軌道に乗るまでの状況が描かれていく。工房はリーチ・ポタリーと名付けられる。2年で、リーチ・ポタリーは著しく成長し、セント・アイヴスの産業として陶芸が認められるまでになる。リーチは、地元とロンドンで個展を開き、知名度が増していく。
亀之介がセント・アイヴスで心に思うシンシアとやすらぎのある清々しい交際を始める。微笑ましいが哀しくもあるこのエピソードが織り込まれていく。
濱田はロンドンで個展を開き、その作品が認知されるに至る。
1923年秋、河井寛次郎から東京で大震災ありと、ひと言の電報が届く。これを契機として濱田は帰国の決意をする。亀乃介は迷うが、リーチ先生の言葉に押されて、濱田とともに帰国することに・・・・・。
このストーリーが、興味深いと私が思うのは、リーチ先生と柳宗悦、濱田庄司、富本憲吉、河井寛次郎、白樺派の文豪たちとの親交・人間関係を、亀乃介の視点から叙述していりことである。リーチ先生の弟子となった亀乃介が、英語の通訳という役割を介して、これらの人々との人間関係の中に自然に加わり、皆から一員と見做されていく。それ故、亀乃介の思いと視点からの描写に全く違和感がない。リーチ先生と亀乃介の関わりが、リーチの人柄をよりイメージしやすくさせていく。
「本作は史実に基づいたフィクションです」と巻末に明記されている。歴史上で名を残す作家・陶芸家など錚錚たる人々が実名で登場する。その中で、沖亀乃介と息子の高市は、フィクションとしてこのストーリーに織り込まれた人物のようだ。実に大胆な構想と設定だと唸りたくなる。だが、それが実に自然なのだ。リーチにとって欠くことのできない人、日本でのリンキング・ポイントとなっている。バーナード・リーチを西の太陽とすれば、沖亀乃介は東の月。このストーリーで二極を構成していると言える。実在するバーナード・リーチの人生の一側面を伝記風に語りながら、沖亀乃介の人生を描き出している。その亀乃介の思いが息子の高市に引き継がれるという形で・・・・。もう一人沖亀乃介の人生が、伝記風に実に自然にフィクション臭を感じさせずに織り込まれている。あたかもリーチと亀之介が、陶芸という一筋の道を一体として歩んだかのように。日本においてリーチを支えた様々な名も無き人々を一人の人物として著者が創造したのだろうと思う。
エピローグは、エピローグは1979年(昭和54年)4月時点を描いてゆく。上記の引用とこのこと以外は触れないでおこう。
あたかも、このエピローグを描くために、プロローグと第1章~第5章が準備されたとすら感じさせる。感動が湧出してきて、涙せずにはいられなくなった。
亀乃介の視点を介して記されるバーナード・リーチの思いを2つ引用する。
*古きを重んじ、手仕事の中に芸術を見いだす。そういう日本の風土や文化が、イギリスと似通っているのだ、とリーチは言った。 p298
*富本の作品に対してリーチが感じたのは、清潔で、明るく、影のない、前向きな印象。それそのまま、富本自身の性質を映しているかのようだった。
しかしながら、リーチは、自分自身の目指しているのは富本が創るものとは違うのだ、と気がついた。
自分が創りたいのは、何か、もっとあたたかみのあるもの、言葉にはできないような、やわらかく、やさしさのあるもの。富本の創るものにはきっと似ていない。けれど、それでいいのだ。 p305-306
リーチ・ポタリーの隣同士の部屋の薄い壁を介して、濱田と亀乃介が対話する場面で、こんな文章が記されている。本作の根底に流れている思いに重なっていると思う。
*わからないことは、決して恥じることではない。わからないからこそ、わかろうとしてもがく。つかみとろうとして、何度も宙をつかむ。知ろうとして、学ぶ。
わからないことを肯定することから、すべてが始まるのだ。 p502
柳宗悦邸の庭に設けられた我孫子窯で、リーチと亀之介が初めて窯の火焚をして一日目の徹夜をしたときの描写が素敵だと思う。これもご紹介しよう。
*ーーー ああ、なんてきれいなんだろう。
すすで黒くなった顔を空に向けて、亀乃介は息を放った。
新しい空気。新しい朝。新しい一日が、いままさに、始まる瞬間。
静かに昇り始めた太陽と、次にやってくる夜のために休息をとらんと沈みゆく月。
二つが同時に空に浮かぶ、そのはざまに、誰もが立っていた。
かすかに赤く輝く火の粉が、明るくなった空に高々と舞い上がっている。もうもうと黒い煙が太陽と月のはざまに立ち上がっている。 p320
この景色を眺めるのは、リーチと亀乃介、そして柳宗悦、同じく我孫子に住む武者小路実篤と志賀直哉である。
改めて、本作に出てきたバーナード・リーチ、濱田庄司、河井寛次郎、富本憲吉たち陶芸家の作品を間近に鑑賞したくなってきた。さらに、柳宗悦が「用の美」を発見し主唱した「民陶」の作品群を。
ご一読ありがとうございます。
補遺
バーナード・リーチ ウィキペディア
バーナード・リーチ作品 :「日本民藝館」
バーナード・リーチの民藝精神を担う後継者と工房 :「CDC」
セント・アイヴス :ウィキペデキア
柳宗悦 :ウィキペデキア
民藝運動の父、柳宗悦 :「日本民藝協会」
柳宗悦と日本民藝館 :「日本民藝館」
思想家紹介 柳宗悦 :「京都大学大学院文学研究科・文学部」
濱田庄司記念益子参考館 ホームページ
濱田庄司 :ウィキペディア
濱田庄司作品 :「日本民藝館」
濱田庄司の略年表 :「とちぎふるさと学習」
旧濱田庄司邸 :「益子陶芸美術館」
富本憲吉 :ウィキペデキア
陶芸家 富本憲吉作品コレクション :「奈良県」
富本憲吉《色絵金銀彩四弁花染付風景文字模様壺》1957年 YouTube
民藝~濱田庄司、富本憲吉、バーナードリーチ・用の美を極めた作品を紹介 YouTube
河井寬次郎記念館 ホームページ
河井寬次郎 :ウィキペデキア
「河井寛次郎記念館」民藝はじまりの地、京都で訪れたい聖地へ:「Discover Japan」
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
私は京都近代国立美術館で、河井寛次郎、富本憲吉、濱田庄司の作品を幾度も見ている間に、バーナード・リーチの作品も見る機会があり、その名を記憶した。陶芸家の彼らの間に交流があったことを知ったが、それ以上の人間関係などについて意識しなかった。
私にとっては、彼ら相互間の人間関係や親交の経緯、さらに柳宗悦や白樺派との交流関係などを、本作で具体的にで知る機会となった。これはうれしい副産物である。バーナード・リーチのことは、美術館で作品を観た以上のことはほとんど知らなかった。本書を通じて、彼の人柄や彼の人生の一端、日本との関わりを具体的にイメージできるようになった。伝記風アート小説の醍醐味といえる。
本書のタイトルは「リーチ先生」。先生と付くので、バーナード・リーチに対し先生と敬称で呼ぶ人が存在することになる。バーナード・リーチとその人もしくは人々との関係がタイトルそのものに現れている。バーナード・リーチ中心の伝記風小説というよりも、バーナード・リーチと人々との関係の中で、バーナード・リーチ像を浮き彫りにしていくアプローチである。
一方、私は著者は、バーナード・リーチを一方の極にして、他方の極に次のメーッセージにあたる人を共に描き出したいのではないかと受け止めた。
それは、エピローグに出てくる次の文:
「----- 名もなき花。
それは、まさしく父のことだった。
ひっそりとつぼみをつけ、せいいっぱい咲いて、靜かに散っていった野辺の花。
けれど、父は種をまいたのだ。東と西の、それぞれの大地に。
そして、自分は、その種から芽を出したのだ」(p584)
が表象している人と受け止めた。
「名もなき花」と題されたこのエピローグ、涙無しには読み通せなかった。ストーリーの流れに感情移入を深めさせる著者の作品構成と筆致は巧みだなと思う。受賞作になったのもうなずける。
本作のプロローグとエピローグは普通の小説からすると、いわばそれぞれ一章分に近いと思えるボリュームがある。それによって、本作は時間軸の展開が入れ子構造のストーリーとなっている。さらに、その入れ子構造の時間経過に、本作のモチーフの巧みさが組み込まれている。読者を感動させる要因がそこにあり、かつバーナード・リーチの最晩年の一コマを描き出してもいる。
ストーリーの入れ子構造の時間軸の経緯と、最小限の経緯をご紹介する。
<プロローグ 春がきた>
1954年(昭和29年)4月時点。バーナード・リーチが大分県の小鹿田(オンダ)という陶芸を生業とする集落を訪れる。受け入れを坂上一郎が代表として行い、小石原の出自で、坂上一郎を師匠として修行に入り、まだ日の浅い高市(コウイチ)がリーチ先生の世話係となる。リーチ先生は小鹿田に3週間ほど滞在し、陶工の指導と己の作品づくりをする。最初の2日間だけ、河井寛次郎と濱田庄司が同行してきた。
窯の焚き口の近くで、高市はリーチ先生から、父親の名は沖亀乃介かと質問される。
第1章から第5章は、時間軸が明治末近くを起点に始まっていく。
<第1章 僕の先生>
1909年(明治42年)4月時点。横浜の食堂で給仕をしていた14歳の亀乃介が、高村光太郎より差し出された住所を記した紙片をきっかけに、17歳で東京の彫刻家・高村光雲邸の住み込み書生になっているところから始まる。そこに、英国で高村光太郎と知り合ったバーナード・リーチが高村光雲邸を訪ねてくる。リーチと亀乃介の出会い。リーチは芸術において英国と日本の架け橋となりたいという大志を抱いて来日した。確たる方針はないままに。リーチはまずはエッチング教室を始める。亀乃介はこの時点からリーチ先生の弟子となる。
<第2章 白樺の梢、炎の土>
1910年(明治43年)6月時点。リーチのロンドンでの美術学校時代の親友、レジナルド・ターヴィーが、母国へ帰る途中に、来日する。その折り、富本憲吉が帰国途中でターヴィーと交流。それで光雲邸にターヴィーを導くことになる。そこから濱田とリーチならびに亀乃介との交流が始まる。
エッチング教室開催を契機にし、リーチと白樺派を結成した人々との交流が始まる。亀之介は横浜で耳から修得した英語力でリーチ先生の通訳を担当し、白樺派の人々とも知り合う。同人誌「白樺」の編集長を柳宗悦が担当したことで、リーチと柳との交流が始まり、リーチと柳が生涯の友になって行く。その親交の経緯が明らかになる。
リーチと亀乃介は富本憲吉に誘われて芸術家下村某の主催する会で絵付けを体験する。この陶芸初体験が、リーチを陶芸の世界に導く。勿論亀乃介も同席するので、亀之介自身もまた陶芸の魅力に引きこまれていく。
<第3章 太陽と月のはざまで>
1911年(明治44年)7月時点。尾形乾山の6代目を名乗る浦野光山のもとに通い、陶芸を始める。それがろくろの神秘を知る契機に。リーチは七代尾形乾山を襲名するまでに至る。が、その後、リーチは北京に引っ越すという決意に至り、亀乃介に告げる。リーチが日本に戻るまでの顛末が、一つのエピソードとなる。
我孫子の手賀沼を望む高台にある柳宗悦邸に、柳の支援のもとでリーチが工房を構え、庭に窯を完成させる。初めて窯に火を入れた時の状況。濱田庄司がリーチに会いに来る顛末。第11回目の窯焚きで工房が火事となる事態。と、ストーリーは進展していく。
リーチは陶芸の世界に深く入って行くことに。火災の原因となった窯からの作品の取り出し場面が感動的である。
<第4章 どこかに、どこにでも>
1920年(大正9年)6月時点。リーチの滞日11年目。「我孫子窯」の全焼後、黒田清輝子爵の好意を受け、麻布の邸内に、リーチは新たに工房と窯を造り、再スタートする。この頃、柳宗悦は陶器の持つ「用の美」に着目し「民陶」の美を主唱し始めていた。
濱田は「アーツ・アンド・クラフツ」の実践をリーチ先生が実践していると理解していた。「無名」の職人としてではなく「有名」な芸術家として陶芸に取り組んでいるのだと。濱田と亀乃介にとり、リーチは理想の陶芸家だった。
リーチはイギリスに帰国し、イギリスのセント・アイヴスで工房を開くという決断にたどり着く。濱田と亀乃介はリーチに同行し、工房の開設への協力という役割を担うことに。亀乃介はどこまでもリーチ先生の弟子として随行する決意を示す。
セント・アイヴスの西、ランズ・エンドで陶芸創作の根幹となる土を発見するまでの経緯が描かれていく。この陶土発見がやはり感動的な場面である。
<第5章 大きな手>
1920年(大正9年)12月時点。セント・アイヴスでの工房と登り窯の建設から工房での作陶が一応軌道に乗るまでの状況が描かれていく。工房はリーチ・ポタリーと名付けられる。2年で、リーチ・ポタリーは著しく成長し、セント・アイヴスの産業として陶芸が認められるまでになる。リーチは、地元とロンドンで個展を開き、知名度が増していく。
亀之介がセント・アイヴスで心に思うシンシアとやすらぎのある清々しい交際を始める。微笑ましいが哀しくもあるこのエピソードが織り込まれていく。
濱田はロンドンで個展を開き、その作品が認知されるに至る。
1923年秋、河井寛次郎から東京で大震災ありと、ひと言の電報が届く。これを契機として濱田は帰国の決意をする。亀乃介は迷うが、リーチ先生の言葉に押されて、濱田とともに帰国することに・・・・・。
このストーリーが、興味深いと私が思うのは、リーチ先生と柳宗悦、濱田庄司、富本憲吉、河井寛次郎、白樺派の文豪たちとの親交・人間関係を、亀乃介の視点から叙述していりことである。リーチ先生の弟子となった亀乃介が、英語の通訳という役割を介して、これらの人々との人間関係の中に自然に加わり、皆から一員と見做されていく。それ故、亀乃介の思いと視点からの描写に全く違和感がない。リーチ先生と亀乃介の関わりが、リーチの人柄をよりイメージしやすくさせていく。
「本作は史実に基づいたフィクションです」と巻末に明記されている。歴史上で名を残す作家・陶芸家など錚錚たる人々が実名で登場する。その中で、沖亀乃介と息子の高市は、フィクションとしてこのストーリーに織り込まれた人物のようだ。実に大胆な構想と設定だと唸りたくなる。だが、それが実に自然なのだ。リーチにとって欠くことのできない人、日本でのリンキング・ポイントとなっている。バーナード・リーチを西の太陽とすれば、沖亀乃介は東の月。このストーリーで二極を構成していると言える。実在するバーナード・リーチの人生の一側面を伝記風に語りながら、沖亀乃介の人生を描き出している。その亀乃介の思いが息子の高市に引き継がれるという形で・・・・。もう一人沖亀乃介の人生が、伝記風に実に自然にフィクション臭を感じさせずに織り込まれている。あたかもリーチと亀之介が、陶芸という一筋の道を一体として歩んだかのように。日本においてリーチを支えた様々な名も無き人々を一人の人物として著者が創造したのだろうと思う。
エピローグは、エピローグは1979年(昭和54年)4月時点を描いてゆく。上記の引用とこのこと以外は触れないでおこう。
あたかも、このエピローグを描くために、プロローグと第1章~第5章が準備されたとすら感じさせる。感動が湧出してきて、涙せずにはいられなくなった。
亀乃介の視点を介して記されるバーナード・リーチの思いを2つ引用する。
*古きを重んじ、手仕事の中に芸術を見いだす。そういう日本の風土や文化が、イギリスと似通っているのだ、とリーチは言った。 p298
*富本の作品に対してリーチが感じたのは、清潔で、明るく、影のない、前向きな印象。それそのまま、富本自身の性質を映しているかのようだった。
しかしながら、リーチは、自分自身の目指しているのは富本が創るものとは違うのだ、と気がついた。
自分が創りたいのは、何か、もっとあたたかみのあるもの、言葉にはできないような、やわらかく、やさしさのあるもの。富本の創るものにはきっと似ていない。けれど、それでいいのだ。 p305-306
リーチ・ポタリーの隣同士の部屋の薄い壁を介して、濱田と亀乃介が対話する場面で、こんな文章が記されている。本作の根底に流れている思いに重なっていると思う。
*わからないことは、決して恥じることではない。わからないからこそ、わかろうとしてもがく。つかみとろうとして、何度も宙をつかむ。知ろうとして、学ぶ。
わからないことを肯定することから、すべてが始まるのだ。 p502
柳宗悦邸の庭に設けられた我孫子窯で、リーチと亀之介が初めて窯の火焚をして一日目の徹夜をしたときの描写が素敵だと思う。これもご紹介しよう。
*ーーー ああ、なんてきれいなんだろう。
すすで黒くなった顔を空に向けて、亀乃介は息を放った。
新しい空気。新しい朝。新しい一日が、いままさに、始まる瞬間。
静かに昇り始めた太陽と、次にやってくる夜のために休息をとらんと沈みゆく月。
二つが同時に空に浮かぶ、そのはざまに、誰もが立っていた。
かすかに赤く輝く火の粉が、明るくなった空に高々と舞い上がっている。もうもうと黒い煙が太陽と月のはざまに立ち上がっている。 p320
この景色を眺めるのは、リーチと亀乃介、そして柳宗悦、同じく我孫子に住む武者小路実篤と志賀直哉である。
改めて、本作に出てきたバーナード・リーチ、濱田庄司、河井寛次郎、富本憲吉たち陶芸家の作品を間近に鑑賞したくなってきた。さらに、柳宗悦が「用の美」を発見し主唱した「民陶」の作品群を。
ご一読ありがとうございます。
補遺
バーナード・リーチ ウィキペディア
バーナード・リーチ作品 :「日本民藝館」
バーナード・リーチの民藝精神を担う後継者と工房 :「CDC」
セント・アイヴス :ウィキペデキア
柳宗悦 :ウィキペデキア
民藝運動の父、柳宗悦 :「日本民藝協会」
柳宗悦と日本民藝館 :「日本民藝館」
思想家紹介 柳宗悦 :「京都大学大学院文学研究科・文学部」
濱田庄司記念益子参考館 ホームページ
濱田庄司 :ウィキペディア
濱田庄司作品 :「日本民藝館」
濱田庄司の略年表 :「とちぎふるさと学習」
旧濱田庄司邸 :「益子陶芸美術館」
富本憲吉 :ウィキペデキア
陶芸家 富本憲吉作品コレクション :「奈良県」
富本憲吉《色絵金銀彩四弁花染付風景文字模様壺》1957年 YouTube
民藝~濱田庄司、富本憲吉、バーナードリーチ・用の美を極めた作品を紹介 YouTube
河井寬次郎記念館 ホームページ
河井寬次郎 :ウィキペデキア
「河井寛次郎記念館」民藝はじまりの地、京都で訪れたい聖地へ:「Discover Japan」
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)