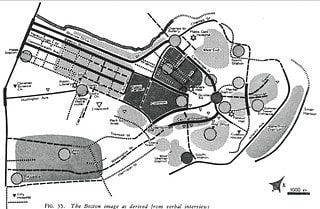いつの頃からか、日本の大学の建築教育でも「コンセプト」「コンセプト」って言うよう
になってしまって、、、、コンセプト(concept)って、僕らの頭の中では「概念」って事
になっていると思うんですけど、僕がこの言葉を始めて聞いたのは、車の設計(つまり、
デザインのこと。)の時に、これから設計する車がどんな車か、つまり力を受ける鋼板の
隔壁によって、その車の内部空間がいくつに仕切られるのか、0(ゼロ)で一つならワンボ
ックス(1BOX、最近はモノボリュームとも言うようです。)、1枚で2つに区切られるなら
ツーボックス(2BOX、ハッチバック?)、以下2枚で3っつに区切られるならスリーボックス
(3BOX、いわゆるノッチバックのセダン)、3枚で区切られた車はあまり見た事ない、、、
を、何人かの人や組織でで設計や議論する時、(または一人でも自分のやっている作業を
確認しながら進める時)に、お互い解かり易くして確認しあいながら(あとで「こんなつも
りんで考えていたんじゃない」みたいに、混乱したりしないように)作業を進める時の確
認事項のようなものだったのではないのかな?(このコンセプトが曖昧だと、ピラーレスの
ハードトップクーペとか、訳のワカンナイ車が出来ちゃったりするのかも、、、、あとは
他の人に説明する時に、お互い勘違いせずに、伝わりやすくて便利とか、、、、、)とこ
ろが、conceptのもう一つの名詞形にconceptionと言うのがあって、こちらは「概念」以
外に「着想」、特に「妊娠、受胎」と言う意味があって、これなら合点がいくのです。
(今現在の巷の使われ方は、、、、日本人は器用で頭が良いから無意識の上で、こちらの
意味で使っているのかも、、、、)
昔、函館の地元のハウスメーカーの社長さんから、その当時、函館に進出してきた某大手
ハウスメーカーのプランニングしてみませんかと言われて打ち合わせに行ったら、若い
営業の方から、いきなり「このプランのコンセプトを説明しろ」って言われて、こちらも
根性が悪いから、「コンセプト?そんなものありません。」って即答したら、(100のプラ
ンがあって、100のコンセプトがある訳ないじゃありませんか、こっちは、ただ「ひらめ
いて」描いているだけなんです、、、。)次から、仕事は来なくなりました。(その某大
手ハウスメーカーは、ほどなくして営業成績が思わしくなかったのか、函館から撤退し
てしまいました。)
写真は、残念ながら日本未導入のルノーのモデュス(modus)という車のカットモデル風の
透視図。(この車のコンセプトは2BOXの5doorハッチバックです。)

これでMTならば実に好ましい小型乗用車です。ルノーならシートも良いだろうし、、、
ルノー・ジャポンさん、お願いだから、5doorのMTの、こういう車を輸入して!RSとか
ゴルディーヌとかは要らないの。普通でいいの。