『同じ状況で前向きに進んでいく人がいる一方で、希望を失ってしまう人がいる理由は文字通り「異なる現実」を生きているからである。・・・人々の「現実」つまりそれを通して世の中を見るレンズ全体を、根本から変化させる方法を理解してもらう必要がある・・・・真の変化が可能だと信じることによって、自分の持つ認知的、知的、感情的リソースを引き出し、ポジティブな変化を生じさせるということである。』
多分、これがコアというか、overviewというか、この本の目的なんだと思います。
もっと短くすると「異なる現実」に見えるのはレンズが違うからでそれはどう認知するかということなんですかね。
『人間の脳は栄養が不足すると疲労し、脅威に対する警告を発し、ネガティブな事柄だけに注目して記憶する傾向がある』
ただ短絡的に考えていけないのは血糖値を常に高くしようとして間食ばかりしていると今度は糖の代謝に問題が出たり、肥満傾向が強くなったりしますし、血糖値が高いと成長ホルモンが分泌されないので細胞やキズが修復されず別のもっとひどい問題がでてきます。
なので、重要事項を決定する時は時間帯を選んだ方が良さそうです。
さらに脳が疲れている時に注意を受けたりするとちょっとしたことがひどく絶望的に感じられるのはこういうところがあるのかもしれません。
ここから回復する方法の一つは幸福優位7つの法則の法則7 ソーシャルへの投資 ー 周囲からの支えを唯一最高の資産とする ですね。ひととのキズナに投資すれば、逆境を成長の機会や新たなチャンスととらえられるようになる。そして本当にストレスに襲われたときも、そこからすみやかに立ち直り、そのストレスがネガティブな影響を後まで残さないように自分を守ることができるとあります。まぁ、仲間を増やせということです。
そして、これも選択性があります。キライな人と無理に付き合う必要もないでしょう。
『遠近感は細部に宿る』
イェール大学の医科大学では学生たちを研修中に美術館に連れていき、奥行きのあるバランスのとれた見方(パースペクティブ)の重要性を教えることで視点を増やす訓練をしているらしい。
広範囲にわたり細部を見られるようになった学生は・・・認知能力が向上し、それらの細部(ものの見方が広がる多様な点)を組み合わせて今まで見逃していた関係に気づくようになる。
1日の午後の時間を使っていくのだそうです。美術鑑賞は拡散系なので、午前中はやっぱり集中系の学習でしょう。













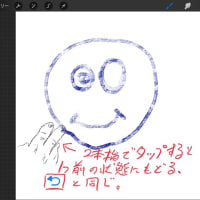

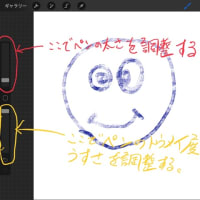




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます