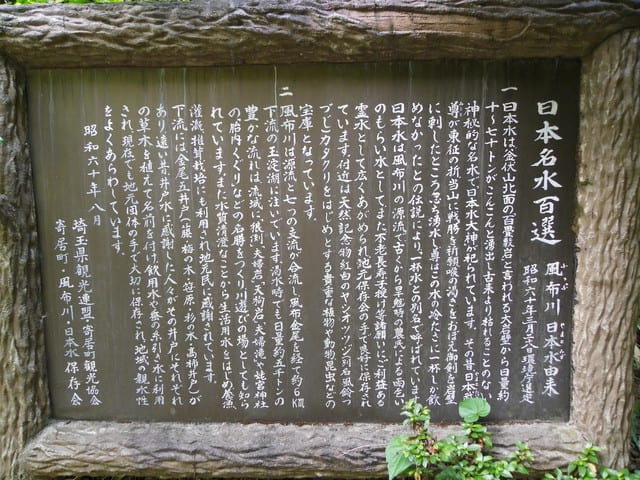本日は、旧妻沼町永井太田にある古刹、能護寺について書きたいと思います。
妻沼のアジサイ寺として知られる能護寺は、解説によれば、天平15年(743年)に行基によって開山され、
後に弘法大師空海により再建されたと伝えられています。
妻沼の歓喜院は、この能護寺の末寺だったということで、その格式の高さがしのばれます。
実は、うちの父は、30年ほど前、このお寺さんのご住職に親しくさせていただいておりました。
有名になったアジサイも、時のご住職が熱心に手入れをなさっていたものです。



現在の本堂は文化11年(1814年)に再建されたものだそうです。


この辺りは利根川の水害が多く、近くには堤防決壊時に出来た沼が残っています。
鐘楼は修復中でした。
鐘楼の鐘は、元禄14年(1701年)に鋳造されたそうで、熊谷市の文化財になっています。

御朱印をやっているそうです。
妻沼のアジサイ寺として知られる能護寺は、解説によれば、天平15年(743年)に行基によって開山され、
後に弘法大師空海により再建されたと伝えられています。
妻沼の歓喜院は、この能護寺の末寺だったということで、その格式の高さがしのばれます。
実は、うちの父は、30年ほど前、このお寺さんのご住職に親しくさせていただいておりました。
有名になったアジサイも、時のご住職が熱心に手入れをなさっていたものです。



現在の本堂は文化11年(1814年)に再建されたものだそうです。


この辺りは利根川の水害が多く、近くには堤防決壊時に出来た沼が残っています。
鐘楼は修復中でした。
鐘楼の鐘は、元禄14年(1701年)に鋳造されたそうで、熊谷市の文化財になっています。

御朱印をやっているそうです。