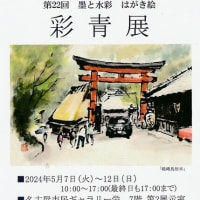先日のブログにも載せましたが、僕は名古屋市内と岡崎市内で開催されている「あいちトリエンナーレ2013」(10月27日まで)の会場巡りを楽しんでいます。「揺れる大地 われわれはどこに立っているのか 場所、記憶、そして復活」。この重いテーマを作家たちはどうとらえ、表現しているのか。まだ全ての作品を見たわけではありませんが、世界的アーティストだけに「僕の目と足と時間をとめる作品」にいくつも出会いました。
《原発事故・大震災へのメッセージ》
そのひとつは、愛知県美術館のある県芸術文化センター会場の映像インスタレーション「フィンランドで最も電化した町」(ミカ・ターニラ)。チェルノブイリ原発事故後、欧州では初の原発建設再開(2015年に完成予定)となったフィンランドの小さな町での建設現場を、10年近くにわたってフィルムに収めています。
3面スクリーンに淡々と映し出される巨大な建屋、原子炉、発電装置を組み立てていく大型クレーンと忙しく働く作業員たち、現場を無言で見守る住民・・・。
ターニラは、この作品を原発に対する賛否をはっきりさせずに制作しています。そのことが見る側に国家、経済、地域の暮らしなど、原子力エネルギーをめぐる問題を、より深く、重く受け止めさせます。
※インスタレーション(installation)=現代美術の表現手法のひとつ。作品を場所や状況など展示環境と関連づけて表現することで、全体を芸術的空間とする。
縮尺模型の原子炉建屋に和風屋根を載せた「福島第1原発神社」と、芸文センターに同様の屋根をかぶせた「福島第一さかえ原発」(宮本佳明)も傑作です。遠い将来まで神社、あるいは廟として祀る、という訳です。
さらに、東日本大震災で避難した多くの家族たちが段ボールで仕切られた空間で生活する光景を再現した「段ボールの壁」。
どちらも、「私たちは原発事故や大震災という事実を過去のものにすることなく、背負い続けていかねばならない」というメッセージが伝わってきます。
《国家・戦争・民主主義・環境・・・・》
同じく芸文センターで展示されている絵画「ころがるさくら・東京大空襲」(岡本信治郎)も、決して風化させてはならない、というメッセージを突き付けられます。1933年生まれの岡本が12歳で出くわした大空襲。独学で画家を志してからのモチーフでしたが、ニューヨークの9・11テロで封印していたという作品です。絵には歴史上のあれこれなどが書き込まれ、見ごたえ、読みごたえのあるエネルギッシュな創作に驚きます。
堀川運河沿いにある納屋橋会場の大きな倉庫に展示されたインスタレーション「戦後」(クリスティーナ・ノルマン)も印象的。ソ連崩壊後に独立したエストニアで、エストニア人にとっては占領・抑圧のシンボル、ロシア人にとってはナチズム対する勝利のシンボルである銅像をめぐる作品です。
銅像は2007年にエストニア政府が首都タリンの中心部から移動させましたが、作者は2年後にその原寸大のレプリカを銅像があった元の場所に持ち込み、集まってきた人たちの議論を通して民主主義、国家、外国人に対する嫌悪・恐れなどなどをレプリカと映像で表現しています。
<o:p></o:p>
岡崎市の康生会場には、ダンボール箱や写真映像などで迷路のような街が造られていました。作者のバシーア・マクールはパレスチナ人。アラブの街、難民キャンプのような中を歩くと、国家、宗教、戦争、経済、貧困などの現実を考えずにはおれません。<o:p></o:p>
東岡崎駅の会場では、ごみ処理場へ送られる大量の衣類を使って制作したオブジェが、消費や環境問題を問いかけています。
《まちなかアート》
名古屋の長者町会場は、いくつもの店がトリエンナーレに協力する「まちなか会場」です。地元の若いアーティストたちの作品に「あいちトリエンナーレの今後は、彼らの活動にかかっている」と思いました。
この会場で道行く人の話題になっているのが、作業員がハシゴを使って電線工事をする様子をビルの3面に描いた壁画。僕もカメラを向けました。
最寄りの地下鉄伏見駅地下街に描かれたトリックアートといえる階段や、展示されているウランガラスの金魚はお見事。長者町界隈の変化でャッターの目立つ地下街ですが、こうしたアートで通行人を呼び戻せれば、と願いつつ喫茶店で一休みした次第です。
公園の中にある名古屋市美術館では、これからの街づくりや建築をテーマにした作品などが展示されています。
岡崎の松本会場は、懐かしい木造アーケードや小路が入り組み、展示スペースも広くありませんが、会場自体がアートともいえる一角。古い空き家の土間に立ち、狭い階段を上り下りして出会う作品は、じっくり考えるひとときを与えてくれました。
※映像や撮影禁止の作品以外で、写真にした作品のいくつかを掲載します。クリックしていただくと大きくなります。








<o:p></o:p>