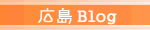今回は、急いでいたので、近場の三十三間堂へ行きました!

正式名は蓮華王院。その本堂は、通称「三十三間堂」とよばれています。それは、南北に延びる御堂の内陣の柱と柱が33間あることから「三十三間堂」とよばれているのです。
平安時代後期、約30年の間、院政を行った後白河上皇が、当時権勢を誇った平清盛の資材協力によって創建されました。
しかし、80年後に焼失し、まもなく後嵯峨上皇によって再建されました 。
鎌倉時代の仏師、湛慶が手がけた木造千手観音坐像、俵屋宗達の『風神雷神図屏風』のモデルになったとも言われる木造
風神・雷神像、木造二十八部衆立像が国宝に指定され、左右に合わせて千体並ぶ千手観音立像、南大門、太閤塀は重要
文化財に指定されている。
1,000体の千手観音立像は圧巻です。厳かな中を一歩一歩進みました。

内陣の後ろ堂です。

境内のさくらです。


次は、おとなりの養源院を拝観しました。
豊臣秀吉の側室・淀殿が、父・浅井長政の追善供養のため、21回忌法要の時に創建した寺。
一度は焼失したが、淀殿の妹で、徳川秀忠の夫人であったお江(おごう)の方の願いにより、伏見城の遺構を移築して再興さ
れた。以降、徳川家の菩提所となり、2代秀忠から15代慶喜まで徳川幕府歴代将軍の位牌が祀られている。
本堂の廊下の天井は有名な「血天井」。
また、俵屋宗達が描いた襖絵「松図」や、白象、唐獅子、麒麟を描いた杉戸絵(重要文化財)が有名。
実物をみることが出来、満足しました。

しだれ桜の開花は、もう少し、先のようです。残念!



境内のさくらは満開でした。

川沿いのさくらがとてもきれいでした。