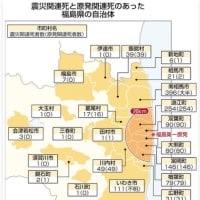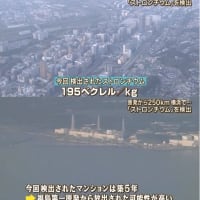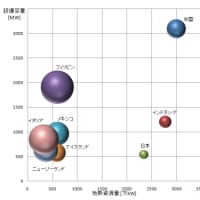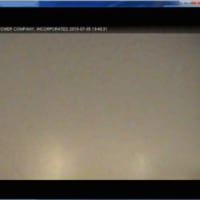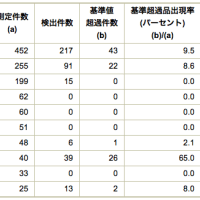一昨日、目の保養も兼ねて、シンワアートオークションの会場にのこのこ出かけて行きました。天気はうっすらと曇ったはっきりしない日の午後でした。会場では、いつものようにTさんが親切に案内してくださいました(私は客と言えるような身分じゃないんですけど)。1階のフロアには、大家というか大御所の日本画家の名品(優品)がズラリときれいに展示されていました。目の保養には申し分ないボリュームというかさすがにシンワはちょっと格が違うなと、私は率直に感じました(誤解しないでほしいのですが、人それぞれ、いろんな意味で立場の違いも含めて美術作品を観る上で、『ある基準』がありますからね)。
安田靫彦先生の『つばき鶯』という題の日本画が、私の眼には一番魅力的に映りました。小林古径先生の『春宵』というフクロウを描いた絵も妙に琴線に触れる優品だと思います。地下1階の油彩画では、安井曽太郎先生の『風景』がダントツにいいですね。空間構成はほぼ完璧で独特のリズム感というか生命の躍動を感じる名品だと思いました(額縁はちょっと・・・)。向井潤吉先生の1940年、第27回二科展出品作品である『豆満江畔』という大作は、いわゆる珍品に属すると思うのですが、民家をモチーフにした画家としてつとに有名な向井潤吉先生の若き日の力作ですね(見識のある美術館が是非ビットしてほしいと思います)。
率直に会場を見て回って思うことは、時節柄、エスティメイトがかなり低く設定されている、ということです。プライスのことについては、いずれ別の機会に触れたいと思います。
(いわゆる近代日本画、洋画というジャンルの絵画作品の著しい値崩れ、というか崩壊に近い現象について、私のようなド素人が論評するのもいかがなものか、と自戒の念を込めながらこの文章を綴っています。)
数年前にある事情通の人から教えてもらったのですけども(真偽のほどはわかりませんが、たぶんあり得る話だと私は判断しています)、ある著名なSという写真家が、近代日本画を密かに体系的にコレクションし続けているという話を私は小耳に挟みました。その話を聞いた時に、なるほど!流石だな、とSさんのことを思いましたね。日本美術史を俯瞰してパースペクティブに物事を捉える、あるいは日本美術史を遡及し、美術作品を本来あるべき正しい位置というかポジションに据え置き、いわゆる現代美術の領域にまで繋げていく崇高な行為は、Sさんのような写真家(あまりにも裕福な、且つ審美眼と洞察力の確かさ、磨き抜かれたセンスの良さを兼ね備えている人物)にしか実現できない正しい行為(美しすぎる出来事)なのだと私は思うのですけど・・・



(写真は携帯電話で撮ったのであまり上手くいきませんでした・・作品を目の前にすると素晴らしかったので、興味のある方は、会場に行かれるか、カタログを見てくださいね。)
安田靫彦先生の『つばき鶯』という題の日本画が、私の眼には一番魅力的に映りました。小林古径先生の『春宵』というフクロウを描いた絵も妙に琴線に触れる優品だと思います。地下1階の油彩画では、安井曽太郎先生の『風景』がダントツにいいですね。空間構成はほぼ完璧で独特のリズム感というか生命の躍動を感じる名品だと思いました(額縁はちょっと・・・)。向井潤吉先生の1940年、第27回二科展出品作品である『豆満江畔』という大作は、いわゆる珍品に属すると思うのですが、民家をモチーフにした画家としてつとに有名な向井潤吉先生の若き日の力作ですね(見識のある美術館が是非ビットしてほしいと思います)。
率直に会場を見て回って思うことは、時節柄、エスティメイトがかなり低く設定されている、ということです。プライスのことについては、いずれ別の機会に触れたいと思います。
(いわゆる近代日本画、洋画というジャンルの絵画作品の著しい値崩れ、というか崩壊に近い現象について、私のようなド素人が論評するのもいかがなものか、と自戒の念を込めながらこの文章を綴っています。)
数年前にある事情通の人から教えてもらったのですけども(真偽のほどはわかりませんが、たぶんあり得る話だと私は判断しています)、ある著名なSという写真家が、近代日本画を密かに体系的にコレクションし続けているという話を私は小耳に挟みました。その話を聞いた時に、なるほど!流石だな、とSさんのことを思いましたね。日本美術史を俯瞰してパースペクティブに物事を捉える、あるいは日本美術史を遡及し、美術作品を本来あるべき正しい位置というかポジションに据え置き、いわゆる現代美術の領域にまで繋げていく崇高な行為は、Sさんのような写真家(あまりにも裕福な、且つ審美眼と洞察力の確かさ、磨き抜かれたセンスの良さを兼ね備えている人物)にしか実現できない正しい行為(美しすぎる出来事)なのだと私は思うのですけど・・・



(写真は携帯電話で撮ったのであまり上手くいきませんでした・・作品を目の前にすると素晴らしかったので、興味のある方は、会場に行かれるか、カタログを見てくださいね。)