上野市街地に住む身には、体に馴染んでるというか耳に馴染んでるというか、
さすがに「いつからミュージックサイレンが鳴っていたのか」記憶にはなかった。
このYouさんの記事を読んで、“1959年”からかぁ~~、人生のほとんどの日々に時計代わりに聞いていたのだなぁ、、、
(ワタシ、1954年生なのですが、昔は「産業会館」から聞こえていたような記憶があるのです、みなさんの記憶はいかがでしょう??)
 情報You (570号)
情報You (570号)
(2009.9.22)以下のような思い出を綴りました。
【我らの芭蕉さん
物心付いた頃から「芭蕉さん」と呼び、夏休みの宿題には「俳句」がつきもの。「芭蕉祭」が近づくと小学校や中学校では「芭蕉さんをしのぶ学校行事」が行われ、
♪斉唱曲「芭蕉さん」(小学生向き)

♪合唱曲「芭蕉翁讃歌」(中学生向き)

♪混声合唱曲「芭蕉」(一般)
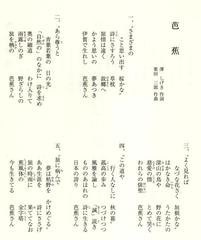
ちなみに、この曲の冒頭の「さまざまの こと思い出す 桜かな」のメロディーは、上野市街地に流れる正午のミュージックサイレンにも使われています。(伊賀市役所から流れるメロディー付きサイレンです。)
その楽譜

♪混声合唱組曲「奥の細道」(一般)

などを歌い継いできました。
親から子へ、子から孫へと歌い継がれる「芭蕉さんの歌」があるのは、きっとここ伊賀だけではないのかな・・・と思います。
伊賀の子供たちの間では、10月になるとどこからか「♪あ~ゝ、ばしょうさん♪」という歌声が聞こえるし、大人になってもすぐに歌うことができる。
これは素晴らしい伝統だと思う。
ミュージックサイレンのことを書いたので、参考までに
♪午前7時の曲は、ビゼー作曲「ペールギュント組曲」より【朝】のテーマ
♪正午は合唱曲「芭蕉」より【さまざまの】
♪午後6時は、ドボルザーク作曲「交響曲・新世界」から【第2楽章・家路より】のテーマ
♪午後10時は、ブラームス作曲【子守唄】 でした。】
2011年12月現在、午後6時の「家路より」は聴くことはできません
その昔、このサイレンをきいて子どもたちは三々五々家路につきました・・・
今は午後5時に、防災無線が「七つの子」を奏でますが、外で遊ぶ子どもたちはいるんだろうか
雑感、芭蕉さんのことを書いたついでにふと思った。
「新芭蕉記念館」って、ほんまに必要なんやろか? 我らの芭蕉さんはそんなこと願ってるんやろか?
後生大事に守り伝えたい歴史資料を、、、きちんと保管したい!そのための「蔵」がほしい!それだけの素朴な想いではないのでしょうか。
誰がこの記念館に「年間○○万人の観光客を望む」のでしょうか?
伊賀市全体の観光客は如何ほどか、年々下降していることをご存知ではないのか!?
それとも芭蕉さんを利用して“起死回生・観光客奪還計画”を狙っているのでしょうか?
まちなかのそこかしこにある「芭蕉さんの軌跡」を歩くだけではいけませんか?
静かなまちを、静かに散策して芭蕉さんを偲ぶ、そして「俳句」を創る。
時折「NINJA」が大活躍する季節もある!
それが「秘蔵の国」。
そんな城下町ではだめなんかなぁ と、(勝手に)思うわけです、、、
と、(勝手に)思うわけです、、、
さすがに「いつからミュージックサイレンが鳴っていたのか」記憶にはなかった。
このYouさんの記事を読んで、“1959年”からかぁ~~、人生のほとんどの日々に時計代わりに聞いていたのだなぁ、、、
(ワタシ、1954年生なのですが、昔は「産業会館」から聞こえていたような記憶があるのです、みなさんの記憶はいかがでしょう??)
 情報You (570号)
情報You (570号)(2009.9.22)以下のような思い出を綴りました。
【我らの芭蕉さん
物心付いた頃から「芭蕉さん」と呼び、夏休みの宿題には「俳句」がつきもの。「芭蕉祭」が近づくと小学校や中学校では「芭蕉さんをしのぶ学校行事」が行われ、
♪斉唱曲「芭蕉さん」(小学生向き)

♪合唱曲「芭蕉翁讃歌」(中学生向き)

♪混声合唱曲「芭蕉」(一般)
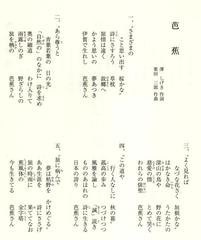
ちなみに、この曲の冒頭の「さまざまの こと思い出す 桜かな」のメロディーは、上野市街地に流れる正午のミュージックサイレンにも使われています。(伊賀市役所から流れるメロディー付きサイレンです。)
その楽譜

♪混声合唱組曲「奥の細道」(一般)

などを歌い継いできました。
親から子へ、子から孫へと歌い継がれる「芭蕉さんの歌」があるのは、きっとここ伊賀だけではないのかな・・・と思います。
伊賀の子供たちの間では、10月になるとどこからか「♪あ~ゝ、ばしょうさん♪」という歌声が聞こえるし、大人になってもすぐに歌うことができる。
これは素晴らしい伝統だと思う。
ミュージックサイレンのことを書いたので、参考までに
♪午前7時の曲は、ビゼー作曲「ペールギュント組曲」より【朝】のテーマ
♪正午は合唱曲「芭蕉」より【さまざまの】
♪午後6時は、ドボルザーク作曲「交響曲・新世界」から【第2楽章・家路より】のテーマ
♪午後10時は、ブラームス作曲【子守唄】 でした。】
2011年12月現在、午後6時の「家路より」は聴くことはできません

その昔、このサイレンをきいて子どもたちは三々五々家路につきました・・・
今は午後5時に、防災無線が「七つの子」を奏でますが、外で遊ぶ子どもたちはいるんだろうか

雑感、芭蕉さんのことを書いたついでにふと思った。
「新芭蕉記念館」って、ほんまに必要なんやろか? 我らの芭蕉さんはそんなこと願ってるんやろか?
後生大事に守り伝えたい歴史資料を、、、きちんと保管したい!そのための「蔵」がほしい!それだけの素朴な想いではないのでしょうか。
誰がこの記念館に「年間○○万人の観光客を望む」のでしょうか?
伊賀市全体の観光客は如何ほどか、年々下降していることをご存知ではないのか!?
それとも芭蕉さんを利用して“起死回生・観光客奪還計画”を狙っているのでしょうか?
まちなかのそこかしこにある「芭蕉さんの軌跡」を歩くだけではいけませんか?
静かなまちを、静かに散策して芭蕉さんを偲ぶ、そして「俳句」を創る。
時折「NINJA」が大活躍する季節もある!
それが「秘蔵の国」。
そんな城下町ではだめなんかなぁ
 と、(勝手に)思うわけです、、、
と、(勝手に)思うわけです、、、








