子どもの教室を主催しているアートセラピストたちとの「面談」を最近つづけています。
30もの教室が北海道から姫路まで開講しているのですが、ボクが直接クラスを見に行くことは全くありません。
自分の作りたいクラスを創りだすわけですから、あんまり口出しすることはしないようにしています。
それでも、始めたばかりの教室は運営に関していろいろわからないこともあるし、長くやっていればそれなりに課題はいくらでも出てきます。
その都度、本部ののりちゃんやユッキーが対応していくのですが、教室数が増えて行くのでその対応も大変な時間を取られます。
ボクは、主に、クラスのプログラムチェックをするのですが、うまくいっている教室は、そのプログラムを読んでいるだけでその楽しさが伝わってきます。
もちろん、文字で書かれているだけなので完璧に表現されているわけではないのですが、イメージが広がるプログラムはワクワクしてしまうのです。
反対に、イメージができないプログラムもあります。
つまり、セラピストのイメージをうまく伝えられないと言うことは、子どもたちにもそれは伝わっていきにくくなるのです。
プログラム作りには、イメージの広がりは欠かせない要素です。
そのためにも、ボクにとっては児童文学やファンタジーを読むことが欠かせない日課となるのです。
『海のたまご』 ルーシー・M・ボストン
記憶のある作家の名前でした。
そう、以前読んだ『クリーン・ノウの子どもたち』の作者でした。
イギリスの良質な児童文学やファンタジーは、いわゆるアメリカ式のエンターテインとは違い、英国の風景や自然の香りが伝わって来るような気がします。

このお話は、トリトンのお話。
男の子の人魚の話です。
人魚と言えば、アンデルセンの『にんぎょ姫』や、小川未明の『赤い蝋燭と人魚』と、大体は女性。
主人公のトビーとジョーは、夏休みで両親とコーンウォールの海にやってきます。
ある日、エビ取りのおじさんが海で拾った美しい石を二人は手に入れます。
何か特別な石のように思えた二人は、二人だけが知っている入江の自然プールにそれを隠しておきます。
実は、それがトリトンの卵だったのです。
人間の男の子のような姿をしているそのトリトンとの暖かくもほほえましい交流と、荒々しい海のチカラが描かれます。
トリトンどころか人魚すら「存在しない(と思い込んでいる)」世界に住んでいるからこそ、こういったファンタジーはイメージを広げてくれます。
イメージの広がりは、現実に向き合うボクの日常に大きな刺激を与えてくれます。
仕事をする上でも、人間関係を作り出すうえでも、このイメージする力は、ボクにとって欠かせないもの。
日常の世界に生きる時に、非日常の世界観を心に持ち続けることは、心の安定に役立つのです。
一つの見方で固定してしまう価値観を広げてくれるのですから、やりきれない現実にも喜びや感動を運んできてくれる。
極端に言えば、「心が育つ」のです。
6月から、また物語の講座をスタートします。
グリム、アンデルセン、ギリシャ神話、そしてミヒャエル・エンデ。
ものがたりが好きな人も、自分を見つめたい人もどうぞ一緒に学んでいきましょう。
30もの教室が北海道から姫路まで開講しているのですが、ボクが直接クラスを見に行くことは全くありません。
自分の作りたいクラスを創りだすわけですから、あんまり口出しすることはしないようにしています。
それでも、始めたばかりの教室は運営に関していろいろわからないこともあるし、長くやっていればそれなりに課題はいくらでも出てきます。
その都度、本部ののりちゃんやユッキーが対応していくのですが、教室数が増えて行くのでその対応も大変な時間を取られます。
ボクは、主に、クラスのプログラムチェックをするのですが、うまくいっている教室は、そのプログラムを読んでいるだけでその楽しさが伝わってきます。
もちろん、文字で書かれているだけなので完璧に表現されているわけではないのですが、イメージが広がるプログラムはワクワクしてしまうのです。
反対に、イメージができないプログラムもあります。
つまり、セラピストのイメージをうまく伝えられないと言うことは、子どもたちにもそれは伝わっていきにくくなるのです。
プログラム作りには、イメージの広がりは欠かせない要素です。
そのためにも、ボクにとっては児童文学やファンタジーを読むことが欠かせない日課となるのです。
『海のたまご』 ルーシー・M・ボストン
記憶のある作家の名前でした。
そう、以前読んだ『クリーン・ノウの子どもたち』の作者でした。
イギリスの良質な児童文学やファンタジーは、いわゆるアメリカ式のエンターテインとは違い、英国の風景や自然の香りが伝わって来るような気がします。

このお話は、トリトンのお話。
男の子の人魚の話です。
人魚と言えば、アンデルセンの『にんぎょ姫』や、小川未明の『赤い蝋燭と人魚』と、大体は女性。
主人公のトビーとジョーは、夏休みで両親とコーンウォールの海にやってきます。
ある日、エビ取りのおじさんが海で拾った美しい石を二人は手に入れます。
何か特別な石のように思えた二人は、二人だけが知っている入江の自然プールにそれを隠しておきます。
実は、それがトリトンの卵だったのです。
人間の男の子のような姿をしているそのトリトンとの暖かくもほほえましい交流と、荒々しい海のチカラが描かれます。
トリトンどころか人魚すら「存在しない(と思い込んでいる)」世界に住んでいるからこそ、こういったファンタジーはイメージを広げてくれます。
イメージの広がりは、現実に向き合うボクの日常に大きな刺激を与えてくれます。
仕事をする上でも、人間関係を作り出すうえでも、このイメージする力は、ボクにとって欠かせないもの。
日常の世界に生きる時に、非日常の世界観を心に持ち続けることは、心の安定に役立つのです。
一つの見方で固定してしまう価値観を広げてくれるのですから、やりきれない現実にも喜びや感動を運んできてくれる。
極端に言えば、「心が育つ」のです。
6月から、また物語の講座をスタートします。
グリム、アンデルセン、ギリシャ神話、そしてミヒャエル・エンデ。
ものがたりが好きな人も、自分を見つめたい人もどうぞ一緒に学んでいきましょう。













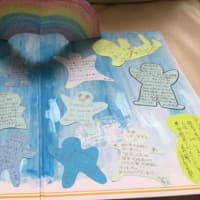



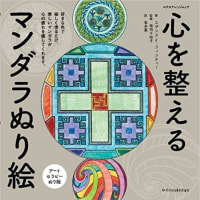
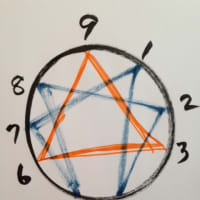

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます