ここのところ、「いじめ」のニュース報道が続いています。
いつの時代にもあって、根本の解決をしないのはどうしてなのでしょうか?
誰かをターゲットにして、仲間外れにする。
それだけじゃなくて、危害まで加えようとする。
悲しい結末を新聞で見るのは、本当につらいものです。
いじめになる前に、なんとかその芽を摘むことはできないものでしょうか?
何か小さな種があるような気がします。
MTBを終え、中央公園での休憩も、芋ほりのための士幌高校へ移動する時間になりました。
集合をかけようとしたときに、ボクの視界に入ってきた不自然な様子。
「はちとひまわり」グループが、離れた場所で真剣に話し合っているように見えます。
実は、このチームの中で、イントラのナオミに対しての「からかいのコトバ」が頻繁に繰り返されていました。
時にはひどい悪口になることも。
グロースのイントラサポーターの鉄則は、「やられたら真剣にやり返す」
子供たちは、親密感を味わおうとして「じゃれて」きます。
中には、キックしてきたり、思い切りたたいたりする子供もいます。
その事の反応として、決してしてはいけないことがあります。
容認してしまうこと。
笑顔でやり過ごしてしまうこと。
これをしてしまうと、子どもとの関係性がうまくいかなくなるのです。
子どもをつかまえて、しっかり目を見ます。
そして、痛い思いをするのは、だれにとっても愉快なことではないことをしっかり伝えるのです。
こういう真剣なかかわり方をすると、それは子供たちにも伝わります。
大人だと、後々しこりが残るようなこともあるでしょうが、長年グロースセミナーで子供たちとかかわってきての経験上、このかかわりは結果として心がつながっていくような気がしています。
子供たちは、そんないやな思いをする可能性のあるじゃれあいではなく、違うやり方でスタッフたちとの、信頼のかかわりが始まるのです。
初イントラのナオミは、この鉄則を守りきれていないようで、なんとなく笑ってそれを受け流していました。
同じチームのハナが、それを真剣に問いかけます。
「ナオミはさぁ、そんな悪口を言われて楽しいの?」
当たり前のことですが、楽しいはずがありません。
でも、なんとなく聞き流したり笑って受け止めてみたり・・・・。
そうすると、子供は調子に乗ってエスカレートしていきます。
見るに見かねてハナが、ナオミにチャレンジしたわけです。
その様子を見ていた、グループの子供たちも、自然にその話に加わります。
悪口を繰り返していた子供に対しても、ハナは、
「○○はさぁ、それをして楽しいの?」
「私はね、小さいころに、言葉でいやなことを言われていたことがあるんだ。」
「その時の心の傷は、大人になった今でも傷ついた体験として残ってる」
「大人になってからだって、そういうことを言われるとね、傷つくこともあるんだよ」
まだ幼いその子供に、はたして通じているのかどうかはわかりません。
グループ全員が、その話に加わり始めます。
そして、みんな楽しいグループにしたいこと、
本当は、イヤなことは言いたくないこと、
みんなで協力して、チャレンジをし続けたいこと、
などの意見が出始めます。
そして、ハナの「悪口を言って楽しいの?」という何度目かの問いかけに、その子の口から、
「・・・・たのしくない・・・・」という言葉が聞こえました。
短い時間でしたが、この真剣な話し合いは、グループに変化をもたらしました。
この子どもの態度や言動がガラッと変わりました。
そうなんです、こういうかかわりがグロースのよさなんです。
自分を超えていく。
越えようと努力する。
それを仲間たちが認め合う。
子どもたちだけじゃなくて、イントラやサポーター自身も成長していく、それがグロースセミナー。
さて今夜の夕ご飯の材料を収穫に、士幌高校へ行ってまいります。
いつの時代にもあって、根本の解決をしないのはどうしてなのでしょうか?
誰かをターゲットにして、仲間外れにする。
それだけじゃなくて、危害まで加えようとする。
悲しい結末を新聞で見るのは、本当につらいものです。
いじめになる前に、なんとかその芽を摘むことはできないものでしょうか?
何か小さな種があるような気がします。
MTBを終え、中央公園での休憩も、芋ほりのための士幌高校へ移動する時間になりました。
集合をかけようとしたときに、ボクの視界に入ってきた不自然な様子。
「はちとひまわり」グループが、離れた場所で真剣に話し合っているように見えます。
実は、このチームの中で、イントラのナオミに対しての「からかいのコトバ」が頻繁に繰り返されていました。
時にはひどい悪口になることも。
グロースのイントラサポーターの鉄則は、「やられたら真剣にやり返す」
子供たちは、親密感を味わおうとして「じゃれて」きます。
中には、キックしてきたり、思い切りたたいたりする子供もいます。
その事の反応として、決してしてはいけないことがあります。
容認してしまうこと。
笑顔でやり過ごしてしまうこと。
これをしてしまうと、子どもとの関係性がうまくいかなくなるのです。
子どもをつかまえて、しっかり目を見ます。
そして、痛い思いをするのは、だれにとっても愉快なことではないことをしっかり伝えるのです。
こういう真剣なかかわり方をすると、それは子供たちにも伝わります。
大人だと、後々しこりが残るようなこともあるでしょうが、長年グロースセミナーで子供たちとかかわってきての経験上、このかかわりは結果として心がつながっていくような気がしています。
子供たちは、そんないやな思いをする可能性のあるじゃれあいではなく、違うやり方でスタッフたちとの、信頼のかかわりが始まるのです。
初イントラのナオミは、この鉄則を守りきれていないようで、なんとなく笑ってそれを受け流していました。
同じチームのハナが、それを真剣に問いかけます。
「ナオミはさぁ、そんな悪口を言われて楽しいの?」
当たり前のことですが、楽しいはずがありません。
でも、なんとなく聞き流したり笑って受け止めてみたり・・・・。
そうすると、子供は調子に乗ってエスカレートしていきます。
見るに見かねてハナが、ナオミにチャレンジしたわけです。
その様子を見ていた、グループの子供たちも、自然にその話に加わります。
悪口を繰り返していた子供に対しても、ハナは、
「○○はさぁ、それをして楽しいの?」
「私はね、小さいころに、言葉でいやなことを言われていたことがあるんだ。」
「その時の心の傷は、大人になった今でも傷ついた体験として残ってる」
「大人になってからだって、そういうことを言われるとね、傷つくこともあるんだよ」
まだ幼いその子供に、はたして通じているのかどうかはわかりません。
グループ全員が、その話に加わり始めます。
そして、みんな楽しいグループにしたいこと、
本当は、イヤなことは言いたくないこと、
みんなで協力して、チャレンジをし続けたいこと、
などの意見が出始めます。
そして、ハナの「悪口を言って楽しいの?」という何度目かの問いかけに、その子の口から、
「・・・・たのしくない・・・・」という言葉が聞こえました。
短い時間でしたが、この真剣な話し合いは、グループに変化をもたらしました。
この子どもの態度や言動がガラッと変わりました。
そうなんです、こういうかかわりがグロースのよさなんです。
自分を超えていく。
越えようと努力する。
それを仲間たちが認め合う。
子どもたちだけじゃなくて、イントラやサポーター自身も成長していく、それがグロースセミナー。
さて今夜の夕ご飯の材料を収穫に、士幌高校へ行ってまいります。













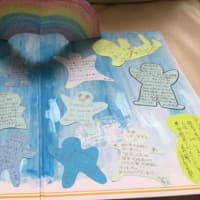



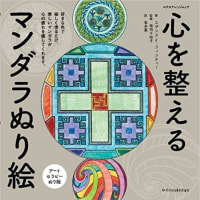
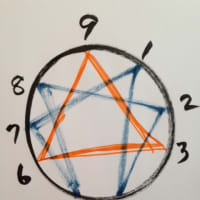

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます