先哲に学ぶ行動哲学―知行合一を実践した日本人 第四回(『祖国と青年』21年7月号掲載)
近江聖人・中江藤樹2
孝徳の実践・愛敬に生きる事で幸福は生れる
二十七歳で母の待つ小川村に戻った中江(なかえ)藤樹(とうじゅ)は、乏(とぼ)しい持ち金を基(もと)に商(あきな)いを始めた。それは、「酒の販売(はんばい)」であり「米の貸付(かしつけ)(低利息)」だった。喘息(ぜんそく)を患(わずら)う藤樹には農業は不可能だったし、土地も有していなかった。母に孝養(こうよう)を尽し慈(じ)顔(がん)を仰ぐ事が喜びだった藤樹にとって、商いはあくまでも生計(せいけい)を立てる為のものであり、それ以外の時間は自らの求道(ぐどう)と学問に費(つい)やした。
幸い、小川村は京都に近く、書物を得る事も可能だったし、学問の友も出来た。一日の労働を終えた農民が酒を求めに来ると、藤樹は話を聞きながら、今日はこの程度飲むと良いとその人に相応(ふさわ)しい分量を計って渡したという。藤樹には医学の心得(こころえ)も有り、その人徳(じんとく)が農民達を安心させたのである。藤樹は村人に請(こ)われるままに「人としての道」を話して回った。藤樹の姿を通して教えは着実に人々に伝わって行った。後に、門人が増えて講義(こうぎ)などで忙(いそが)しくなると、門前に酒(さか)瓶(びん)を置き、「代金は竹筒(たけづつ)に入れて下さい」と張り紙をする無人販売を行った。現在でも高島市上(たかしましかみ)小川(おがわ)の藤樹(とうじゅ)書院(しょいん)では、藤樹先生に関する書籍等の販売はこの無人販売で行っており、その遺風(いふう)が受け継がれている。
真実の師を求めていた熊沢蕃山(くまざわばんざん)が藤樹の存在を知った「正直(しょうじき)な馬方(うまかた)」の話は、藤樹の感化が庶民(しょみん)に迄浸透(しんとう)していた事を物語(ものがた)っている。それは、客として乗せた加賀藩(かがはん)の飛脚(ひきゃく)が馬の鞍(くら)に二百両の大金を置き忘れていたのに気付いた馬方(うまかた)が、わざわざその飛脚を探して届け、「人として当然の事をしただけです。」と言ってお礼を受け取らなかったという話である。その馬方は藤樹から教えを聞いていた。藤樹の求道(ぐどう)は実践(じっせん)に裏打(うらう)ちされたものであり、回りの人々をも感化した。
●根本(こんぽん)真実(しんじつ)の教化(きょうか)は、徳(とく)教(きょう)なり。くちにてはをしへずして、我身(わがみ)をたてみちをおこなひて、人(ひと)のをのずから変化(へんか)すを徳(とく)教(きょう)といふ。たとへば水(みず)の物(もの)をうるほし、火(ひ)のものをかはかすがごとし。(根本真実の教化は徳の力によるものである。口先(くちさき)で教えずに我が身の行いを示す事によって人が自(おの)ずから変化する事を徳の教えと言う。例(たと)えれば、水が周(まわ)りを潤(うるお)し、火が周りの物を乾(かわ)かすように、其の人物の存在が周りを感化するのが人徳(じんとく)の力なのだ。)(『翁(おきな)問答(もんどう)』上巻之本)
●いかで我(わが)こころの月(つき)をあらはしてやみにまどへる人(ひと)をてらさむ(どうにかして、私の心の中に存する明徳(めいとく)・良知(りょうち)の光を現(あらわ)し出して、心の闇(やみ)に迷っている人々の生き方を照(て)らし導(みちび)いて行きたいものである。)
「愛」と「敬」の教え
寛永(かんえい)十七年夏、三十三歳の藤樹は、毎朝『孝(こう)経(きょう)』を拝誦(はいしょう)する行(ぎょう)を自らに課(か)した。孝経の拝誦によって心が清められ一日を始める事が出来るのだった。『孝経』には、親を愛する者は人を憎(にく)む事が無く、親を敬(けい)する者は人を侮(あなど)る事が無い、と親への「愛敬(あいけい)」が万人に対する「愛敬」へと繋(つな)がって行く事を「孝」の功徳(くどく)として説(と)いている。
●孝(こう)徳(とく)の感通(かんつう)をてぢかくなづけいへば、愛敬(あいけい)の二字(にじ)につづまれり。愛(あい)はねんごろにしたしむ意(こころ)なり。敬(けい)は上(かみ)をうやまひ、下(しも)をかろしめあなどらざる義(ぎ)也(なり)。孝(こう)はたとへば明(あきらか))なる鏡(かがみ)のごとし。愛敬(あいけい)の至(し)徳(とく)は、通(つう)ぜざるところなし。(孝徳が感じ通じる所のものを手近(てぢか)に名付(なづ)けて言うならば、愛と敬の二(ふた)文字(もじ)に集約(しゅうやく)出来る。愛は懇(ねんご)ろに親しむという意味であり、敬は自分より上の人を敬い、下の人を軽んじたり侮(あなど)ったりしない事の意味である。孝は例(たと)えて言うならば明らかに光(ひかり)輝(かがや)く鏡の様なものであり、愛敬の徳が至(いた)る所通じない事が無いのである。)(『翁問答』上巻之本)
●人間(にんげん)千々(ちぢ)よろづのまよひ、みな私(わたくし)よりおこれり。わたくしは我身(わがみ)を、わが物(もの)と思(おも)ふよりおこれり。孝(こう)はその私(わたくし)をやぶりすつる主人公(しゅじんこう)なる(人間の様々(さまざま)の迷いは皆、私心(わたくしごころ)から起こって来る。私心は自分の身を自分だけのものだと思う所から起こって来る。生命(いのち)の連続性を体現(たいげん)する「孝」はその私心を破り捨てる事の出来る主人公と言っても良い。)((『翁問答』上巻之本)
愛と敬に基づく実践(じっせん)は村人を自(おの)ずと感化(かんか)し、『藤樹先生行状(こうじょう)』には、「先生の心はさっぱりとして、わだかまりがなく、人に愛敬の心をもって接した。だから周(まわ)りの者たちは、先生といると、ゆったりとくつろいで楽しくなるのだった。」
と記(しる)されている。
教育者の鑑
寛永(かんえい)十四年三十歳を迎えた藤樹は、十七歳の久子(ひさこ)を妻に迎えた。甲斐甲斐(かいがい)しく仕(つか)え支える久子夫人のおかげで、藤樹は学問に教育にその大半の時間を費(つい)やす事が可能となった。大洲藩(おおずはん)からも弟子達が藤樹の下を訪(おとず)れる様になる。大洲に居た時、医者を志して藤樹を頼ってきた大野(おおの)了(りょう)佐(さ)という青年が居(い)た。しかし、了左は極(きわ)めて記憶力(きおくりょく)が悪く、午後の時間帯に努力して学んでもわずか数行(すうぎょう)しか覚(おぼ)えきれず、しかも夕食を摂(と)った後には又その大半を忘却(ぼうきゃく)してしまうという、愚鈍(ぐどん)さであった。その了佐が藤樹を頼(たよ)って寛永十五年に藤樹の下にやってきた。藤樹は了佐の為に、毎日医学(いがく)の手解(てほど)きを数枚書いて与えた。其の為に藤樹は莫大(ばくだい)な医学書を播(ひもと)いた。それは、後に『捷径医(しょうけいい)筌(せん)』と題して纏(まと)められ出版されたが、580ページに及ぶ膨大(ぼうだい)なものであった。一人の弟子の為だけに藤樹は医学のテキストを著述(ちょじゅつ)したのである。正に、教育者の鑑(かがみ)と言って良い。藤樹は次の様な和歌を残している。
●志(こころざし)つよく引(ひき)立(たて)はげむべし石(いし)に立(た)つ矢(や)のためし聞(き)くにも(志を強く立てて励んで行こうではないか。強く引いた矢は石をも貫(つらぬ)くと言うではないか。)
藤樹は岡村氏に答えた書簡の中で「明徳(めいとく)を明(あきらか)にせんと思ふ気(き)なきものと、明(あきらか)にする道筋(みちすじ)をしらざる人」(心の中に存(そん)する明徳を明らかにしようと言う気持ちを抱(いだ)かない人と、明らかにして行く道筋を知らない人)は、人徳(じんとく)ある人物に成れないと諭(さと)している。
真の幸福とは
何故(なぜ)藤樹先生の教えは小川村(おがわむら)の人々や心ある武士達に染(し)み入っていったのだろうか。それは、人間の真の幸せについて深い洞察(どうさつ)に基づきつつも解(わか)り易(やす)い言葉で説(と)いていったからに他ならない。藤樹は、「分形連(ぶんけいれん)気(き)(形は分かれていても気は繋(つな)がっている)」「万物(ばんぶつ)一体(いったい)の仁(じん)心」という事も説(と)いている。人は別々の様に見えるが、その奥では繋(つな)がっているという確信を持っていた。
●万物(ばんぶつ)一体(いったい)の仁(じん)心(しん)を明(あきら)かにし、人(ひと)はいかようにもあれ、吾(われ)は何(なん)の心(こころ)もなく、ひたすらに親(したし)み和(やわら)ぎぬれば、人(ひと)も又(また)岩木(いわき)ならざれば、感動(かんどう)するところありて、仁愛(じんあい)をもて我(われ)を親(したし)むものなり。(万物はその根元(こんげん)に於て一つのものであるという「万物一体」の仁の心を明らかにして、他人はどうあれ、自分は他人に偏見(へんけん)を抱(いだ)かず、ひたすらに親(した)しんで和(なご)んで接すれば、人には心があって岩や木ではないのだから、感動する所があって仁愛の心が生じてその人も私に温(あたた)かく接する様になるのである。)『鑑(かがみ)草(ぐさ)』巻之六 淑睦報)
それ故、藤樹は、人の「慢心(まんしん)」を最も戒(いまし)め、それが不幸を生み出す元凶(げんきょう)であると教えた。
●人心(じんしん)のわたくしを種(たね)として、知(ち)あるもおろかなるも、自満(じまん)のこころなきはまれなり。この満心(まんしん)明徳(めいとく)をくらまし、わざはひをまねくくせものにして、よろずのくるしみも又(また)大(おお)かた是(これ)よりおこれり。(人の心の中の私心(わたくしごころ)を種として、知力(ちりょく)の多寡(たか)に拘(かかわ)らず、自分だけが偉(えら)いと思う慢心(まんしん)の心を抱かない者は非常に少ない。この慢心こそが心の明徳を眩(くら)まして禍(わざわい)を招く元凶であり、様々な苦しみは実はその殆(ほと)んどがこの慢心から生じて来るのである。)(『翁問答』下 丙戌冬)
藤樹は、「五事(ごじ)」を正(ただ)し、「自反慎(じはんしん)独(どく)(自己(じこ)を省(かえり)みて独(ひと)りを慎(つつし)む」の実践(じっせん)を勧(すす)めた。「五事」とは、貌(ぼう)・言(げん)・視(し)・聴(ちょう)・思(し)、即ち、顔つき・言葉遣(ことばづか)い・視(み)る事・聴(き)く事・思いの五つである。それを、和(なご)やかな顔・思いやりある言葉遣い・正しく視る事・本当の気持ちを聞く事・良い思いを持つこと、の五事に亘(わた)って正して行く事を勧めた。
●我(わが)心(こころ)石(いし)のごとくかたくすくみて角(かど)ある故(ゆえ)に、火(ひ)いで胸(むね)をこがし候(そうろう)。我(わが)心(こころ)わたの如(ごと)くやはらかに、水(みず)のごとくすくみなく候(そうら)えば、天下(てんか)一(いち)の火打(ひうち)にあたり候(そうろう)ても火(ひ)出(いで)申(もうさ)ず候。(自分の心が石の様に固くこわばり角(かど)が立っているから、他人と揉(も)めて火が出て胸が焼(や)け焦(こ)がれてしまうのだ。自分の心が綿(わた)の様に柔(やわ)らかで、水の様にしなやかであれば、天下一の火打ちの様な無理(むり)難題(なんだい)を吹っかけて来る人があってもそれを受け流して摩擦(まさつ)の火が生じない様になる事が出来る。)(書簡「早藤子に答へる」)
●思(おも)ひきやつらくうかりし世(よ)の中(なか)を学(まな)びて安(やす)く楽(たのしま)んとは(辛(つら)く憂(うれ)える事の多い世の中にあって、真実の学問を実践(じっせん)する事で、安らかで楽しく生きる事が出来るようになるとは思ってもいなかった。本当に学問の力は有り難い。)
良知に致る
中江藤樹が陽明学(ようめいがく)と出会ったのは、三三歳の時だった。繙(ひもと)いた『性(せい)理会通(りかいつう)』の中に王陽明(おうようめい)語録(ごろく)が十五篇(へん)含(ふく)まれていた。更(さら)には王陽明の弟子である『王(おう)龍渓(りゅうけい)語録』も繙(ひもと)いた。だが、本格的に王陽明の思想と対面(たいめん)したのは、亡くなる四年前の三七歳の時で、『陽明(ようめい)全書(ぜんしょ)』を手に入れてからだった。自らの心学(しんがく)を磨(みが)き上げて来た藤樹は、中国の先哲(せんてつ)にも同じ心境(しんきょう)を開拓(かいたく)した人物が居(い)るはずだと思っていた。王陽明の言葉に藤樹は「わが意(い)を得(え)たり」の思いで熟読(じゅくどく)した。自らの指針(ししん)となる「良知(りょうち)」の体認(たいにん)と良知を曇(くも)らす意(い)念(ねん)の解消(かいしょう)こそ藤樹が求めていた生き方だった。「致(ち)良知(りょうち)」を藤樹は「良知(りょうち)に致(いた)る」と読んで、学問の到達点(とうたつてん)とした。
だが、天は藤樹に長命(ちょうめい)を与えなかった。慶安(けいあん)元年(1648年)八月二八日、藤樹は四一歳で亡(な)くなる。しかし、その「心学(しんがく)」は熊沢蕃山(くまざわばんざん)を通じて実学(じつがく)として花開き、その教えは淵(ふち)岡山(こうざん)を通じて全国各地に広がって行った。
近江聖人・中江藤樹2
孝徳の実践・愛敬に生きる事で幸福は生れる
二十七歳で母の待つ小川村に戻った中江(なかえ)藤樹(とうじゅ)は、乏(とぼ)しい持ち金を基(もと)に商(あきな)いを始めた。それは、「酒の販売(はんばい)」であり「米の貸付(かしつけ)(低利息)」だった。喘息(ぜんそく)を患(わずら)う藤樹には農業は不可能だったし、土地も有していなかった。母に孝養(こうよう)を尽し慈(じ)顔(がん)を仰ぐ事が喜びだった藤樹にとって、商いはあくまでも生計(せいけい)を立てる為のものであり、それ以外の時間は自らの求道(ぐどう)と学問に費(つい)やした。
幸い、小川村は京都に近く、書物を得る事も可能だったし、学問の友も出来た。一日の労働を終えた農民が酒を求めに来ると、藤樹は話を聞きながら、今日はこの程度飲むと良いとその人に相応(ふさわ)しい分量を計って渡したという。藤樹には医学の心得(こころえ)も有り、その人徳(じんとく)が農民達を安心させたのである。藤樹は村人に請(こ)われるままに「人としての道」を話して回った。藤樹の姿を通して教えは着実に人々に伝わって行った。後に、門人が増えて講義(こうぎ)などで忙(いそが)しくなると、門前に酒(さか)瓶(びん)を置き、「代金は竹筒(たけづつ)に入れて下さい」と張り紙をする無人販売を行った。現在でも高島市上(たかしましかみ)小川(おがわ)の藤樹(とうじゅ)書院(しょいん)では、藤樹先生に関する書籍等の販売はこの無人販売で行っており、その遺風(いふう)が受け継がれている。
真実の師を求めていた熊沢蕃山(くまざわばんざん)が藤樹の存在を知った「正直(しょうじき)な馬方(うまかた)」の話は、藤樹の感化が庶民(しょみん)に迄浸透(しんとう)していた事を物語(ものがた)っている。それは、客として乗せた加賀藩(かがはん)の飛脚(ひきゃく)が馬の鞍(くら)に二百両の大金を置き忘れていたのに気付いた馬方(うまかた)が、わざわざその飛脚を探して届け、「人として当然の事をしただけです。」と言ってお礼を受け取らなかったという話である。その馬方は藤樹から教えを聞いていた。藤樹の求道(ぐどう)は実践(じっせん)に裏打(うらう)ちされたものであり、回りの人々をも感化した。
●根本(こんぽん)真実(しんじつ)の教化(きょうか)は、徳(とく)教(きょう)なり。くちにてはをしへずして、我身(わがみ)をたてみちをおこなひて、人(ひと)のをのずから変化(へんか)すを徳(とく)教(きょう)といふ。たとへば水(みず)の物(もの)をうるほし、火(ひ)のものをかはかすがごとし。(根本真実の教化は徳の力によるものである。口先(くちさき)で教えずに我が身の行いを示す事によって人が自(おの)ずから変化する事を徳の教えと言う。例(たと)えれば、水が周(まわ)りを潤(うるお)し、火が周りの物を乾(かわ)かすように、其の人物の存在が周りを感化するのが人徳(じんとく)の力なのだ。)(『翁(おきな)問答(もんどう)』上巻之本)
●いかで我(わが)こころの月(つき)をあらはしてやみにまどへる人(ひと)をてらさむ(どうにかして、私の心の中に存する明徳(めいとく)・良知(りょうち)の光を現(あらわ)し出して、心の闇(やみ)に迷っている人々の生き方を照(て)らし導(みちび)いて行きたいものである。)
「愛」と「敬」の教え
寛永(かんえい)十七年夏、三十三歳の藤樹は、毎朝『孝(こう)経(きょう)』を拝誦(はいしょう)する行(ぎょう)を自らに課(か)した。孝経の拝誦によって心が清められ一日を始める事が出来るのだった。『孝経』には、親を愛する者は人を憎(にく)む事が無く、親を敬(けい)する者は人を侮(あなど)る事が無い、と親への「愛敬(あいけい)」が万人に対する「愛敬」へと繋(つな)がって行く事を「孝」の功徳(くどく)として説(と)いている。
●孝(こう)徳(とく)の感通(かんつう)をてぢかくなづけいへば、愛敬(あいけい)の二字(にじ)につづまれり。愛(あい)はねんごろにしたしむ意(こころ)なり。敬(けい)は上(かみ)をうやまひ、下(しも)をかろしめあなどらざる義(ぎ)也(なり)。孝(こう)はたとへば明(あきらか))なる鏡(かがみ)のごとし。愛敬(あいけい)の至(し)徳(とく)は、通(つう)ぜざるところなし。(孝徳が感じ通じる所のものを手近(てぢか)に名付(なづ)けて言うならば、愛と敬の二(ふた)文字(もじ)に集約(しゅうやく)出来る。愛は懇(ねんご)ろに親しむという意味であり、敬は自分より上の人を敬い、下の人を軽んじたり侮(あなど)ったりしない事の意味である。孝は例(たと)えて言うならば明らかに光(ひかり)輝(かがや)く鏡の様なものであり、愛敬の徳が至(いた)る所通じない事が無いのである。)(『翁問答』上巻之本)
●人間(にんげん)千々(ちぢ)よろづのまよひ、みな私(わたくし)よりおこれり。わたくしは我身(わがみ)を、わが物(もの)と思(おも)ふよりおこれり。孝(こう)はその私(わたくし)をやぶりすつる主人公(しゅじんこう)なる(人間の様々(さまざま)の迷いは皆、私心(わたくしごころ)から起こって来る。私心は自分の身を自分だけのものだと思う所から起こって来る。生命(いのち)の連続性を体現(たいげん)する「孝」はその私心を破り捨てる事の出来る主人公と言っても良い。)((『翁問答』上巻之本)
愛と敬に基づく実践(じっせん)は村人を自(おの)ずと感化(かんか)し、『藤樹先生行状(こうじょう)』には、「先生の心はさっぱりとして、わだかまりがなく、人に愛敬の心をもって接した。だから周(まわ)りの者たちは、先生といると、ゆったりとくつろいで楽しくなるのだった。」
と記(しる)されている。
教育者の鑑
寛永(かんえい)十四年三十歳を迎えた藤樹は、十七歳の久子(ひさこ)を妻に迎えた。甲斐甲斐(かいがい)しく仕(つか)え支える久子夫人のおかげで、藤樹は学問に教育にその大半の時間を費(つい)やす事が可能となった。大洲藩(おおずはん)からも弟子達が藤樹の下を訪(おとず)れる様になる。大洲に居た時、医者を志して藤樹を頼ってきた大野(おおの)了(りょう)佐(さ)という青年が居(い)た。しかし、了左は極(きわ)めて記憶力(きおくりょく)が悪く、午後の時間帯に努力して学んでもわずか数行(すうぎょう)しか覚(おぼ)えきれず、しかも夕食を摂(と)った後には又その大半を忘却(ぼうきゃく)してしまうという、愚鈍(ぐどん)さであった。その了佐が藤樹を頼(たよ)って寛永十五年に藤樹の下にやってきた。藤樹は了佐の為に、毎日医学(いがく)の手解(てほど)きを数枚書いて与えた。其の為に藤樹は莫大(ばくだい)な医学書を播(ひもと)いた。それは、後に『捷径医(しょうけいい)筌(せん)』と題して纏(まと)められ出版されたが、580ページに及ぶ膨大(ぼうだい)なものであった。一人の弟子の為だけに藤樹は医学のテキストを著述(ちょじゅつ)したのである。正に、教育者の鑑(かがみ)と言って良い。藤樹は次の様な和歌を残している。
●志(こころざし)つよく引(ひき)立(たて)はげむべし石(いし)に立(た)つ矢(や)のためし聞(き)くにも(志を強く立てて励んで行こうではないか。強く引いた矢は石をも貫(つらぬ)くと言うではないか。)
藤樹は岡村氏に答えた書簡の中で「明徳(めいとく)を明(あきらか)にせんと思ふ気(き)なきものと、明(あきらか)にする道筋(みちすじ)をしらざる人」(心の中に存(そん)する明徳を明らかにしようと言う気持ちを抱(いだ)かない人と、明らかにして行く道筋を知らない人)は、人徳(じんとく)ある人物に成れないと諭(さと)している。
真の幸福とは
何故(なぜ)藤樹先生の教えは小川村(おがわむら)の人々や心ある武士達に染(し)み入っていったのだろうか。それは、人間の真の幸せについて深い洞察(どうさつ)に基づきつつも解(わか)り易(やす)い言葉で説(と)いていったからに他ならない。藤樹は、「分形連(ぶんけいれん)気(き)(形は分かれていても気は繋(つな)がっている)」「万物(ばんぶつ)一体(いったい)の仁(じん)心」という事も説(と)いている。人は別々の様に見えるが、その奥では繋(つな)がっているという確信を持っていた。
●万物(ばんぶつ)一体(いったい)の仁(じん)心(しん)を明(あきら)かにし、人(ひと)はいかようにもあれ、吾(われ)は何(なん)の心(こころ)もなく、ひたすらに親(したし)み和(やわら)ぎぬれば、人(ひと)も又(また)岩木(いわき)ならざれば、感動(かんどう)するところありて、仁愛(じんあい)をもて我(われ)を親(したし)むものなり。(万物はその根元(こんげん)に於て一つのものであるという「万物一体」の仁の心を明らかにして、他人はどうあれ、自分は他人に偏見(へんけん)を抱(いだ)かず、ひたすらに親(した)しんで和(なご)んで接すれば、人には心があって岩や木ではないのだから、感動する所があって仁愛の心が生じてその人も私に温(あたた)かく接する様になるのである。)『鑑(かがみ)草(ぐさ)』巻之六 淑睦報)
それ故、藤樹は、人の「慢心(まんしん)」を最も戒(いまし)め、それが不幸を生み出す元凶(げんきょう)であると教えた。
●人心(じんしん)のわたくしを種(たね)として、知(ち)あるもおろかなるも、自満(じまん)のこころなきはまれなり。この満心(まんしん)明徳(めいとく)をくらまし、わざはひをまねくくせものにして、よろずのくるしみも又(また)大(おお)かた是(これ)よりおこれり。(人の心の中の私心(わたくしごころ)を種として、知力(ちりょく)の多寡(たか)に拘(かかわ)らず、自分だけが偉(えら)いと思う慢心(まんしん)の心を抱かない者は非常に少ない。この慢心こそが心の明徳を眩(くら)まして禍(わざわい)を招く元凶であり、様々な苦しみは実はその殆(ほと)んどがこの慢心から生じて来るのである。)(『翁問答』下 丙戌冬)
藤樹は、「五事(ごじ)」を正(ただ)し、「自反慎(じはんしん)独(どく)(自己(じこ)を省(かえり)みて独(ひと)りを慎(つつし)む」の実践(じっせん)を勧(すす)めた。「五事」とは、貌(ぼう)・言(げん)・視(し)・聴(ちょう)・思(し)、即ち、顔つき・言葉遣(ことばづか)い・視(み)る事・聴(き)く事・思いの五つである。それを、和(なご)やかな顔・思いやりある言葉遣い・正しく視る事・本当の気持ちを聞く事・良い思いを持つこと、の五事に亘(わた)って正して行く事を勧めた。
●我(わが)心(こころ)石(いし)のごとくかたくすくみて角(かど)ある故(ゆえ)に、火(ひ)いで胸(むね)をこがし候(そうろう)。我(わが)心(こころ)わたの如(ごと)くやはらかに、水(みず)のごとくすくみなく候(そうら)えば、天下(てんか)一(いち)の火打(ひうち)にあたり候(そうろう)ても火(ひ)出(いで)申(もうさ)ず候。(自分の心が石の様に固くこわばり角(かど)が立っているから、他人と揉(も)めて火が出て胸が焼(や)け焦(こ)がれてしまうのだ。自分の心が綿(わた)の様に柔(やわ)らかで、水の様にしなやかであれば、天下一の火打ちの様な無理(むり)難題(なんだい)を吹っかけて来る人があってもそれを受け流して摩擦(まさつ)の火が生じない様になる事が出来る。)(書簡「早藤子に答へる」)
●思(おも)ひきやつらくうかりし世(よ)の中(なか)を学(まな)びて安(やす)く楽(たのしま)んとは(辛(つら)く憂(うれ)える事の多い世の中にあって、真実の学問を実践(じっせん)する事で、安らかで楽しく生きる事が出来るようになるとは思ってもいなかった。本当に学問の力は有り難い。)
良知に致る
中江藤樹が陽明学(ようめいがく)と出会ったのは、三三歳の時だった。繙(ひもと)いた『性(せい)理会通(りかいつう)』の中に王陽明(おうようめい)語録(ごろく)が十五篇(へん)含(ふく)まれていた。更(さら)には王陽明の弟子である『王(おう)龍渓(りゅうけい)語録』も繙(ひもと)いた。だが、本格的に王陽明の思想と対面(たいめん)したのは、亡くなる四年前の三七歳の時で、『陽明(ようめい)全書(ぜんしょ)』を手に入れてからだった。自らの心学(しんがく)を磨(みが)き上げて来た藤樹は、中国の先哲(せんてつ)にも同じ心境(しんきょう)を開拓(かいたく)した人物が居(い)るはずだと思っていた。王陽明の言葉に藤樹は「わが意(い)を得(え)たり」の思いで熟読(じゅくどく)した。自らの指針(ししん)となる「良知(りょうち)」の体認(たいにん)と良知を曇(くも)らす意(い)念(ねん)の解消(かいしょう)こそ藤樹が求めていた生き方だった。「致(ち)良知(りょうち)」を藤樹は「良知(りょうち)に致(いた)る」と読んで、学問の到達点(とうたつてん)とした。
だが、天は藤樹に長命(ちょうめい)を与えなかった。慶安(けいあん)元年(1648年)八月二八日、藤樹は四一歳で亡(な)くなる。しかし、その「心学(しんがく)」は熊沢蕃山(くまざわばんざん)を通じて実学(じつがく)として花開き、その教えは淵(ふち)岡山(こうざん)を通じて全国各地に広がって行った。
















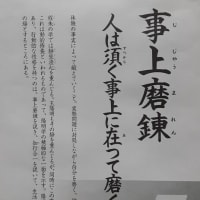



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます