先哲に学ぶ行動哲学―知行合一を実践した日本人第三十一回(『祖国と青年』23年11月号掲載)
三島由紀夫―現代に蘇る文武両道の思想2
生死を賭けた戦ひのあとに、判定を下すものは歴史であり、精神の価値であり、道義性である
三島由紀夫は、『文化防衛論』の中で「政治概念」ではない「文化概念としての天皇」こそが、守るべき「究極の価値」だと記している。
三島は天皇を論じるに当り、ドイツ語の「ザイン(存在)」と「ゾルレン(当為・あるべき姿)」を使って独自の天皇論を表現している。「天皇といふものが現実の社会体制や政治体制のザインに対してゾルレンとしての価値を持つ」「このゾルレンの要素の復活によつて初めて天皇が革新の原理になり得る」「私はその観念的、空想的あるひは理想的な天皇を文化的天皇制と名づけ、これの護持を私の政治理念の中核に置いてゐる」(「砂漠の住民への論理的弔辞」)と。
文士三島は、自らが抱く「文化的天皇制」を中核に据えた国体を守る為に、「武人」としての行動を決意する。
昭和四十二年四・五月、三島は一人で自衛隊への体験入隊を行う。その体験を下に自衛隊関係者の協力も得て、間接侵略に対抗する研究を行い民兵組織を考案していく。十月には『「國土防衛隊」草案』を、暮には『祖國防衛隊はなぜ必要か?』という小冊子を執筆した。
三島はその中で、間接侵略の脅威に対し「国民自らが一朝事あれば剣を執って、国の歴史と伝統を守る決意」と「気魄」が必要である事を述べ、「気魄だけでは実際の役に立たないので、武器の取扱にも周到な教育を要し、指揮統率の能力も、又これに応ずる能力も、一定の訓練体験なしには、つひに画に描いた餅にすぎ」ないとして、祖國防衛の為の「民兵」養成の必要性を訴えている。
「祖国防衛隊基本綱領(案)」には次の様に記されている。
●祖国防衛隊は、わが祖国・国民及びその文化を愛し、自由にして平和な市民生活の秩序と矜りと名誉を守らんとする市民による戦士共同体である。われら祖国防衛隊は、われらの矜りと名誉の根源である人間の尊厳・文化の本質及びわが歴史の連続性を破壊する一切の武力的脅威に対しては、剣を執つて立ち上がることを以て、その任務とする。(『裁判記録「三島由紀夫事件」』)
三島は「まだ法制化を急ぐ段階ではありませんから、純然たる民間団体として民族資本の協力に仰ぐの他はなく、一方、一般公募にいたる準備段階に数年をかけ、少くとも百人の中核体を一種の民間将校団として暗々裡に養成する」事を考え、その構想への協力を政財界の要人に訴えて行った。
だがその理解と協力を得る事は出来なかった。間接侵略に対する危機感に思想の落差があったのである。
三島は落胆し、自らの資金のみで祖国防衛の戦士を養成すべく決意した。三島は、中核要員を生み出すべく、四十三年三月、後の「楯の会」会員を伴って自衛隊に体験入隊を行う。以後、毎年三月と八月に会員を引率して体験入隊を行っている。十月、行動を共にした大学生達と正式に「楯の会」を結成する。この間、八月には剣道五段を修得している。
青年との相互感化
三島が「祖國防衛隊」構想に着手するに当っては、左翼でもノンポリでも無く、祖国の将来を真剣に考えている「民族派学生」との出会いと交流とがあった。四十二年暮に訪ねて来た「論争ジャーナル」編集の大学生達や日本学生同盟、生学連、全国学協(学生協議会)など大学で左翼の学生運動と果敢に戦っている大学生の存在は三島に大いなる刺激を与えた。
三島は青年について次の様に記している。
●私はかつて、私が青年から何かを学ぶといふことなどありえない、といふ傲岸な自信を抱いてゐたが、世の中には一方的な交渉といふものはありえない。覚悟のない私に覚悟を固めさせ、勇気のない私に勇気を与へるものがあれば、それは多分、私に対する青年の側からの教育の力であらう。(「青年について」42年10月)
●私は、ごく簡単に言つて、青年に求められるものは「高い道義性」の一語に尽きると思ふ。さう言ふとバカに古めかしいやうだが、道義といふものは、青年の愚直な盲目的な純粋性なしには、この世に姿を現はすことはないのである。(「現代青年論」44年1月)
●私は、今年こそ、立派な、さはやかな、日本人らしい「維新の若者」が陸続と姿を現はす年になるだらうと信じてゐる。日本はこのままではいけないことは明らかで、戦後二十三年の垢がたまりにたまつて、経済的繁栄のかげに精神的ゴミためが累積してしまつた。われわれ壮年も若者に伍して、何ものをも怖れず、歩一歩、新らしい日本の建設へ踏み出すべき年が来たのである。(「維新の若者」44年1月)
四十四年五月には東京大学に招かれて思想的に敵対する全共闘の学生と討論を行う。この討論の中で、全共闘の学生と三島との対決の視座は明確になり、三島は全共闘の学生たちを、文化と断絶した「砂漠の住民」と総括した。
●私が全学連諸君に問ひたかつたことは、彼らがその過去、現在、未来の連鎖をどのやうにとらへてゐるかといふことであつた。彼らは私の期待したとほり過去をすべて否定し、歴史を否定し、伝統を否定し、連続性を否定し、記憶をすら否定した。(『討論 三島由紀夫VS東大全共闘』の「討論を終えて」)
この全共闘を否定する思想的立場について三島は、四十三年十二月一日、学園正常化運動に尽力する全国学生協議会の都学協・関東学協結成大会で「日本の歴史と文化と伝統に立って」と題し大学生達に次の様に呼びかけている。
●われわれは、自分が遠い遠い祖先から受け継いできた文化の集積の最後の精華であり、これこそ自分であるという気持で以って、全身に自分の歴史と伝統が籠っているという気持ちを持たなければ、今日の仕事に完全な成熟というものを信じられないのではなかろうか。或いは自分一個の現実性も信じられないのではないか。自分は過程ではないのだ。道具ではないのだ。自分の背中に日本を背負い、日本の歴史と伝統と文化の全てを背負っているのだという気持ちに一人一人がなることが、それが即ち今日の行動の本になる。
同様の事を三島は「反革命宣言」(44年2月)の中で「われわれは、護るべき日本の文化・歴史・伝統の最後の保持者であり、最終の代表者であり、且つその精華であることを以て自ら任ずる。」「日本精神の清明、闊達、正直、道義的な高さはわれわれのものである。」と謳い上げている。
陽明学と三島由紀夫
三島由紀夫は、陽明学の創始者である王陽明が提唱した「知行合一」という言葉を好んで使った。
海上自衛隊幹部候補生学校教官の菊地勝夫宛の手紙には「日本の教育には、一般学校では、全く知行合一ということが忘れられています。」と記している(『三島由紀夫と自衛隊』)。
宮崎正弘氏の『三島由紀夫はいかにして日本回帰したのか』によれば三島は昭和三十八年の頃から陽明学の本格的な研究を開始している。
三島は、陽明学の大家である安岡正篤を会合に招き、その後、四十三年五月二十六日付で安岡にその著書を戴いたお礼の手紙を記し、その中で「小生のはうは、先生の御著書を手はじめとして、ゆつくり時間をかけて勉強いたし、ずつと先になつて、知行合一の陽明学の何たるかを証明したい」(林繁之『安岡正篤先生動記』)と述べている。
心中の真実の叫び(良知)のみに従つて生きていく事を訴える陽明学は、三島に行動の確信を与え、日本陽明学の流れに位置付けられる西郷隆盛・吉田松陰・大塩平八郎などに対する思慕の情を愈々高め上げて行った。
●西郷さん。(略)恥づかしいことですが、実は私は最近まで、あなたがなぜそんなに人気があり、なぜそんなに偉いのか、よくわからなかつたのです。(略)しかし、あなたの心の美しさが、夜明けの光りのやうに、私の中ではつきりしてくる時が来ました。時代といふよりも、年齢のせゐかもしれません。とはいへそれは、日本人の中にひそむもつとも危険な要素と結びついた美しさです。この美しさをみとめるとき、われわれは否応なしに、ヨーロッパ的知性を否定せざるをえないでせう。あなたは涙を知つてをり、力を知つてをり、力の空しさを知つてをり、理想の脆さを知つてゐました。それから責任とは何か、人の信にこたへるとは何か、といふことを知つてゐました。知つてゐて、行ひました。(「銅像との対話―西郷隆盛」43年4月)
●われわれの決意としては、吉田松陰の「汝は功業をなせ、我は忠義をなす」との信念で行くほかないと思つてゐる。「功業」といふのは、自分が大政治家として権力を握らなければ役立たない。(略)しかし、「忠義」は枯野に野垂れ死にするみちです(「孤立ノススメ」45年9月)
●われわれは(大塩)平八郎の学説を検討していくとこの辺りからだんだん現代との共通点へ入っていく。われわれは心の死にやすい時代に生きている、しかも平均年齢は年々延びていき、ともすると日本には、平八郎とは反対に、「心の死するを恐れず、ただ身の死するを恐れる」という人が無数にふえていくことが想像される。(略)われわれの戦後民主主義が立脚しているヒューマニズムは、ひたすら肉体の安全無事を主張して、魂や精神の生死を問わないのである。(略)大塩の思想にわれわれがさらに親近感を抱くのは、彼が他に、虚偽を去るの説を唱えたことであった。己を欺き人を欺くのは良知に反する所業である、とは彼の信念であった。われわれはこのような徹底的絶対的な誠実に立つときに、直ちに身の危険を感じなければならない。(略)現代という巨大な偽善の時代にあって、虚偽を卑しんだ大塩の精神は、われわれが一つの偽善を容認すれば、百、千の偽善を容認しなければならないことを教えている。そして、偽善はたちまち馴合いを生じ、一つの偽善に荷担した人間は、同じ偽善に荷担した百万の人間と結ぶのである。大塩はこの偽善に体をぶつけて死んだのだともいえよう。(「革命哲学としての陽明学」45年9月『諸君』掲載)
魂の叫び
この大塩平八郎に対する共感の言葉は、三島由紀夫の決起・自死の意味について示唆している。
三島は四十四年秋の革命派による騒乱が自衛隊の治安出動を齎し、それを契機に憲法が改正される事を夢見、「楯の会」がその魁たらんと欲したが、自衛隊の治安出動は不要となり、三島の夢は絶たれる。
戦後日本の「偽善」に対する三島の悲しみは愈々深まり、身体をぶつけて魂の叫びを遺さんと志して行く。
●私は日本の戦後の偽善にあきあきしていた。(略)日本の平和憲法が左右そうほうからの政治的口実に使はれた結果、日本ほど、平和主義が偽善の代名詞になつた国はないと信じてゐる。(略)私は文士として、日本ではあらゆる言葉が軽くなり、(略)使はれるやうになつたのを、いやといふほど見てきた。あらゆる言葉には偽善がしみ入つてゐた(「楯の会」のこと」44年11月)
●一九六九年の今、私が政治に参加しないといふ方法論はほぼ整つた。私は精神の戦ひにだけ私の劒を使ひたい。(「仮面はがれる時代」44年11月)
●変革とは一つのプランに向つて着々と進むことではなく、一つの叫びを叫びつづけることだ(「「変革の思想」とは」45年1月)
●私はこれからの日本に大して希望をつなぐことができない。このまま行つたら「日本」はなくなつてしまふのではないかといふ感を日ましに深くする。日本はなくなつて、その代はりに、無機的な、からつぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜目がない、或る経済大国が極東の一角に残るのであらう。それでもいいと思つてゐる人たちと、私は口をきく気にもなれなくなつてゐるのである。(「私の中の二十五年」45年7月)
●戦ひはただ一回であるべきであり、生死を賭けた戦ひでなくてはならぬ。生死を賭けた戦ひのあとに、判定を下すものは歴史であり、精神の価値であり、道義性である。(「反革命宣言」)
四十五年十一月二十五日、三島は、楯の会の学生四名と共に、市ヶ谷の陸上自衛隊東部方面総監部に於て、「激文」を撒き、自衛隊員を前に一場の演説を試み「天皇陛下萬歳」を叫んだ後、壮絶なる割腹自決を遂げ四十五年の生涯を閉じた。日本を熱愛した天才文学者三島由紀夫が、自らの生命を捧げて訴えた、戦後日本に対する警鐘の叫びと行動を、心ある人々は「三島義挙」と讃え、その志の継承を誓った。
●今こそわれわれは生命尊重以上の価値の所在を諸君の目に見せてやる。それは自由でも民主々義でもない。日本だ。われわれの愛する歴史と伝統の国、日本だ。これを骨抜きにしてしまつた憲法に体をぶつけて死ぬ奴はゐないのか。もしゐれば、今からでも共に起ち、共に死なう。われわれは至純の魂を持つ諸君が、一個の男子、真の武士として蘇へることを熱望するあまり、この挙に出たのである。(「檄」)
● 辞 世
益荒男がたばさむ太刀の鞘鳴りに幾とせ耐へて今日の初霜
散るをいとふ世にも人にもさきがけて散るこそ花と吹く小夜嵐
三島由紀夫―現代に蘇る文武両道の思想2
生死を賭けた戦ひのあとに、判定を下すものは歴史であり、精神の価値であり、道義性である
三島由紀夫は、『文化防衛論』の中で「政治概念」ではない「文化概念としての天皇」こそが、守るべき「究極の価値」だと記している。
三島は天皇を論じるに当り、ドイツ語の「ザイン(存在)」と「ゾルレン(当為・あるべき姿)」を使って独自の天皇論を表現している。「天皇といふものが現実の社会体制や政治体制のザインに対してゾルレンとしての価値を持つ」「このゾルレンの要素の復活によつて初めて天皇が革新の原理になり得る」「私はその観念的、空想的あるひは理想的な天皇を文化的天皇制と名づけ、これの護持を私の政治理念の中核に置いてゐる」(「砂漠の住民への論理的弔辞」)と。
文士三島は、自らが抱く「文化的天皇制」を中核に据えた国体を守る為に、「武人」としての行動を決意する。
昭和四十二年四・五月、三島は一人で自衛隊への体験入隊を行う。その体験を下に自衛隊関係者の協力も得て、間接侵略に対抗する研究を行い民兵組織を考案していく。十月には『「國土防衛隊」草案』を、暮には『祖國防衛隊はなぜ必要か?』という小冊子を執筆した。
三島はその中で、間接侵略の脅威に対し「国民自らが一朝事あれば剣を執って、国の歴史と伝統を守る決意」と「気魄」が必要である事を述べ、「気魄だけでは実際の役に立たないので、武器の取扱にも周到な教育を要し、指揮統率の能力も、又これに応ずる能力も、一定の訓練体験なしには、つひに画に描いた餅にすぎ」ないとして、祖國防衛の為の「民兵」養成の必要性を訴えている。
「祖国防衛隊基本綱領(案)」には次の様に記されている。
●祖国防衛隊は、わが祖国・国民及びその文化を愛し、自由にして平和な市民生活の秩序と矜りと名誉を守らんとする市民による戦士共同体である。われら祖国防衛隊は、われらの矜りと名誉の根源である人間の尊厳・文化の本質及びわが歴史の連続性を破壊する一切の武力的脅威に対しては、剣を執つて立ち上がることを以て、その任務とする。(『裁判記録「三島由紀夫事件」』)
三島は「まだ法制化を急ぐ段階ではありませんから、純然たる民間団体として民族資本の協力に仰ぐの他はなく、一方、一般公募にいたる準備段階に数年をかけ、少くとも百人の中核体を一種の民間将校団として暗々裡に養成する」事を考え、その構想への協力を政財界の要人に訴えて行った。
だがその理解と協力を得る事は出来なかった。間接侵略に対する危機感に思想の落差があったのである。
三島は落胆し、自らの資金のみで祖国防衛の戦士を養成すべく決意した。三島は、中核要員を生み出すべく、四十三年三月、後の「楯の会」会員を伴って自衛隊に体験入隊を行う。以後、毎年三月と八月に会員を引率して体験入隊を行っている。十月、行動を共にした大学生達と正式に「楯の会」を結成する。この間、八月には剣道五段を修得している。
青年との相互感化
三島が「祖國防衛隊」構想に着手するに当っては、左翼でもノンポリでも無く、祖国の将来を真剣に考えている「民族派学生」との出会いと交流とがあった。四十二年暮に訪ねて来た「論争ジャーナル」編集の大学生達や日本学生同盟、生学連、全国学協(学生協議会)など大学で左翼の学生運動と果敢に戦っている大学生の存在は三島に大いなる刺激を与えた。
三島は青年について次の様に記している。
●私はかつて、私が青年から何かを学ぶといふことなどありえない、といふ傲岸な自信を抱いてゐたが、世の中には一方的な交渉といふものはありえない。覚悟のない私に覚悟を固めさせ、勇気のない私に勇気を与へるものがあれば、それは多分、私に対する青年の側からの教育の力であらう。(「青年について」42年10月)
●私は、ごく簡単に言つて、青年に求められるものは「高い道義性」の一語に尽きると思ふ。さう言ふとバカに古めかしいやうだが、道義といふものは、青年の愚直な盲目的な純粋性なしには、この世に姿を現はすことはないのである。(「現代青年論」44年1月)
●私は、今年こそ、立派な、さはやかな、日本人らしい「維新の若者」が陸続と姿を現はす年になるだらうと信じてゐる。日本はこのままではいけないことは明らかで、戦後二十三年の垢がたまりにたまつて、経済的繁栄のかげに精神的ゴミためが累積してしまつた。われわれ壮年も若者に伍して、何ものをも怖れず、歩一歩、新らしい日本の建設へ踏み出すべき年が来たのである。(「維新の若者」44年1月)
四十四年五月には東京大学に招かれて思想的に敵対する全共闘の学生と討論を行う。この討論の中で、全共闘の学生と三島との対決の視座は明確になり、三島は全共闘の学生たちを、文化と断絶した「砂漠の住民」と総括した。
●私が全学連諸君に問ひたかつたことは、彼らがその過去、現在、未来の連鎖をどのやうにとらへてゐるかといふことであつた。彼らは私の期待したとほり過去をすべて否定し、歴史を否定し、伝統を否定し、連続性を否定し、記憶をすら否定した。(『討論 三島由紀夫VS東大全共闘』の「討論を終えて」)
この全共闘を否定する思想的立場について三島は、四十三年十二月一日、学園正常化運動に尽力する全国学生協議会の都学協・関東学協結成大会で「日本の歴史と文化と伝統に立って」と題し大学生達に次の様に呼びかけている。
●われわれは、自分が遠い遠い祖先から受け継いできた文化の集積の最後の精華であり、これこそ自分であるという気持で以って、全身に自分の歴史と伝統が籠っているという気持ちを持たなければ、今日の仕事に完全な成熟というものを信じられないのではなかろうか。或いは自分一個の現実性も信じられないのではないか。自分は過程ではないのだ。道具ではないのだ。自分の背中に日本を背負い、日本の歴史と伝統と文化の全てを背負っているのだという気持ちに一人一人がなることが、それが即ち今日の行動の本になる。
同様の事を三島は「反革命宣言」(44年2月)の中で「われわれは、護るべき日本の文化・歴史・伝統の最後の保持者であり、最終の代表者であり、且つその精華であることを以て自ら任ずる。」「日本精神の清明、闊達、正直、道義的な高さはわれわれのものである。」と謳い上げている。
陽明学と三島由紀夫
三島由紀夫は、陽明学の創始者である王陽明が提唱した「知行合一」という言葉を好んで使った。
海上自衛隊幹部候補生学校教官の菊地勝夫宛の手紙には「日本の教育には、一般学校では、全く知行合一ということが忘れられています。」と記している(『三島由紀夫と自衛隊』)。
宮崎正弘氏の『三島由紀夫はいかにして日本回帰したのか』によれば三島は昭和三十八年の頃から陽明学の本格的な研究を開始している。
三島は、陽明学の大家である安岡正篤を会合に招き、その後、四十三年五月二十六日付で安岡にその著書を戴いたお礼の手紙を記し、その中で「小生のはうは、先生の御著書を手はじめとして、ゆつくり時間をかけて勉強いたし、ずつと先になつて、知行合一の陽明学の何たるかを証明したい」(林繁之『安岡正篤先生動記』)と述べている。
心中の真実の叫び(良知)のみに従つて生きていく事を訴える陽明学は、三島に行動の確信を与え、日本陽明学の流れに位置付けられる西郷隆盛・吉田松陰・大塩平八郎などに対する思慕の情を愈々高め上げて行った。
●西郷さん。(略)恥づかしいことですが、実は私は最近まで、あなたがなぜそんなに人気があり、なぜそんなに偉いのか、よくわからなかつたのです。(略)しかし、あなたの心の美しさが、夜明けの光りのやうに、私の中ではつきりしてくる時が来ました。時代といふよりも、年齢のせゐかもしれません。とはいへそれは、日本人の中にひそむもつとも危険な要素と結びついた美しさです。この美しさをみとめるとき、われわれは否応なしに、ヨーロッパ的知性を否定せざるをえないでせう。あなたは涙を知つてをり、力を知つてをり、力の空しさを知つてをり、理想の脆さを知つてゐました。それから責任とは何か、人の信にこたへるとは何か、といふことを知つてゐました。知つてゐて、行ひました。(「銅像との対話―西郷隆盛」43年4月)
●われわれの決意としては、吉田松陰の「汝は功業をなせ、我は忠義をなす」との信念で行くほかないと思つてゐる。「功業」といふのは、自分が大政治家として権力を握らなければ役立たない。(略)しかし、「忠義」は枯野に野垂れ死にするみちです(「孤立ノススメ」45年9月)
●われわれは(大塩)平八郎の学説を検討していくとこの辺りからだんだん現代との共通点へ入っていく。われわれは心の死にやすい時代に生きている、しかも平均年齢は年々延びていき、ともすると日本には、平八郎とは反対に、「心の死するを恐れず、ただ身の死するを恐れる」という人が無数にふえていくことが想像される。(略)われわれの戦後民主主義が立脚しているヒューマニズムは、ひたすら肉体の安全無事を主張して、魂や精神の生死を問わないのである。(略)大塩の思想にわれわれがさらに親近感を抱くのは、彼が他に、虚偽を去るの説を唱えたことであった。己を欺き人を欺くのは良知に反する所業である、とは彼の信念であった。われわれはこのような徹底的絶対的な誠実に立つときに、直ちに身の危険を感じなければならない。(略)現代という巨大な偽善の時代にあって、虚偽を卑しんだ大塩の精神は、われわれが一つの偽善を容認すれば、百、千の偽善を容認しなければならないことを教えている。そして、偽善はたちまち馴合いを生じ、一つの偽善に荷担した人間は、同じ偽善に荷担した百万の人間と結ぶのである。大塩はこの偽善に体をぶつけて死んだのだともいえよう。(「革命哲学としての陽明学」45年9月『諸君』掲載)
魂の叫び
この大塩平八郎に対する共感の言葉は、三島由紀夫の決起・自死の意味について示唆している。
三島は四十四年秋の革命派による騒乱が自衛隊の治安出動を齎し、それを契機に憲法が改正される事を夢見、「楯の会」がその魁たらんと欲したが、自衛隊の治安出動は不要となり、三島の夢は絶たれる。
戦後日本の「偽善」に対する三島の悲しみは愈々深まり、身体をぶつけて魂の叫びを遺さんと志して行く。
●私は日本の戦後の偽善にあきあきしていた。(略)日本の平和憲法が左右そうほうからの政治的口実に使はれた結果、日本ほど、平和主義が偽善の代名詞になつた国はないと信じてゐる。(略)私は文士として、日本ではあらゆる言葉が軽くなり、(略)使はれるやうになつたのを、いやといふほど見てきた。あらゆる言葉には偽善がしみ入つてゐた(「楯の会」のこと」44年11月)
●一九六九年の今、私が政治に参加しないといふ方法論はほぼ整つた。私は精神の戦ひにだけ私の劒を使ひたい。(「仮面はがれる時代」44年11月)
●変革とは一つのプランに向つて着々と進むことではなく、一つの叫びを叫びつづけることだ(「「変革の思想」とは」45年1月)
●私はこれからの日本に大して希望をつなぐことができない。このまま行つたら「日本」はなくなつてしまふのではないかといふ感を日ましに深くする。日本はなくなつて、その代はりに、無機的な、からつぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜目がない、或る経済大国が極東の一角に残るのであらう。それでもいいと思つてゐる人たちと、私は口をきく気にもなれなくなつてゐるのである。(「私の中の二十五年」45年7月)
●戦ひはただ一回であるべきであり、生死を賭けた戦ひでなくてはならぬ。生死を賭けた戦ひのあとに、判定を下すものは歴史であり、精神の価値であり、道義性である。(「反革命宣言」)
四十五年十一月二十五日、三島は、楯の会の学生四名と共に、市ヶ谷の陸上自衛隊東部方面総監部に於て、「激文」を撒き、自衛隊員を前に一場の演説を試み「天皇陛下萬歳」を叫んだ後、壮絶なる割腹自決を遂げ四十五年の生涯を閉じた。日本を熱愛した天才文学者三島由紀夫が、自らの生命を捧げて訴えた、戦後日本に対する警鐘の叫びと行動を、心ある人々は「三島義挙」と讃え、その志の継承を誓った。
●今こそわれわれは生命尊重以上の価値の所在を諸君の目に見せてやる。それは自由でも民主々義でもない。日本だ。われわれの愛する歴史と伝統の国、日本だ。これを骨抜きにしてしまつた憲法に体をぶつけて死ぬ奴はゐないのか。もしゐれば、今からでも共に起ち、共に死なう。われわれは至純の魂を持つ諸君が、一個の男子、真の武士として蘇へることを熱望するあまり、この挙に出たのである。(「檄」)
● 辞 世
益荒男がたばさむ太刀の鞘鳴りに幾とせ耐へて今日の初霜
散るをいとふ世にも人にもさきがけて散るこそ花と吹く小夜嵐
















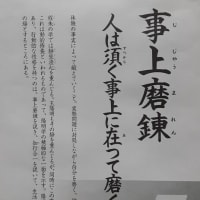



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます