会津武士道 その三(『祖国と青年』平成25年10月号掲載)
絶対的な社会規範の存在
ならぬことはならぬものです。
(「什の掟」)
会津藩と言ったら、この「ならぬものはならぬものです」との厳しい掟が有名である。会津の武家社会には、絶対的な社会規範=掟が存在していた。それは「什の掟」と呼ばれたもので、何と、六歳から九歳までの子供達が毎日唱えていたのである。
会津藩は、地域を区割りしてそれを「什」と呼び、その地域の中で年長者が年少者を教え導いていく社会を築いていた。六歳から九歳を「遊びの什」と言って、什の子供達は毎日集まって遊び学んだ。十歳になると藩校日新館に通うが、その際も同じ什の少年達は常に行動を共にしていた。十歳~十八歳は「学びの什」と呼ばれた。その什で厳しくしつけられたのが「什の掟」である。(中元寺智信『会津藩 什の掟』の解説をかっこで表示。)
一、年長者の言うことに背いてはなりませぬ。(→従順・忠誠→「忠」)
二、年長者には御辞儀をしなければなりませぬ。(→礼儀・秩序→「礼」)
三、虚言を言うてはなりませぬ。(→誠実・信頼→「信」)
四、卑怯な振舞をしてはなりませぬ。(→正義→「義」)
五、弱い者をいじめてはなりませぬ。(→優しさ・仁愛→「仁」)
六、戸外で物を食べてはなりませぬ。(→品格→「品」)
七、戸外で婦人と言葉を交してはなりませぬ。(→自覚)
ならぬことはならぬものです。
忠・礼・信・義・仁・品格・自覚を、解り易い言葉で、幼少の頃から生き方の柱として涵養している。見事な教育である。「弱い者をいじめてはなりませぬ。」を忠実に守った少年達の社会には陰湿なイジメなど存在しなかった。「弱きを助け、強きを挫く」事は当然のふるまいだった。
容保よ、共に心を合わせて世の様々な難題を解決して行こうではないか。
武士と心あはしていはほをも貫きてまし世々の思ひ出(孝明天皇が会津藩主松平容保に下された御製)
幕末期、京都守護職の任を受けた会津藩主松平容保は、孝明天皇の宸襟を安んずべく、京都の治安確立の為身を粉にして奮闘した。その様な容保の姿に孝明天皇は深い信頼を寄せられて行く。『京都守護職始末』を繙くと、天皇は幾度も容保に御宸翰(手紙)を下されている。
その中で有名なものが次の御宸翰と御製である。明治を迎えた後も容保は終生、身の側に大切に保管していた。
「堂上以下、暴論を疎ね不正の処置増長につき、痛心に堪え難く、内命を下せしところ、すみやかに領掌し、憂患掃攘、朕の存念貫徹の段、まったくその方の忠誠にて、深く感悦のあまり、右一箱これを遣わすもの也。
文久三年十月九日
たやすからざる世に武士の忠誠の心
を喜びてよめる
和らくも武き心も相生の松の落葉のあらず栄えん
武士と心あはしていはほをも貫きてまし世々の思ひ出 」
」
孝明天皇は攘夷の御信念を抱かれていたが、あくまでも幕府を信頼され、公武合体して我が国に迫りくる欧米を打ち払いたいとお考えになっていた。
一方、三条実美等の急進派公卿と長州藩や尊攘浪士達は、幕府のままでは攘夷は実行出来ないとして倒幕の為の大和行幸を企図した。その様な不穏な動きを憂慮された孝明天皇は、中川宮等の穏健派公卿にそのお考えを示され、それを受けて会津・薩摩の武力を背景とした政変(文久三年の八月十八日の政変)が起こり、急進派の七卿と長州藩が京都から追放された。その際の容保の活躍に感激されてこの直筆の御宸翰が下されたのだ。孝明天皇の憂慮と悦びの御心が伺われる内容である。
松平容保はあまり健康がすぐれず、京都での激務に身体を壊す事も多かった。病気となり京都守護職の任を解かれん事を願い出る容保だったが、天皇は決して認められず、逆に天皇は容保の為に平癒祈願を行われた。臣下たる者の病気快癒の為に天皇親ら祈願されたのである。容保は天皇の為に生命を捨てるしかなかった。そして、天皇と容保の君臣の強い絆は会津の人々をして、深い感動を抱かせ、自分達こそが勤王第一の藩だとの信念を抱かせたのである。
大義は会津にある。もし戦争になったら力を合わせ、心を一つにして敵を倒し大いに武勇を天下に轟かそうではないか。
力を合せ、心を一にして、兵起らば早く国家の敵を討滅し、武を益々天下に輝かさん
(慶応四年正月布告)
だが、歴史は残酷である。慶応二年七月に将軍家茂が薨去し、十二月には孝明天皇が崩御になられた。時代と人心は激変し、徳川幕府は孤立し、薩摩は長州と結び幕府に代る新しい政治勢力が生み出されて行った。そして、慶応四年の鳥羽伏見の戦いで敗北した幕府と会津藩には「朝敵」の汚名が着せられる事となったのである。その結果、官軍が江戸に、更には会津に向けられる事となった。
幕府軍が敗北した鳥羽伏見の戦いでも会津藩は良く戦っている。陣地を死守して玉砕した会津藩士白井五郎太夫の言葉として「此の地破れなば何の面目かあらん、一歩も退くなかれ寧ろ進んで死せよ」「恥を知り君恩を思ふものは須らく此処に死すべし」との言葉が『會津戊辰戦争』には記されている。
鳥羽伏見の戦いの直後、会津藩では長文の布告が出された。それは、松平容保公が京都守護職を引き受けられた理由と、京都での精忠の姿、天皇の御信任の様、天皇崩御後の状況の激変は先帝及び今上天皇の御志と違っている事等が熱く語られ、それでも薩長が会津に兵を差し向ける事態が起こるのであれば、会津藩は上下一心となってその汚名を雪ぐために戦い抜く覚悟を記している。正に、「会津の大義」を明らかにした文章である。
その最後の決意の一文を紹介する。
「藩の四民貴賤となく 祖宗以来徳沢に浴するもの面々此意を領掌し、力を合せ、心を一にして、兵起らば早く国家の敵を討滅し、武を益々天下に輝かさんことを期し、日夜肝に銘じ暫時も忘るゝことなく、国論一途に帰し万人の心一人の如くならば、我公の精忠天地を貫き神明の擁護ありて再青天白日を仰ぐこと豈疑あらんや、縦令身死すとも励鬼と為て祟を為し、姦賊を滅絶するの心なき者は天地の神祇其れ請ふ之を殪せよ。」
すさまじい気魄の文章である。この文章が会津藩の藩士全員の家に配布され、老若男女全てがそれを心魂に刻みつけた。その三か月後に会津戦争が開始され、八月二十二日には城下に攻め込まれ、降伏までの一か月の籠城戦を戦い抜く。降伏の決断は容保自らが下した。自らの身を擲って会津藩の全滅を阻止した。孤城よく耐えて戦い抜いた会津藩の姿は、勝敗を超えて人々を感激せしめた。
時代の激流に翻弄されるか弱い女性であっても、守るべき操は決して失わない。
なよ竹の風にまかする身ながらもたわまぬ節はありとこそきけ
(家老西郷頼母夫人千重子辞世)
会津武士を育てたのは、会津の女性達である。会津藩の危急存亡の戦いに際して、会津の女性達は果敢に立ち向かった。城に籠った女性達は食事の世話や弾丸の製作、負傷者の看護など献身的に銃後を支えた。更には自ら武器(薙刀や銃)を取って戦った女性も居た。又、城に籠れば足手まといになると考え自ら命を絶った婦女子も多数存在した。会津藩の殉難婦女子は二百三十八名に及んだ。
家老西郷頼母の家では、一族二十一人が自刃した。母・律子(五十八歳)は「秋霜飛んで金風冷し 白雲去りて月輪高し」と詠み、妻・千重子(三十四歳)は「なよ竹の風にまかする身ながらもたわまぬ節はありとこそきけ」と辞世を記した。
妹・眉寿子(二十六歳)は「死にかへり幾度世には生るともますら武夫となりなんものを」、妹・由布子(二十三歳)は「武士の道と聞きしをたよりにて思ひ立ちぬるよみの旅かな」と記した。
次女・ 瀑布子(十三歳)は「手をとりて共に行きなば迷はじよ」と、長女・細布子(十六歳)は「いざたどらまし死出の山路」と、二人で一首詠んだ。三女・田鶴子(九歳)四女・ 常盤子(四歳)五女・季子(二歳)も共に自害した。
中野こう子(四十四歳)・竹子(二十二歳)・優子(十六歳)・依田まさ子(三十五歳)・菊子(十八歳)ら二十余人は若松郊外涙橋の戦いに参戦し、「娘子隊」と呼ばれた。その時戦死した中野竹子の薙刀には次の辞世がつけられていた。
「武夫の猛き心にくらぶれば数にも入らぬ我が身ながらも」
ここまで記し、涙が溢れて止まらない。会津の女性達は世に言う女傑では決してなかった。女性としての嗜みを身に付け、母となっては子供達に強さと優しさとを兼ね備えた精神を涵養して行った。凛とした気高い女性達であった。
西郷千重子の「なよ竹」の歌は、日本女性のつつましやかだが毅然とした高潔なる叫びを、気負う事無く静かに表している。中野竹子の歌は、女性としての会津を思う已むに已まれぬ思いを表現し、余韻を漂わせている。
日本国の精神の再建は、女性の心映えの再建から行われなくては難しいのではないだろうか。そして日本女性が甦った時、その下から日本男児が陸続として生れて来るのだろう。
絶対的な社会規範の存在
ならぬことはならぬものです。
(「什の掟」)
会津藩と言ったら、この「ならぬものはならぬものです」との厳しい掟が有名である。会津の武家社会には、絶対的な社会規範=掟が存在していた。それは「什の掟」と呼ばれたもので、何と、六歳から九歳までの子供達が毎日唱えていたのである。
会津藩は、地域を区割りしてそれを「什」と呼び、その地域の中で年長者が年少者を教え導いていく社会を築いていた。六歳から九歳を「遊びの什」と言って、什の子供達は毎日集まって遊び学んだ。十歳になると藩校日新館に通うが、その際も同じ什の少年達は常に行動を共にしていた。十歳~十八歳は「学びの什」と呼ばれた。その什で厳しくしつけられたのが「什の掟」である。(中元寺智信『会津藩 什の掟』の解説をかっこで表示。)
一、年長者の言うことに背いてはなりませぬ。(→従順・忠誠→「忠」)
二、年長者には御辞儀をしなければなりませぬ。(→礼儀・秩序→「礼」)
三、虚言を言うてはなりませぬ。(→誠実・信頼→「信」)
四、卑怯な振舞をしてはなりませぬ。(→正義→「義」)
五、弱い者をいじめてはなりませぬ。(→優しさ・仁愛→「仁」)
六、戸外で物を食べてはなりませぬ。(→品格→「品」)
七、戸外で婦人と言葉を交してはなりませぬ。(→自覚)
ならぬことはならぬものです。
忠・礼・信・義・仁・品格・自覚を、解り易い言葉で、幼少の頃から生き方の柱として涵養している。見事な教育である。「弱い者をいじめてはなりませぬ。」を忠実に守った少年達の社会には陰湿なイジメなど存在しなかった。「弱きを助け、強きを挫く」事は当然のふるまいだった。
容保よ、共に心を合わせて世の様々な難題を解決して行こうではないか。
武士と心あはしていはほをも貫きてまし世々の思ひ出(孝明天皇が会津藩主松平容保に下された御製)
幕末期、京都守護職の任を受けた会津藩主松平容保は、孝明天皇の宸襟を安んずべく、京都の治安確立の為身を粉にして奮闘した。その様な容保の姿に孝明天皇は深い信頼を寄せられて行く。『京都守護職始末』を繙くと、天皇は幾度も容保に御宸翰(手紙)を下されている。
その中で有名なものが次の御宸翰と御製である。明治を迎えた後も容保は終生、身の側に大切に保管していた。
「堂上以下、暴論を疎ね不正の処置増長につき、痛心に堪え難く、内命を下せしところ、すみやかに領掌し、憂患掃攘、朕の存念貫徹の段、まったくその方の忠誠にて、深く感悦のあまり、右一箱これを遣わすもの也。
文久三年十月九日
たやすからざる世に武士の忠誠の心
を喜びてよめる
和らくも武き心も相生の松の落葉のあらず栄えん
武士と心あはしていはほをも貫きてまし世々の思ひ出 」
」
孝明天皇は攘夷の御信念を抱かれていたが、あくまでも幕府を信頼され、公武合体して我が国に迫りくる欧米を打ち払いたいとお考えになっていた。
一方、三条実美等の急進派公卿と長州藩や尊攘浪士達は、幕府のままでは攘夷は実行出来ないとして倒幕の為の大和行幸を企図した。その様な不穏な動きを憂慮された孝明天皇は、中川宮等の穏健派公卿にそのお考えを示され、それを受けて会津・薩摩の武力を背景とした政変(文久三年の八月十八日の政変)が起こり、急進派の七卿と長州藩が京都から追放された。その際の容保の活躍に感激されてこの直筆の御宸翰が下されたのだ。孝明天皇の憂慮と悦びの御心が伺われる内容である。
松平容保はあまり健康がすぐれず、京都での激務に身体を壊す事も多かった。病気となり京都守護職の任を解かれん事を願い出る容保だったが、天皇は決して認められず、逆に天皇は容保の為に平癒祈願を行われた。臣下たる者の病気快癒の為に天皇親ら祈願されたのである。容保は天皇の為に生命を捨てるしかなかった。そして、天皇と容保の君臣の強い絆は会津の人々をして、深い感動を抱かせ、自分達こそが勤王第一の藩だとの信念を抱かせたのである。
大義は会津にある。もし戦争になったら力を合わせ、心を一つにして敵を倒し大いに武勇を天下に轟かそうではないか。
力を合せ、心を一にして、兵起らば早く国家の敵を討滅し、武を益々天下に輝かさん
(慶応四年正月布告)
だが、歴史は残酷である。慶応二年七月に将軍家茂が薨去し、十二月には孝明天皇が崩御になられた。時代と人心は激変し、徳川幕府は孤立し、薩摩は長州と結び幕府に代る新しい政治勢力が生み出されて行った。そして、慶応四年の鳥羽伏見の戦いで敗北した幕府と会津藩には「朝敵」の汚名が着せられる事となったのである。その結果、官軍が江戸に、更には会津に向けられる事となった。
幕府軍が敗北した鳥羽伏見の戦いでも会津藩は良く戦っている。陣地を死守して玉砕した会津藩士白井五郎太夫の言葉として「此の地破れなば何の面目かあらん、一歩も退くなかれ寧ろ進んで死せよ」「恥を知り君恩を思ふものは須らく此処に死すべし」との言葉が『會津戊辰戦争』には記されている。
鳥羽伏見の戦いの直後、会津藩では長文の布告が出された。それは、松平容保公が京都守護職を引き受けられた理由と、京都での精忠の姿、天皇の御信任の様、天皇崩御後の状況の激変は先帝及び今上天皇の御志と違っている事等が熱く語られ、それでも薩長が会津に兵を差し向ける事態が起こるのであれば、会津藩は上下一心となってその汚名を雪ぐために戦い抜く覚悟を記している。正に、「会津の大義」を明らかにした文章である。
その最後の決意の一文を紹介する。
「藩の四民貴賤となく 祖宗以来徳沢に浴するもの面々此意を領掌し、力を合せ、心を一にして、兵起らば早く国家の敵を討滅し、武を益々天下に輝かさんことを期し、日夜肝に銘じ暫時も忘るゝことなく、国論一途に帰し万人の心一人の如くならば、我公の精忠天地を貫き神明の擁護ありて再青天白日を仰ぐこと豈疑あらんや、縦令身死すとも励鬼と為て祟を為し、姦賊を滅絶するの心なき者は天地の神祇其れ請ふ之を殪せよ。」
すさまじい気魄の文章である。この文章が会津藩の藩士全員の家に配布され、老若男女全てがそれを心魂に刻みつけた。その三か月後に会津戦争が開始され、八月二十二日には城下に攻め込まれ、降伏までの一か月の籠城戦を戦い抜く。降伏の決断は容保自らが下した。自らの身を擲って会津藩の全滅を阻止した。孤城よく耐えて戦い抜いた会津藩の姿は、勝敗を超えて人々を感激せしめた。
時代の激流に翻弄されるか弱い女性であっても、守るべき操は決して失わない。
なよ竹の風にまかする身ながらもたわまぬ節はありとこそきけ
(家老西郷頼母夫人千重子辞世)
会津武士を育てたのは、会津の女性達である。会津藩の危急存亡の戦いに際して、会津の女性達は果敢に立ち向かった。城に籠った女性達は食事の世話や弾丸の製作、負傷者の看護など献身的に銃後を支えた。更には自ら武器(薙刀や銃)を取って戦った女性も居た。又、城に籠れば足手まといになると考え自ら命を絶った婦女子も多数存在した。会津藩の殉難婦女子は二百三十八名に及んだ。
家老西郷頼母の家では、一族二十一人が自刃した。母・律子(五十八歳)は「秋霜飛んで金風冷し 白雲去りて月輪高し」と詠み、妻・千重子(三十四歳)は「なよ竹の風にまかする身ながらもたわまぬ節はありとこそきけ」と辞世を記した。
妹・眉寿子(二十六歳)は「死にかへり幾度世には生るともますら武夫となりなんものを」、妹・由布子(二十三歳)は「武士の道と聞きしをたよりにて思ひ立ちぬるよみの旅かな」と記した。
次女・ 瀑布子(十三歳)は「手をとりて共に行きなば迷はじよ」と、長女・細布子(十六歳)は「いざたどらまし死出の山路」と、二人で一首詠んだ。三女・田鶴子(九歳)四女・ 常盤子(四歳)五女・季子(二歳)も共に自害した。
中野こう子(四十四歳)・竹子(二十二歳)・優子(十六歳)・依田まさ子(三十五歳)・菊子(十八歳)ら二十余人は若松郊外涙橋の戦いに参戦し、「娘子隊」と呼ばれた。その時戦死した中野竹子の薙刀には次の辞世がつけられていた。
「武夫の猛き心にくらぶれば数にも入らぬ我が身ながらも」
ここまで記し、涙が溢れて止まらない。会津の女性達は世に言う女傑では決してなかった。女性としての嗜みを身に付け、母となっては子供達に強さと優しさとを兼ね備えた精神を涵養して行った。凛とした気高い女性達であった。
西郷千重子の「なよ竹」の歌は、日本女性のつつましやかだが毅然とした高潔なる叫びを、気負う事無く静かに表している。中野竹子の歌は、女性としての会津を思う已むに已まれぬ思いを表現し、余韻を漂わせている。
日本国の精神の再建は、女性の心映えの再建から行われなくては難しいのではないだろうか。そして日本女性が甦った時、その下から日本男児が陸続として生れて来るのだろう。
















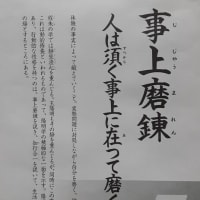



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます