「武士道の言葉」第三十五回 大東亜戦争・祖国の盾「玉砕」その1(『祖国と青年』平成27年6月号掲載)
文字通り最後の一兵まで戦った日本軍の勇気
誰もが最後の一兵最後の一画までというようなことをいうが、文字通りそれをやるのは日本兵だけだ(ビルマ戦英軍指揮官スリム大将)
大東亜戦争に於ける日本軍将兵の鬼神をも泣かせる勇戦の姿については、敵であった米英の指揮官達が、驚嘆と敬意とを持って様々に書き残している。
アーサー・スウィンソン『四人のサムライ 太平洋戦争を戦った悲劇の将軍たち』には、次の記述がある。
「西欧の兵隊はとうてい日本兵の無条件の勇気に太刀打ちできない。ビルマ戦のさなか、スリム大将は、『誰もが最後の一兵最後の一画までというようなことをいうが、文字通りそれをやるのは日本兵だけだ』と言ったものだ。これができるのは武士道のためだと思う。武士道とは武士の法典でこれにより死に対する非常に積極的な態度が育成されていく。」と。
実際、日本軍の将兵たちは太平洋の孤島のみならず、大陸の孤塁に於ても最後の一兵となるまで見事に戦い抜き、敵の心胆を寒からしめている。
その様を日本人は「玉砕」と呼んだ。西郷南洲の漢詩にも「丈夫は玉砕するも甎全を恥ず」とある。「立派な男児たる者は玉の様に砕け散ったとしても、無価値な瓦のようにいたずらに生き長らえる事を恥じる」の意味である。
しかし、様々な戦記を読むと、日本軍将兵の戦いの姿は、「死に急ぎ」では無く、最後の最後まで戦い抜き、敵を一人でも多く斃す事に執念を燃やしている。それは、自らの戦いが祖国に残る人々の為の防衛戦だとの自覚故であった。祖国への強い愛情が、彼らをして世界史に類を見ない勇者にしたのである。
湾岸戦争の時、砂漠で次々と米軍に降伏するイラク兵の姿に驚きを覚えたが、昨年のクリミアのウクライナ軍、ISとの戦いのイラク軍と、戦わずして降伏する軍隊の様は異常に思わる。だが、彼らにとっては玉砕してまで守るべき祖国は存在しないのであろう。「祖国との絆」、それこそが日本軍勇戦の秘密である。
国家永遠の生命に殉じる
我軍は最後まで善戦奮闘し、国家永遠の生命を信じ、武士道に殉ずるであろう。(アッツ島守備隊打電)
北太平洋アリューシャン列島のアッツ島を占領した日本軍守備隊に対し、昭和十八年五月十二日より米軍の奪還(アッツ島は米国本土である)作戦が開始された。
米軍は十九隻の艦隊と約一万一千人の陸軍部隊を投入。対する日本軍守備隊は二千六百人。実に四倍の敵だった。
大本営は、未だ戦闘が開始されてない隣島のキスカ島からの救出しか行い得ず、アッツを放棄するという苦渋の決断を行ない「軍は海軍と万策(ばんさく)を尽くして人員の救出に務むるも、地区隊長以下凡百の手段を講じて、敵兵員の燼滅(じんめつ)を図り、最後に至らば潔(いさぎよ)く玉砕し、皇国軍人精神の精華(せいか)を発揮するの覚悟あらんことを望む」と打電した。
それに対し守備隊長山崎(やまざき)保代(やすよ)陸軍大佐は、「国家国軍の苦しき立場は了承した。我軍は最後まで善戦奮闘し、国家永遠の生命を信じ、武士道に殉ずるであろう」と返電した。
当初、米軍は三日で降伏させると豪語していたが、十八日間も日本軍の攻撃は続いた。その中でも米軍を恐怖に陥れたのは日本刀や銃剣をかざしての肉弾突撃(米軍は「バンザイ・アタック」と呼んだ)と、兵士が地雷を抱いて敵戦車に突っ込む「対戦車肉攻」だった。共に、捨て身の戦法である。
山崎大佐はアッツ島赴任に際し、妻子宛の遺書を残している。妻の栄子さん宛の一節には「思ひ残すこと更になし、結婚以来茲(ここ)に約三十年、良く孝貞(こうてい)の道を尽す、内助の功深く感謝す。子供には賢母、私には良妻、そして変らざる愛人なりき、衷心満足す。」とある。
又、四人の子供達宛の一文には「行く道は何にても宜し、立派な人になって下さい。」とある。山崎大佐の人柄が偲ばれる言葉である。
戸川幸夫『山崎保代中将と一人の兵長』には、佐藤国夫兵長が撃墜した敵飛行士の墓を作った事に対し、「それが本当の武士道というもんだよ。いいことをした。戦いは戦い、情けは情け。情けあればこそ戦いも強い……といえる」と、山崎隊長が述べた事が紹介されてある。
昭和二十五年八月、米軍は山崎部隊玉砕地に、銅板の碑を建立し、「一九四三年、日本の山崎陸軍大佐はこの地点近くの戦闘によって戦死された。山崎大佐はアッツ島における日本軍隊を指揮した。」と記した。アッツ島将兵の勇戦を米軍が歴史に刻んだのである。
太平洋の防波堤
我身を以て太平洋の防波堤たらん(サイパン守備隊の誓いの言葉)
私が大学生だった四十年前、七夕の七月七日が近付くと大学構内には極左過激セクトが書いた「糾弾!中国侵略 盧溝橋事件○○年」と書かれたでっかい立看板が出されていた。どの国の大学なのか解らない程、彼らは中国共産党と一体化した歴史観に呪縛されていた。
その看板を見る度に私は、七月七日はサイパン守備隊の玉砕の日であり、日本人ならその事を記し、守備隊を追悼すべきではないのか、と怒りに胸を震わせていた。
昭和十八年九月三十日、米軍の本格的な反攻に対抗す可く大本営は絶対国防圏を設置した。この圏内に敵の侵入を許せば、日本本土が敵の爆撃機によって恒常的に空襲を受ける事となる為、絶対に守り抜くとの覚悟がこの言葉には籠められていた。
この絶対国防圏の西太平洋の端に位置していたのが、マリアナ諸島にあるサイパン島やテニアン島だった。それ故、サイパンの守備隊は「我身を以て太平洋の防波堤たらん」との合言葉を以て、押し寄せる米軍を必ず撃退するとの信念に燃えていた。
昭和十九年六月十一日より米軍は大空襲、艦砲射撃を繰返した後、十五日に上陸を開始した。艦艇は空母十五を含む七百七十五隻 陸軍十万 海軍二十五万という大規模なものだった。迎え撃つ日本軍守備隊は四万四千人。圧倒的な火力で日本軍を制圧したと考えた米軍は北と南の海岸に殺到したが、海岸に迫る米兵に日本側の砲弾が集中し、米軍は思いの外の損害を被った。
だが、火力・物量の差は如何ともし難く、日本軍の「水際(みずぎわ)邀撃(ようげき)作戦」は頓挫(とんざ)し、島内での消耗戦となって行く。そして遂に七月七日に防衛司令官・南雲(なぐも)忠一(ちゅういち)中将が自決し、組織的な戦闘は終結した。
だが、残存将兵は島内の密林地帯に立て籠もってゲリラ戦を展開した。
数年前に映画にもなり反響を呼んだが、その元になったのは、ドン・ジョーンズ『タッポーチョ「敵ながら天晴」大場隊の勇戦512日』である。大場大尉は、ばらばらになった敗残兵を見事に再組織する。所属部隊を失った兵隊達は別人と思える程無力化していたが、一旦指揮・命令系統が確立すると再び勇敢な兵隊に甦ったのである。大場隊は昭和二十年十二月一日まで戦い抜き、上官の命令を受けて降伏した。その姿は米国でも報道され、感動を与えた。
名誉の戦死
チチハリッパニハタライテ、メイヨノセンシヲトゲタ(アンガウル守備隊松島上等兵の遺言)
東京渋谷にある大盛堂(たいせいどう)書店の店主だった船坂(ふなさか)弘(ひろし)氏は、パラオのアンガウル島玉砕戦の数少ない生き残りの方だった。戦闘での凄まじい負傷の為に気絶して捕虜となり、生き長らえた船坂氏の体内には二十四個もの弾丸の破片が残されていたと言う。
その船坂氏が自らの体験をもとに記した『英霊の絶叫(ぜっきょう) 玉砕島アンガウル』は、私にとって忘れる事の出来ない書物である。
映画「連合艦隊」では、サイパンの玉砕戦を、敗色濃厚になって武器弾薬も食糧も欠乏した将兵が自殺の為に力なく敵に向って行く姿で描いていた。ところが、船坂氏の著書には、身が傷つき不具となろうが最後の最期まで、敵を斃(たお)さんと戦いを挑んでいく凄まじい姿の日本軍将兵の姿と、彼らの真情が記されており、真実に眼を開かされたのだった。
船坂氏に付き従った松島上等兵の最期の場面は何度読んでも涙を禁じ得ない。
重体に陥った松島上等兵は船坂氏の手のひらに人差し指で三十忿程かけて「ハンチョウドノ、ゴオン(御恩)ハシンデモワスレマセン。……ツマトカツボー(勝坊・三歳の愛息)ニヨロシク。……チチハリッパニハタライテ、メイヨノセンシヲトゲタ」と記して亡くなった。「名誉の戦死」、正に英霊の絶叫だった。
船坂氏はこの本を書いた已むに已まれぬ気持ちを次の様に記している。
「戦後二十一年、その間に過去の戦争を批難し、軍部の横暴を痛憤し、軍隊生活の非人道性を暴き、戦死した者は犬死であるかのような論や、物語がしきりにだされた。私はこの風潮をみながら心中こみあげてくる怒りをじっと堪えてきた。
やっと今、この記録をだすことができるに当って、私は心の底から訴えたい、戦死した英霊は決して犬死ではない。純情一途な農村出身者の多いわがアンガウル守備隊の如きは、真に故国に殉ずる気持に嘘はなかった。彼らは、青春の花を開かせることもなく穢れのない心と身体を祖国に捧げ、「われわれのこの死を平和の礎として、日本よ家族よ、幸せであってくれ」と願いながら逝ったのである。ただ徒らに軍隊を批判し、戦争を批難する者は「平和の価値」を知らない人である。」と。
終戦七十年の今日、船坂氏の絶叫を決して忘れてはならない。
尚、執筆当時船坂氏は、剣道を通じて三島由紀夫氏と親交があり、当時『英霊の聲』を執筆中だった三島氏が、序文を寄せ、かつ文章の指導にも当っている。
文字通り最後の一兵まで戦った日本軍の勇気
誰もが最後の一兵最後の一画までというようなことをいうが、文字通りそれをやるのは日本兵だけだ(ビルマ戦英軍指揮官スリム大将)
大東亜戦争に於ける日本軍将兵の鬼神をも泣かせる勇戦の姿については、敵であった米英の指揮官達が、驚嘆と敬意とを持って様々に書き残している。
アーサー・スウィンソン『四人のサムライ 太平洋戦争を戦った悲劇の将軍たち』には、次の記述がある。
「西欧の兵隊はとうてい日本兵の無条件の勇気に太刀打ちできない。ビルマ戦のさなか、スリム大将は、『誰もが最後の一兵最後の一画までというようなことをいうが、文字通りそれをやるのは日本兵だけだ』と言ったものだ。これができるのは武士道のためだと思う。武士道とは武士の法典でこれにより死に対する非常に積極的な態度が育成されていく。」と。
実際、日本軍の将兵たちは太平洋の孤島のみならず、大陸の孤塁に於ても最後の一兵となるまで見事に戦い抜き、敵の心胆を寒からしめている。
その様を日本人は「玉砕」と呼んだ。西郷南洲の漢詩にも「丈夫は玉砕するも甎全を恥ず」とある。「立派な男児たる者は玉の様に砕け散ったとしても、無価値な瓦のようにいたずらに生き長らえる事を恥じる」の意味である。
しかし、様々な戦記を読むと、日本軍将兵の戦いの姿は、「死に急ぎ」では無く、最後の最後まで戦い抜き、敵を一人でも多く斃す事に執念を燃やしている。それは、自らの戦いが祖国に残る人々の為の防衛戦だとの自覚故であった。祖国への強い愛情が、彼らをして世界史に類を見ない勇者にしたのである。
湾岸戦争の時、砂漠で次々と米軍に降伏するイラク兵の姿に驚きを覚えたが、昨年のクリミアのウクライナ軍、ISとの戦いのイラク軍と、戦わずして降伏する軍隊の様は異常に思わる。だが、彼らにとっては玉砕してまで守るべき祖国は存在しないのであろう。「祖国との絆」、それこそが日本軍勇戦の秘密である。
国家永遠の生命に殉じる
我軍は最後まで善戦奮闘し、国家永遠の生命を信じ、武士道に殉ずるであろう。(アッツ島守備隊打電)
北太平洋アリューシャン列島のアッツ島を占領した日本軍守備隊に対し、昭和十八年五月十二日より米軍の奪還(アッツ島は米国本土である)作戦が開始された。
米軍は十九隻の艦隊と約一万一千人の陸軍部隊を投入。対する日本軍守備隊は二千六百人。実に四倍の敵だった。
大本営は、未だ戦闘が開始されてない隣島のキスカ島からの救出しか行い得ず、アッツを放棄するという苦渋の決断を行ない「軍は海軍と万策(ばんさく)を尽くして人員の救出に務むるも、地区隊長以下凡百の手段を講じて、敵兵員の燼滅(じんめつ)を図り、最後に至らば潔(いさぎよ)く玉砕し、皇国軍人精神の精華(せいか)を発揮するの覚悟あらんことを望む」と打電した。
それに対し守備隊長山崎(やまざき)保代(やすよ)陸軍大佐は、「国家国軍の苦しき立場は了承した。我軍は最後まで善戦奮闘し、国家永遠の生命を信じ、武士道に殉ずるであろう」と返電した。
当初、米軍は三日で降伏させると豪語していたが、十八日間も日本軍の攻撃は続いた。その中でも米軍を恐怖に陥れたのは日本刀や銃剣をかざしての肉弾突撃(米軍は「バンザイ・アタック」と呼んだ)と、兵士が地雷を抱いて敵戦車に突っ込む「対戦車肉攻」だった。共に、捨て身の戦法である。
山崎大佐はアッツ島赴任に際し、妻子宛の遺書を残している。妻の栄子さん宛の一節には「思ひ残すこと更になし、結婚以来茲(ここ)に約三十年、良く孝貞(こうてい)の道を尽す、内助の功深く感謝す。子供には賢母、私には良妻、そして変らざる愛人なりき、衷心満足す。」とある。
又、四人の子供達宛の一文には「行く道は何にても宜し、立派な人になって下さい。」とある。山崎大佐の人柄が偲ばれる言葉である。
戸川幸夫『山崎保代中将と一人の兵長』には、佐藤国夫兵長が撃墜した敵飛行士の墓を作った事に対し、「それが本当の武士道というもんだよ。いいことをした。戦いは戦い、情けは情け。情けあればこそ戦いも強い……といえる」と、山崎隊長が述べた事が紹介されてある。
昭和二十五年八月、米軍は山崎部隊玉砕地に、銅板の碑を建立し、「一九四三年、日本の山崎陸軍大佐はこの地点近くの戦闘によって戦死された。山崎大佐はアッツ島における日本軍隊を指揮した。」と記した。アッツ島将兵の勇戦を米軍が歴史に刻んだのである。
太平洋の防波堤
我身を以て太平洋の防波堤たらん(サイパン守備隊の誓いの言葉)
私が大学生だった四十年前、七夕の七月七日が近付くと大学構内には極左過激セクトが書いた「糾弾!中国侵略 盧溝橋事件○○年」と書かれたでっかい立看板が出されていた。どの国の大学なのか解らない程、彼らは中国共産党と一体化した歴史観に呪縛されていた。
その看板を見る度に私は、七月七日はサイパン守備隊の玉砕の日であり、日本人ならその事を記し、守備隊を追悼すべきではないのか、と怒りに胸を震わせていた。
昭和十八年九月三十日、米軍の本格的な反攻に対抗す可く大本営は絶対国防圏を設置した。この圏内に敵の侵入を許せば、日本本土が敵の爆撃機によって恒常的に空襲を受ける事となる為、絶対に守り抜くとの覚悟がこの言葉には籠められていた。
この絶対国防圏の西太平洋の端に位置していたのが、マリアナ諸島にあるサイパン島やテニアン島だった。それ故、サイパンの守備隊は「我身を以て太平洋の防波堤たらん」との合言葉を以て、押し寄せる米軍を必ず撃退するとの信念に燃えていた。
昭和十九年六月十一日より米軍は大空襲、艦砲射撃を繰返した後、十五日に上陸を開始した。艦艇は空母十五を含む七百七十五隻 陸軍十万 海軍二十五万という大規模なものだった。迎え撃つ日本軍守備隊は四万四千人。圧倒的な火力で日本軍を制圧したと考えた米軍は北と南の海岸に殺到したが、海岸に迫る米兵に日本側の砲弾が集中し、米軍は思いの外の損害を被った。
だが、火力・物量の差は如何ともし難く、日本軍の「水際(みずぎわ)邀撃(ようげき)作戦」は頓挫(とんざ)し、島内での消耗戦となって行く。そして遂に七月七日に防衛司令官・南雲(なぐも)忠一(ちゅういち)中将が自決し、組織的な戦闘は終結した。
だが、残存将兵は島内の密林地帯に立て籠もってゲリラ戦を展開した。
数年前に映画にもなり反響を呼んだが、その元になったのは、ドン・ジョーンズ『タッポーチョ「敵ながら天晴」大場隊の勇戦512日』である。大場大尉は、ばらばらになった敗残兵を見事に再組織する。所属部隊を失った兵隊達は別人と思える程無力化していたが、一旦指揮・命令系統が確立すると再び勇敢な兵隊に甦ったのである。大場隊は昭和二十年十二月一日まで戦い抜き、上官の命令を受けて降伏した。その姿は米国でも報道され、感動を与えた。
名誉の戦死
チチハリッパニハタライテ、メイヨノセンシヲトゲタ(アンガウル守備隊松島上等兵の遺言)
東京渋谷にある大盛堂(たいせいどう)書店の店主だった船坂(ふなさか)弘(ひろし)氏は、パラオのアンガウル島玉砕戦の数少ない生き残りの方だった。戦闘での凄まじい負傷の為に気絶して捕虜となり、生き長らえた船坂氏の体内には二十四個もの弾丸の破片が残されていたと言う。
その船坂氏が自らの体験をもとに記した『英霊の絶叫(ぜっきょう) 玉砕島アンガウル』は、私にとって忘れる事の出来ない書物である。
映画「連合艦隊」では、サイパンの玉砕戦を、敗色濃厚になって武器弾薬も食糧も欠乏した将兵が自殺の為に力なく敵に向って行く姿で描いていた。ところが、船坂氏の著書には、身が傷つき不具となろうが最後の最期まで、敵を斃(たお)さんと戦いを挑んでいく凄まじい姿の日本軍将兵の姿と、彼らの真情が記されており、真実に眼を開かされたのだった。
船坂氏に付き従った松島上等兵の最期の場面は何度読んでも涙を禁じ得ない。
重体に陥った松島上等兵は船坂氏の手のひらに人差し指で三十忿程かけて「ハンチョウドノ、ゴオン(御恩)ハシンデモワスレマセン。……ツマトカツボー(勝坊・三歳の愛息)ニヨロシク。……チチハリッパニハタライテ、メイヨノセンシヲトゲタ」と記して亡くなった。「名誉の戦死」、正に英霊の絶叫だった。
船坂氏はこの本を書いた已むに已まれぬ気持ちを次の様に記している。
「戦後二十一年、その間に過去の戦争を批難し、軍部の横暴を痛憤し、軍隊生活の非人道性を暴き、戦死した者は犬死であるかのような論や、物語がしきりにだされた。私はこの風潮をみながら心中こみあげてくる怒りをじっと堪えてきた。
やっと今、この記録をだすことができるに当って、私は心の底から訴えたい、戦死した英霊は決して犬死ではない。純情一途な農村出身者の多いわがアンガウル守備隊の如きは、真に故国に殉ずる気持に嘘はなかった。彼らは、青春の花を開かせることもなく穢れのない心と身体を祖国に捧げ、「われわれのこの死を平和の礎として、日本よ家族よ、幸せであってくれ」と願いながら逝ったのである。ただ徒らに軍隊を批判し、戦争を批難する者は「平和の価値」を知らない人である。」と。
終戦七十年の今日、船坂氏の絶叫を決して忘れてはならない。
尚、執筆当時船坂氏は、剣道を通じて三島由紀夫氏と親交があり、当時『英霊の聲』を執筆中だった三島氏が、序文を寄せ、かつ文章の指導にも当っている。
















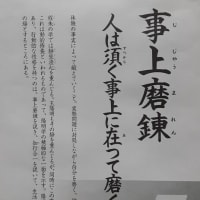



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます