先哲に学ぶ行動哲学―知行合一を実践した日本人第三十二回(『祖国と青年』23年12月号掲載)
安岡正篤 東洋哲学の泰斗・人間学を提唱した昭和の導師1
天下を憤るは易いが、天下を救ふは難し
日本の陽明学の脈流を語る場合、大正から昭和にかけて、わが国の政治家・教育者・官僚・軍人に多大な影響を及ぼした碩学・安岡正篤の存在を抜きにする事は出来ない。
安岡は陽明学を始めとする儒教・老荘思想・仏教・神道等の東洋哲学を深く学び、その哲理によって自らを錬成して行く「人間学」を生涯示し続けた。
安岡は青年の頃に北一輝や大川周明と活動を共にした時代があった。しかし安岡は、当時の革新運動の底の浅さに失望して独自の道を歩み始めた。昭和六年の血盟団事件(一人一殺テロ)に対する安岡の次の言葉は安岡が求めた国家革新の理想が那辺にあったかを示している。
●王道は天下の為と雖も一民の命も忽にせぬものである。武士道は最もよくその敵を敬重することを教へる。刀を抜くことは最後として居る。(略)大丈夫止むを得ずして起つ時は天下環視の下に堂々義旗を翻すべきで、暗殺の様なことは避けねばならぬ。それに天下を救ふは一朝一夕で出来ない。幾段にも構成せられた人材が必要であり、また出来るだけ精透な時務眼と更に厳粛な徳操もなければならぬ。天下を憤るは易いが、天下を救ふは難い。出でゝ蒼生を誤る自任的英雄が如何に多いことか。(『童心残筆』)
安岡は、国家革新を唱える者の内実・人格の高潔さを問うたのだった。自らの生き方を正さずして国を正す事などありえないと信じた。『大学』に言う「修身→斉家→治国→平天下」の君子の道を安岡は自ら実践し、かつ教え導いたのだ。常に自らに反って内実を問う「自反の学」である。
王陽明の生き様に感動して成った『王陽明研究』
安岡正篤の名前を一躍世に知らしめたのが、安岡が東京帝国大学の卒業記念に著した『王陽明研究』である。大正八年に東京帝大法学部政治学科に入学した安岡は、大学の授業に何ら魅力を感じなかった為、もっぱら図書館に通って支那思想及び人物研究を独学で切り拓いて行く。その成果を大正十年に『支那思想及び人物講話』、翌年『王陽明研究』として出版した。安岡二十五歳(数え)の時である。
この中で安岡は王陽明の生き方を感動の言葉で記している。
●王陽明―陽明学の名はひさしく邦人に知られてきた。およそ人間の創造し得べき最も荘厳なる人格が陽明によつて実現されてをり、かかる人格の創造的白熱に燃ゆる力強い思想が凝つてその学となつてゐる
●陽明学によつてその真骨頭を養うた人物が、すべて卓然として富貴も淫する能はず、貧賤も移す能はず、威武も屈する能はざる底の大丈夫的風格に富んでゐるのは誠に必然の理由がある。(略)陽明はしばしば吾党の士は豪傑でなければならぬ。豪傑の士でなければ事を共にするに足らぬといつてゐる。(略)彼の所謂豪傑とは自己内心の至上要求に率うて、内面的にも外面的にも一切の盲目的他律的圧迫を排脱せんとする精神的勇気の謂である。
戦後の講演でも王陽明の魅力を次の様に語っている。
●実にあの病苦をひっさげて、あの艱難辛苦を極めた間に、よくあれだけの学問と講学ができたものであります。その事績を追い、彼の文を読み、彼の詩を読み、彼の書簡、および彼の献策、あるいは匪賊征伐・内乱鎮定の際の建白書、そういったものをしみじみ読んでおりますと、何とも言えぬ感激に打たれます。人間にはこういう人がおるのか、また人間はこういう境地にあって、こういうことができるものかとしみじみ感じます。敬虔かつ熱烈な門弟たちとの問答や書簡は、現代の評論家やジャーナリストによる、簡単な、軽薄な流行思想や評論の対象になるような人物や思索や学問とは全然違う。実にこれは深刻で霊活といいますか、陽明学とは、限りない感激のこもった、人間として地上における最も荘厳なる学問であり文章である、という気がいたします。(現代活学講話選集『王陽明』)
「処士」に生きる
安岡正篤は、明治三十一年二月十三日、大阪市で、堀田喜一・悦子夫妻の四男として誕生した。堀田家の祖先は四条畷の戦いで楠木正行を援け勇戦して戦死しており、代々南朝の勤皇家として令名があった。小学校一年の頃から四書五経を学び始めた。四条畷中学校に進学し、卒業までの五年間、通学時には歩きながら書物を読み、電柱や牛にぶつかったり、集中しすぎて家を通り越したエピソードが残っている。
近所の春日神社の神官浅見晏斎や陽明学者岡村閑翁に感化を受けた。中学時代に王陽明に傾倒し伝習録を貪り読んだという。
又、学校では剣道部で心身を鍛え、五年時には主将を務め、全関西中学校大会で優勝している。
秀才の誉れ高い正篤だったが、家の経済状態では進学もままならなかった為、教官の島長代が親交のあった東京の安岡盛治に養子縁組と第一高等学校進学を相談し、堀田家も了解して、正篤は安岡の養子となり上京して一高に入学、その後東京帝大に進学した。
この間安岡は、西洋哲学も学び書物を読破して行く。だが、西洋哲学では魂は振起されず、再び東洋聖賢の書に戻り、東洋哲学を研究し論文を次々と発表する。
大学卒業に際し、上杉慎吉教授から研究室に残るように懇請されるが、社会への道を選び、文部省に奉職。しかし六ヶ月で退職した。爾後、安岡は官職には就かず「処士(民間にいて仕官しない人)」の道を生涯貫いた。
●世の中に出てなにかになるということは、別の面からいうと、さびしいことです。専門をきめるということは、自分の生活の舞台を、全き無限のものから局限してしまうことです。なにかになるということは限定である。それになじんでしまうと、本当に区々たる人間になってしまいます。(『安岡正篤の世界』)
●爾来私は出世街道を断念して、ひたすら内心の至上命令にしたがつて生活した。学問も一つの目的から資料を集め、これ等を比較検討して、何等かの結論を出してゆくやうな客観的・科学的なことよりも、自分の内心に強く響く、自分の生命・情熱・霊魂を揺り動かすやうな文献を探求し、遍参した。丁度竹の根が地中に蔓延して、処々に筍を出すやうに、学問し執筆した。さうして伝習録が縁で、陽明を研究し、沈白沙、李卓吾、李ニ曲、劉念台、呂新吾、遡つて陸象山、朱晦庵、程明道、伊川、張横渠、邵康節、周茂叔などを遍歴し、日本では藤原惺窩、山鹿素行、中江藤樹、熊沢蕃山、山田方谷、春日潜庵、大塩中斎などに参究した。その間に法然、親鸞、日蓮、道元などから深い感化を受けた。特に、歴史的社会的に背骨ができたように思へたのは、史記と資治通鑑を読破したことであつた。(『王陽明研究』新序)
北一輝・大川周明との出会いと訣別
大正十一年七月、安岡は沼波瓊音の紹介で国家改造を志す猶存社の北一輝や満川亀太郎と会う。北は十五歳も年下の安岡の学と人物に驚嘆し、大川周明にも紹介した。
安岡は国家革新の志を抱く大川達との出会いを「活ける魂に触れ道徳的雄心の高鳴りを覚えた。」と記している。
●大学時代棄身になつてよく学問したが、その頃から私は一面強烈に革命を考へるやうになつた。しかし東洋先哲の学問の力であらう、今日の学生のやうに浅薄皮相な集団活動に趨らず、まづ深い政治哲学を持つた優れた同志の糾合を考へた。それが私の社会生活を築きあげる不思議な原動力になつてしまつた。当時第一次大戦の後で、社会的思想的混乱が甚だしく、共産主義革命思想運動も、正直強烈であつたが、それに対して勃然として民族主義に立つ昭和維新運動が始まつた。私はいつのまにかその激流の中にあつた。(『王陽明研究』新序)
十月、安岡は満川の紹介で原田政治と会い、酒井忠正伯爵を知る。酒井伯は安岡を高く評価し、酒井伯邸・金鶏園に東洋思想の研究所設立を勧めた。そこで亜細亜文化協会研究所が設立され、「東洋思想研究」を発刊し、安岡は学術主任に就任した。十二月には陽明学研究会が発足した。十三年、東洋思想研究所を組織して「東洋思想研究」を続刊する。
そして『日本精神の研究』を出版する。その中で日本の国体を語り、山鹿素行・吉田松陰・高杉東行・高橋泥舟・楠木正成・武士道・大塩中斎・西郷南洲について語った。安岡はこの著書を「一昨年来、私の参学生活に於いて自我の奥殿を通じて国民精神の真髄に触れ得た魂の記録である。」と述べている。
この本で安岡は「日本に於ては、革命は必ず天皇より出でなければならぬ。」「国家が政府の頽廃に依つて危殆に瀕する時、革命を遂行して新たなる局面を新開するは天徳である、天皇の御威徳である。」と「錦旗革命」論を述べている。
「白人の世界支配からのアジア解放」など、思想的には一致するが、考え方の齟齬から同志間の分裂が始まって行く。四月に北一輝と大川周明の対立で猶存社は分裂、大川・満川・安岡は猶存社を離れ、行地社を結成した。十四年四月、行地社は、国の柱となる人士養成の為の「大学寮」を開講する。だが十月に起こった安田共済事件で露見した運動家達の堕落の姿に安岡は嫌悪を感じ、大川達と別の独自の道を開始するのだった。
●国家革新・改造の名分確かなるも、身を正しそれに相応しい行を為す指導者でなければ維新の達成は難しい。迂遠な様でも古今ノ聖賢に学び之を行なえる人物の養成こそ急務なり(大正十五年一月『安岡正篤先生年譜』)
安岡は再び自らを見つめ直し、自らの天命を慎思した。
●草堂の縁にうずくまり、自分というものを沁々考えさせられる。一体お前は此の頃何をしてるんだ。教育者否、学者否、無職否、では処士とでも開き直るか。一不朽人なるべし。学問の意味を解し始めたのは、菜根をかむに決めた日(文部省辞職の日)からで爾来四年となる。かくて天地独往の客となり得たとき、堂々と教育者・学者と称するであろう。自ら樸学生と覚り樸学(儒学の事)十年の志を述ぶ。(大正十四年「秋風処士の感」)
金鶏学院・日本農士学校
深思する事一年、大正十五年十月、安岡の下に新しく塾風を興す議が起こり、御世が代わった昭和二年元旦、金鶏学院が創設された。三月には金鶏学寮(二階建各室四畳半―上下十八室)が新築落成。四月に開院した。
安岡は有為な青年をこの私塾道場で磨き上げ、国家を支える人材を生み出さんと志したのである。
●夫れ君子は本を務む。本立って道生ず。而して治国の本は教学に在り。教学の要は人格の切磋琢磨に存す。(金鶏学院「設立趣意」より)
●この金鶏学院は古聖賢の学問研究所であり、同時に敬虔な道場であり君子のクラブである。徒に耳目三寸の学とか見聞の知識を修むる処にあらず。(『金鶏学院の風景』)
金鶏学院では「古道を究め時務を明かにすべき」諸般の講習・講演・出版が行われた。課目は、日本民族精神の研究・日本国体の研究・日本文化史・陽明学・農村経済及び風教振興の研究・東洋思想講話・亜細亜問題及び国際事情・現代思潮解説・剣道・柔術などだった。
学院には十七条から成る「学道箴規」が定められた。
一は「賢を尊び、道を慕ひ、恥を知る者入るべし。自負して信ならず、慚愧する所無き者は容さず。」
二は「天下の為に志を立て、生民の為に命を立てんとする者入るべし。徒に慷慨激越なるものは容さず。」である。
安岡は学監として、院生と起居を共にした。安岡は朝四時起床と真剣の素振りを自らに課し、自己習錬の目標を「人間は背後で線香を点けていても、灰が落ちたのが聞こえるぐらいでなけりゃいかん」「内に火山の熱火は蓄えても、外には湖水の平静を保たなくちゃいかん」(『安岡正篤の世界』)に定めて峻厳なる生活を送っていた。生活即学問であり、安岡の極めんとする学問は生き方に反映される力強いものでなければならなかった。
設立の翌年、安岡は、「入れ物はできたから、これに魂を入れなければならない」として、自らが長年に亘って参究実践してきた原理を系統立てて論述した教範書『東洋倫理概論』を執筆出版した。
更に、六年四月、埼玉県に日本農士学校を開校した。安岡は日本の精神復興は都会の頽廃文化に汚されていない農村の精神復興から成ると考えており、その信念の実践だった。六年七月には九州にも福岡農士学校が開校した。
これらの教育事業と並行して安岡を師と仰ぎ「哲人的教学を修め民族精神や国体を明らめ王道を学ぶ」集いは、政治家や財界、官僚、軍人の中にも広がって行く。官僚や政治家を中心に、昭和七年元旦には国維会が結成された。『列子』の「礼儀廉恥は国の維である」にちなんだ安岡の命名だった。
安岡の回りには道を求める多くの人々が教えを受けに集まった。作家の吉川英治や横綱双葉山もその一人だった。『荘子』の中の軍鶏の調教訓練の話に出て来る「木鶏」の事を学んだ双葉山が、六十九連勝がストップした時に、安岡宛に「ワレイマダモッケイタリエズ フタバヤマ」と打電した話は有名である。その頃の安岡の言葉を二つ紹介する。
●指導の力はそういふ理論に在るのではなくて、信念情操気魄に在る。人格の英邁に在る。練行の雄風に在る。そこに輝く睿智こそ、理屈屋の煩瑣な議論の思ひも及ばぬ尊いものなのである。(「国維」第九号 昭和八年二月)
●日本人である以上、日本精神はいづれも内具して居るのであるから、軽薄な外求を去って、己を誠にすれば日本精神はおのずと体現されるのである。(『国維』第五号・昭和七年十月「日本主義とは何ぞや」)
安岡正篤 東洋哲学の泰斗・人間学を提唱した昭和の導師1
天下を憤るは易いが、天下を救ふは難し
日本の陽明学の脈流を語る場合、大正から昭和にかけて、わが国の政治家・教育者・官僚・軍人に多大な影響を及ぼした碩学・安岡正篤の存在を抜きにする事は出来ない。
安岡は陽明学を始めとする儒教・老荘思想・仏教・神道等の東洋哲学を深く学び、その哲理によって自らを錬成して行く「人間学」を生涯示し続けた。
安岡は青年の頃に北一輝や大川周明と活動を共にした時代があった。しかし安岡は、当時の革新運動の底の浅さに失望して独自の道を歩み始めた。昭和六年の血盟団事件(一人一殺テロ)に対する安岡の次の言葉は安岡が求めた国家革新の理想が那辺にあったかを示している。
●王道は天下の為と雖も一民の命も忽にせぬものである。武士道は最もよくその敵を敬重することを教へる。刀を抜くことは最後として居る。(略)大丈夫止むを得ずして起つ時は天下環視の下に堂々義旗を翻すべきで、暗殺の様なことは避けねばならぬ。それに天下を救ふは一朝一夕で出来ない。幾段にも構成せられた人材が必要であり、また出来るだけ精透な時務眼と更に厳粛な徳操もなければならぬ。天下を憤るは易いが、天下を救ふは難い。出でゝ蒼生を誤る自任的英雄が如何に多いことか。(『童心残筆』)
安岡は、国家革新を唱える者の内実・人格の高潔さを問うたのだった。自らの生き方を正さずして国を正す事などありえないと信じた。『大学』に言う「修身→斉家→治国→平天下」の君子の道を安岡は自ら実践し、かつ教え導いたのだ。常に自らに反って内実を問う「自反の学」である。
王陽明の生き様に感動して成った『王陽明研究』
安岡正篤の名前を一躍世に知らしめたのが、安岡が東京帝国大学の卒業記念に著した『王陽明研究』である。大正八年に東京帝大法学部政治学科に入学した安岡は、大学の授業に何ら魅力を感じなかった為、もっぱら図書館に通って支那思想及び人物研究を独学で切り拓いて行く。その成果を大正十年に『支那思想及び人物講話』、翌年『王陽明研究』として出版した。安岡二十五歳(数え)の時である。
この中で安岡は王陽明の生き方を感動の言葉で記している。
●王陽明―陽明学の名はひさしく邦人に知られてきた。およそ人間の創造し得べき最も荘厳なる人格が陽明によつて実現されてをり、かかる人格の創造的白熱に燃ゆる力強い思想が凝つてその学となつてゐる
●陽明学によつてその真骨頭を養うた人物が、すべて卓然として富貴も淫する能はず、貧賤も移す能はず、威武も屈する能はざる底の大丈夫的風格に富んでゐるのは誠に必然の理由がある。(略)陽明はしばしば吾党の士は豪傑でなければならぬ。豪傑の士でなければ事を共にするに足らぬといつてゐる。(略)彼の所謂豪傑とは自己内心の至上要求に率うて、内面的にも外面的にも一切の盲目的他律的圧迫を排脱せんとする精神的勇気の謂である。
戦後の講演でも王陽明の魅力を次の様に語っている。
●実にあの病苦をひっさげて、あの艱難辛苦を極めた間に、よくあれだけの学問と講学ができたものであります。その事績を追い、彼の文を読み、彼の詩を読み、彼の書簡、および彼の献策、あるいは匪賊征伐・内乱鎮定の際の建白書、そういったものをしみじみ読んでおりますと、何とも言えぬ感激に打たれます。人間にはこういう人がおるのか、また人間はこういう境地にあって、こういうことができるものかとしみじみ感じます。敬虔かつ熱烈な門弟たちとの問答や書簡は、現代の評論家やジャーナリストによる、簡単な、軽薄な流行思想や評論の対象になるような人物や思索や学問とは全然違う。実にこれは深刻で霊活といいますか、陽明学とは、限りない感激のこもった、人間として地上における最も荘厳なる学問であり文章である、という気がいたします。(現代活学講話選集『王陽明』)
「処士」に生きる
安岡正篤は、明治三十一年二月十三日、大阪市で、堀田喜一・悦子夫妻の四男として誕生した。堀田家の祖先は四条畷の戦いで楠木正行を援け勇戦して戦死しており、代々南朝の勤皇家として令名があった。小学校一年の頃から四書五経を学び始めた。四条畷中学校に進学し、卒業までの五年間、通学時には歩きながら書物を読み、電柱や牛にぶつかったり、集中しすぎて家を通り越したエピソードが残っている。
近所の春日神社の神官浅見晏斎や陽明学者岡村閑翁に感化を受けた。中学時代に王陽明に傾倒し伝習録を貪り読んだという。
又、学校では剣道部で心身を鍛え、五年時には主将を務め、全関西中学校大会で優勝している。
秀才の誉れ高い正篤だったが、家の経済状態では進学もままならなかった為、教官の島長代が親交のあった東京の安岡盛治に養子縁組と第一高等学校進学を相談し、堀田家も了解して、正篤は安岡の養子となり上京して一高に入学、その後東京帝大に進学した。
この間安岡は、西洋哲学も学び書物を読破して行く。だが、西洋哲学では魂は振起されず、再び東洋聖賢の書に戻り、東洋哲学を研究し論文を次々と発表する。
大学卒業に際し、上杉慎吉教授から研究室に残るように懇請されるが、社会への道を選び、文部省に奉職。しかし六ヶ月で退職した。爾後、安岡は官職には就かず「処士(民間にいて仕官しない人)」の道を生涯貫いた。
●世の中に出てなにかになるということは、別の面からいうと、さびしいことです。専門をきめるということは、自分の生活の舞台を、全き無限のものから局限してしまうことです。なにかになるということは限定である。それになじんでしまうと、本当に区々たる人間になってしまいます。(『安岡正篤の世界』)
●爾来私は出世街道を断念して、ひたすら内心の至上命令にしたがつて生活した。学問も一つの目的から資料を集め、これ等を比較検討して、何等かの結論を出してゆくやうな客観的・科学的なことよりも、自分の内心に強く響く、自分の生命・情熱・霊魂を揺り動かすやうな文献を探求し、遍参した。丁度竹の根が地中に蔓延して、処々に筍を出すやうに、学問し執筆した。さうして伝習録が縁で、陽明を研究し、沈白沙、李卓吾、李ニ曲、劉念台、呂新吾、遡つて陸象山、朱晦庵、程明道、伊川、張横渠、邵康節、周茂叔などを遍歴し、日本では藤原惺窩、山鹿素行、中江藤樹、熊沢蕃山、山田方谷、春日潜庵、大塩中斎などに参究した。その間に法然、親鸞、日蓮、道元などから深い感化を受けた。特に、歴史的社会的に背骨ができたように思へたのは、史記と資治通鑑を読破したことであつた。(『王陽明研究』新序)
北一輝・大川周明との出会いと訣別
大正十一年七月、安岡は沼波瓊音の紹介で国家改造を志す猶存社の北一輝や満川亀太郎と会う。北は十五歳も年下の安岡の学と人物に驚嘆し、大川周明にも紹介した。
安岡は国家革新の志を抱く大川達との出会いを「活ける魂に触れ道徳的雄心の高鳴りを覚えた。」と記している。
●大学時代棄身になつてよく学問したが、その頃から私は一面強烈に革命を考へるやうになつた。しかし東洋先哲の学問の力であらう、今日の学生のやうに浅薄皮相な集団活動に趨らず、まづ深い政治哲学を持つた優れた同志の糾合を考へた。それが私の社会生活を築きあげる不思議な原動力になつてしまつた。当時第一次大戦の後で、社会的思想的混乱が甚だしく、共産主義革命思想運動も、正直強烈であつたが、それに対して勃然として民族主義に立つ昭和維新運動が始まつた。私はいつのまにかその激流の中にあつた。(『王陽明研究』新序)
十月、安岡は満川の紹介で原田政治と会い、酒井忠正伯爵を知る。酒井伯は安岡を高く評価し、酒井伯邸・金鶏園に東洋思想の研究所設立を勧めた。そこで亜細亜文化協会研究所が設立され、「東洋思想研究」を発刊し、安岡は学術主任に就任した。十二月には陽明学研究会が発足した。十三年、東洋思想研究所を組織して「東洋思想研究」を続刊する。
そして『日本精神の研究』を出版する。その中で日本の国体を語り、山鹿素行・吉田松陰・高杉東行・高橋泥舟・楠木正成・武士道・大塩中斎・西郷南洲について語った。安岡はこの著書を「一昨年来、私の参学生活に於いて自我の奥殿を通じて国民精神の真髄に触れ得た魂の記録である。」と述べている。
この本で安岡は「日本に於ては、革命は必ず天皇より出でなければならぬ。」「国家が政府の頽廃に依つて危殆に瀕する時、革命を遂行して新たなる局面を新開するは天徳である、天皇の御威徳である。」と「錦旗革命」論を述べている。
「白人の世界支配からのアジア解放」など、思想的には一致するが、考え方の齟齬から同志間の分裂が始まって行く。四月に北一輝と大川周明の対立で猶存社は分裂、大川・満川・安岡は猶存社を離れ、行地社を結成した。十四年四月、行地社は、国の柱となる人士養成の為の「大学寮」を開講する。だが十月に起こった安田共済事件で露見した運動家達の堕落の姿に安岡は嫌悪を感じ、大川達と別の独自の道を開始するのだった。
●国家革新・改造の名分確かなるも、身を正しそれに相応しい行を為す指導者でなければ維新の達成は難しい。迂遠な様でも古今ノ聖賢に学び之を行なえる人物の養成こそ急務なり(大正十五年一月『安岡正篤先生年譜』)
安岡は再び自らを見つめ直し、自らの天命を慎思した。
●草堂の縁にうずくまり、自分というものを沁々考えさせられる。一体お前は此の頃何をしてるんだ。教育者否、学者否、無職否、では処士とでも開き直るか。一不朽人なるべし。学問の意味を解し始めたのは、菜根をかむに決めた日(文部省辞職の日)からで爾来四年となる。かくて天地独往の客となり得たとき、堂々と教育者・学者と称するであろう。自ら樸学生と覚り樸学(儒学の事)十年の志を述ぶ。(大正十四年「秋風処士の感」)
金鶏学院・日本農士学校
深思する事一年、大正十五年十月、安岡の下に新しく塾風を興す議が起こり、御世が代わった昭和二年元旦、金鶏学院が創設された。三月には金鶏学寮(二階建各室四畳半―上下十八室)が新築落成。四月に開院した。
安岡は有為な青年をこの私塾道場で磨き上げ、国家を支える人材を生み出さんと志したのである。
●夫れ君子は本を務む。本立って道生ず。而して治国の本は教学に在り。教学の要は人格の切磋琢磨に存す。(金鶏学院「設立趣意」より)
●この金鶏学院は古聖賢の学問研究所であり、同時に敬虔な道場であり君子のクラブである。徒に耳目三寸の学とか見聞の知識を修むる処にあらず。(『金鶏学院の風景』)
金鶏学院では「古道を究め時務を明かにすべき」諸般の講習・講演・出版が行われた。課目は、日本民族精神の研究・日本国体の研究・日本文化史・陽明学・農村経済及び風教振興の研究・東洋思想講話・亜細亜問題及び国際事情・現代思潮解説・剣道・柔術などだった。
学院には十七条から成る「学道箴規」が定められた。
一は「賢を尊び、道を慕ひ、恥を知る者入るべし。自負して信ならず、慚愧する所無き者は容さず。」
二は「天下の為に志を立て、生民の為に命を立てんとする者入るべし。徒に慷慨激越なるものは容さず。」である。
安岡は学監として、院生と起居を共にした。安岡は朝四時起床と真剣の素振りを自らに課し、自己習錬の目標を「人間は背後で線香を点けていても、灰が落ちたのが聞こえるぐらいでなけりゃいかん」「内に火山の熱火は蓄えても、外には湖水の平静を保たなくちゃいかん」(『安岡正篤の世界』)に定めて峻厳なる生活を送っていた。生活即学問であり、安岡の極めんとする学問は生き方に反映される力強いものでなければならなかった。
設立の翌年、安岡は、「入れ物はできたから、これに魂を入れなければならない」として、自らが長年に亘って参究実践してきた原理を系統立てて論述した教範書『東洋倫理概論』を執筆出版した。
更に、六年四月、埼玉県に日本農士学校を開校した。安岡は日本の精神復興は都会の頽廃文化に汚されていない農村の精神復興から成ると考えており、その信念の実践だった。六年七月には九州にも福岡農士学校が開校した。
これらの教育事業と並行して安岡を師と仰ぎ「哲人的教学を修め民族精神や国体を明らめ王道を学ぶ」集いは、政治家や財界、官僚、軍人の中にも広がって行く。官僚や政治家を中心に、昭和七年元旦には国維会が結成された。『列子』の「礼儀廉恥は国の維である」にちなんだ安岡の命名だった。
安岡の回りには道を求める多くの人々が教えを受けに集まった。作家の吉川英治や横綱双葉山もその一人だった。『荘子』の中の軍鶏の調教訓練の話に出て来る「木鶏」の事を学んだ双葉山が、六十九連勝がストップした時に、安岡宛に「ワレイマダモッケイタリエズ フタバヤマ」と打電した話は有名である。その頃の安岡の言葉を二つ紹介する。
●指導の力はそういふ理論に在るのではなくて、信念情操気魄に在る。人格の英邁に在る。練行の雄風に在る。そこに輝く睿智こそ、理屈屋の煩瑣な議論の思ひも及ばぬ尊いものなのである。(「国維」第九号 昭和八年二月)
●日本人である以上、日本精神はいづれも内具して居るのであるから、軽薄な外求を去って、己を誠にすれば日本精神はおのずと体現されるのである。(『国維』第五号・昭和七年十月「日本主義とは何ぞや」)
















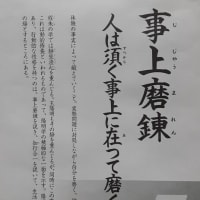



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます