忠臣蔵・大石内蔵助その二(『祖国と青年』平成25年6月号掲載)
個人の恩讐ではない。同志全員の戦いなのだ。「抜け駆け」は絶対に許さない。
一人のあだにてはこれなく候間 独り立ち本意を遂げ申すまじき事
(「大石内蔵助の平間村より同志に与えたる第一訓令」10月25日から11月5日の間)
リーダーは常に、組織(会社)の行く末に思いを致す中で、自らの身を処す宿命を担っている。組織(会社)には使命があり、そこに結集した数多人材の人生に責任を負わねばならないからである。大石内蔵助もその様な立場にいた。
幕府によって取り潰された(解散を命じられた)「お家」を如何に再興するのか。可能性がある限り、その努力を続ける事は、全体に責任を取るべき者の義務だった。同時に、それが叶わない時には、やはり、集団を率いる者として、同志の「無念の志」を晴らさせる責任も負っていた。前者が、浅野内匠頭の弟浅野大学によるお家再興の働きかけであり、後者が、主君の仇・吉良上野介を斃す事であった。
元禄十五年七月十八日、浅野大学の安芸藩へのお預けが決定し、浅野家再興の望みは断たれた。もはや残された道は後者しか無い。七月二十八日に円山で会議を行い、討入りへの具体的な手筈が話し合われた。
先ずは、百三十名まで膨らんだ同志の中から生死を共にする本物の人材を選りすぐる事だった。その結果五十五名が残った。
十月七日、愈々大石内蔵助は京都から江戸へと向かった。途中、箱根で鎌倉時代に仇討を果した曽我兄弟の墓に参り、墓の苔を削ってお守りとした。直ぐには江戸へ入らず、川崎の平間村に一旦居を構えた。何事にも慎重を期す大石らしい判断である。そこから既に江戸に潜入していた同志に十か条の訓令を発した。
それは、討入り時の衣服の事、武器はそれぞれ得意の物を用いる事、油断なく無用な事を慎む事、抜け駆けをしない事、敵の情報を集める事、金銭の慎み、集まった時の雑談や言行を慎む事、討入りの配置の事、敵は百人を超えるが必死の覚悟があれば勝利は間違いない事、改めて神文を出してもらう事、である。
公私混同は一切無い。預かった公金の全てを記した帳簿、とくとご覧下さい。
払い出し候趣 帳面に記し置き候 毛頭自分用事に仕り候儀御座無く候 委細帳面御引合わせ とくと御披見下さる可く候
(「大石内蔵助より落合与左衛門へ残務処理報告の状」抄 十一月二十九日)
大石内蔵助のリーダーシップの背景には、大石の持つ「資金」が威力を発揮していた。大石は、赤穂城の明け渡しの際、藩札の処理、藩士への手当金の処理、諸帳簿・諸目録の整理、浅野家縁故の寺への寄進、明け渡し時の使者への対応など、見事な手腕を発揮した。
特に、藩札処理に伴って生じた、塩田業者への貸付金の回収及び税金の未納分の回収などによって多額の財が生み出された。そこで、それらを旧藩士たちへの分配金に充てる事が可能となった。分配金は石高に応じて定められたが、下級者に厚く高級者ほど割りの薄い累減率とした。その上、自らの分配金三百両は放棄した。
それらを全て行なった上で残ったお金を「公金」として、大石が管理した。
その公金は討入りまでの間に、主家再興運動・亡主の供養・会議費・支援者への謝礼・義士たちの往来・一年十ヵ月に亘る浪士の生活の逼迫・東下り・弓鎗調達代などに支出された。大石は討入りの半月前の十一月二十九日に、その詳細を記した「預置候金銀請払帳」(決算書)を、傍証資料(領収証等)と共に、浅野内匠頭の奥方である瑤泉院の用人落合与左衛門に届けさせた。
その内容は、預かった公金が、金六百九十両二朱(約7400万円)、銀四十六匁九分五厘で、最終的には七両一歩の赤字となり、その分は大石が自分のお金で補填した。大石は私的には、家財道具等を売り払って得た百三十両を持っていた。
だが、自己及び家族の生計を営みかつ困窮する同志の支援の為には、それだけでは足りずに借財を頼んだりもしている。大石は同志達の生活費の援助に、私財から百四十両(現在の約1500万円)を支出したと言われている。
大石が多数の同志を束ねる事が出来たのは、同志達の生活の相談に親身になって応じ、公私両面に亘って面倒を見る優しさがあったからである。その為には私財を投じ借財をも厭わなかった。
更には、公的な資金の管理も素晴らしい。討入りが決まるまではかなりの日月があったにも拘らず、同志が江戸に集結する為の費用や武器・武具等の購入費は十分に確保していたのである。赤字が七両一分(約76万円)しか出なかった事は、大石の資金管理力の賜であろう。リーダーには、この様な金銭管理能力が求められる。
心一つに討ち入った以上、吉良親子の首を取った者も、警護の任についた者も、その功績は全く同じである。
上野介屋敷え押し込み候働きの儀 功の深浅これあるべからず 上州(上野介)父子印揚げ候者も 警固一と通りの者も同前たるべし
(「討入起請文前書」十一月七日・八日)
大石は、最後の最後まで同志の団結を徹底させた。一か月前に記した起請文の前書きでは、四カ条の掟を記し、「右四箇条あい背き候時は この一大事成就仕るべからず」と述べ、背いた者は、大事を前に逃げ出した卑怯者と同罪になると、きつく戒めている。
その四点とは、
一、讐敵吉良上野介親子を討ち取る志を確認した所、臆病心に駆られて逃げ出す者が出た。彼らを打ち捨てて今や必死の覚悟の者だけが残ったので、必ず亡き主君の霊魂が見ていて下さるであろう事。
二、吉良の屋敷に討ち入る時の働きに於て、功績の深浅は無い。吉良上野介親子の首を挙げた者も、警固の為持ち場を離れなかった者も同様の働きなのである。それ故、グループの組み合わせや与えられた任務に対し、好き嫌いを言ってはならない。前と後ろとで争う様な事があってはならない。全員が心を一つにして、どんな役割が与えられ様とも少しも難渋したりする事が無い様にすべき事。
三、皆がこのようにすべきだという事に対して我意を貫き約束事を破ったりしてはならない。理の当然に従わなくてはならない。同志の中で、日頃はあまりよく思わない者が居ても、討入りの際には互いに助け合い、急な対応に抜かりなく、勝利を万全の事としなければならない。
四、吉良上野介父子を討ち取った後、自分だけが生き延びようなどと思う者は居ないので、あくまでも同志一同申し合わせて、散り散りに成る様な事があってはならない。手負いの者があったなら、皆で助け合いその場に全員が集合する事。
大石は四十七士全員の心が一つになり、一丸となって目的達成の為に突き進む事を求めた。その事を確認した上で、それぞれの個性が最も生かせる組み合わせや配置を考え抜いて決定した。
勝利を導くのは、天の時・地の利・人の和と言うが、最も大事なのは人の和である。目立つ華々しい役割を見事にこなす者も居れば、目立たず地道に下支えする者も居る。与えられた役割には貴賤も上下もない。又、組織の中には「うまが合わない者」も必らず居る。だが、戦いの場に於ては皆が仲間であり、お互い支え合い助け合わなければ勝利は覚束ない。
赤穂浪士の討ち入り成功の要因は、大石を中心に心を一つにして大義を貫いた点に在る。
もはや心にかかる雲は全くない。全く澄み渡った心境である。
あら楽し思ひははるゝ身はすつる浮世の月にかゝる雲なし(辞世〈泉岳寺にて〉)
討入りの際、大石内蔵助達は吉良邸玄関の前に、「浅野内匠頭匠家来口上」を文箱に入れて青竹に結び付けて立てた。この口上書は、討入り趣意書とも言うべきもので、幾度も文言を練り、最終的には儒者の細井広沢にも相談して確定したものである。
何故討入りに至ったのかが簡潔に表現されており、幕府の大目付・老中や将軍綱吉までも、その名文に感嘆したという。
その中に「君父の讎共に天を戴く可からざるの儀、黙止難く、今日上野介殿御宅へ推参仕り候。」とある。支那の古典である『礼記』曲礼には「父の讎は與に共に天を戴かず」とあるが、それを「君父の讎」と直して家来としての忠義の志を示したのである。この名文によって赤穂浪士は赤穂義士となり、武士を始め町人達からもその快挙は称えられる様になって行く。
討入り成就後、訳あって脱落せしめた一人を除いた四十六士は、細川家(肥後)、松平〈久松〉家(松山)、毛利家(長府)、水野家(岡崎)の四家に分かれてお預けになり、幕府の罪人ではあるけれども、「武士の鑑」として、敬意を以て遇せられ、翌年二月四日に切腹し、全員が浅野内匠頭の眠る泉岳寺に手厚く葬られた。
この項で紹介しているのは、討入りが成功し泉岳寺に引き上げた際、大石内蔵助が詠んだ歌である。それが辞世にもなった。浅野内匠頭切腹から一年九か月に亘る大石の戦いはここに集結した。物事を成し遂げた者のみが抱く事の出来るすがすがしさがこの歌にはこめられている。
大石は討入り直前に菩提寺の住職に送った手紙の中で、自分達の名誉回復が叶った後の世には、残した次男吉之進によって家を再興させたいものだと漏らしている。吉之進は仏門に入り若死にしたが、三男の良恭は、後に広島の浅野家に引き取られ父内蔵助と同じ千五百石を以て召し抱えられ、大石家は再興した。大石内蔵助の心にかかって居たわずかな雲も一切が晴れ渡ったのである。
大石内蔵助が切腹した旧細川藩邸跡地には、今尚「大石良雄等自刃ノ跡」が囲いをもって保存され、「正義を愛し名節を重んずる者は暫くここに歩を停めよ。」と記されている。「節義」とは何か、そしてそれを貫く事の出来る力量とは何かを、大石内蔵助は私達に示し続けている。
個人の恩讐ではない。同志全員の戦いなのだ。「抜け駆け」は絶対に許さない。
一人のあだにてはこれなく候間 独り立ち本意を遂げ申すまじき事
(「大石内蔵助の平間村より同志に与えたる第一訓令」10月25日から11月5日の間)
リーダーは常に、組織(会社)の行く末に思いを致す中で、自らの身を処す宿命を担っている。組織(会社)には使命があり、そこに結集した数多人材の人生に責任を負わねばならないからである。大石内蔵助もその様な立場にいた。
幕府によって取り潰された(解散を命じられた)「お家」を如何に再興するのか。可能性がある限り、その努力を続ける事は、全体に責任を取るべき者の義務だった。同時に、それが叶わない時には、やはり、集団を率いる者として、同志の「無念の志」を晴らさせる責任も負っていた。前者が、浅野内匠頭の弟浅野大学によるお家再興の働きかけであり、後者が、主君の仇・吉良上野介を斃す事であった。
元禄十五年七月十八日、浅野大学の安芸藩へのお預けが決定し、浅野家再興の望みは断たれた。もはや残された道は後者しか無い。七月二十八日に円山で会議を行い、討入りへの具体的な手筈が話し合われた。
先ずは、百三十名まで膨らんだ同志の中から生死を共にする本物の人材を選りすぐる事だった。その結果五十五名が残った。
十月七日、愈々大石内蔵助は京都から江戸へと向かった。途中、箱根で鎌倉時代に仇討を果した曽我兄弟の墓に参り、墓の苔を削ってお守りとした。直ぐには江戸へ入らず、川崎の平間村に一旦居を構えた。何事にも慎重を期す大石らしい判断である。そこから既に江戸に潜入していた同志に十か条の訓令を発した。
それは、討入り時の衣服の事、武器はそれぞれ得意の物を用いる事、油断なく無用な事を慎む事、抜け駆けをしない事、敵の情報を集める事、金銭の慎み、集まった時の雑談や言行を慎む事、討入りの配置の事、敵は百人を超えるが必死の覚悟があれば勝利は間違いない事、改めて神文を出してもらう事、である。
公私混同は一切無い。預かった公金の全てを記した帳簿、とくとご覧下さい。
払い出し候趣 帳面に記し置き候 毛頭自分用事に仕り候儀御座無く候 委細帳面御引合わせ とくと御披見下さる可く候
(「大石内蔵助より落合与左衛門へ残務処理報告の状」抄 十一月二十九日)
大石内蔵助のリーダーシップの背景には、大石の持つ「資金」が威力を発揮していた。大石は、赤穂城の明け渡しの際、藩札の処理、藩士への手当金の処理、諸帳簿・諸目録の整理、浅野家縁故の寺への寄進、明け渡し時の使者への対応など、見事な手腕を発揮した。
特に、藩札処理に伴って生じた、塩田業者への貸付金の回収及び税金の未納分の回収などによって多額の財が生み出された。そこで、それらを旧藩士たちへの分配金に充てる事が可能となった。分配金は石高に応じて定められたが、下級者に厚く高級者ほど割りの薄い累減率とした。その上、自らの分配金三百両は放棄した。
それらを全て行なった上で残ったお金を「公金」として、大石が管理した。
その公金は討入りまでの間に、主家再興運動・亡主の供養・会議費・支援者への謝礼・義士たちの往来・一年十ヵ月に亘る浪士の生活の逼迫・東下り・弓鎗調達代などに支出された。大石は討入りの半月前の十一月二十九日に、その詳細を記した「預置候金銀請払帳」(決算書)を、傍証資料(領収証等)と共に、浅野内匠頭の奥方である瑤泉院の用人落合与左衛門に届けさせた。
その内容は、預かった公金が、金六百九十両二朱(約7400万円)、銀四十六匁九分五厘で、最終的には七両一歩の赤字となり、その分は大石が自分のお金で補填した。大石は私的には、家財道具等を売り払って得た百三十両を持っていた。
だが、自己及び家族の生計を営みかつ困窮する同志の支援の為には、それだけでは足りずに借財を頼んだりもしている。大石は同志達の生活費の援助に、私財から百四十両(現在の約1500万円)を支出したと言われている。
大石が多数の同志を束ねる事が出来たのは、同志達の生活の相談に親身になって応じ、公私両面に亘って面倒を見る優しさがあったからである。その為には私財を投じ借財をも厭わなかった。
更には、公的な資金の管理も素晴らしい。討入りが決まるまではかなりの日月があったにも拘らず、同志が江戸に集結する為の費用や武器・武具等の購入費は十分に確保していたのである。赤字が七両一分(約76万円)しか出なかった事は、大石の資金管理力の賜であろう。リーダーには、この様な金銭管理能力が求められる。
心一つに討ち入った以上、吉良親子の首を取った者も、警護の任についた者も、その功績は全く同じである。
上野介屋敷え押し込み候働きの儀 功の深浅これあるべからず 上州(上野介)父子印揚げ候者も 警固一と通りの者も同前たるべし
(「討入起請文前書」十一月七日・八日)
大石は、最後の最後まで同志の団結を徹底させた。一か月前に記した起請文の前書きでは、四カ条の掟を記し、「右四箇条あい背き候時は この一大事成就仕るべからず」と述べ、背いた者は、大事を前に逃げ出した卑怯者と同罪になると、きつく戒めている。
その四点とは、
一、讐敵吉良上野介親子を討ち取る志を確認した所、臆病心に駆られて逃げ出す者が出た。彼らを打ち捨てて今や必死の覚悟の者だけが残ったので、必ず亡き主君の霊魂が見ていて下さるであろう事。
二、吉良の屋敷に討ち入る時の働きに於て、功績の深浅は無い。吉良上野介親子の首を挙げた者も、警固の為持ち場を離れなかった者も同様の働きなのである。それ故、グループの組み合わせや与えられた任務に対し、好き嫌いを言ってはならない。前と後ろとで争う様な事があってはならない。全員が心を一つにして、どんな役割が与えられ様とも少しも難渋したりする事が無い様にすべき事。
三、皆がこのようにすべきだという事に対して我意を貫き約束事を破ったりしてはならない。理の当然に従わなくてはならない。同志の中で、日頃はあまりよく思わない者が居ても、討入りの際には互いに助け合い、急な対応に抜かりなく、勝利を万全の事としなければならない。
四、吉良上野介父子を討ち取った後、自分だけが生き延びようなどと思う者は居ないので、あくまでも同志一同申し合わせて、散り散りに成る様な事があってはならない。手負いの者があったなら、皆で助け合いその場に全員が集合する事。
大石は四十七士全員の心が一つになり、一丸となって目的達成の為に突き進む事を求めた。その事を確認した上で、それぞれの個性が最も生かせる組み合わせや配置を考え抜いて決定した。
勝利を導くのは、天の時・地の利・人の和と言うが、最も大事なのは人の和である。目立つ華々しい役割を見事にこなす者も居れば、目立たず地道に下支えする者も居る。与えられた役割には貴賤も上下もない。又、組織の中には「うまが合わない者」も必らず居る。だが、戦いの場に於ては皆が仲間であり、お互い支え合い助け合わなければ勝利は覚束ない。
赤穂浪士の討ち入り成功の要因は、大石を中心に心を一つにして大義を貫いた点に在る。
もはや心にかかる雲は全くない。全く澄み渡った心境である。
あら楽し思ひははるゝ身はすつる浮世の月にかゝる雲なし(辞世〈泉岳寺にて〉)
討入りの際、大石内蔵助達は吉良邸玄関の前に、「浅野内匠頭匠家来口上」を文箱に入れて青竹に結び付けて立てた。この口上書は、討入り趣意書とも言うべきもので、幾度も文言を練り、最終的には儒者の細井広沢にも相談して確定したものである。
何故討入りに至ったのかが簡潔に表現されており、幕府の大目付・老中や将軍綱吉までも、その名文に感嘆したという。
その中に「君父の讎共に天を戴く可からざるの儀、黙止難く、今日上野介殿御宅へ推参仕り候。」とある。支那の古典である『礼記』曲礼には「父の讎は與に共に天を戴かず」とあるが、それを「君父の讎」と直して家来としての忠義の志を示したのである。この名文によって赤穂浪士は赤穂義士となり、武士を始め町人達からもその快挙は称えられる様になって行く。
討入り成就後、訳あって脱落せしめた一人を除いた四十六士は、細川家(肥後)、松平〈久松〉家(松山)、毛利家(長府)、水野家(岡崎)の四家に分かれてお預けになり、幕府の罪人ではあるけれども、「武士の鑑」として、敬意を以て遇せられ、翌年二月四日に切腹し、全員が浅野内匠頭の眠る泉岳寺に手厚く葬られた。
この項で紹介しているのは、討入りが成功し泉岳寺に引き上げた際、大石内蔵助が詠んだ歌である。それが辞世にもなった。浅野内匠頭切腹から一年九か月に亘る大石の戦いはここに集結した。物事を成し遂げた者のみが抱く事の出来るすがすがしさがこの歌にはこめられている。
大石は討入り直前に菩提寺の住職に送った手紙の中で、自分達の名誉回復が叶った後の世には、残した次男吉之進によって家を再興させたいものだと漏らしている。吉之進は仏門に入り若死にしたが、三男の良恭は、後に広島の浅野家に引き取られ父内蔵助と同じ千五百石を以て召し抱えられ、大石家は再興した。大石内蔵助の心にかかって居たわずかな雲も一切が晴れ渡ったのである。
大石内蔵助が切腹した旧細川藩邸跡地には、今尚「大石良雄等自刃ノ跡」が囲いをもって保存され、「正義を愛し名節を重んずる者は暫くここに歩を停めよ。」と記されている。「節義」とは何か、そしてそれを貫く事の出来る力量とは何かを、大石内蔵助は私達に示し続けている。
















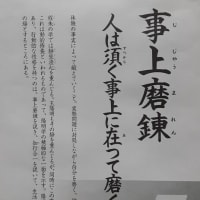



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます