忠臣蔵・大石内蔵助その一(『祖国と青年』平成25年5月号掲載)
素行が残した『精神』は赤穂藩危急の時にこそ甦る
将来万一緩急の場合など生じ申さば、思ひ当らせられる節もおはさう歟(浅野長矩公に語った山鹿素行の言葉)
前回まで紹介した山鹿素行は、赤穂藩に二度お世話になっている。素行には、三代将軍家光に取り立てられ幕臣となる内命があった為、諸大名の招聘を断り続けていた。ところが慶安四年(1651)に家光は逝去、将軍家出仕の見込みも無くなる。素行三十歳の時だった。
そこで翌年、素行は播州赤穂藩主浅野長直からの招聘に応じ、家臣となった。石高は千石(現在の約一億円)である。翌年九月から次の年の五月迄は赤穂に滞在したが、その後は江戸に戻り、万治三年(1660)まで仕えた。
二回目は、寛文六年(1666)である。素行は、官学である朱子学を批判する内容を含む著書『聖教要録』を前年に出版していた。その著書が幕府から譴責を受け、江戸から追放処分を受け、赤穂藩配流となった。爾来、延宝三年(1675)まで十年、赤穂の地で過ごした。
素行は、罪を許されて赤穂から江戸へ赴く際に、赤穂藩主浅野長矩公に次の様に述べたという。
「先君以来、殿様にはこの愚かな私をお見捨てならずに、国士として扱って戴きました。その御恩は報いる事も難しい程のものであります。それ故、せめて万分の一の御奉公にと思い、日頃から御家臣の教育について力を尽して参りました。将来、御家に万一の事が生じた際には、思い当たられる事もあるかと存じます。」
素行が赤穂に配流されていた時、大石内蔵助良雄は七歳~十七歳である。素行の世話に当ったのが大叔父の大石頼母助良重だった。素行が赤穂を去って二十六年後に浅野内匠頭長矩の吉良上野介に対する刃傷事件が起こり、赤穂浪士の討ち入りが行われる。それを担った赤穂浪士の精神を培ったものが、山鹿素行の残した「士道」教育であった。
納得出来ないものは認める訳には行かない
(相手方恙なき段之を承り)家中納得仕るべき筋お立て下され候
(「大石内蔵助より両目付へ差出さんとしたる嘆願書」元禄十四年三月二十九日)
毎年、十二月になると赤穂浪士の忠臣蔵が思い起こされ、テレビでも様々に放映されている。幕府の理不尽な判定に異を唱え、家臣達が様々な苦難を乗り越えて、主君の仇を討つ「忠臣蔵」は日本人の心を大きく揺り動かす物語である。
赤穂浪士四十七士の討ち入りが元禄十五年(1702)、その四十六年後には浄瑠璃として「仮名手本忠臣蔵」が上演され大喝采を博した。大東亜戦争敗戦後、米占領軍は忠臣蔵の上演を禁止した。理不尽な占領軍に対する日本人の「討ち入り」を恐怖したのだった。
だが、忠臣蔵は日本人の中に脈々と受け継がれている。ちなみに私は、熊本の済々黌高校を昭和四十七年に卒業したので、私達の同窓会は「討入会」と称している。
浅野内匠頭が吉良上野介に斬りかかった原因については様々な説がある。だが、それは不問に付され、江戸城内での刃傷沙汰というだけで、内匠頭は即日切腹、赤穂藩は取り潰された。一方、吉良上野介には御咎めなしだった。実は、それ迄にも江戸城内での刃傷事件は幾つか起こっていた。そして、当時の法度(法律)では「喧嘩両成敗」であり、双方に死が命じられていた。浅野内匠頭の切腹の報を聞いた家臣達は、主君の遺恨の相手も当然成敗されたものと思っていた。だが、吉良には御咎めなしだった。
家老の大石内蔵助は、赤穂城の明け渡しを粛々と進め、見分役の目付二人に二度にわたってお家再興の嘆願を行った。その際の嘆願書には、婉曲な表現ながら、納得できないものは認める訳には参らぬ、との大石の強い意志が込められている。
「わが藩の者達は無骨者ばかりで一心に主君の事を思い、相手方(上野介)が無事な事を知り、心安らかでない者が多数おります。年寄りの料簡ではなだめがたいものがあります。何も上野介様に対するお仕置きを願っている訳ではありませんが、何卒、家中の者達が納得出来る措置を御取り戴きますならとても有り難い事でございます。」
この時、大石内蔵助は内匠頭の弟である浅野大学によるお家再興を嘆願している。昼行燈と呼ばれた大石内蔵助、礼儀を尽して幕府の目付に応対したが、その心の中には、「納得できない者は許さない」との赤々と燃える思いが秘められていた。
私心を捨てて本質を見定めれば世間の批判など気にする必要はない
私を捨て根元を見候えば世間の批判差して貪着申すべきこととは存ぜず候
(「大石内蔵助より三士へ事理を説き自重を望むの状」元禄十四年十月五日)
大石内蔵助は、「お家再興運動」と「上野介処分要求(討入り準備)の両面を見据えて準備を行っていく。その際、大石には、様々な年代、考え方の同志を如何に束ねて計画を遂行していくか、大変なリーダーシップが要求された。
討入り時の大石内蔵助は四十五歳、他の同志の年代は、七十歳代一人、六十歳代五人、五十歳代四人、四十歳代六人、三十歳代十七人、二十歳代十三人、十歳代二人、である。大石の年代以上の者が十二人居た。これらの者達が、江戸や大坂・赤穂など各地に潜伏していたのである。特に江戸の急進派である高田郡兵衛・堀部安兵衛・奥田孫大夫の三士からは、討入りの決行を求める矢の如き催促が寄せられた。
全てそうだが、追いつめられた際、勢いのある言論の方が勝を決する事が多い。冷静な議論は「弱腰」「軟弱」との評を受け易い。大石は、お家復興運動に批判的な堀部安兵衛に「今度の事はわしに任せろ。此の事だけで終わる事は無い、以後の含みもあるのだ。」と述べている。
だが、江戸に居る浪士達は、吉良上野介が同地に居り、江戸の庶民達の「赤穂の浪人たちは何をしている。主君の仇討もせず腰抜けばかりではないか。」との声にプライドを傷つけられていた。
大石は、急進派三士に次の様に述べる。「我々が時を待っているのは、大学様(内匠頭の弟)によるお家復興に万一の望みをかけているからではないか。事を急いで私心を行うなら、浅野家の根本まで絶ってしまう事になりかねない。世間の者がとやかくいおうとも、私心を捨てて根元を見据えるならば、世間の批判にはさして頓着する事もあるまい。今は、幕府が大学様を如何に扱うのかを見定めているのだ。大学様が如何になられようとも、我々の志さえしっかり立っているなら、その時に応じた対応が出来るではないか。世間の事は気にする必要は無い。」
江戸の地では無く、少し距離を置いた京都山科に自らの居を構える事によって、大石は状況を冷静に分析する事が出来た。正に深謀遠慮である。我々も、日々様々な問題に直面するが、その渦中から少し離れて冷静に考える事でその解決の糸口が見えて来る事が多々ある。それを「間」という。間をとる事により、より冷静・客観的な議論が可能となるのである。
物事を為すのは、家を建てる様なものであり、念を入れて取り掛からねば成功しない
幾重にも幾重にも地形から慥かに 宜しく念を入れ候て 取り立て候儀第一と存じ候
(「大石内蔵助より堀部弥兵衛へ三士説得を依頼するの状」元禄十四年十二月二十五日)
元禄十四年十二月二十五日、大石内蔵助は「江戸三士へ急挙を誡むるの状」「堀部弥兵衛へ三士説得を依頼するの状」を送っている。その中で大石は、急進派の面々を「下手大工衆(下手な大工)」という言葉で表現している。その内容は次の様なものである。
「主君の遺恨を晴らす事は大変な事業であり。必らず成功させねばならない。それは家や土地の普請工事の様な物である。普請の際は、幾度も幾度も地形調査を念入りに行って取り掛かるのが第一である。更には材料準備から始めて、念には念を入れて基礎を固め、設計図を描いて話し合って行わなければならない。いらだって急いで事を行っては、材木も粗末なものとなり出来上がりも不充分な事になりかねない。例え手に入る材木でも十分念入りに検討せねば完成は覚束ない。」
「ご隠居(吉良上野介)にお目にかかりたくても、御隠居は気ままに引き籠っておられ、中々お会いする事も難しい。どうしてもお会いする事ができないなら若旦那(吉良の継嗣の左兵衛)にお会いすればよい。苛立って御普請を急ぐ事はない。下手な大工衆達が色々と物事を進め様とも、大工衆を統括する奉行が確りと落ち着いて物事を進めたなら、大工衆のあせりも落ち着くのだ。」
この書簡の二週間前に、吉良上野介が隠居し、左兵衛が吉良家を相続する事が決まっていた。主君の仇である上野介の隠居は、敵の雲隠れという新たな事態を生み出すかもしれず、更に慎重かつ緻密な準備が必要となった。それ故軽挙を厳しく戒めたのである。
物事を為すリーダーは良く「大工の棟梁」に例えられる。
棟梁は、為さんとする事業の、①構想を描き、②材料を精査して準備し、③力量ある大工を揃え適材適所し、④計画を具体的実行に移し、⑤士気を高めて全力投球させ、⑥日々の進捗を計って計画を再調整し、⑦大工個々人の癖を相補わせ、⑧最後まで手を抜かず、⑨完成に至らしめる、のである。日本人は「集団力(和の力)」が他民族と較べて極めて高いと言われている。その意味で、集団の成否はその中心者の力量に全てがかかっている。
「長」と名のつく役職にある者には、大石内蔵助のリーダーシップはとても参考になると思う。
素行が残した『精神』は赤穂藩危急の時にこそ甦る
将来万一緩急の場合など生じ申さば、思ひ当らせられる節もおはさう歟(浅野長矩公に語った山鹿素行の言葉)
前回まで紹介した山鹿素行は、赤穂藩に二度お世話になっている。素行には、三代将軍家光に取り立てられ幕臣となる内命があった為、諸大名の招聘を断り続けていた。ところが慶安四年(1651)に家光は逝去、将軍家出仕の見込みも無くなる。素行三十歳の時だった。
そこで翌年、素行は播州赤穂藩主浅野長直からの招聘に応じ、家臣となった。石高は千石(現在の約一億円)である。翌年九月から次の年の五月迄は赤穂に滞在したが、その後は江戸に戻り、万治三年(1660)まで仕えた。
二回目は、寛文六年(1666)である。素行は、官学である朱子学を批判する内容を含む著書『聖教要録』を前年に出版していた。その著書が幕府から譴責を受け、江戸から追放処分を受け、赤穂藩配流となった。爾来、延宝三年(1675)まで十年、赤穂の地で過ごした。
素行は、罪を許されて赤穂から江戸へ赴く際に、赤穂藩主浅野長矩公に次の様に述べたという。
「先君以来、殿様にはこの愚かな私をお見捨てならずに、国士として扱って戴きました。その御恩は報いる事も難しい程のものであります。それ故、せめて万分の一の御奉公にと思い、日頃から御家臣の教育について力を尽して参りました。将来、御家に万一の事が生じた際には、思い当たられる事もあるかと存じます。」
素行が赤穂に配流されていた時、大石内蔵助良雄は七歳~十七歳である。素行の世話に当ったのが大叔父の大石頼母助良重だった。素行が赤穂を去って二十六年後に浅野内匠頭長矩の吉良上野介に対する刃傷事件が起こり、赤穂浪士の討ち入りが行われる。それを担った赤穂浪士の精神を培ったものが、山鹿素行の残した「士道」教育であった。
納得出来ないものは認める訳には行かない
(相手方恙なき段之を承り)家中納得仕るべき筋お立て下され候
(「大石内蔵助より両目付へ差出さんとしたる嘆願書」元禄十四年三月二十九日)
毎年、十二月になると赤穂浪士の忠臣蔵が思い起こされ、テレビでも様々に放映されている。幕府の理不尽な判定に異を唱え、家臣達が様々な苦難を乗り越えて、主君の仇を討つ「忠臣蔵」は日本人の心を大きく揺り動かす物語である。
赤穂浪士四十七士の討ち入りが元禄十五年(1702)、その四十六年後には浄瑠璃として「仮名手本忠臣蔵」が上演され大喝采を博した。大東亜戦争敗戦後、米占領軍は忠臣蔵の上演を禁止した。理不尽な占領軍に対する日本人の「討ち入り」を恐怖したのだった。
だが、忠臣蔵は日本人の中に脈々と受け継がれている。ちなみに私は、熊本の済々黌高校を昭和四十七年に卒業したので、私達の同窓会は「討入会」と称している。
浅野内匠頭が吉良上野介に斬りかかった原因については様々な説がある。だが、それは不問に付され、江戸城内での刃傷沙汰というだけで、内匠頭は即日切腹、赤穂藩は取り潰された。一方、吉良上野介には御咎めなしだった。実は、それ迄にも江戸城内での刃傷事件は幾つか起こっていた。そして、当時の法度(法律)では「喧嘩両成敗」であり、双方に死が命じられていた。浅野内匠頭の切腹の報を聞いた家臣達は、主君の遺恨の相手も当然成敗されたものと思っていた。だが、吉良には御咎めなしだった。
家老の大石内蔵助は、赤穂城の明け渡しを粛々と進め、見分役の目付二人に二度にわたってお家再興の嘆願を行った。その際の嘆願書には、婉曲な表現ながら、納得できないものは認める訳には参らぬ、との大石の強い意志が込められている。
「わが藩の者達は無骨者ばかりで一心に主君の事を思い、相手方(上野介)が無事な事を知り、心安らかでない者が多数おります。年寄りの料簡ではなだめがたいものがあります。何も上野介様に対するお仕置きを願っている訳ではありませんが、何卒、家中の者達が納得出来る措置を御取り戴きますならとても有り難い事でございます。」
この時、大石内蔵助は内匠頭の弟である浅野大学によるお家再興を嘆願している。昼行燈と呼ばれた大石内蔵助、礼儀を尽して幕府の目付に応対したが、その心の中には、「納得できない者は許さない」との赤々と燃える思いが秘められていた。
私心を捨てて本質を見定めれば世間の批判など気にする必要はない
私を捨て根元を見候えば世間の批判差して貪着申すべきこととは存ぜず候
(「大石内蔵助より三士へ事理を説き自重を望むの状」元禄十四年十月五日)
大石内蔵助は、「お家再興運動」と「上野介処分要求(討入り準備)の両面を見据えて準備を行っていく。その際、大石には、様々な年代、考え方の同志を如何に束ねて計画を遂行していくか、大変なリーダーシップが要求された。
討入り時の大石内蔵助は四十五歳、他の同志の年代は、七十歳代一人、六十歳代五人、五十歳代四人、四十歳代六人、三十歳代十七人、二十歳代十三人、十歳代二人、である。大石の年代以上の者が十二人居た。これらの者達が、江戸や大坂・赤穂など各地に潜伏していたのである。特に江戸の急進派である高田郡兵衛・堀部安兵衛・奥田孫大夫の三士からは、討入りの決行を求める矢の如き催促が寄せられた。
全てそうだが、追いつめられた際、勢いのある言論の方が勝を決する事が多い。冷静な議論は「弱腰」「軟弱」との評を受け易い。大石は、お家復興運動に批判的な堀部安兵衛に「今度の事はわしに任せろ。此の事だけで終わる事は無い、以後の含みもあるのだ。」と述べている。
だが、江戸に居る浪士達は、吉良上野介が同地に居り、江戸の庶民達の「赤穂の浪人たちは何をしている。主君の仇討もせず腰抜けばかりではないか。」との声にプライドを傷つけられていた。
大石は、急進派三士に次の様に述べる。「我々が時を待っているのは、大学様(内匠頭の弟)によるお家復興に万一の望みをかけているからではないか。事を急いで私心を行うなら、浅野家の根本まで絶ってしまう事になりかねない。世間の者がとやかくいおうとも、私心を捨てて根元を見据えるならば、世間の批判にはさして頓着する事もあるまい。今は、幕府が大学様を如何に扱うのかを見定めているのだ。大学様が如何になられようとも、我々の志さえしっかり立っているなら、その時に応じた対応が出来るではないか。世間の事は気にする必要は無い。」
江戸の地では無く、少し距離を置いた京都山科に自らの居を構える事によって、大石は状況を冷静に分析する事が出来た。正に深謀遠慮である。我々も、日々様々な問題に直面するが、その渦中から少し離れて冷静に考える事でその解決の糸口が見えて来る事が多々ある。それを「間」という。間をとる事により、より冷静・客観的な議論が可能となるのである。
物事を為すのは、家を建てる様なものであり、念を入れて取り掛からねば成功しない
幾重にも幾重にも地形から慥かに 宜しく念を入れ候て 取り立て候儀第一と存じ候
(「大石内蔵助より堀部弥兵衛へ三士説得を依頼するの状」元禄十四年十二月二十五日)
元禄十四年十二月二十五日、大石内蔵助は「江戸三士へ急挙を誡むるの状」「堀部弥兵衛へ三士説得を依頼するの状」を送っている。その中で大石は、急進派の面々を「下手大工衆(下手な大工)」という言葉で表現している。その内容は次の様なものである。
「主君の遺恨を晴らす事は大変な事業であり。必らず成功させねばならない。それは家や土地の普請工事の様な物である。普請の際は、幾度も幾度も地形調査を念入りに行って取り掛かるのが第一である。更には材料準備から始めて、念には念を入れて基礎を固め、設計図を描いて話し合って行わなければならない。いらだって急いで事を行っては、材木も粗末なものとなり出来上がりも不充分な事になりかねない。例え手に入る材木でも十分念入りに検討せねば完成は覚束ない。」
「ご隠居(吉良上野介)にお目にかかりたくても、御隠居は気ままに引き籠っておられ、中々お会いする事も難しい。どうしてもお会いする事ができないなら若旦那(吉良の継嗣の左兵衛)にお会いすればよい。苛立って御普請を急ぐ事はない。下手な大工衆達が色々と物事を進め様とも、大工衆を統括する奉行が確りと落ち着いて物事を進めたなら、大工衆のあせりも落ち着くのだ。」
この書簡の二週間前に、吉良上野介が隠居し、左兵衛が吉良家を相続する事が決まっていた。主君の仇である上野介の隠居は、敵の雲隠れという新たな事態を生み出すかもしれず、更に慎重かつ緻密な準備が必要となった。それ故軽挙を厳しく戒めたのである。
物事を為すリーダーは良く「大工の棟梁」に例えられる。
棟梁は、為さんとする事業の、①構想を描き、②材料を精査して準備し、③力量ある大工を揃え適材適所し、④計画を具体的実行に移し、⑤士気を高めて全力投球させ、⑥日々の進捗を計って計画を再調整し、⑦大工個々人の癖を相補わせ、⑧最後まで手を抜かず、⑨完成に至らしめる、のである。日本人は「集団力(和の力)」が他民族と較べて極めて高いと言われている。その意味で、集団の成否はその中心者の力量に全てがかかっている。
「長」と名のつく役職にある者には、大石内蔵助のリーダーシップはとても参考になると思う。
















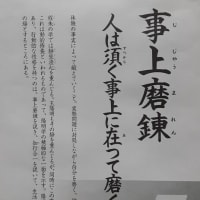



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます