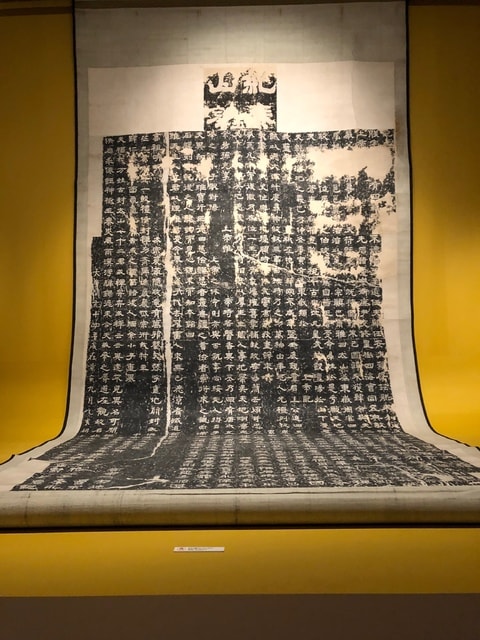お友だちが、
「名刺を作ろうかな」
というので、便乗して私も作ることにした。
めったにないけど、たまーに、
「名刺あったらよかったのにな」
と思う時がある。
友人は「物を作る人」だ。
こういう人はやっぱりセンスが良くて、しかも仕事が丁寧。
一緒に作らせてもらったおかげで、私の名刺も、ブログへのQRコードがプリントされた、シンプルでかっこいいのになった。
一人でやってたら、面倒だからとQRコードの作成なんかしなかっただろうし、もっとしつこくてぐちゃっとしたのになっただろうな。
この名刺で、良いご縁ができますように^^
「名刺を作ろうかな」
というので、便乗して私も作ることにした。
めったにないけど、たまーに、
「名刺あったらよかったのにな」
と思う時がある。
友人は「物を作る人」だ。
こういう人はやっぱりセンスが良くて、しかも仕事が丁寧。
一緒に作らせてもらったおかげで、私の名刺も、ブログへのQRコードがプリントされた、シンプルでかっこいいのになった。
一人でやってたら、面倒だからとQRコードの作成なんかしなかっただろうし、もっとしつこくてぐちゃっとしたのになっただろうな。
この名刺で、良いご縁ができますように^^