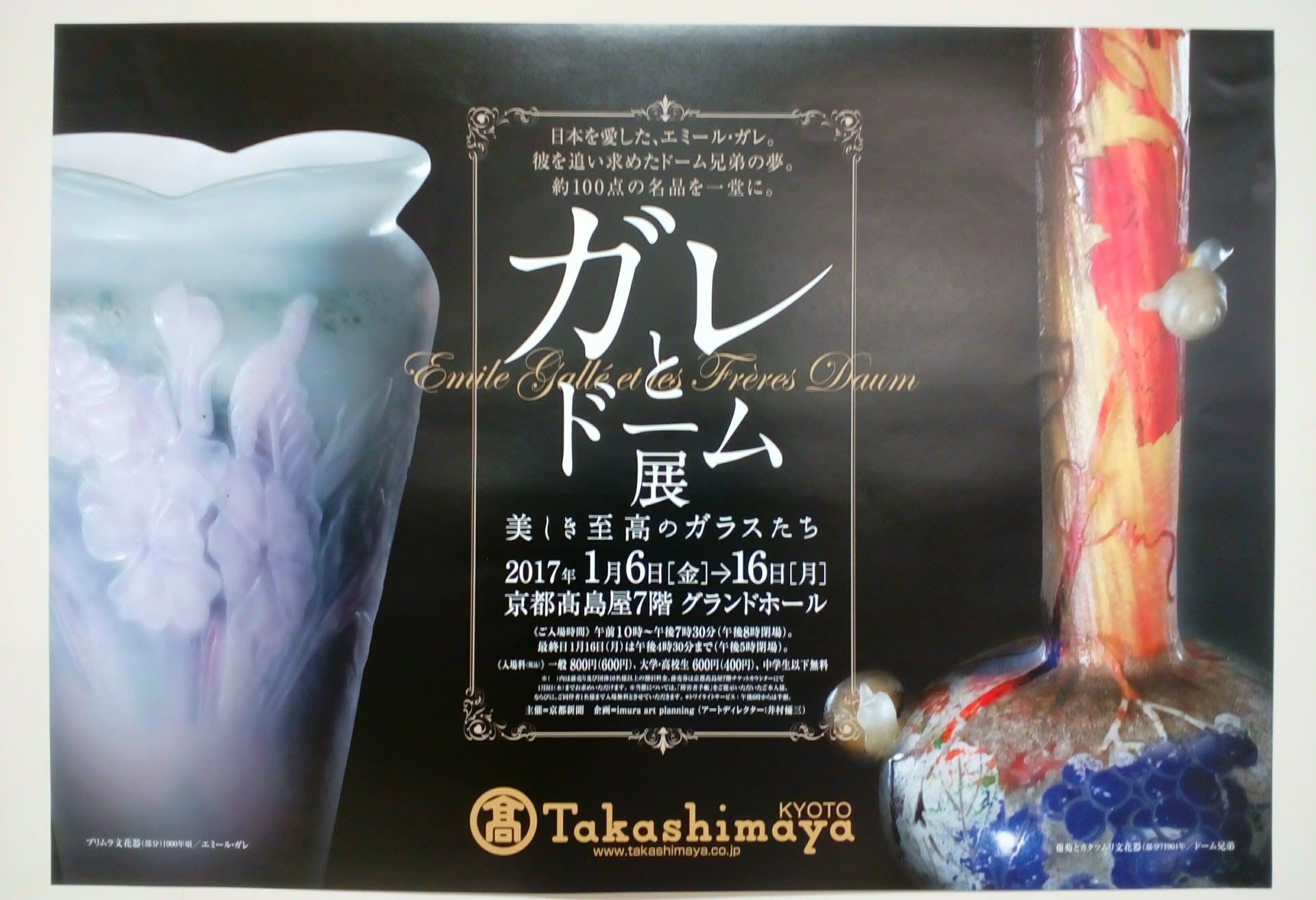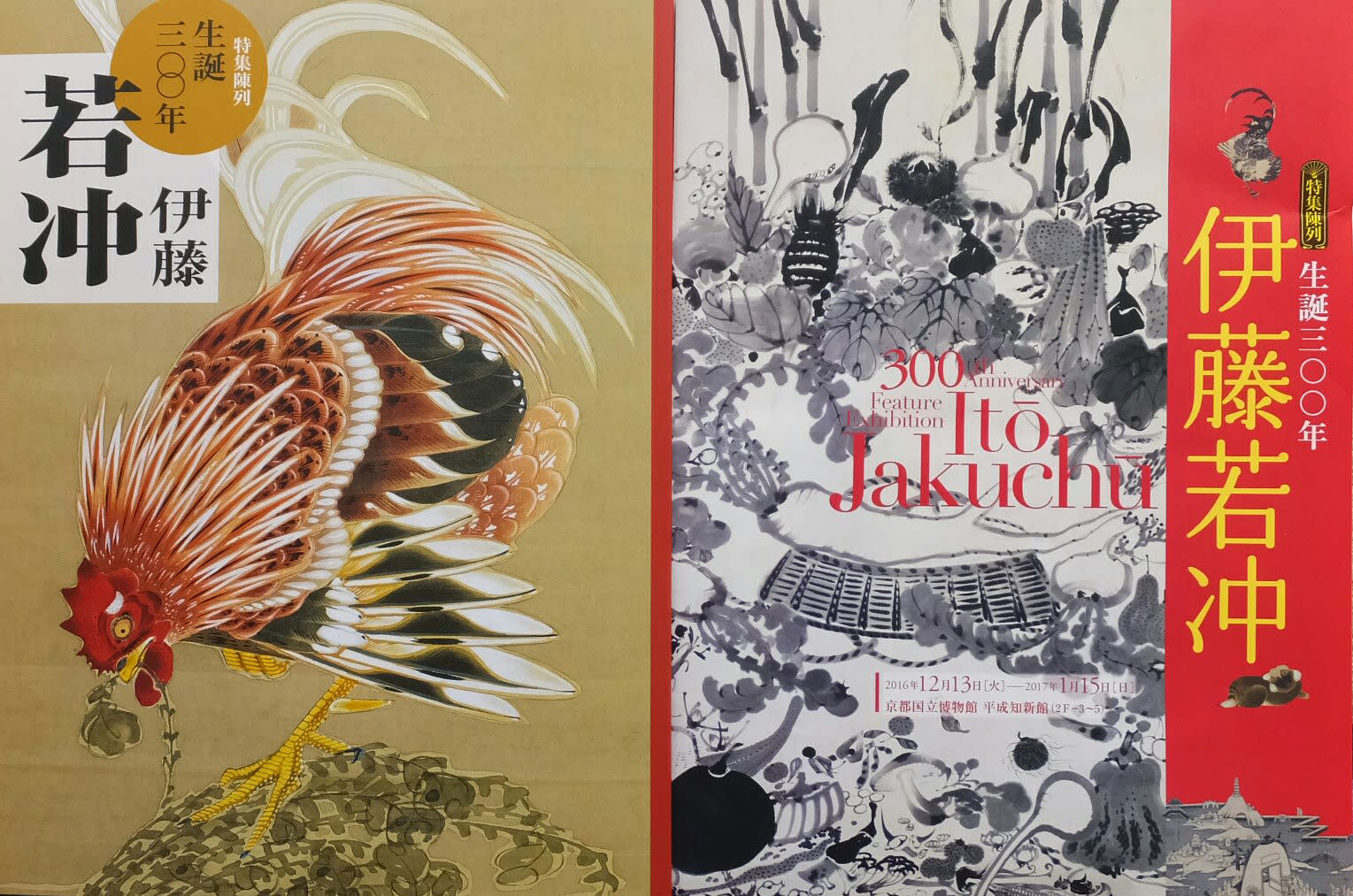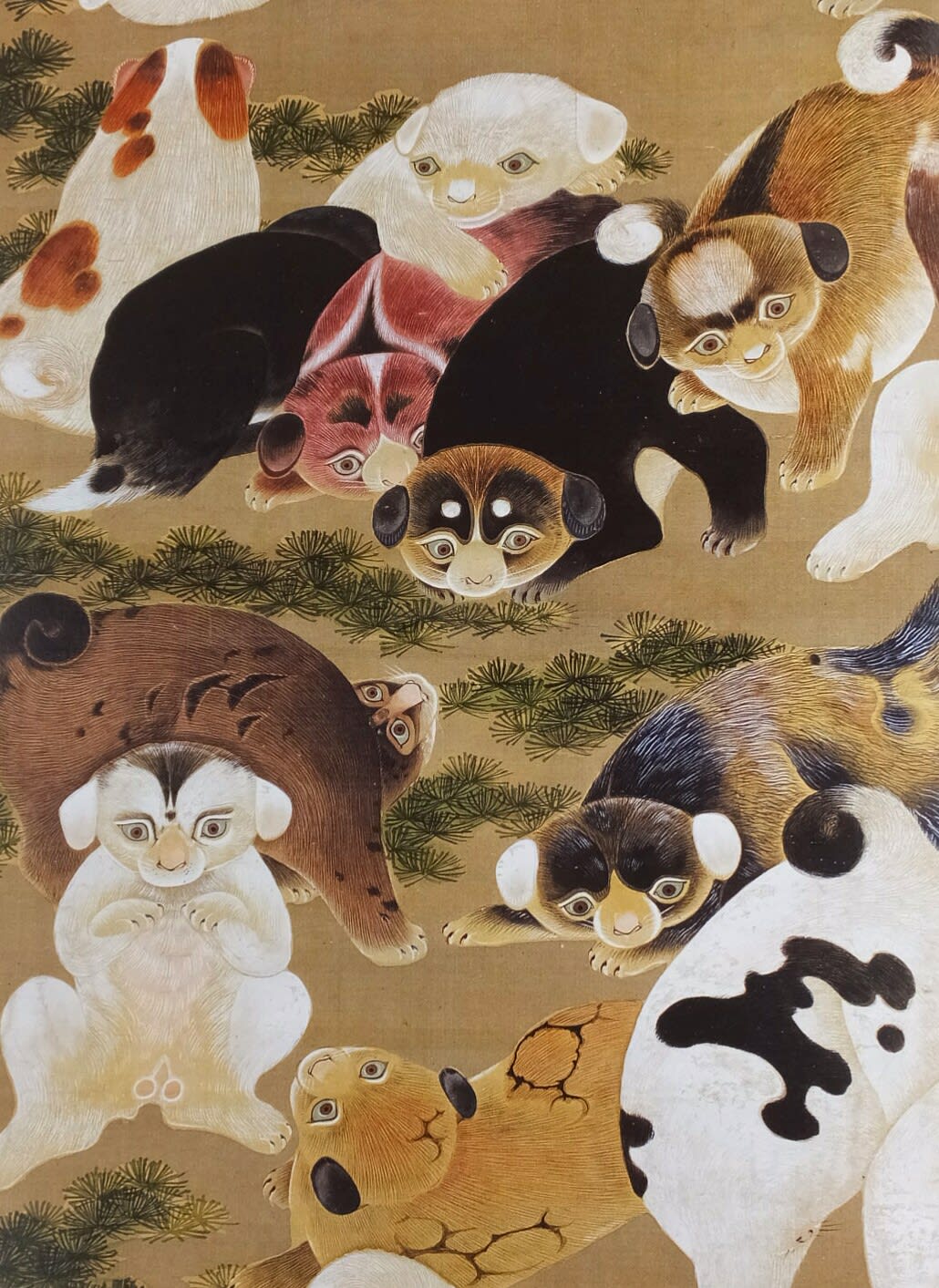昨日の散策は北嵯峨へでかけたのですが、もしやと思い印空寺に寄りました。
印空寺は松尾芭蕉が「名月や池をめぐりて 夜もすがら」と詠んだと言われる広沢池の東にあります。
毎年この寺院に2月頃熱海寒桜が咲きますが、最近は暖冬の影響でしょうか1月には開花します。
昨年の投稿は1月10日、今年は少し遅れましたがそれでも1月中の開花となりました。
まだ花数は少ないですが、薄いピンクの可愛い桜です。
寒桜の一種で、名前の付いている熱海では1月上旬~2月に咲くようです。






印空寺


今日明日強い寒波が近畿地方にも下りてくるそうです。
京都市内でも雪になりそうです。
印空寺の熱海寒桜の花数が増えるのは寒波明けになりそうです。