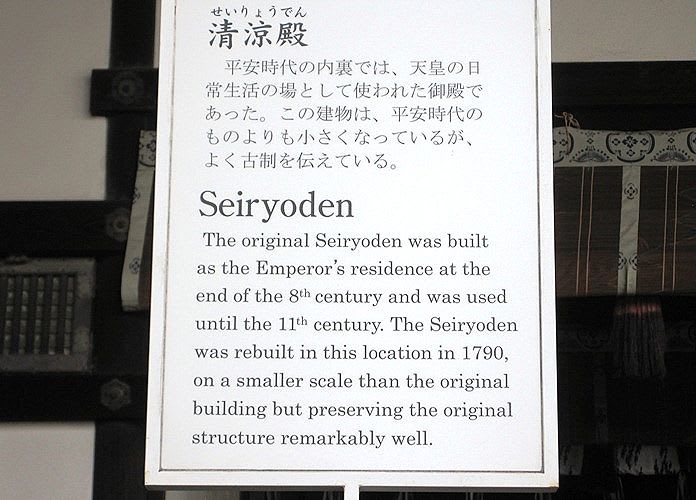醍醐寺は真言宗醍醐派総本山の寺院。本尊は薬師如来、東方に広がる醍醐山に200万坪以上
の広大な境内をもつ寺院である。桜で有名な三宝院庭園は豊臣秀吉による「醍醐の花見」の行
われた地とよく知られている。とにかくここではよく歩いた。





庭園内での写真撮影は禁止されている。中心の池には「亀島」「鶴島」が配されていて
安土桃山時代の日本庭園である。



春なればさぞ美しいだろうと残念。又来よう。

三宝院唐門



仁王門の金剛力士像は平安時代後期の作




下醍醐は広い!






金堂の中央には、薬師三尊像(中央:薬師如来、脇侍:日光・月光菩薩)が座しています