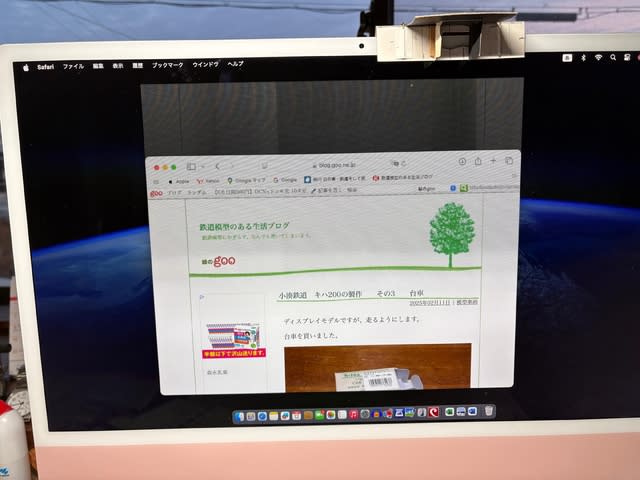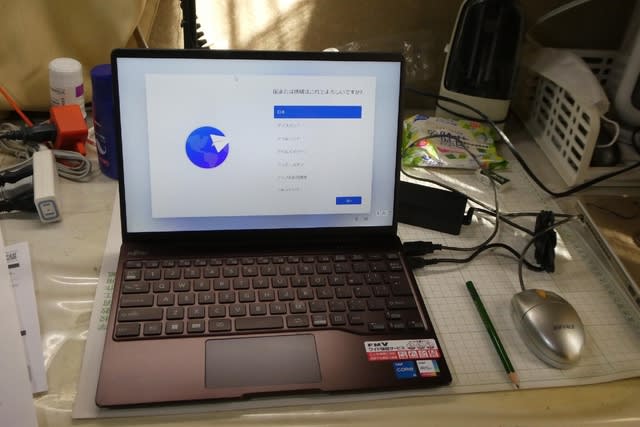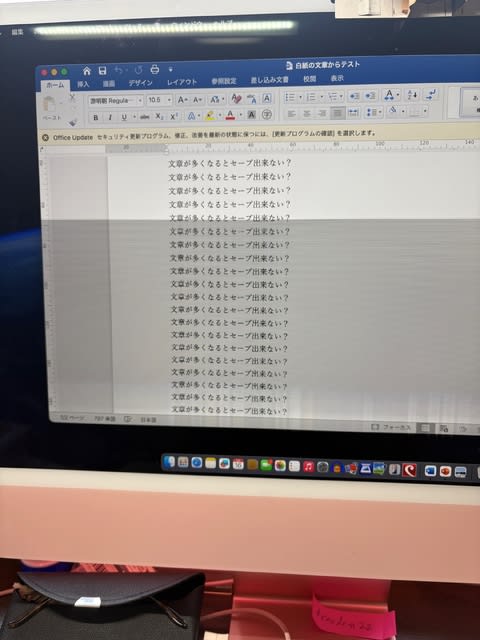京都に桂離宮があります。
以前に修学院離宮に行きましたが桂離宮は行ったことがない、やはり京都の住んでいれば一度は行かなければと思って出かけました。
と言ってもあらかじめ宮内庁に見学依頼を出さなければなりませんが簡単です。

一般入口への道。 指定された時間に行きます。
中で身分証明をを見せてチケットを買って、グループ番号の札を首からぶら下げて、待合室で待ちます。

池の周りを回るコースです。

人組20名ぐらいかな? ガイドさんに連れられて見学が始まりました。
桂離宮は後陽成天皇の弟、八条宮初代智仁親王により、1615年頃宮家の別荘として創建されました。・・・・ その後明治16年1883年に宮内省所管となり、とか説明してくれています。
後ろに見える門が正門で、宮家はこちらから入って来ます。

道は石畳になっていますが、水捌けも考えられとても綺麗に並んでいます。
でも、この先は大きな石が並んで、その石から落ちない様に歩くので必死になって足元ばかり見て景色が見えなかったり。 まあ、年寄りはそういう事。

正門から続く門です。 桂離宮の特徴は門の柱に使っている木が、皮付きのままです。

皮がついたままの木は、休憩所などでもあり、自然の感じを大事にしているとか。

この休憩所の木も自然木です、左端は化粧室とか。 トイレじゃないんです、昔姫君たちがここで衣装を直したりしたとかいう本当の化粧用です。

ガイドさんを先頭にお庭の周りを回ります。 完全に一列縦隊でしか歩けないので、ガイドさんから遠く離れてしまいますが、静かなところなので説明は聞こえます。 このお庭は何を表現しているとか。

立派な池庭です。 向こうの館には入れませんが、あそこから月を見るそうです。

一列に並んでいる道、わかるかな? 一抱えぐらいの大きさの石が並んだ道で、横には竹の柵があり、幅は30cmぐらいしかない。飛び石伝いに歩く様に石の上を歩いて竹の柵に足を引っ掛けない様に、下ばかり見て歩くのです。 人数が少なければ風流でしょうが、もう必死で転ばない様に歩いたのでした。

この石橋は風流なのですが、これを1人で渡ればどうもないのですが、前の人がこの上で止まると、こちらも停止。 怖いんです。 石の道も見えていますね。 ということで、歩くのが怖いとばかり書きましたが、年寄りにとっては事実で他の人も言って居ましたから。

松琴亭という茶室です。 躙口もあります。 右手の建物からこの松琴亭に上がる月を愛でていたそうですが、通は池に映った月を眺めるとか。

手前は台所があります。 青と白の市松模様のふすまは結構近代的ですね。 ここで客に料理を振る舞ったそうですが、この竈では温めるのがせいぜいでしょう。

ここは小山になっているので、ここから借景でお山が見えます。 多分愛宕山だと思います。
池を掘った土で小山を作った。

こちらは笑意軒で、やはり茶室です。

この建物は園林堂で、ここも通って来ましたが、遠くから見た方が綺麗です。 屋根が格好よい。

池の修復や、庭木の剪定など、ここを守る人がいて昔の面影を維持できているのです。
昨年だったか、テレビで足立美術館と桂離宮の樹木の剪定の方法が違うと丁寧な説明がありました。 どう違うのかと言われても私には説明できませんが、コンセプトが違うので自ずと剪定技術が全くと言っていいほど違うそうです

お庭に鳥がいたよ。 なんという鳥か知りません。

と言うことで1時間の見学ツアーが終わりました。
また時期を変えて来てください、お花が綺麗ですよととの事でした。

赤い矢印が見学ルートです。
桂離宮 おわり