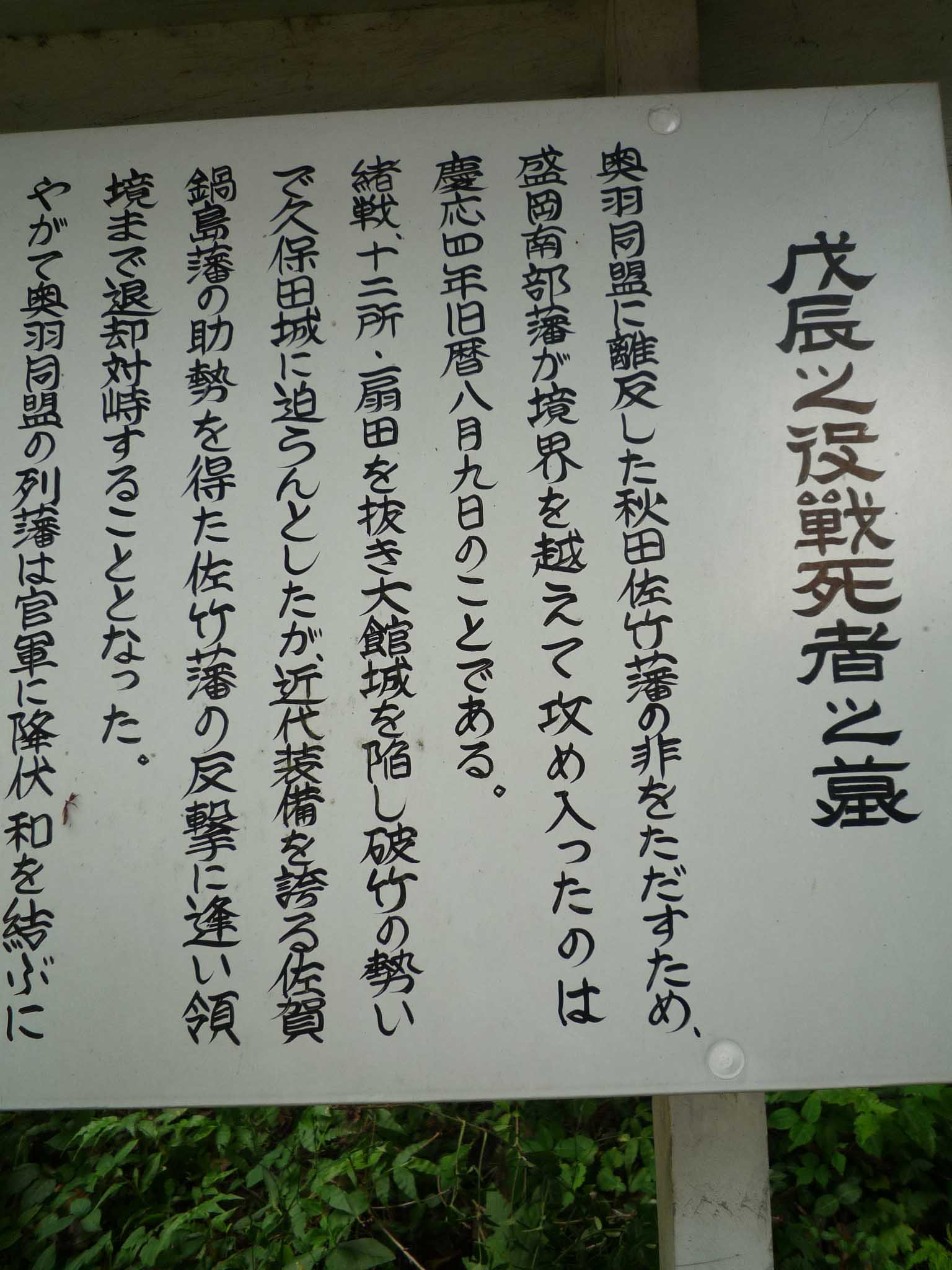午後2時着をめざし沢目に向かいました。隣の市のKさんご一家も2時着で向かう予定と聞いていました。午後2時に同時に到着、Kさんご夫妻、Sさんご夫妻、ゆなちゃん、まみちゃん、そしてSAWAMEのお婆ちゃんと一緒に先ずはお墓参りにいきました。

お墓のあるお寺の「手水鉢」に添えられた竜の水の出口は見事で印象に残るお寺さんです。別のお寺に古いお札を焚き上げしてもらうためにおにいさんと出かけました。以前郷土史学習会で管江真澄の歩いた道を訪ねたときにお邪魔したお寺さんです。

焚き上げはここで夜になったら行われ、この火の周りで盆踊りが行われるということでした。炊き上げのお札はまだたくさんは集まっていないようでした。

ゆなちゃんはひなこちゃんよりも8ヶ月の先輩お姉ちゃんで、元気に走って歩きます。最初人見知りをして私にはなついてくれませんでしたが、やがてスイカを手渡しで貰うことも出来たし、抱っこすることも出来ました。大きな風船でキャッチボールをして遊んだりもしました。随分運動神経がよい子と感心しました。
小さな赤ちゃんにもそれぞれの個性があって楽しく、9人での夕食もとても楽しく過ごしました 

























 上が近用、下が遠用です
上が近用、下が遠用です




















































 恩徳寺山門
恩徳寺山門