
11/24にサントリーホールで行われた読売日響の定期演奏会に行って来ました。今月と来月は土曜日のコンサートなんで、ラフな格好の人も多く、私自身もちょっと違った気分です。プログラムはオスモ・ヴァンスカ指揮で、前半がシベリウスの「イン・メモリアム(葬送行進曲)」とベートーヴェンの交響曲第1番、後半が第2番です。演奏時間はシベリウスが11分、第1番が28分、第2番が35分くらいですからとても短いですね。編成もシベリウスが少し大きいくらいで、ベトベンは舞台がすかすかしています。細川俊夫やルトスワフスキ、メシアンといった巨大編成が続いたんでちょっとさびしい感じです。予算内に収めるための工夫かなw。
中身で勝負といきたいところですが、シベリウスはあまり演奏されない曲を聞かせてもらったということではありがたいんでしょうけど、ずっと小太鼓がリズムを刻んでてなんか暗い軍隊行進曲って感じです。フィンランドがロシアに占領されてた時にフィンランド総督だったロシアの軍人を暗殺して自殺したオイゲン・シャウマンって若者に捧げられた作品だそうです。そうだとするともっとフィンランディアみたいな泣かせる盛り上がりがあってもよさそうなんですけど、ヴァイオリンが奏でる霧の中からクラリネットの描く人影がちらちら見えるのがせいぜいで、どうも機会音楽の域を出ないようでした。
この曲もベートーヴェンの交響曲も指揮者から向かって左から第1ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、第2ヴァイオリンで、コントラバスは第1ヴァイオリンの後ろという今どきめずらしい配置でした。この日の曲から来る必然性というよりは単純にヴァンスカの趣味かなって思いました。第1も第2も編成は同じで、金管はトランペットとホルンのみ、打楽器はティンパニだけでモーツァルトやハイドンとほとんど同じでしょう。だのにまあこんなに野蛮な音楽になるもんだと改めて感心しました。30年ほど後に幻想交響曲が現れるまでびゅーびゅー風が吹くような暴力性はベートーヴェンの独擅場で、まるで領邦国家だったドイツをプロシアが統一したのを先取りしたような感すらあります。
野蛮とか暴力とか穏やかじゃない言葉を使っていますが、そうしたものなくしてベルリオーズもヴァーグナーもブルックナーもマーラーもバルトークもストラヴィンスキーもショスタコーヴィッチも今ほどの人気はないでしょう。まあ、殺人事件が必須と言わないまでもオペラの大事な要素なのと同じです。ふつうはベートーヴェンの力強さは勃興する市民階級のエネルギーを背景にしているとか言われますが、そんな時代がかった言葉で片付けられるようなものではなく、指揮者がコンマスの前に杭を打ち込むみたいな格好をしてしまうのはポストモダンなんて言われる現代でも自然なわけです。
弦とティンパニがスピード感と荒々しさを担っているとすると優雅さと流露感は木管が担っているのかなと思いました。宮廷風と言ってもいいような典雅なパッセージを木管が挟むからダイナミズムも引き立つんでしょう。極端とも思えるほどのコントラストもまたベートーヴェンの特徴でしょう。特に第2番の第2楽章のラルゲットはヴァンスカはタクトを持たずに指揮していて、あの夢見ながら踊るような美しいフレーズでは指揮をやめて合掌していました。第1と第2って作曲時期も近いし、似たようなものかなって思ってましたけど、2つ並べて聴くと第2の方が後年の作品につながっていく要素が多いのがよくわかりました。それは優れたところがもちろん多いんですが、スケルツォがちょっとオートマティックな感じがするといったところに現れているようでした。










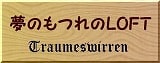










なんて感じだからベトベンの楽譜には苦労のあとが表れるんじゃないでしょか…
なんて、自分と同じ次元で考えるのは罰当たりでした…
罰当たりなのは私も勝るとも劣らないですし、自分の思うように主張するのがロック魂だぜ。いぇぃ♪