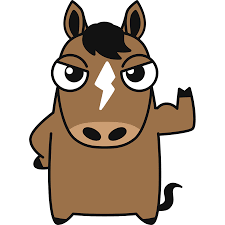=こんな話題が=
そか25年ぶりの逆転現象→「東高西低」
うんうん、昔は「どこまで行っても東高西低」の時代だったのが懐かしいw
この記事は納得だが、美浦の坂路が改装されたのは今年で、すぐに効果が現れたからというのはちと違うやろ
生産界のガリバー、ノーザンの取り組みとか、馬主の意識の変化が大きいんじゃないんかな
前は関東の有力オーナーが栗東厩舎に馬を預ける事が多かったようにも思ったし、活躍馬は関西の有力オーナーの馬が多かったようにも思ってたんだが
今は様子が変わって来た気がする
まあ、西が優勢になった原因が栗東坂路にあったのはほぼ間違いないと思うし、美浦の坂路効果が栗東に比べて見劣りしてたのも一因かも知れん
だとすると今後は間違いなく「坂路効果」に関しては互角になるだろうし、馬の質の勝負になるんじゃないか?
そして関東には勢いのある新興厩舎も増えてきた
それぞれ調教技術の向上もあるやろけど、本質は「馬」の問題でっしゃろ
今後はそれの勝負になるんじゃなかろか
(お借りした)
「西高東低」に終止符か 25年ぶりに関東馬がG1勝ち越しの理由とは
長年続いた競馬の“西高東低”に終止符が打たれる時が来たのかもしれない。阪神JFを終えた時点で、平地G1の勝ち数が関東馬14勝、関西馬8勝。残りの朝日杯FS、有馬記念、ホープフルSの決着を待たずに、98年以来、25年ぶりとなる関東馬のG1勝ち越しが決まった。
阪神JFはまさに、今の流れを象徴するような結果となった。5頭出走していた関東馬が上位3着までを独占。それだけでなく、牡馬クラシックの連対は全て関東勢が占めた(ダービーと菊花賞はワンツースリー)。このように、今年の関東馬はG1での活躍が目覚ましいのだ。
※これは衝撃ですな
ドゥレッツァで菊花賞を制した尾関師は、こう推察する。「イクイノックスやソングラインのような強い馬が、しっかり結果を残したからでしょう。そこに引っ張られた部分はあるかもしれませんね」。それぞれ路線の中心となるトップホースがG1を勝ち切ることで、それに続けとばかりに関東馬の地力が底上げされる-。振り返れば、98年も年度代表馬に輝いたタイキシャトルを筆頭に、エルコンドルパサーやセイウンスカイといった実力馬が続々と走っていた。
また、今夏に美浦坂路が閉鎖されていたことが、秋の躍進に好影響を与えたのだという。尾関師も「あの時期、各厩舎はいろいろと工夫してやっていました。大変でしたが、その時の経験が今につながっているのでは」と語る。止め際がはっきり決まっている坂路よりも、トラックコースの方が馬とのコンタクトを求められるというのは定説。坂路を使えないことが乗り手の技術向上につながった可能性もある。
そして満を持して、10月4日に改修された坂路がオープン。全長1200メートルは変わらないものの、高低差がこれまでの18メートルから33メートルになった(栗東坂路の高低差は32メートル)。まだオープンから2カ月ほどしかたってないが、美浦の“鬼門”だったはずの砂G1・チャンピオンズCで関東馬がワンツー(1着レモンポップ、2着ウィルソンテソーロ)したのは、栗東並みかそれ以上の負荷をかけられるようになった坂路の効果が少なからずあったはずだ。
とはいえ、今はビッグレースの活躍が目立つだけで、トータルでは関西馬が変わらず圧倒している(12月3日終了時点で関東1371勝、関西1872勝)。今年の流れが来年以降も続き、条件馬たちも全体的に底上げされれば-。イクイノックスが引退した来年以降も、継続して関東馬が勝ち続けられるかどうかが鍵になるだろう。スターズオンアース、タスティエーラ、ソールオリエンスなど、関東に多数の有力候補が控える有馬記念が楽しみだ。(デイリースポーツ・刀根善郎)