「手塚先生、締め切り過ぎてます!」
という新書が出ている。
集英社新書だ。
著者は福元一義という、
手塚プロで手塚マンガのチーフアシスタントをしていた人だという。

今年は手塚治虫生誕80周年だそうで、
それでBS放送でも手塚特集を組んだりしている。
で、新書業界でも80周年記念として
ひっそりとこの本が発売された。
驚いたのは文章中に所々挿入されている
カットというかイラストで、
てっきり手塚治虫の書いたカットを転用しているのだと思ったら、
本文イラストは著者(福元氏)という注意書きが…。
手塚そっくりの絵柄なのだ。
線のタッチも、手書きの文字も。
アシスタントをしていると、絵柄まで似て来るようだ。
著者はある時は編集者だったり、
アシスタントだったり、漫画家も経験したそうで、
もともと漫画家を目指していたらしい。
編集者だった時に手塚にアシスタントとして引き抜かれた。
漫画家を目指した時、
編集者として手塚氏の仕事ぶりを見ていて漫画家なんてちょろい、
と思っていたら、手塚治虫のようには仕事が出来なくて、
自分と手塚とは違うと思い知ったという。
この著者のように手塚治虫のごくそばにいた人は、
手塚治虫を尊敬していて、決して悪いことを言わないが、
福井英一への嫉妬のような、
どろどろした話はいろいろあるのではないだろうか。
手塚治虫は月日が経つごとに神格化され、
アンタッチャブルな聖人になってゆくような気もするが、
もっとどろどろした手塚も知りたいところだ。
でもこの本ではやっぱり、
という手塚ならではのエピソードが沢山書いてあって、
もっと読みたいと思った。

美術館・ギャラリーランキング
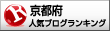
京都府ランキング
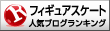
フィギュアスケートランキング
↓ブログ村もよろしくお願いします!

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村
という新書が出ている。
集英社新書だ。
著者は福元一義という、
手塚プロで手塚マンガのチーフアシスタントをしていた人だという。

今年は手塚治虫生誕80周年だそうで、
それでBS放送でも手塚特集を組んだりしている。
で、新書業界でも80周年記念として
ひっそりとこの本が発売された。
驚いたのは文章中に所々挿入されている
カットというかイラストで、
てっきり手塚治虫の書いたカットを転用しているのだと思ったら、
本文イラストは著者(福元氏)という注意書きが…。
手塚そっくりの絵柄なのだ。
線のタッチも、手書きの文字も。
アシスタントをしていると、絵柄まで似て来るようだ。
著者はある時は編集者だったり、
アシスタントだったり、漫画家も経験したそうで、
もともと漫画家を目指していたらしい。
編集者だった時に手塚にアシスタントとして引き抜かれた。
漫画家を目指した時、
編集者として手塚氏の仕事ぶりを見ていて漫画家なんてちょろい、
と思っていたら、手塚治虫のようには仕事が出来なくて、
自分と手塚とは違うと思い知ったという。
この著者のように手塚治虫のごくそばにいた人は、
手塚治虫を尊敬していて、決して悪いことを言わないが、
福井英一への嫉妬のような、
どろどろした話はいろいろあるのではないだろうか。
手塚治虫は月日が経つごとに神格化され、
アンタッチャブルな聖人になってゆくような気もするが、
もっとどろどろした手塚も知りたいところだ。
でもこの本ではやっぱり、
という手塚ならではのエピソードが沢山書いてあって、
もっと読みたいと思った。
美術館・ギャラリーランキング
京都府ランキング
フィギュアスケートランキング
↓ブログ村もよろしくお願いします!
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村


















