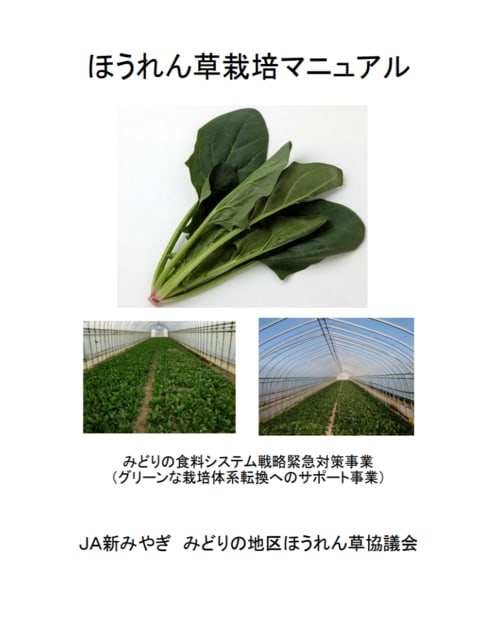登米市は環境保全米の栽培が県内一盛んな地域です。
昨年度は、「ペースト肥料の田植同時施用によるプラスチック被覆肥料の利用削減及び減肥栽培」や「ペースト肥料以外の非プラスチックコーティング肥料を用いた栽培」等、従来の環境保全米から一歩進んだ「グリーンな栽培体系」と生産者の選択肢拡大に向けた検証を行い、従来の環境保全米とほぼ同等の品質・収量が得られることを実証しました。
今年度も、「グリーンな栽培体系」の普及拡大に向け、JAみやぎ登米、肥料・農機メーカーの協力のもと5か所の展示ほを設置しました。
このうち5月20日の登米市豊里町の展示ほでは、「田植えと同時に、10a当たり2.1kgの窒素成分量のペースト肥料を3cmと9cmの深さに施肥」という設計のもと、最新式の8条田植機で田植を実施しました。
当日はあいにくの雨となりましたが、大きなトラブルもなく、60aの田植えは約1時間で終了しました。また,「雨でも肥料補給が可能」というペースト肥料のメリットも確認することができました。
今後は、定期的な生育等の調査でグリーンな栽培体系の検証を行うとともに、情報発信により普及拡大を図っていきます。
雨の中行われた田植えの様子
<連絡先>
宮城県登米農業改良普及センター 先進技術班
〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼150-5
電話:0220-22-6127 FAX:0220-22-7522