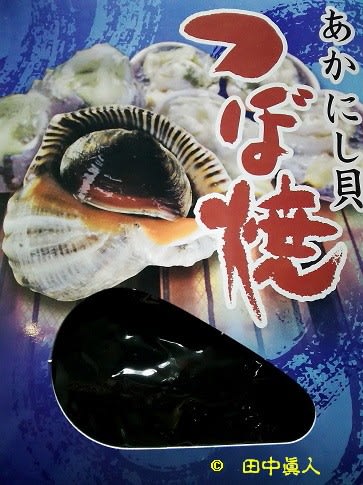この日の午前中は、写真家のKさんとともに、同行取材していた。
これまで、幾たびか訪れては、拝見していた京都府木津川市加茂町銭司の・銭司(ぜず)宮小谷に鎮座する春日神社。
正月迎えに設える砂撒き作業。
氏子たちが、みなそろって整える境内一面に撒く砂の筋。
すべてが格子状態の撒き方だった。
実は、拝見していたのは、砂撒きをした後だった。
平成30年は1月6日。
令和3年は1月3日に拝見した格子状の砂撒き。
併せて拝見した勧請縄もまた格子状に編み上げる様式に感動していた。
氏子たちの作業は、どのようにされるのか。その状態を拝見したく、写真家Kさんのお奨め取材を了承した。
宮司を勤める中岡宮司は岡田国神社の宮司。
ここ銭司の春日神社も兼務されている、とわかり承諾を得て村行事を取材した。
お昼の食事を済ませて、さて午後はどちらへ。
私が訪れたい神社は、銭司より西方の地にある木津川市吐師(はぜ)宮ノ前に鎮座する大宮神社である。
大宮神社にはじめて訪れたのは、昨年の令和2年の正月過ぎ。
1月10日に訪れた目的は、御田祭の調査であったが、どなたにも逢えなかった。
ただ、簾型のしめ縄の確認はしたが、鳥居から下して座小屋の床下付近に置いてあった状態。
それだけでも十分な調査になったわけだが、今日は12月30日。
もしか、とすればその簾型しめ縄が拝見できるのでは、と思って車を走らせた。
到着時間帯は、午後1時過ぎ。

な、な、なんとな遭遇である。
簾型のしめ縄も架けているし、神社下の道に、数多くの砂撒きが見つかった。
そのカタチは、すべてが円形から円形をつないでいく形態であった。

この形態は、同じ京都南部の民家の習俗に拝見していた同様の様式である。
取材地は、木津川市山城町・上狛(かみこま)。
平成28年12月31日の取材先はO家。
終えてすぐさま取材したご近所のM家もまた同様の円形様式。
砂の撒き方は、まったく同じ。
本日、拝見した吐師(はぜ)も同様の円形仕様。
加茂町銭司(ぜず)・春日神社は格子状仕様。
地域が違えれば、仕様も異なる、ということだが、2例だけでは判断できない暮らしの民俗である。
砂撒きの痕跡から、おそらく午前中に済まされたのだろう。

素晴らしき伝統を拝見させてもらった吐師(はぜ)の大宮神社に参拝する。
ふと、狛犬の下を見た視線にあった賽銭玉。

銅貨の十円玉を捧げたのはおそらく参拝者であろう。
本社殿右の建物。
たぶんに社務所と思われるが、軒下から吊っていた果物は干し柿。

熟し具合から判断した干し柿。
そろそろ食べどきか。
あくまで可能性か、の話であるが、この干し柿は、神前に供える鏡餅に飾る縁起物では・・
「中にこにこ睦まじく」の呼称もある10個の干し柿を串に刺した串柿にするのでは、と思った次第。
撮影していたそのときである。
一人の女性が参拝された。

拝礼する前に拝殿前においたお酒。
参拝を終えて伺った女性,Uさんの話によれば、目出度い祝いの奉納。
息子さんが、司法書士試験に合格したお礼である。
母親は、合格祈願に、ここ大宮神社に参拝し、願掛けしていた。
その結果、息子さんが合格した。
つまりは願満お礼に奉納した献酒であった。
そうこうしているうちに、また一人の女性が参拝していた。

その女性、Tさんは高校生。
実は、と話してくれた女高生。
空手の全国試合に優勝したので、お礼参り。
ずっと一人で、大宮神社に参拝し続け、願掛けしていた結果が優勝に繋がった。
ほぼ同時刻に満願のお礼参り。
ここ大宮神社は願掛けの来訪が多い、とみた。

去った跡にみた狛犬・牛像に、小銭賽銭が増えていた。
いい場所に、いい神社。

そして出合えた満願お礼の人たち。
私たち撮影者は、さらに頭を深く下げた。
ところで、砂撒きは何時ごろにされたのだろうか。
砂の乾きは、日陰と日当たりによって異なる。
日のあたる場所であれば、乾きに白くなる。
日陰であれば、まだ水分を含んでいるから、やや黒っぽい。
赤い橋は、おそらく宮前橋。
その前に見えた砂山。
そう、軽トラかなにかの運搬装置によって砂を持ち込み、そこに落とした。
そしてはじめた作業が、同市内の山城町上狛の円形砂撒きと同じように象る。
砂山から運ぶのは一輪車か。
なんらかの運搬道具に砂を積んで運び、所定の位置に撒く。
その状況は、平成28年12月30日に拝見していた京田辺市宮津宮ノ内・白山神社の正月飾りを参考にしていただきたい。
今の時間帯は午後2時。
そろそろ引き上げるが、砂撒きの地は車の往来もある参道の道らしい。

車輪の轍は、赤い橋から北に抜けるまで、ずっと続く痕跡があった。
(R3.12.30 SB805SH/EOS7D 撮影)
これまで、幾たびか訪れては、拝見していた京都府木津川市加茂町銭司の・銭司(ぜず)宮小谷に鎮座する春日神社。
正月迎えに設える砂撒き作業。
氏子たちが、みなそろって整える境内一面に撒く砂の筋。
すべてが格子状態の撒き方だった。
実は、拝見していたのは、砂撒きをした後だった。
平成30年は1月6日。
令和3年は1月3日に拝見した格子状の砂撒き。
併せて拝見した勧請縄もまた格子状に編み上げる様式に感動していた。
氏子たちの作業は、どのようにされるのか。その状態を拝見したく、写真家Kさんのお奨め取材を了承した。
宮司を勤める中岡宮司は岡田国神社の宮司。
ここ銭司の春日神社も兼務されている、とわかり承諾を得て村行事を取材した。
お昼の食事を済ませて、さて午後はどちらへ。
私が訪れたい神社は、銭司より西方の地にある木津川市吐師(はぜ)宮ノ前に鎮座する大宮神社である。
大宮神社にはじめて訪れたのは、昨年の令和2年の正月過ぎ。
1月10日に訪れた目的は、御田祭の調査であったが、どなたにも逢えなかった。
ただ、簾型のしめ縄の確認はしたが、鳥居から下して座小屋の床下付近に置いてあった状態。
それだけでも十分な調査になったわけだが、今日は12月30日。
もしか、とすればその簾型しめ縄が拝見できるのでは、と思って車を走らせた。
到着時間帯は、午後1時過ぎ。

な、な、なんとな遭遇である。
簾型のしめ縄も架けているし、神社下の道に、数多くの砂撒きが見つかった。
そのカタチは、すべてが円形から円形をつないでいく形態であった。

この形態は、同じ京都南部の民家の習俗に拝見していた同様の様式である。
取材地は、木津川市山城町・上狛(かみこま)。
平成28年12月31日の取材先はO家。
終えてすぐさま取材したご近所のM家もまた同様の円形様式。
砂の撒き方は、まったく同じ。
本日、拝見した吐師(はぜ)も同様の円形仕様。
加茂町銭司(ぜず)・春日神社は格子状仕様。
地域が違えれば、仕様も異なる、ということだが、2例だけでは判断できない暮らしの民俗である。
砂撒きの痕跡から、おそらく午前中に済まされたのだろう。

素晴らしき伝統を拝見させてもらった吐師(はぜ)の大宮神社に参拝する。
ふと、狛犬の下を見た視線にあった賽銭玉。

銅貨の十円玉を捧げたのはおそらく参拝者であろう。
本社殿右の建物。
たぶんに社務所と思われるが、軒下から吊っていた果物は干し柿。

熟し具合から判断した干し柿。
そろそろ食べどきか。
あくまで可能性か、の話であるが、この干し柿は、神前に供える鏡餅に飾る縁起物では・・
「中にこにこ睦まじく」の呼称もある10個の干し柿を串に刺した串柿にするのでは、と思った次第。
撮影していたそのときである。
一人の女性が参拝された。

拝礼する前に拝殿前においたお酒。
参拝を終えて伺った女性,Uさんの話によれば、目出度い祝いの奉納。
息子さんが、司法書士試験に合格したお礼である。
母親は、合格祈願に、ここ大宮神社に参拝し、願掛けしていた。
その結果、息子さんが合格した。
つまりは願満お礼に奉納した献酒であった。
そうこうしているうちに、また一人の女性が参拝していた。

その女性、Tさんは高校生。
実は、と話してくれた女高生。
空手の全国試合に優勝したので、お礼参り。
ずっと一人で、大宮神社に参拝し続け、願掛けしていた結果が優勝に繋がった。
ほぼ同時刻に満願のお礼参り。
ここ大宮神社は願掛けの来訪が多い、とみた。

去った跡にみた狛犬・牛像に、小銭賽銭が増えていた。
いい場所に、いい神社。

そして出合えた満願お礼の人たち。
私たち撮影者は、さらに頭を深く下げた。
ところで、砂撒きは何時ごろにされたのだろうか。
砂の乾きは、日陰と日当たりによって異なる。
日のあたる場所であれば、乾きに白くなる。
日陰であれば、まだ水分を含んでいるから、やや黒っぽい。
赤い橋は、おそらく宮前橋。
その前に見えた砂山。
そう、軽トラかなにかの運搬装置によって砂を持ち込み、そこに落とした。
そしてはじめた作業が、同市内の山城町上狛の円形砂撒きと同じように象る。
砂山から運ぶのは一輪車か。
なんらかの運搬道具に砂を積んで運び、所定の位置に撒く。
その状況は、平成28年12月30日に拝見していた京田辺市宮津宮ノ内・白山神社の正月飾りを参考にしていただきたい。
今の時間帯は午後2時。
そろそろ引き上げるが、砂撒きの地は車の往来もある参道の道らしい。

車輪の轍は、赤い橋から北に抜けるまで、ずっと続く痕跡があった。
(R3.12.30 SB805SH/EOS7D 撮影)