 最近はなにやら「不振にあえぐ日本デパート業界の希望」などと褒めそやされているらしい伊勢丹本店の明治通りを挟んだ向かいに昔、ATGのフラッグシップとして名を馳せた「アートシアター新宿文化」という劇場があった(1962-74)。現在は、角川シネマ及びシネマート新宿になっている。ついでに言うと、隣にあった新宿スカラ座とビレッジ1・2の入っていたビルもいまは取り壊されて、再開発中である。渋谷にかつての勢いがなくなった分、新宿三丁目が騒がしくなっている。
最近はなにやら「不振にあえぐ日本デパート業界の希望」などと褒めそやされているらしい伊勢丹本店の明治通りを挟んだ向かいに昔、ATGのフラッグシップとして名を馳せた「アートシアター新宿文化」という劇場があった(1962-74)。現在は、角川シネマ及びシネマート新宿になっている。ついでに言うと、隣にあった新宿スカラ座とビレッジ1・2の入っていたビルもいまは取り壊されて、再開発中である。渋谷にかつての勢いがなくなった分、新宿三丁目が騒がしくなっている。渋い紙質であしらわれた表紙カバーに惹かれるまま、新宿文化の創設者・葛井欣士郎の自伝的インタビューと若干の資料で構成された新刊『遺言』(河出書房新社)を手に取った。遺言などといかめしいタイトルは示唆的で、往時の愉しい思い出話、苦労話の影に、未来の映画界へのメッセージが、なにごとかを成し遂げた矜持を秘めた老人の口から言外に示されている。
当時から葛井が、斉藤耕一の『津軽じょんがら節』や増村保造の『音楽』はATGの名前には値せず、真のATGとは『戒厳令』であり『エロス+虐殺』であり『天使の恍惚』であり『儀式』であると考えていたこと、『津軽~』あたりからATGが変節してきてしまった、という意見が吐露されている。この変節というのはまさにそうで、私が映画狂になり始めた十代前半の時点ではすでにATGといえば失礼ながら、『Keiko』だの『もう頬づえはつかない』だの『海潮音』だのといった有象無象をだらだらとロングランしている配給会社、としか思えなかったのである。ちなみに私にとっての新宿文化でのもっとも素晴らしい思い出は、改築後の時代になってしまうが、高校時代、ベルトルッチの大作『1900年』初公開を、満員の客席で見た興奮の体験であった。
しかしそれにしても、旧・アートシアター新宿文化とその地下にあった蠍座の記憶に関しては、幼少期に通りがかったわずかな外観の記憶しか持っていないのがなんとも残念だ。1970年代半ばまで、祖父母の家が新宿戸山町にあったため、あの付近の記憶は風景としてだけなら、私の網膜の奥に刻まれている。そして網膜の奥では、いまも靖国通りに都電が走っている。
もちろん幼少期の一番の強烈な記憶は、市街における闘争の光景だ。おそらく私という存在は、新宿を舞台にした左翼闘争をこの目で目撃したもっとも若い、最後の世代であろう。1960年代末か70年ごろのある寒い夜、祖父母宅の居間で、当時大好きな曲だったピンキーとキラーズ『恋の季節』のドーナツ盤(穴の大きい、いまで言う7 inch singleのビニール盤のこと。『恋の季節』のドーナツ盤は自宅用と祖父母宅用の2枚持っていた)を何度もかけているうちに、外が騒然となってくる。市街戦が始まると、縁日の要領、一族総出で騒乱見物に出かけるのだ。夜でもサングラスをかけた学生が、幼い私の前を走り抜け、槍投げのフォームで火炎瓶を投げる! 彼らは怒りの表情で、何度も何度も機動隊の隊列に向かって火炎瓶や石を投げている。
明治通りの奥は真っ赤に燃えさかっている。夜の闇に輝くその巨大な炎は、子ども心に、ある種の「美」を感じてしまったほどだ。あんなに大勢の激怒した大人たちを見たのは初めてだったが、不思議と恐怖は感じなかった。恐怖と言えば、昔は軍事パレートというものがあって、あれの方が怖かった。なにしろ、明治通りを白昼堂々、ミサイル運搬車やら戦車やらが、ドーッと通り過ぎるのだ。今では考えられないだろう、明治通りを通行止めにしてあんな大がかりな軍事パレードを実施するなんて。いや逆に、現代人は喜んだりしてしまうのかもしれないが。
朝、祖母と共に付近の牛乳屋に牛乳を買いに行くと、交番が真っ黒に焼け焦げていた。きつい悪臭が鼻をついた。

















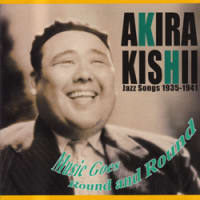


生前のご活躍に最大の敬意を抱くと共に、ご冥福をお祈り申し上げます。