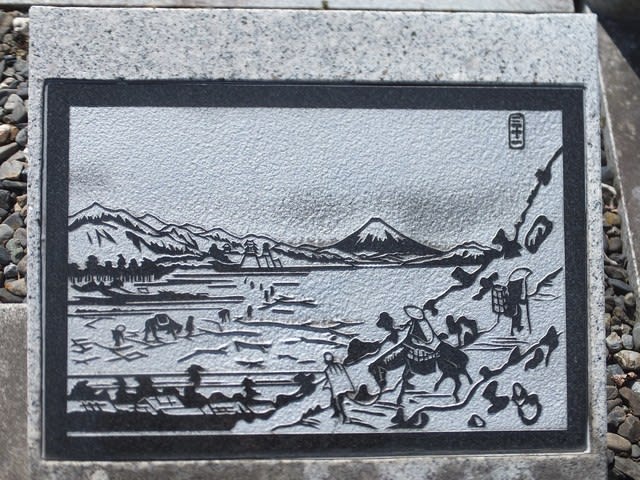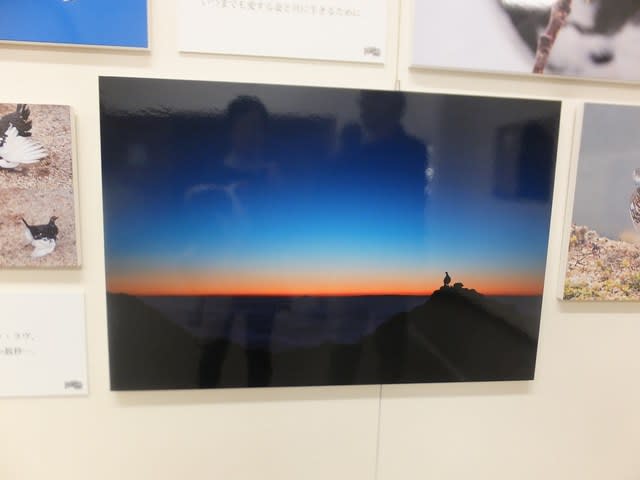原村にはたまにしか行かないので野鳥にもなかなか出会えません…
この冬、久しぶりに見た「アカゲラ」です。
素早い動きで樹をつついていました。



昨年の秋、義兄が作って掛けてくれた巣箱…偵察に来た野鳥(スズメでしょうか?→「モズ」でした!)がいました!
まず巣箱の中を何度も覗き…


下に回り、裏も見ていました。気にいったでしょうか…


別の樹に掛けてある巣箱では中に入っていました!
顔をのぞかせているのは「シジュウカラ」でした。


巣箱から出てきたシジュウカラ、気に入って使ってくれると嬉しいのですが…

ここでは冬の間ストーブを焚いて暖をとります。
ストーブの上に無水鍋、中に入っているのは那智黒(石)です。
これで作る石焼き芋はとっても美味しいです。

そのままでも美味しいのですが、スイートポテトを作ってみました。

ストーブの近くに置いておくとちょうど発酵具合がいいもの…パン生地、ヨーグルト、甘酒などです。
麹ともち米で久しぶりに甘酒をつくってみました。

ピザもストーブで焼きます。ピザ生地の発酵もストーブ脇で…


諏訪湖の海老でえびせんべいを作りました。
せんべいを焼くプレートです。これに生地を流して挟んで焼きます。


ストーブで焼いてみたのですが、火加減が難しくてコンロで…
、

厚さもまちまち…手作り感あふれるえびせんべいですが美味しかったです。

燻製作りは夫の仕事…ビーフジャーキーを作ってくれました。

立派な文旦をいただいたのでピールとジャムを作りました。

皮は何度も茹でこぼして砂糖で煮て乾燥させてピールにしました。その後チョコ掛けの予定…

果実は煮詰めてジャムにしました。


おまけの原村の庭…1週間ほど前の状態です。
落ち葉の上にスノードロップが花を咲かせ、水仙が芽生えてきました。
そしてその後大雪が!30㎝近くも積もったそうです。