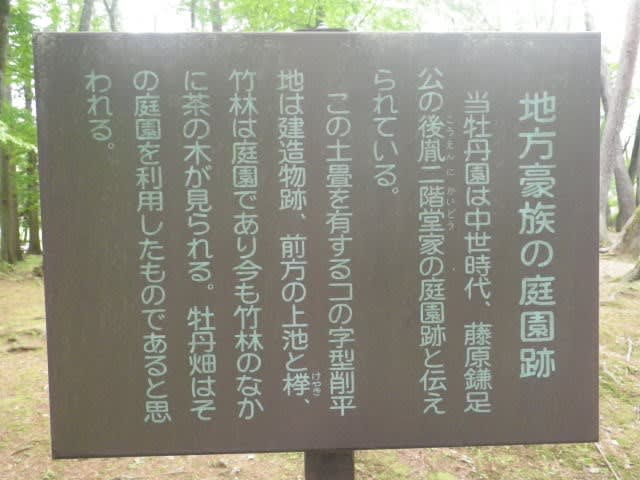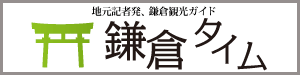昨年まではこまエコ散歩のお手伝いと、すこやか歩こう会の活動は別々に行っていたのですが、今年度からノルディックウォーキング講習会が加わり日程調整がにっちもさっちもゆかなくなり、すこやか歩こう会の活動はこまエコ散歩に合流させていただくことになりました。
こまエコ散歩は駒場体育館が主催するウォーキング事業で、この企画が始まった時から目黒ウォーキング協会が協力して実施されてきました。

写真:講習の様子
従来は「エコ」についての講習と「ウォーキング」についての講習を行い、実習として駒場や大橋周辺をウォーキングしていました。「エコ」の話は突き詰めると結構難しく、「割り箸を使わないようにしましょう!」という話になると、「割り箸を使わないことが本当にエコなのか?」との意見もあって、実際素人が取り扱う話題としてはハードルが高い印象です。「ウォーキングが究極のエコ!」という話は反論を受けにくく、今年度は「散歩に行く前に天気予報をチェックしましょう」ということで、『散歩に役立つお天気ミニ知識』というテーマで、気象予報士の池田洋人さんがお話をしてくれました。

写真:カリンの実
講習の後は駒場野公園でストレッチをして出発です。カリン、梅、桃など様々な果実が実をつけ始めています。ウォーキングは駒場野公園のバラ園を見て、筑波大学駒場中高の正門で騎兵第一連隊の話をしてから先へ進みます。

写真:馬神碑
この日は日本ダービーが開催される5月27日で、いつもよりお供えされている人参が多いように思います。台地を目黒川が削った地元で「騎兵山」と呼ばれる場所は南西の視界が開けており、供養碑を建てるにはよい場所だったのでしょう。マンションの裏側には秋山好古が揮毫した石碑が残されています。
目黒川暗渠に整備された緑道公園を歩き、玉川通りを渡ったところで大橋の町名の由来、鮎飛脚が通った大山街道の話、首都高大橋ジャンクションの話などをした後、天空庭園へ向かいます。ジャンクションについてWikipediaから引用します。
概要
当地には1969年まで東急玉川線大橋車庫が設置されていた。東急玉川線の廃止後は東急バス大橋営業所となったが、2002年に廃止された。
2010年3月28日に、中央環状新宿線の全通(大橋JCT - 西新宿JCT間)により部分的に供用を開始した。残る品川線区間の大井JCT - 大橋JCT間は2015年3月7日に供用開始した。
構造
旧山手通りの地下を走っている中央環状線からの連絡線がループを描き3号渋谷線の上まで昇り、そこで都心方面・東名方面に分岐し3号渋谷線の本線に取り付く(なお、3号渋谷線側は建設当時からジャンクションへの分合流を考慮した構造で建設されている)。
ループの両端につながる3号渋谷線・中央環状線とは上下/内外全4方面に接続する。中央環状新宿線のジャンクション群の中で、土地の制約上一部方面の連絡がない熊野町・西新宿両ジャンクションと違い、全方面への接続を確保できたのは、連絡線を一個のらせんにまとめたループ部分による所が大きい。
ループ部分には広大な土地が必要であるが、その見返りとしてループに隣接した敷地に東京都が再開発事業主体となり、超高層ビル型のタワーマンション2棟と公共施設の開発を不動産デベロッパーと共同で行う。建設敷地は約25,000m2である。
再開発敷地(O-path目黒大橋)には、まず27階建てのタワーマンション「プリズムタワー」が2009年1月に竣工し、42階建てのタワーマンション「クロスエアタワー」が2013年1月に竣工した。
ループ部分の構造
・地上約35m、地下約36m 高低差約71m
・一周約400m
・4層構造
・制限速度は40Km/h
ループ部分は国立霞ヶ丘競技場程の広大なもので、騒音対策のため4層ループのトンネル構造となっている。また排気ガス対策のため、ループの内側部分には換気所が設けられる。
ループ内は急勾配・急カーブのため、ジャンクション内の制限速度を40km/hに設定する事、外観が見えないループで方向感覚が分かりにくくなる事から、行先を色で示す様に路面に塗装する工夫がされている。
外観はコロッセオのイメージが一部に取り入れられている。ループの屋上部分は公園として緑化され、周囲のマンションと直結した目黒天空庭園として整備されている。

写真:富士山が見える方角


写真:おおはし里の杜
富士山はキャロットタワーの右側に見えるようですが、マンションに隠れてあまりよくは見えないようです。私が子供の頃は烏森小学校の窓からも見えたのですが。。。

写真:ナデシコ

写真:ギンバイカ(マートル)

写真:クチナシ

写真:何の実?

写真:ブドウ

写真:アカンサス(葉アザミ)
天空庭園についてWikipediaから引用します。
目黒天空庭園(めぐろてんくうていえん)とは、東京都目黒区大橋に存在する屋上庭園。 首都高速道路の大橋ジャンクションの屋上に造成され、2013年3月30日にオープンした。
概要
首都高速道路の3号渋谷線と中央環状線を結ぶ大橋ジャンクションの屋上を緑地化した庭園で、目黒区の区立公園として整備されている。
ドーナツのような楕円形が特長。高さは地上11メートルから35メートル、延長距離は約400メートルで、平均勾配約6%のループ状である。最も低い部分は歩道橋経由で国道246号へと通じている。庭園には芝生を基礎として約30種類の樹木や花が植えられている。
開園時間は午前7時から午後9時まで。南側に設置されているエレベーターの3階が庭園となっており、バリアフリー対策が施されているため車椅子やベビーカーでの入場も可能。
造成の背景
首都高速道路において、高架の3号渋谷線と地下トンネルの中央環状線をジャンクションで結ぶためには高低差の問題と用地の問題があった。そのため、少ない敷地面積で高低差を稼げるループ状として建設されたのが大橋ジャンクションである。
その建設計画として環境対策が盛り込まれており、また、公園の数が少なく面積も狭い都心において子どもたちが走り回れる場所が欲しいという住民のニーズにも応える形で緑地化、公園化する案が採用された。
庭園の造成にあたっては、目黒区が首都高速道路から占用使用許可を受け、都市公園法に基づく立体都市公園として整備した。
この公園もオープン当初は「人工的に公園を作りました」感が満載で違和感を感じましたが、開園から5年がたち少し枯れてきてよくなりました。アカンサスは最近よく見るようになりましたが、10年前には珍しくウォーキングでわざわざ見に行ったというような話も聞きました。「葉アザミ」と聞くと皇居二重橋のお濠の柵にデザインされており、明治時代には日本で見られた植物なのかなぁと想像してしまいます。
天空庭園を後にして上目黒氷川神社で富士登山。明治時代、目黒元富士があった場所に岩倉具視の別荘が建てられ、富士塚に埋められた富士山の溶岩などがこちらに移され浅間神社がまつられました。松見坂を通り駒場バラ園の前を抜けて、東京大学教養学部の中を歩きます。重要文化財の前田邸洋館が耐震工事中の駒場公園を見て、駒場野公園へ戻ってきました。

写真:田植え前のケルネル田圃
ゴールの駒場野公園は東京教育大学農学部があった場所で、ケルネル田圃はその名残を残し、教育大が筑波大学に変わった今でもその付属高校の生徒たちにより田植えが行われています。このあたり、江戸時代は将軍お鷹狩りのための鷹場で、明治時代になり駒場農学校が置かれます。駒場農学校についてWikipediaから引用します。
駒場農学校(こまばのうがっこう)は、日本の旧制教育機関。現在の東京大学農学部、筑波大学生命環境学群生物資源学類、東京農工大学農学部の前身にあたる農学に関する日本初の総合教育・研究機関であった。
概要
黎明期の日本近代農学の発展に大きな役割を果たし、日本近代農学発展の礎となった。
アメリカの農業を教育の柱にしたクラーク博士で有名な札幌農学校に対して、もっぱらドイツ農法に範を求めた駒場農学校は、やがて欧米の農作物を試植する「泰西(たいせい)農場」、在来農法の改良を期した「本邦農場」などの農場のほかに、園芸・植物園、家畜病院、気象台などまで備えた農業の総合教育・研究機関となった。当初、約6万坪の敷地であったが、その後、次第に拡張され、1884年には、敷地面積が16万5千坪に達した。
跡地の一部は1986年に駒場野公園として開園した。広さ2.8ヘクタールの園内には、雑木林や水田がある。
日差しがあって少し暑いくらいでしたが、気持ちの良いウォーキングでした。この後ほとんどのメンバーで東山のインド料理へ行き食事しました。これで収まりがつかないおじさんたちは、ONCEのモニターに日本ダービーを映してもらって競馬観戦。その後大相撲観戦で盛り上がりました。
すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。
まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。
sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。
すこやか歩こう会活動スケジュール
こまエコ散歩は駒場体育館が主催するウォーキング事業で、この企画が始まった時から目黒ウォーキング協会が協力して実施されてきました。

写真:講習の様子
従来は「エコ」についての講習と「ウォーキング」についての講習を行い、実習として駒場や大橋周辺をウォーキングしていました。「エコ」の話は突き詰めると結構難しく、「割り箸を使わないようにしましょう!」という話になると、「割り箸を使わないことが本当にエコなのか?」との意見もあって、実際素人が取り扱う話題としてはハードルが高い印象です。「ウォーキングが究極のエコ!」という話は反論を受けにくく、今年度は「散歩に行く前に天気予報をチェックしましょう」ということで、『散歩に役立つお天気ミニ知識』というテーマで、気象予報士の池田洋人さんがお話をしてくれました。

写真:カリンの実
講習の後は駒場野公園でストレッチをして出発です。カリン、梅、桃など様々な果実が実をつけ始めています。ウォーキングは駒場野公園のバラ園を見て、筑波大学駒場中高の正門で騎兵第一連隊の話をしてから先へ進みます。

写真:馬神碑
この日は日本ダービーが開催される5月27日で、いつもよりお供えされている人参が多いように思います。台地を目黒川が削った地元で「騎兵山」と呼ばれる場所は南西の視界が開けており、供養碑を建てるにはよい場所だったのでしょう。マンションの裏側には秋山好古が揮毫した石碑が残されています。
目黒川暗渠に整備された緑道公園を歩き、玉川通りを渡ったところで大橋の町名の由来、鮎飛脚が通った大山街道の話、首都高大橋ジャンクションの話などをした後、天空庭園へ向かいます。ジャンクションについてWikipediaから引用します。
概要
当地には1969年まで東急玉川線大橋車庫が設置されていた。東急玉川線の廃止後は東急バス大橋営業所となったが、2002年に廃止された。
2010年3月28日に、中央環状新宿線の全通(大橋JCT - 西新宿JCT間)により部分的に供用を開始した。残る品川線区間の大井JCT - 大橋JCT間は2015年3月7日に供用開始した。
構造
旧山手通りの地下を走っている中央環状線からの連絡線がループを描き3号渋谷線の上まで昇り、そこで都心方面・東名方面に分岐し3号渋谷線の本線に取り付く(なお、3号渋谷線側は建設当時からジャンクションへの分合流を考慮した構造で建設されている)。
ループの両端につながる3号渋谷線・中央環状線とは上下/内外全4方面に接続する。中央環状新宿線のジャンクション群の中で、土地の制約上一部方面の連絡がない熊野町・西新宿両ジャンクションと違い、全方面への接続を確保できたのは、連絡線を一個のらせんにまとめたループ部分による所が大きい。
ループ部分には広大な土地が必要であるが、その見返りとしてループに隣接した敷地に東京都が再開発事業主体となり、超高層ビル型のタワーマンション2棟と公共施設の開発を不動産デベロッパーと共同で行う。建設敷地は約25,000m2である。
再開発敷地(O-path目黒大橋)には、まず27階建てのタワーマンション「プリズムタワー」が2009年1月に竣工し、42階建てのタワーマンション「クロスエアタワー」が2013年1月に竣工した。
ループ部分の構造
・地上約35m、地下約36m 高低差約71m
・一周約400m
・4層構造
・制限速度は40Km/h
ループ部分は国立霞ヶ丘競技場程の広大なもので、騒音対策のため4層ループのトンネル構造となっている。また排気ガス対策のため、ループの内側部分には換気所が設けられる。
ループ内は急勾配・急カーブのため、ジャンクション内の制限速度を40km/hに設定する事、外観が見えないループで方向感覚が分かりにくくなる事から、行先を色で示す様に路面に塗装する工夫がされている。
外観はコロッセオのイメージが一部に取り入れられている。ループの屋上部分は公園として緑化され、周囲のマンションと直結した目黒天空庭園として整備されている。

写真:富士山が見える方角


写真:おおはし里の杜
富士山はキャロットタワーの右側に見えるようですが、マンションに隠れてあまりよくは見えないようです。私が子供の頃は烏森小学校の窓からも見えたのですが。。。

写真:ナデシコ

写真:ギンバイカ(マートル)

写真:クチナシ

写真:何の実?

写真:ブドウ

写真:アカンサス(葉アザミ)
天空庭園についてWikipediaから引用します。
目黒天空庭園(めぐろてんくうていえん)とは、東京都目黒区大橋に存在する屋上庭園。 首都高速道路の大橋ジャンクションの屋上に造成され、2013年3月30日にオープンした。
概要
首都高速道路の3号渋谷線と中央環状線を結ぶ大橋ジャンクションの屋上を緑地化した庭園で、目黒区の区立公園として整備されている。
ドーナツのような楕円形が特長。高さは地上11メートルから35メートル、延長距離は約400メートルで、平均勾配約6%のループ状である。最も低い部分は歩道橋経由で国道246号へと通じている。庭園には芝生を基礎として約30種類の樹木や花が植えられている。
開園時間は午前7時から午後9時まで。南側に設置されているエレベーターの3階が庭園となっており、バリアフリー対策が施されているため車椅子やベビーカーでの入場も可能。
造成の背景
首都高速道路において、高架の3号渋谷線と地下トンネルの中央環状線をジャンクションで結ぶためには高低差の問題と用地の問題があった。そのため、少ない敷地面積で高低差を稼げるループ状として建設されたのが大橋ジャンクションである。
その建設計画として環境対策が盛り込まれており、また、公園の数が少なく面積も狭い都心において子どもたちが走り回れる場所が欲しいという住民のニーズにも応える形で緑地化、公園化する案が採用された。
庭園の造成にあたっては、目黒区が首都高速道路から占用使用許可を受け、都市公園法に基づく立体都市公園として整備した。
この公園もオープン当初は「人工的に公園を作りました」感が満載で違和感を感じましたが、開園から5年がたち少し枯れてきてよくなりました。アカンサスは最近よく見るようになりましたが、10年前には珍しくウォーキングでわざわざ見に行ったというような話も聞きました。「葉アザミ」と聞くと皇居二重橋のお濠の柵にデザインされており、明治時代には日本で見られた植物なのかなぁと想像してしまいます。
天空庭園を後にして上目黒氷川神社で富士登山。明治時代、目黒元富士があった場所に岩倉具視の別荘が建てられ、富士塚に埋められた富士山の溶岩などがこちらに移され浅間神社がまつられました。松見坂を通り駒場バラ園の前を抜けて、東京大学教養学部の中を歩きます。重要文化財の前田邸洋館が耐震工事中の駒場公園を見て、駒場野公園へ戻ってきました。

写真:田植え前のケルネル田圃
ゴールの駒場野公園は東京教育大学農学部があった場所で、ケルネル田圃はその名残を残し、教育大が筑波大学に変わった今でもその付属高校の生徒たちにより田植えが行われています。このあたり、江戸時代は将軍お鷹狩りのための鷹場で、明治時代になり駒場農学校が置かれます。駒場農学校についてWikipediaから引用します。
駒場農学校(こまばのうがっこう)は、日本の旧制教育機関。現在の東京大学農学部、筑波大学生命環境学群生物資源学類、東京農工大学農学部の前身にあたる農学に関する日本初の総合教育・研究機関であった。
概要
黎明期の日本近代農学の発展に大きな役割を果たし、日本近代農学発展の礎となった。
アメリカの農業を教育の柱にしたクラーク博士で有名な札幌農学校に対して、もっぱらドイツ農法に範を求めた駒場農学校は、やがて欧米の農作物を試植する「泰西(たいせい)農場」、在来農法の改良を期した「本邦農場」などの農場のほかに、園芸・植物園、家畜病院、気象台などまで備えた農業の総合教育・研究機関となった。当初、約6万坪の敷地であったが、その後、次第に拡張され、1884年には、敷地面積が16万5千坪に達した。
跡地の一部は1986年に駒場野公園として開園した。広さ2.8ヘクタールの園内には、雑木林や水田がある。
日差しがあって少し暑いくらいでしたが、気持ちの良いウォーキングでした。この後ほとんどのメンバーで東山のインド料理へ行き食事しました。これで収まりがつかないおじさんたちは、ONCEのモニターに日本ダービーを映してもらって競馬観戦。その後大相撲観戦で盛り上がりました。
すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。
まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。
sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。
すこやか歩こう会活動スケジュール