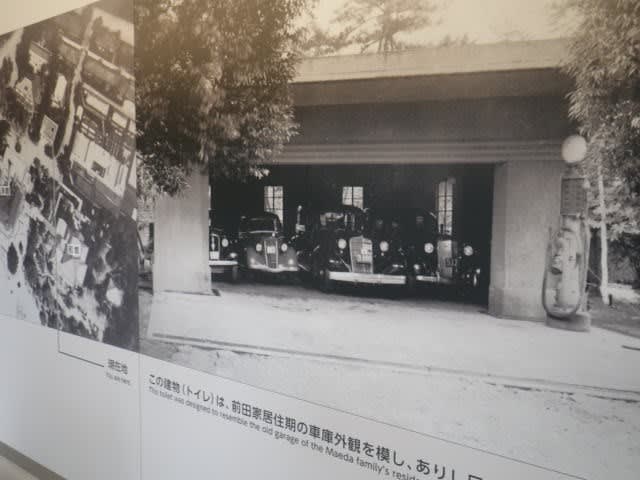暑さ寒さも彼岸までとはよく言ったもので、九月に入りウォーキングが中止になることもなくなりました。一週目二週目は「熱中症対策をしてご参加ください」と書いたのですが、ここ二回はそれも不要になりました。

田楽橋からアトラスタワー

ヒルガオ

目黒清掃工場の工事現場
前日までぐずついた天気が続き、この日も「雨が降るかもしれないし、降らないかもしれないし」と予報の難しい状況だったようですが、朝は降っておらず曇りの予報になっていたので実施の決断は簡単で、この曇り空ですが雨は降ってきませんでした。
中目黒GTに集合して目黒川舟入場でストレッチをして目黒川下流へ向かいウォーキングスタートです。ヒルガオもまもなく終了ですね。

目黒区健康都市宣言
区民センターの掲示板に張ってあり、この宣言が活字になっているのを見たのは初めてかもしれません。平和都市宣言とかだと石碑があったりしますが、どこかに石碑を設置するようなものでもないでしょうから。
健康都市宣言は我々のウォーキングクラブ設立のきっかけになったものでこれが無ければウォーキング活動をしてなかったかもしれません。健康都市宣言を受け、スポーツ推進課の担当者はラジオ体操とウォーキング事業を企画しました。これをきっかけにスタートしたラジオ体操は碑文谷体育館グランドに三千人を集めラジオで放送されました。ラジオ体操は現在も続けられ、withコロナで参加者が増えているとのこと。健康に留意したり、おしゃべりする相手を求めてのことでしょう。
目黒健康ウォークが企画され北部地区は烏森小学校での講義と、地区のウォーキングが行われました。健康ウォークが終了した時に北部、東部、中央、南部、西部の五地区にウォーキングクラブが設立され北部地区は「すこやか歩こう会」として活動をスタートさせています。「すこやかに」生きてゆきたいという意味と「す=菅刈」「こ=駒場」「や=東山」「か=烏森」の北部を構成する四つの住区からいち文字をとり命名されました。
五地区のウォーキングクラブは協力して事業を進めてゆこうと、翌年目黒ウォーキングクラブを設立しました。目黒健康ウォークは「めぐろウォーキング塾」として今年度コロナ自粛の影響で途切れるまでずっと続けてきましたし、来年度は実施できるものと信じています。

区民センター花壇のコスモス

羽
区民センターでトイレ休憩をとり再スタートで歩き始めると、羽が動いているんです。「なぜ動いているんだ?」とよく見てみると、アリが運んでいました。よく見ると右のほうに映っているのがわかると思います。無事巣まで持ちかえることが出来たでしょうか

今年は三の酉

七五三
私が住んでいる地域の秋祭りは軒並み中止または縮小でしたが、酉の市は行われるようですね。GoToイベントも始まるし徐々に通常モードへ移行しつつあるということですね。

ゴクラクチョウカ

お風呂屋さんの後

目黒区みどりの散歩道
大鳥神社の交差点から目黒通りを西へ向かい寄生虫会館手前で南に折れます。以前から営業はしていないような大きなお風呂屋さんでしたが、知らぬ間に駐車場に変わりました。

目黒不動尊

役行者様

縁日の予定

水かけ不動

縁日の準備
28日はお不動様御開帳で縁日です。西村知美がからくりテレビメンバーを誘ったけど、誰も参加しなかった縁日です。秋祭りの出店は皆無でしたが、お不動様の縁日はあるようですね。

三福神

恵比寿様
この神社も龍泉寺の境内案内に含まれているのですが、あまり説明もなくさらなる究明が必要なようです。

都立林試の森公園

ヒガンバナは蕾

キカラスウリ
林試の森は目黒区と品川区にまたがる都立公園です。お彼岸も過ぎたのにまだ蕾とは、今年のヒガンバナは遅いです。暑さが続いたせいかな?

マケドニア松
マケドニアもどこにあるのかすぐには思い浮かばない国です。ちょっと考えると「ユーゴスラビアか!」と思い出します。大学時代のディスカッションのテーマで東西問題が取り上げられ、チトー大統領がいなければユーゴスラビアは分裂すると言われていましたがまさにその通りになりました。調べてみるとマケドニアは国名ではなくなり「北マケドニア共和国」に変更されていました。ギリシャとの論争の結果ですね。独立宣言が1991年、国連加盟が1993年、国名の改称が2019年ということで最近の話の割には日本とはなじみが薄い。東ヨーロッパ全般に言えることですが。


ヒガンバナ
園内では咲いているヒガンバナも見ることが出来ました。

慈光院
個人のお宅のようなお寺さんで調べてみても曹洞宗のお寺ということ以外わかりません。奈良の慈光院が有名なようですがあちらは臨済宗です。

目黒七中

円融寺阿弥陀堂

円融寺釈迦堂

円融寺仁王門

円融寺参道
円融寺は目黒不動龍泉寺に次ぐ目黒区内で二番目に古いお寺で、仁王門に納められた黒仁王で知られており、古い道標にも「くろにおう」と書かれたものがあります。

立会川緑道

みどりの散歩道

たぶんキンモクセイ
ウォーキング中かすかにキンモクセイの香りがしたような気がするのですが、このモクセイはまだまだ香りを発していませんでした。ヒガンバナと並びキンモクセイも遅れているようです。

碑文谷八幡宮

小さなどんぐり
旧碑文谷村の鎮守で碑文谷の地名の由来となった碑が本殿の隣に飾ってあります。

竹林のヒガンバナ

敷居

青紅葉
すずめのお宿緑地公園で休憩。「敷居を踏むことはお父さんの頭を踏むのと同じこと」と子供の頃に言われたことを思い出します。

白いヒガンバナ
赤と黄色のヒガンバナを交配してできたものとのこと。素人考えではオレンジ色になりそうなものですが。。。

スッポン雑炊
スッポン食べたい!安心院で食べたい!

ヤナセ
以前は工場のようでしたが立て替えてギャラリーになりました。すずめのお宿から碑さくら通りを東へ進み、サレジオ通りを北上し目黒通りを横断します。

碑文谷公園のコキア
withコロナ時代のウォーキングの在り方はまだまだ手探り。すこやか歩こう会の特徴である「いろいろなところを歩く」を全開にするにはまだ時期尚早の様な気がします。鉄道で遠出をしない範囲で9月10月の8回分のウォーキングを企画しました。来年二月までこの8コースの繰り返しになるでしょう。となれば次回碑文谷公園を訪れるのは二か月後。その時にはこのコキアも赤く染まっているでしょうか。
この日も反省会なしで解散。withコロナにはなじめそうにありません。
すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。
まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。
sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。
すこやか歩こう会活動スケジュール

田楽橋からアトラスタワー

ヒルガオ

目黒清掃工場の工事現場
前日までぐずついた天気が続き、この日も「雨が降るかもしれないし、降らないかもしれないし」と予報の難しい状況だったようですが、朝は降っておらず曇りの予報になっていたので実施の決断は簡単で、この曇り空ですが雨は降ってきませんでした。
中目黒GTに集合して目黒川舟入場でストレッチをして目黒川下流へ向かいウォーキングスタートです。ヒルガオもまもなく終了ですね。

目黒区健康都市宣言
区民センターの掲示板に張ってあり、この宣言が活字になっているのを見たのは初めてかもしれません。平和都市宣言とかだと石碑があったりしますが、どこかに石碑を設置するようなものでもないでしょうから。
健康都市宣言は我々のウォーキングクラブ設立のきっかけになったものでこれが無ければウォーキング活動をしてなかったかもしれません。健康都市宣言を受け、スポーツ推進課の担当者はラジオ体操とウォーキング事業を企画しました。これをきっかけにスタートしたラジオ体操は碑文谷体育館グランドに三千人を集めラジオで放送されました。ラジオ体操は現在も続けられ、withコロナで参加者が増えているとのこと。健康に留意したり、おしゃべりする相手を求めてのことでしょう。
目黒健康ウォークが企画され北部地区は烏森小学校での講義と、地区のウォーキングが行われました。健康ウォークが終了した時に北部、東部、中央、南部、西部の五地区にウォーキングクラブが設立され北部地区は「すこやか歩こう会」として活動をスタートさせています。「すこやかに」生きてゆきたいという意味と「す=菅刈」「こ=駒場」「や=東山」「か=烏森」の北部を構成する四つの住区からいち文字をとり命名されました。
五地区のウォーキングクラブは協力して事業を進めてゆこうと、翌年目黒ウォーキングクラブを設立しました。目黒健康ウォークは「めぐろウォーキング塾」として今年度コロナ自粛の影響で途切れるまでずっと続けてきましたし、来年度は実施できるものと信じています。

区民センター花壇のコスモス

羽
区民センターでトイレ休憩をとり再スタートで歩き始めると、羽が動いているんです。「なぜ動いているんだ?」とよく見てみると、アリが運んでいました。よく見ると右のほうに映っているのがわかると思います。無事巣まで持ちかえることが出来たでしょうか

今年は三の酉

七五三
私が住んでいる地域の秋祭りは軒並み中止または縮小でしたが、酉の市は行われるようですね。GoToイベントも始まるし徐々に通常モードへ移行しつつあるということですね。

ゴクラクチョウカ

お風呂屋さんの後

目黒区みどりの散歩道
大鳥神社の交差点から目黒通りを西へ向かい寄生虫会館手前で南に折れます。以前から営業はしていないような大きなお風呂屋さんでしたが、知らぬ間に駐車場に変わりました。

目黒不動尊

役行者様

縁日の予定

水かけ不動

縁日の準備
28日はお不動様御開帳で縁日です。西村知美がからくりテレビメンバーを誘ったけど、誰も参加しなかった縁日です。秋祭りの出店は皆無でしたが、お不動様の縁日はあるようですね。

三福神

恵比寿様
この神社も龍泉寺の境内案内に含まれているのですが、あまり説明もなくさらなる究明が必要なようです。

都立林試の森公園

ヒガンバナは蕾

キカラスウリ
林試の森は目黒区と品川区にまたがる都立公園です。お彼岸も過ぎたのにまだ蕾とは、今年のヒガンバナは遅いです。暑さが続いたせいかな?

マケドニア松
マケドニアもどこにあるのかすぐには思い浮かばない国です。ちょっと考えると「ユーゴスラビアか!」と思い出します。大学時代のディスカッションのテーマで東西問題が取り上げられ、チトー大統領がいなければユーゴスラビアは分裂すると言われていましたがまさにその通りになりました。調べてみるとマケドニアは国名ではなくなり「北マケドニア共和国」に変更されていました。ギリシャとの論争の結果ですね。独立宣言が1991年、国連加盟が1993年、国名の改称が2019年ということで最近の話の割には日本とはなじみが薄い。東ヨーロッパ全般に言えることですが。


ヒガンバナ
園内では咲いているヒガンバナも見ることが出来ました。

慈光院
個人のお宅のようなお寺さんで調べてみても曹洞宗のお寺ということ以外わかりません。奈良の慈光院が有名なようですがあちらは臨済宗です。

目黒七中

円融寺阿弥陀堂

円融寺釈迦堂

円融寺仁王門

円融寺参道
円融寺は目黒不動龍泉寺に次ぐ目黒区内で二番目に古いお寺で、仁王門に納められた黒仁王で知られており、古い道標にも「くろにおう」と書かれたものがあります。

立会川緑道

みどりの散歩道

たぶんキンモクセイ
ウォーキング中かすかにキンモクセイの香りがしたような気がするのですが、このモクセイはまだまだ香りを発していませんでした。ヒガンバナと並びキンモクセイも遅れているようです。

碑文谷八幡宮

小さなどんぐり
旧碑文谷村の鎮守で碑文谷の地名の由来となった碑が本殿の隣に飾ってあります。

竹林のヒガンバナ

敷居

青紅葉
すずめのお宿緑地公園で休憩。「敷居を踏むことはお父さんの頭を踏むのと同じこと」と子供の頃に言われたことを思い出します。

白いヒガンバナ
赤と黄色のヒガンバナを交配してできたものとのこと。素人考えではオレンジ色になりそうなものですが。。。

スッポン雑炊
スッポン食べたい!安心院で食べたい!

ヤナセ
以前は工場のようでしたが立て替えてギャラリーになりました。すずめのお宿から碑さくら通りを東へ進み、サレジオ通りを北上し目黒通りを横断します。

碑文谷公園のコキア
withコロナ時代のウォーキングの在り方はまだまだ手探り。すこやか歩こう会の特徴である「いろいろなところを歩く」を全開にするにはまだ時期尚早の様な気がします。鉄道で遠出をしない範囲で9月10月の8回分のウォーキングを企画しました。来年二月までこの8コースの繰り返しになるでしょう。となれば次回碑文谷公園を訪れるのは二か月後。その時にはこのコキアも赤く染まっているでしょうか。
この日も反省会なしで解散。withコロナにはなじめそうにありません。
すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。
まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。
sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。
すこやか歩こう会活動スケジュール