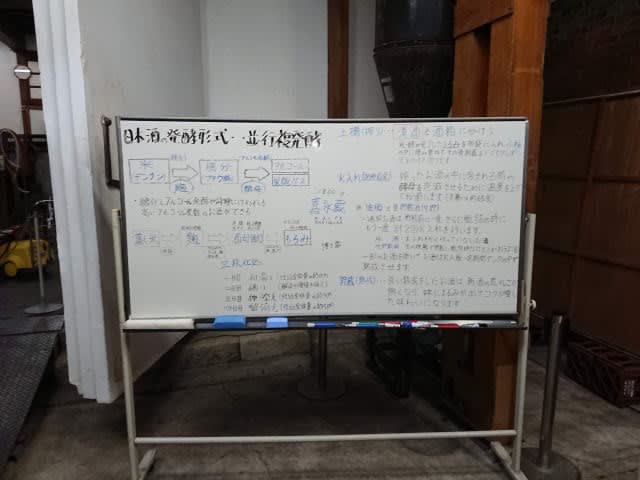11月3日の本番を前にして最後の研修ウォーキングとなります。目黒ウォーキング協会事務局の私は4月のコース選定から歩き始め、この日は実行委員のほとんどが参加し、コースの確認とともに各自の役割も確認をしながら最終チェックとなりました。

日比谷公園松本楼
日比谷公園開店当初から続く老舗の洋食店。沖縄返還協定反対デモでの焼失など、日比谷公園の歴史そのものといっても過言ではないでしょう。Wikipediaから10円カレーの項目を引用してみましょう。
10円カレー
1971年の2度目の焼失では、警備員1人が犠牲になるなど被害も大きかった。歴史あるレストランが焼失したこの知らせに全国から再興の願いが集まり、3代目松本楼がオープンできた。これに感謝の意を示す記念行事として、松本楼は「10円カレー」セールを始めた。通常は880円(2015年時点)のハイカラビーフカレーが、1973年以来毎年(1988年を除く)9月25日に限り、先着1500名に限り10円で振る舞われ、現在も毎年この日には大勢の来客があり、度々ニュースでも取り上げられている。10円を受け取るのは「無料ではお客様としてもてなすことにならない」という趣旨であり、代金以外に寄付金を置いていく人が多い。カレーの売上や寄付金は交通遺児育英会や日本ユニセフ協会などに渡され、1995年には阪神淡路大震災の義援金として贈られた。「10円カレー」は秋の季語にもなっている。

雲形池
紅葉の雲形池もきれいですが、冬に鶴の噴水にツララが出来る頃が一番の見頃でしょう。お鷹狩り本番の時にはもう少し紅葉が進んでいることでしょう。

慈恵医大西新橋キャンパス
慈恵医大の略歴をWikipediaから引用します。
東京慈恵会医科大学の起源は、高木兼寛によって1881年(明治14年)5月1日に創立された医術開業試験受験予備校(乙種医学校)の「成医会講習所」である。高木は1875年(明治8年)から5年間、海軍生徒として英国セント・トーマス病院医学校(現:ロンドン大学群キングス・カレッジ・ロンドン医学部)に学び、このように権威のある医学校を日本につくりたいと思っていた。高木は帰国後、廃止された慶應義塾医学所に関わっていた松山棟庵とともに1881年(明治14年)1月、「成医会」なる研究団体を設立し、次いで同5月にこの成医会講習所を設立している。
その後、高木は戸塚文海とともに、1882年(明治15年)、有志共立東京病院なる慈善病院を発足させている。この病院の設立趣意には「貧乏であるために治療の時期を失したり、手を施すことなく、いたずらに苦しみにさらされている者を救うこと」にあるとしている。このような趣意も、高木が英国留学中に受けた人道主義や博愛主義の強い影響による。同病院の資金は有志の拠金によるものであり、有志共立という名はそのためであった。病院総長としては有栖川威仁親王を戴き、また大日本帝国海軍軍医団の強い支援があった。
有志共立東京病院は、こうした慈善病院のほかに医学教育の場としても重要な役割を果たし、成医会講習所や海軍軍医学校の実習病院の役割を担った。これも、英国で経験した慈善病院と医学校の関係を東京に実現しようとしたものである。1887年(明治20年)、同病院は皇后を総裁に迎え、その名も東京慈恵医院と改め、経費は主に皇室資金によることになった。成医会講習所も成医学校に、次いで東京慈恵医院医学校に改称され、同病院構内(当時は東京市芝区愛宕町二丁目、現:港区西新橋三丁目)に移転した。
有志共立東京病院時代の特筆すべき事業の一つに看護婦教育所の設立がある。英国留学時代、セント・トーマス病院に付設されていたナイチンゲール看護学校を目の当たりにした高木は、日本の近代看護教育の導入にも極めて積極的であった。彼は1884年(明治17年)10月、米国女性宣教師のリードを招き看護婦教育を実践した。これが日本での近代看護教育の始まりである。第一回生はわずか5名であったが、総裁皇后の臨席を得て卒業式が行われた。現在の慈恵看護専門学校及び医学部看護学科、大学院医学研究科看護学専攻修士課程はこの流れを汲むものである。
1907年(明治40年)、有栖川宮威仁親王妃慰子を総裁とする社団法人東京慈恵会が設立され、東京慈恵医院の経済的支援をすることになったので、東京慈恵医院は東京慈恵会医院と改称された。また既に医学専門学校に昇格していた東京慈恵医院医学専門学校は、1908年(明治41年)に東京慈恵会医院医学専門学校と改められた。
1921年(大正10年)、大学令の公布を機会に東京慈恵会医院医学専門学校は東京慈恵会医科大学に昇格した。その時、高木家私有の東京病院が大学に寄付されたため、医科大学として附属病院を持つことになった。1952年(昭和27年)に学制改革による新制大学となり、1956年(昭和31年)に大学院医学研究科博士課程、1992年(平成4年)に医学看護学科、2009年(平成21年)に看護学専攻修士課程が設置された。

有章院霊廟 二天門
今回のお鷹狩りではショートコース、ロングコースともに御成門、二天門の前を通ります。二天門は改修されたばかりで今回のコースのハイライトの一つです。

プリンス芝公園からの東京タワー
増上寺の三解脱門、台徳院霊廟惣門の前を通過し、港区立芝公園で平和の灯を見て、芝丸山古墳の脇を通りプリンス芝公園に出ます。増上寺三門は江戸で一番高い展望台として人気でした。その後ろにそびえる東京タワーはいまでは日本一の座をスカイツリーに明け渡しましたが、人気の展望台です。東京タワーはメインデッキの改修が終わり大人料金が900円から1200円へ改訂されましたが、学校団体だと中学生が400円(スカイツリーは950円)、高校生が500円(同1100円)とリーズナブルです。
写真にありませんが三解脱門も戦災を逃れ重要文化財となっています。この項目をWikipediaから引用します。
三解脱門(さんげだつもん、重要文化財) - 戦災を免れた建物の1つで、元和8年(1622年)建立の二重門(重層で、各層に屋根が付く門)。この門をくぐると、三毒(3つの煩悩、即ち貪、瞋、癡)から解脱できるとされる。内部には釈迦三尊像と十六羅漢像が安置されている。

春日神社の鹿
桜田通り慶応大学の隣に春日神社があり、社務所に鹿の像がありました。総本社は奈良の春日大社で全国で千余りの春日神社があります。多くは近畿地方にありますが、Wikipediaによると都内に四か所となっていて目黒区の春日神社は表記がありませんでした。Wikipediaの「三田春日神社」の項目から一部を抜粋してみましょう。
由緒
958年(天徳2年)、武蔵国国司の藤原正房が任国の際、春日大社の第三殿に祀る天児屋根命の御神霊を目黒区三田に勧請。天文年間(1533-1555)当地へ遷座した。旧社格は村社。
備考
最初に鎮座した目黒区三田には1934年(昭和9年)跡地に目黒三田春日神社が再興され、1947年(昭和22年)より当社の兼務社となっている。
文京区に春日神社はなく、春日の字名は春日局の拝領地に由来しています。

高輪皇族邸
台風15号でなぎ倒された木はすでに片付けられて、金網に傷跡が見えます。

旧国立公衆衛生院
ゆかしの杜でトイレと場所をお借りし、15分の休憩を予定します。

ススキとサッポロビール本社

茶屋坂と爺が茶屋
目黒区ページから引用します。
目黒の坂 茶屋坂
更新日:2014年2月3日
「目黒の坂」は、「月刊めぐろ」1972年3月号から1984年2月号の掲載記事を再構成し編集したものです。
目黒のさんま
江戸の初め、田道橋を渡り三田方面に通ずる坂上の眺望のよいところに、1軒の茶屋があった。徳川3代将軍家光は、目黒筋遊猟の帰りにしばしばこの茶屋に寄って休息をとっていた。家光は、茶屋の主人彦四郎の素朴な人柄を愛し、「爺、爺」と話しかけたため、この茶屋は「爺々が茶屋」と呼ばれるようになった。あるとき、家光は「いつもお前の世話になっている。何か欲しいものがあったら取らせるからいってみよ」との仰せ。彦四郎は恐縮しながら、自分の屋敷の周囲を1町ほど拝領したいむね申して、これをいただいた。
ここからは落語として創作された話である。
例によって遊猟の帰途、茶屋に寄った将軍は、空腹を感じて彦四郎に食事の用意を命じた。だが、草深い郊外の茶屋に、将軍の口にあうものがあろうはずはない。そのむねを申しあげたが「何でもよいから早く出せ」とのこと。やむをえず、ありあわせのさんまを焼いて差しあげたところ、山海の珍味にあきた将軍の口に、脂ののったさんまの味は、また格別だったのだろう。その日は、たいへんご満悦のようすで帰った。
それからしばらくして、殿中で将軍は、ふとさんまの美味であったことを思い出し、家来にさんまを所望した。当時さんまは、庶民の食べ物とされていたので家来は前例がないこと、たいへん困ったが、さっそく房州の網元から早船飛脚で取り寄せた。ところが料理法がわからない。気をきかせた御膳奉行は、さんまの頭をとり、小骨をとり、すっかり脂肪を抜いて差し出した。びっくりしたのは殿様。美しい姿もこわされ、それこそ味も素っ気もなくなったさんまに不興のようす。
「これを何と申す」
「は、さんまにございます」
「なに、さんまとな。してどこでとれたものじゃ」
「は、銚子沖にございます」
「なに銚子とな。銚子はいかん。さんまは目黒に限る」
この話が、落語「目黒のさんま」である。
さて、目黒のさんまの話はともかくとして、爺々が茶屋の子孫は、坂下の方に住んでおられた。目黒ニ丁目の島村家がそれで、同家は、代々彦四郎を襲名してきたが、やめたという。
島村家には、今なお当時の模様を伝える古文書―御成之節記録覚―や一軒茶屋の図が保存されている。そのなかから、将軍と彦四郎のほほえましいやりとりを紹介しよう。これは、元文3年4月13日猪狩りの折りに、茶屋場に立ち寄ったときのものである。
「藤の花は、咲くか咲かないか」
「少々、20房から30房ばかりですが咲きます」
「花は長いか短いか」
「野藤なので短こうございます」
「どのくらいの長さか」
「せいぜい7寸から8寸でございます」
「野藤ゆえ、そうであろう」
会話の調子が、前述のさんまのそれに似ているところがおもしろい。
そのほか、鷹狩りの折り、団子150串、田楽100串というような注文が出ていること、その代金が支払われていることなどが記録として残されている。
茶屋坂の今昔
茶屋坂は、昔はたいへん寂しいところだったらしく明治維新で世情が混乱のころには、茶屋場はたびたび泥棒に見舞われ、島村家は、ついに坂下の村の方に移ってくることになったという。今日では、茶屋場の跡を正確に知る由もないが、茶屋坂には、昔からきれいな清水がコンコンと湧いて樹木が茂っていた。
明治にはいって、山手線が通ると、目黒、恵比寿の中間ほどに位置する茶屋坂一帯は、工場立地の条件がそろい、海軍の火薬製造所が建設された。同工場は、あたりに住宅が建ち始める昭和の初めに移転したが、その後も海軍技術研究所などの施設が入った。
茶屋坂
やがて、今日のマンション時代を迎えることになるが、そうなると、このあたりは高台で展望がきくうえ目黒というイメージがマンションにぴったり合って、高層建物が建ち並ぶようになり、まちの景観を変えてしまった。
昔から湧いていた清水も、マンション建設のつち音が響き始めると、水脈が変わってか、パッタリ止まってしまったという。将軍も食べたという目黒のさんま。今では秋に催される「目黒のさんま」祭りで、その味を楽しむことができる。


ハギ
茶屋坂下で垂れ下がる見事なハギ(とうに見頃は過ぎていますが)を見て、ゴールの田道広場公園に到着しました。ストレッチをして、別行動だったショートコース組と合流し、茶屋坂にまた戻ってゆきます。


ガーデンプレイス
再び戻ってきたガーデンプレイスではイルミネーションの準備が進められていました。恒例のバカラシャンデリアの点灯式は11月2日。お鷹狩りウォークの前日です。
お鷹狩りウォーク当日も、ここで祝杯をあげられるよう頑張って成功に導きたいと思っています。
すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。
まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。
sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。
すこやか歩こう会活動スケジュール

日比谷公園松本楼
日比谷公園開店当初から続く老舗の洋食店。沖縄返還協定反対デモでの焼失など、日比谷公園の歴史そのものといっても過言ではないでしょう。Wikipediaから10円カレーの項目を引用してみましょう。
10円カレー
1971年の2度目の焼失では、警備員1人が犠牲になるなど被害も大きかった。歴史あるレストランが焼失したこの知らせに全国から再興の願いが集まり、3代目松本楼がオープンできた。これに感謝の意を示す記念行事として、松本楼は「10円カレー」セールを始めた。通常は880円(2015年時点)のハイカラビーフカレーが、1973年以来毎年(1988年を除く)9月25日に限り、先着1500名に限り10円で振る舞われ、現在も毎年この日には大勢の来客があり、度々ニュースでも取り上げられている。10円を受け取るのは「無料ではお客様としてもてなすことにならない」という趣旨であり、代金以外に寄付金を置いていく人が多い。カレーの売上や寄付金は交通遺児育英会や日本ユニセフ協会などに渡され、1995年には阪神淡路大震災の義援金として贈られた。「10円カレー」は秋の季語にもなっている。

雲形池
紅葉の雲形池もきれいですが、冬に鶴の噴水にツララが出来る頃が一番の見頃でしょう。お鷹狩り本番の時にはもう少し紅葉が進んでいることでしょう。

慈恵医大西新橋キャンパス
慈恵医大の略歴をWikipediaから引用します。
東京慈恵会医科大学の起源は、高木兼寛によって1881年(明治14年)5月1日に創立された医術開業試験受験予備校(乙種医学校)の「成医会講習所」である。高木は1875年(明治8年)から5年間、海軍生徒として英国セント・トーマス病院医学校(現:ロンドン大学群キングス・カレッジ・ロンドン医学部)に学び、このように権威のある医学校を日本につくりたいと思っていた。高木は帰国後、廃止された慶應義塾医学所に関わっていた松山棟庵とともに1881年(明治14年)1月、「成医会」なる研究団体を設立し、次いで同5月にこの成医会講習所を設立している。
その後、高木は戸塚文海とともに、1882年(明治15年)、有志共立東京病院なる慈善病院を発足させている。この病院の設立趣意には「貧乏であるために治療の時期を失したり、手を施すことなく、いたずらに苦しみにさらされている者を救うこと」にあるとしている。このような趣意も、高木が英国留学中に受けた人道主義や博愛主義の強い影響による。同病院の資金は有志の拠金によるものであり、有志共立という名はそのためであった。病院総長としては有栖川威仁親王を戴き、また大日本帝国海軍軍医団の強い支援があった。
有志共立東京病院は、こうした慈善病院のほかに医学教育の場としても重要な役割を果たし、成医会講習所や海軍軍医学校の実習病院の役割を担った。これも、英国で経験した慈善病院と医学校の関係を東京に実現しようとしたものである。1887年(明治20年)、同病院は皇后を総裁に迎え、その名も東京慈恵医院と改め、経費は主に皇室資金によることになった。成医会講習所も成医学校に、次いで東京慈恵医院医学校に改称され、同病院構内(当時は東京市芝区愛宕町二丁目、現:港区西新橋三丁目)に移転した。
有志共立東京病院時代の特筆すべき事業の一つに看護婦教育所の設立がある。英国留学時代、セント・トーマス病院に付設されていたナイチンゲール看護学校を目の当たりにした高木は、日本の近代看護教育の導入にも極めて積極的であった。彼は1884年(明治17年)10月、米国女性宣教師のリードを招き看護婦教育を実践した。これが日本での近代看護教育の始まりである。第一回生はわずか5名であったが、総裁皇后の臨席を得て卒業式が行われた。現在の慈恵看護専門学校及び医学部看護学科、大学院医学研究科看護学専攻修士課程はこの流れを汲むものである。
1907年(明治40年)、有栖川宮威仁親王妃慰子を総裁とする社団法人東京慈恵会が設立され、東京慈恵医院の経済的支援をすることになったので、東京慈恵医院は東京慈恵会医院と改称された。また既に医学専門学校に昇格していた東京慈恵医院医学専門学校は、1908年(明治41年)に東京慈恵会医院医学専門学校と改められた。
1921年(大正10年)、大学令の公布を機会に東京慈恵会医院医学専門学校は東京慈恵会医科大学に昇格した。その時、高木家私有の東京病院が大学に寄付されたため、医科大学として附属病院を持つことになった。1952年(昭和27年)に学制改革による新制大学となり、1956年(昭和31年)に大学院医学研究科博士課程、1992年(平成4年)に医学看護学科、2009年(平成21年)に看護学専攻修士課程が設置された。

有章院霊廟 二天門
今回のお鷹狩りではショートコース、ロングコースともに御成門、二天門の前を通ります。二天門は改修されたばかりで今回のコースのハイライトの一つです。

プリンス芝公園からの東京タワー
増上寺の三解脱門、台徳院霊廟惣門の前を通過し、港区立芝公園で平和の灯を見て、芝丸山古墳の脇を通りプリンス芝公園に出ます。増上寺三門は江戸で一番高い展望台として人気でした。その後ろにそびえる東京タワーはいまでは日本一の座をスカイツリーに明け渡しましたが、人気の展望台です。東京タワーはメインデッキの改修が終わり大人料金が900円から1200円へ改訂されましたが、学校団体だと中学生が400円(スカイツリーは950円)、高校生が500円(同1100円)とリーズナブルです。
写真にありませんが三解脱門も戦災を逃れ重要文化財となっています。この項目をWikipediaから引用します。
三解脱門(さんげだつもん、重要文化財) - 戦災を免れた建物の1つで、元和8年(1622年)建立の二重門(重層で、各層に屋根が付く門)。この門をくぐると、三毒(3つの煩悩、即ち貪、瞋、癡)から解脱できるとされる。内部には釈迦三尊像と十六羅漢像が安置されている。

春日神社の鹿
桜田通り慶応大学の隣に春日神社があり、社務所に鹿の像がありました。総本社は奈良の春日大社で全国で千余りの春日神社があります。多くは近畿地方にありますが、Wikipediaによると都内に四か所となっていて目黒区の春日神社は表記がありませんでした。Wikipediaの「三田春日神社」の項目から一部を抜粋してみましょう。
由緒
958年(天徳2年)、武蔵国国司の藤原正房が任国の際、春日大社の第三殿に祀る天児屋根命の御神霊を目黒区三田に勧請。天文年間(1533-1555)当地へ遷座した。旧社格は村社。
備考
最初に鎮座した目黒区三田には1934年(昭和9年)跡地に目黒三田春日神社が再興され、1947年(昭和22年)より当社の兼務社となっている。
文京区に春日神社はなく、春日の字名は春日局の拝領地に由来しています。

高輪皇族邸
台風15号でなぎ倒された木はすでに片付けられて、金網に傷跡が見えます。

旧国立公衆衛生院
ゆかしの杜でトイレと場所をお借りし、15分の休憩を予定します。

ススキとサッポロビール本社

茶屋坂と爺が茶屋
目黒区ページから引用します。
目黒の坂 茶屋坂
更新日:2014年2月3日
「目黒の坂」は、「月刊めぐろ」1972年3月号から1984年2月号の掲載記事を再構成し編集したものです。
目黒のさんま
江戸の初め、田道橋を渡り三田方面に通ずる坂上の眺望のよいところに、1軒の茶屋があった。徳川3代将軍家光は、目黒筋遊猟の帰りにしばしばこの茶屋に寄って休息をとっていた。家光は、茶屋の主人彦四郎の素朴な人柄を愛し、「爺、爺」と話しかけたため、この茶屋は「爺々が茶屋」と呼ばれるようになった。あるとき、家光は「いつもお前の世話になっている。何か欲しいものがあったら取らせるからいってみよ」との仰せ。彦四郎は恐縮しながら、自分の屋敷の周囲を1町ほど拝領したいむね申して、これをいただいた。
ここからは落語として創作された話である。
例によって遊猟の帰途、茶屋に寄った将軍は、空腹を感じて彦四郎に食事の用意を命じた。だが、草深い郊外の茶屋に、将軍の口にあうものがあろうはずはない。そのむねを申しあげたが「何でもよいから早く出せ」とのこと。やむをえず、ありあわせのさんまを焼いて差しあげたところ、山海の珍味にあきた将軍の口に、脂ののったさんまの味は、また格別だったのだろう。その日は、たいへんご満悦のようすで帰った。
それからしばらくして、殿中で将軍は、ふとさんまの美味であったことを思い出し、家来にさんまを所望した。当時さんまは、庶民の食べ物とされていたので家来は前例がないこと、たいへん困ったが、さっそく房州の網元から早船飛脚で取り寄せた。ところが料理法がわからない。気をきかせた御膳奉行は、さんまの頭をとり、小骨をとり、すっかり脂肪を抜いて差し出した。びっくりしたのは殿様。美しい姿もこわされ、それこそ味も素っ気もなくなったさんまに不興のようす。
「これを何と申す」
「は、さんまにございます」
「なに、さんまとな。してどこでとれたものじゃ」
「は、銚子沖にございます」
「なに銚子とな。銚子はいかん。さんまは目黒に限る」
この話が、落語「目黒のさんま」である。
さて、目黒のさんまの話はともかくとして、爺々が茶屋の子孫は、坂下の方に住んでおられた。目黒ニ丁目の島村家がそれで、同家は、代々彦四郎を襲名してきたが、やめたという。
島村家には、今なお当時の模様を伝える古文書―御成之節記録覚―や一軒茶屋の図が保存されている。そのなかから、将軍と彦四郎のほほえましいやりとりを紹介しよう。これは、元文3年4月13日猪狩りの折りに、茶屋場に立ち寄ったときのものである。
「藤の花は、咲くか咲かないか」
「少々、20房から30房ばかりですが咲きます」
「花は長いか短いか」
「野藤なので短こうございます」
「どのくらいの長さか」
「せいぜい7寸から8寸でございます」
「野藤ゆえ、そうであろう」
会話の調子が、前述のさんまのそれに似ているところがおもしろい。
そのほか、鷹狩りの折り、団子150串、田楽100串というような注文が出ていること、その代金が支払われていることなどが記録として残されている。
茶屋坂の今昔
茶屋坂は、昔はたいへん寂しいところだったらしく明治維新で世情が混乱のころには、茶屋場はたびたび泥棒に見舞われ、島村家は、ついに坂下の村の方に移ってくることになったという。今日では、茶屋場の跡を正確に知る由もないが、茶屋坂には、昔からきれいな清水がコンコンと湧いて樹木が茂っていた。
明治にはいって、山手線が通ると、目黒、恵比寿の中間ほどに位置する茶屋坂一帯は、工場立地の条件がそろい、海軍の火薬製造所が建設された。同工場は、あたりに住宅が建ち始める昭和の初めに移転したが、その後も海軍技術研究所などの施設が入った。
茶屋坂
やがて、今日のマンション時代を迎えることになるが、そうなると、このあたりは高台で展望がきくうえ目黒というイメージがマンションにぴったり合って、高層建物が建ち並ぶようになり、まちの景観を変えてしまった。
昔から湧いていた清水も、マンション建設のつち音が響き始めると、水脈が変わってか、パッタリ止まってしまったという。将軍も食べたという目黒のさんま。今では秋に催される「目黒のさんま」祭りで、その味を楽しむことができる。


ハギ
茶屋坂下で垂れ下がる見事なハギ(とうに見頃は過ぎていますが)を見て、ゴールの田道広場公園に到着しました。ストレッチをして、別行動だったショートコース組と合流し、茶屋坂にまた戻ってゆきます。


ガーデンプレイス
再び戻ってきたガーデンプレイスではイルミネーションの準備が進められていました。恒例のバカラシャンデリアの点灯式は11月2日。お鷹狩りウォークの前日です。
お鷹狩りウォーク当日も、ここで祝杯をあげられるよう頑張って成功に導きたいと思っています。
すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。
まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。
sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。
すこやか歩こう会活動スケジュール