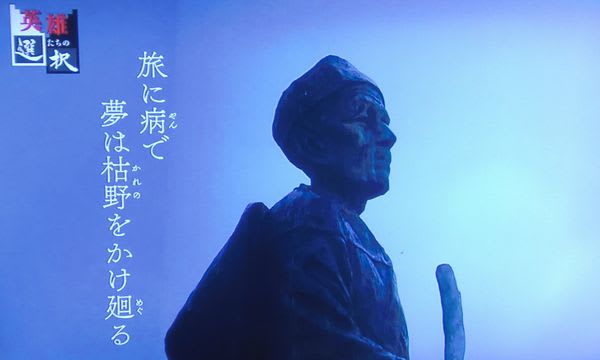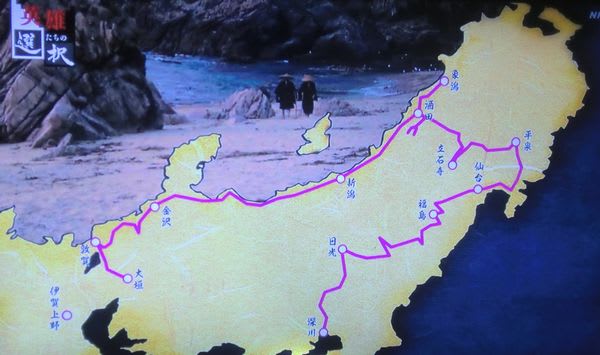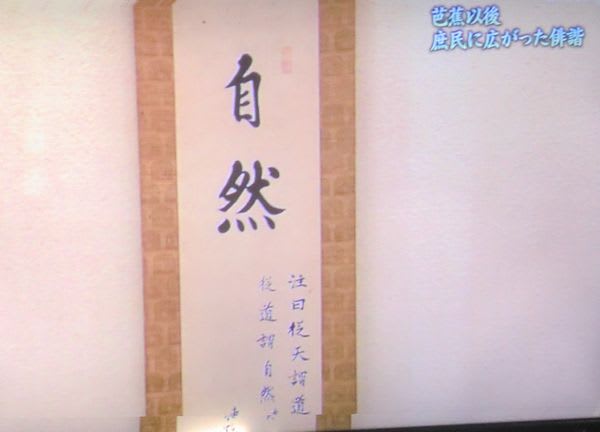🌸『純粋理性批判』7(生きることを考える)
☆私自身、すぐ忘れますが書いている時
*間違かも知れませんが、それなりに少し理解出来てます?
☆今につながる世界観を築き上げた歴史的1冊
☆思考のフィールドを明確に規定
☆矛盾する二律背反に耐える力を学ぶ
☆矛盾する二律背反に耐える力を学ぶ
☆著者、イマヌエル・カント
⛳人間が世界をどのように認識できるかを規定した
☆従前までの思想対立を批判的に総合する
*のちの哲学、政治・文化にまで及ぶ世界観を作りあげた
*「カント以前」「カント以後」という言葉が使われる
☆宗教改革の混乱の時代を経て、欧州では2つの認識論が発展
☆フランスのデカルトを祖とする大陸合理論
*従来までのあらゆる学問を徹底的に疑う
*疑いようのない原理を見出し、そこを出発点として思考を重ねる
*正しく世界認識ができるというもの
☆大陸合理論に異を唱えるイギリスで興った経験論
*正しく世界認識ができるというもの
☆大陸合理論に異を唱えるイギリスで興った経験論
*科学技術の発展をベースに理性ヘの過度の信頼を基に
*人間が経験もしていない原理を仮定してもそれすら疑わしい
*事実や経験を積み重ねてる
*共通事項を見出していく方が科学的である
⛳ドイツのカントは、経験論的な考え方を引き継ぐ
☆人間の理性が認識しうる限界を、精密に分析しようとした
*人間の理性によつて認識しうる世界のみ
*学問的認識の対象とすべきであるとした
☆思考のフィールドを明確に規定した点
*後世へのカントの影響は絶大だった
☆カントの思考の前提は、ニュートンカ学のパラダイムに立つ
☆カントの思考の前提は、ニュートンカ学のパラダイムに立つ
*時間と空間を、人間の先天的な判断形式としている
*その後、アインシュタインの字宙論によつて覆されてしまったが
⛳現実の国際政治の場で
☆国連のメカニズム
*ニュートンのカ学的な勢力均衡がメカニズム
*カント的世界観に立脚している
☆カントの哲学は、合理論と経験論を見事に昇華した
*互いに矛盾し対立するアンチノミー(二律背反)
*耐える力に満ちている
⛳『純粋理性批判』が問題にしていること
☆「世界には果てが在るのか」「人間は死んだらどうなるのか」
*答えは出そうにないけども、疑問に思わないのも変だ
☆宗教や科学の存在がそれを雄弁に物語っている
*「自分では答えられないけれど、神様だったらきっとご存じだ」
*「偉い物理学者だったら知っているはずだ」ということ
*その言葉を信じればもうそれ以上考えないで済むというわけ
☆私たちは経験により納得したことや確信したこと
*一般的な命題に仕立て上げ、その普遍性を主張する
☆そうしたやり方ではこの問いに答えることはできない
*この種の認識は、感覚的な世界を超えたもの
*経験が導きの糸を示すことも、正すこともできない
⛳カント以前の形而上学は、問いに答えようとしてきた
☆純粋理性にとって避けられない課題(神、自由、不死)
☆この様な課題を究極の目的として、解決を目指す学を形而上学と呼ぶ
*この学の取る方法は、最初は独断論的である
☆形而上学には
*理性によってこれらに答えることができという自負があった
⛳カントによれば、神、自由、不死
☆こういう問いに対しては、経験によって答えることができない
*自ずから答えることができると形而上学は考えた
*本当に理性は、形而上学的な問いに答える力があるのだろうか
*本当に理性は、形而上学的な問いに答える力があるのだろうか
*カントはこのことが、長い歴史の中で見過ごされてきたと考えた
☆知性はこのようなアプリオリな認識どの様に獲得した?
*アプリオリ(経験的認識に先立つ先天的、自明的な認識や概念 )
*アプリオリな認識の範囲、妥当性、価値があるのか?
☆私たちが経験という試金石で、その真偽を確かめることができない
*何らかの形而上学的な概念を持つことは事実でも
*それを信頼し何らかの形而上学を打ち立てようとすべきではない
*否定できないから真理であるというのは暴論
☆形而上学的な問いに「答え」が互いに矛盾し、闘争状態にあるのは
*私たちにそれに答える力がないからではないのか?
☆カントは、形而上学的な概念の起源を明らかにした
*理性は何をどこまで認識することができるのか?
*問題意識のもと、理性の限界について探究していく
*その探究を記したのが、『純粋理性批判』にほかならない
☆課題に従来の形而上学は気づかなかったために失敗した
*理性が自分自身の力のみで知識を拡張させることが必要である
(敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
⛳出典、『世界の古典』
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
⛳出典、『世界の古典』


『純粋理性批判』7(生きることを考える)
(ネットより画像引用)