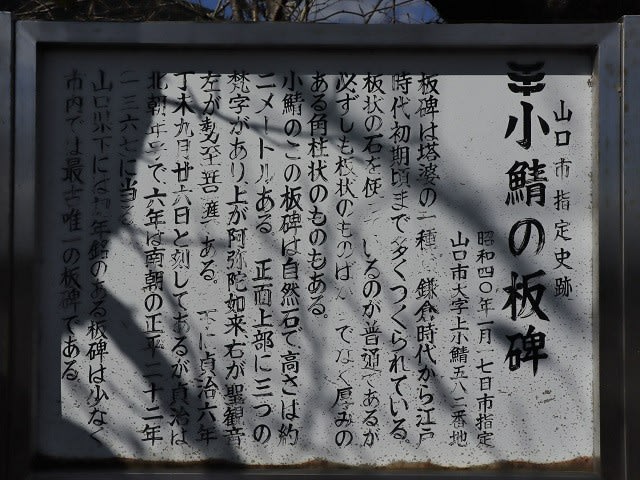ゲンノショウコという名は、煎じ薬として昔から聞いています。
もう半世紀とひと昔前になりますが、(笑) 歩いている時、畑の側に可愛い花が咲いていました。
やっと、畑を作っておられる方に出会った時、「このお花は何ですか?」と聞いてみました。
「ゲンノショウコですよ!煎じて飲むと苦い!苦い!薬です。」と言われ、お腹を壊した時に飲むのだと教えて
もらったことがあります。
まだ、二十歳頃のことです。あれから、名前は憶えていても、どんな花だったかはすっかり忘れていました。
ブログを始め、ゲンノショウコのお花を見るたびにこんなキレイなお花をどうして忘れているのかが不思議でした。
いつも、実物が見てみたいと、画像に出会う度に思っていました。
22日の日曜日に山口市の郊外に銀杏の黄葉が見られるかと出かけてみました。
銀杏はまだ青く駐車場もなく、引き返すため、横道に入った時のことです。
きれいなピンクの小さな花がたくさん咲いていました。
「これは何?」車を降り近づくとゲンノショウコではありませんか( ^ω^)・・・
こんなに小さいの?……1.1・2cmしかありません。
まるで、ゲンノショウコを育てておられるように、白花もたくさんあります。
もう、花期も終わりに近づいたと見え、種や実の燭台も沢山見えますね。
出かけるといいことがありますね。ラッキーな日でした。
学名:Geranium thunbergii 科名:フウロソウ 属名:フウロソウの多年草
別名:フウロソウ・ミコシグサ・イシャイラズ・タチマチグサ 中国植物名:童氏老鸛草(どうしろうかんそう)
花期:7~10月ごろ




カタバミと、比べると大きさが分かると思います。


東日本では白花が多く、西日本では淡紅、日本海側で紅色の花が多く分布しているそうですが・・・
種もたくさん、ありますね。見事だったでしょうね。もう、花の終わりに近づいています。

燭台は残っていますが、実は落ちています。

すっからかんです。

コセンダングサもありました。ピンボケですね。(-_-;)



チカラシバ


ヒヨドリバナとフジバカマの区別がつきませんでした。感じではヒゲの長さから、ヒヨドリバナと・・・

イヌタデでも沢山!キレイでした。

今年は遅く・・・あきらめていましたが、やっと今日、アサギマダラが2匹、山口県防府市に来ました。
お昼ごろ気が付き撮影し、脳クリニックに・・・

帰ると4時過ぎでしたが、まだ2匹がいました。5時前にサヨナラでした。ラッキーなことが続き、心はブギウギ💕