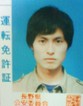2020年、2回目の映画は、1/5(日)に、去年見逃していた「ぼくらの7日間戦争」を観てきました。
予告編はこんな感じです。
もともと、1985年に宗田理さんの「ぼくらシリーズ」の記念すべき一作目である原作小説「ぼくらの七日間戦争」が書かれており、それが1988年に「ぼくらの七日間戦争」として映画化されているのですが、本作は1998年の映画「ぼくらの七日間戦争」の30年後を舞台に現代の若者達を主人公に描いたアニメ映画です。
僕は、原作小説も、元の映画も大好きなので、本作ももちろん楽しみにしていました。
一応、本作の感想を語る前に、1988年の「ぼくらの七日間戦争」について軽く話しておきたいのですが、学校の管理教育に抵抗するために、中学生たちが工場に立て籠もって大人達と七日間戦争という名の喧嘩を売るという、何歳になっても「あの頃の気持ち」を思い出させてくれるような本当に最高の青春映画です。
友情も恋愛も冒険も詰まった青春映画の金字塔であり、当時まだ15歳だった宮沢りえさんのデビュー作であることもあまりにも有名ですが、個人的に一番好きなシーンは喧嘩した安永が雨の中を去っていこうとした時、びしょぬれになりながらガリ勉の中尾が「たった一人になっても僕はここに残る!」とあまりにもカッコいい台詞を叫ぶところだったりします。
要するに、こういう、大人に喧嘩を売るガキってやつが僕は大好きで、大人になっても、それこそ「30年後の映画」が作られたように僕自身も30代になっても、それでもずっと、こういう気持ちは自分の中にずっとあるし、こういうガキどもが大好きだし、憧れている自分もいます。
そんな自分は、物凄く本作を楽しみにしていた反面、面白さのハードルが物凄く上がってしまっていたなとも思ったんですよね。
そういう点では、本作は前半に大人たちの理不尽さがあまり出てこないから、主人公たちの反抗の動機(好きな女の子の誕生日までの一週間、工場に籠城するというやつ)に若干、感情移入しづらかったとか、他にもいくつかちょっと強引な展開が多かったなとか、そもそもアニメの絵がきれいすぎて泥臭さが物足りないとか、確かに思うところはいくつかありました。
とは言え、SNSを駆使した戦いとか、LGBT的な多様性とか、色んな現代的なテーマ盛り込んで頑張っている脚本には驚かされたし、恋も友情も涙も笑いもアクションも青春映画の全部乗せみたいなストーリーは単純に楽しかったし、実写では難しいだろうけどアニメ映画だからこそ美しく描けたクライマックスはぐっときたわけで、何だかんだ感動してちょっと泣いたりもしたので、なんていうか結果的には100点満点でした。
ところで、僕は「ぼくらの七日間戦争」の登場人物たちと同じ中学生の時に元の小説や映画に出会ったから物凄くハマったし今でも大好きなんだけど、こういう大人に反抗する子供達の作品って、今の若い子達は、楽しんでくれるんでしょうかね。
そもそも僕は1988年の「ぼくらの七日間戦争」や宗田理さんの原作小説が好きだから、最後に出てくる大人になったひとみの声優が宮沢りえさんとか、よく見ると免許証の名前が菊池ひとみになっていたり(リーダーの菊池英治くんと結婚したのね)、そこで流れ出すT.M.Networkの名曲「Seven Days War」とか、なんならひとみの車が宗田ナンバーという小ネタなんかにもぐっときちゃうんですけど、知らない世代には何のこっちゃじゃないんでしょうかね…
そもそもやっぱり、1988年の「ぼくらの七日間戦争」があまりに角川青春映画のレジェンド映画だから、アニメ化ってなるとどうしても僕みたいな元の映画と比べる勢が出て来ちゃうのは仕方ないわけで、同時に今の若い世代にも面白さを伝える必要もあるわけで、そう考えるとこの映画の作り手たちのSeven Days Warだったのかも知れませんね…
って、世界を七日間で作った聖書の神じゃないんだから、7日間戦争どころか果てしない時間と労力をかけてこの映画は作られているわけで、映画って結局、時代と戦って作られるものなのかもしれないなあ…なんて考えると、そのテーマが本作とリンクしているように思えたりもして、この映画の登場人物たち同様に、この映画の作り手達や、もっと言えば「ぼくらの7日間戦争」という本作自体を応援したくなってしまうような、そんな映画でした。
















![【お知らせ】パレスチナ連帯スタンディング@新潟[4/12(土) 12:30~13:30、シネ・ウインド前]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3c/7d/2200c40918b9bb7adb71125aea8de3d3.jpg)
![【お知らせ】パレスチナ連帯スタンディング@新潟[4/12(土) 12:30~13:30、シネ・ウインド前]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/72/51/7c8136aa68b16a4695e04debee5b3e3f.jpg)