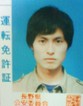5/27(木)、新潟県立近代美術館の「久保田成子展」にやっと行けました。
久保田成子さんは、新潟市西蒲区(旧巻町)出身の芸術家で、若手の頃はニューヨークで活動していたそうです。
主に映像作品を作る芸術家だったので、映像作品がたくさん展示されていたのですが、1時間や2時間では見切れないほど膨大な内容でした(なので、実は5/25(火)にも行ったけど、見きれなくて5/27(木)にまた行った)。
展示の前半では、若手時代に作った映像作品が展示されていたのですが、日本で行った観客参加型の実験企画のような記録映像、ニューヨークの町中で色々な芸術家がパフォーマンスしている様子の記録映像、海外を訪問して現地の人々の生活を記録した映像などなど、映像から久保田成子さんの溢れ出す行動力と創造力を感じ、やっぱり芸術家は積極的に行動しないとダメだなと思わされました。
映像作品も決してワンパターンではなく、作品ごとに久保田成子さんが本気でやりたいと思ったことを記録に残している感じがして、そういう、自分の生きた証として作品を残していくスタイルは、僕もそういう部分があるので参考にしたいと思いました。


やがて、久保田成子さんは、映像作品を映したモニターを立体作品と組み合わせた「ヴィデオ彫刻」というものを作るようになり、後半はその展示が中心でした。

回転する車輪の上で映像を流す作品。

不思議な形の立体作品の様々な部分で映像が流れ、作品と作品の間を歩きながら見るという作品。

天井から吊るされたモニターから床に向かって映像が流れ、それが舟のような作品(中で水が流れる)に映るという作品。

天井から吊るされた銀色の球体に取り付けられたモニターから映像が流れ、それが床の歪んだ鏡に映るという作品。

壁に取り付けられたモニターの前を水が流れ、それが床の割れた鏡とその上に流れる水に映るという作品。

ロボットのような人形にモニターが取り付けられ、映像を映しながら回転するという作品。

そして、最後には、丸い山みたいな場所の様々なモニターから映像が流れるという作品。
ちょっと見たことない感じの作品の数々を興味深く見ました。
僕なりの解釈なんですけど、作品の内容と同じくらい、作品そのものの材質や実在感も意味がある、ということを表現したんじゃないかと思うんですよ。
例えば絵画でも、描かれているものだけならデジタル化された映像でも問題ないけど、実際に額装して会場に飾ると、例えば絵の具の質感とか、その会場の雰囲気と合っているかとか、そういう作品の物理的な存在感も、作品の印象に影響を与えるじゃないですか。
それと同じように、久保田成子さんの映像作品も、映像の内容そのものと同じくらい、その映像を流すモニターの存在感を強調して展示したっていいじゃないか、という意図を感じたんですよね。
考えてみれば、映像作品って、ネットもなく動画サイトもないような時代には、やっぱりそれを映すモニターやスクリーンがないと成立しないものなので、やはり内容だけではなく、その映像を映す環境などについて考える必要があったのかもしれません。
いや、これは僕の勝手な解釈で、実際に久保田成子さんの意図がどうだったのかは分かりませんが、純粋に作品の内容そのものだけでなく、それをどう人前で提示するかも大事だよ、という気持ちを受け取りました。