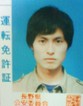9/3(火)、午前中に地域活動支援センターで「ネバーエンディング・ストーリー」を観てきました。
地域活動支援センターでは時々こうして映画鑑賞会もあり、頑張って観てきました。
「ネバーエンディング・ストーリー」は1985年、僕が生まれる一年前に公開されたファンタジーのヒット作。
ミヒャエル・エンデの原作小説「はてしない物語」は読んでいましたが、映画は初めてでした。
物語は、いじめられっこのバスチアンが古本屋で「ネバーエンディング・ストーリー」という本を手にし、学校をサボってその本を読みふける。
そこに書かれていたのは、ファンタージェンという世界が崩壊の危機にあり、女王・幼ごころの君の命を受けて、少年アトレーユが世界を救う冒険をするファンタジーアドベンチャー。
本の中の冒険と並行して、時折その本を読むバスチアンの物語も描かれ、やがて本を読む自分自身がファンタージェンの救世主であると知ったバスチアンは、本の中に飛び込みファンタージェンを新しく創造するための冒険をする。
だからこそ、まるで本を読む自分も本の中に入って冒険するような気持ちになれる作品なので、この物語を一番楽しむにはやはり本だと思いいます。
しかもこの本自体がとても厚くて、全部を完全に映画化するには何時間かかるんだよ…という壮大な原作をどうやって1時間半の映画にまとめたのか本当に謎だったんですよ。
で、実際に観てみたところ、原作の前半を映画化したものなんですね。
バスチアンが本の世界に飛び込む前半のラストをクライマックスに持ってくる構成は悪くなかったです。
ちなみに、原作の後半は映画化しないのかな…と思ったら、「ネバーエンディング・ストーリー 第2章」もあるそうなので、いつか観てみたいです。
そして、ファンタジーの不思議な生き物たちが暮らす世界を、特殊造形や着ぐるみを多用したアナログ特撮と、今見るとちょっとレトロで懐かしい合成や特殊効果で描かれ、この手作りの温かさは、もしこれがCGのクリアの映像だったら出ないだろうと思いました。
幸いの竜ファルコン(原作ではフッフール)、岩食い巨人、カタツムリに乗った小人、コウモリに乗った夜魔、沼に暮らす巨大な亀・太古の媼モーラ、地霊小人の夫婦、神秘を守るスフィンクスなど、ファンタジーの生き物たちが本当に生きているように登場するのはワクワクしました。
特に、巨大な生き物や小さな生き物が、合成によって人間と一緒に存在しているように見える不思議な映像は、怪獣映画のような空想の世界が感じられました。
ただちょっと物足りなかったのは、冒頭でエルフェンバイン塔に集まるファンタージェンの不思議な生き物たちがちょっとしか登場しないところで、「スター・ウォーズ」のようにもっと彼らの出番が見たかったです。
ただ、映画化にあたり原作を改変するのは悪くないと思うのですが、どれだけ改変しても原作の肝となるメッセージだけは変えてはいけないと思うのです。
原作「はてしない物語」では、いじめられっ子の主人公は本の中で大活躍しますが、次第に現実を忘れ調子に乗ったために間違いを犯し、自分がピンチになってしまいます。
そして本の中でどんなに強い力を得ても現実世界に持っていけず、最後には元のいじめられっ子のカッコ悪い自分に戻り、それでも彼は本の中で成長し、その経験を現実に持ち帰り大人になっていく。
これは「ゲド戦記」にも通じるような教訓で、名作ファンタジーにはそういう人生の大切な教訓があります。
しかし映画「ネバーエンディング・ストーリー」のラストは、なんとバスチアンが竜のファルコンに乗って本の中から現実に飛び出し、いじめっ子に仕返しをする。
これは、そうやって調子に乗ったらいけないぞという原作のメッセージを完全に無視している上に、それをハッピーエンドとて描くのは絶対にダメだろ…
本の中に入ったバスチアンが竜に乗って空を駆け巡り、復活したファンタージェンの美しい世界が広がり、地上を見下ろすとずっと本を読みながら一緒に冒険してきたアトレーユが走っている…ここまではすごく感動的なのに、そのあとのオチが完全に蛇足。
そのままファンタージェンの空を飛び立っていって「冒険はまだまだ続く…」とかで終わればすごく良かったのに、本当に勿体ない。
実際、作者のミヒャエル・エンデはこの映画のラストに納得せずに裁判まで起こしていたそうです。
裁判では敗訴してしまったそうですが、その気持ち、俺は分かるぞ…
とはいえ、それでも僕がこの映画が嫌いになれないのは、リマールの歌う主題歌「The NeverEnding Story」が本当に名曲だからです。
聴くだけで、想像力の翼を広げて果てしない冒険の旅に出ようというワクワクした気持ちになります。
実際この曲は世界的に多くのミュージシャンにカバーされ、日本でも坂本美雨さんのカバーは本当に素晴らしいです。
しかし、当時この曲の日本語カバーを歌ったのが何故か羽賀研二で、ファンタジーと全然関係ない暴走族みたいな世界観の歌詞になっていたのは本当に謎…どうしてこうなった…