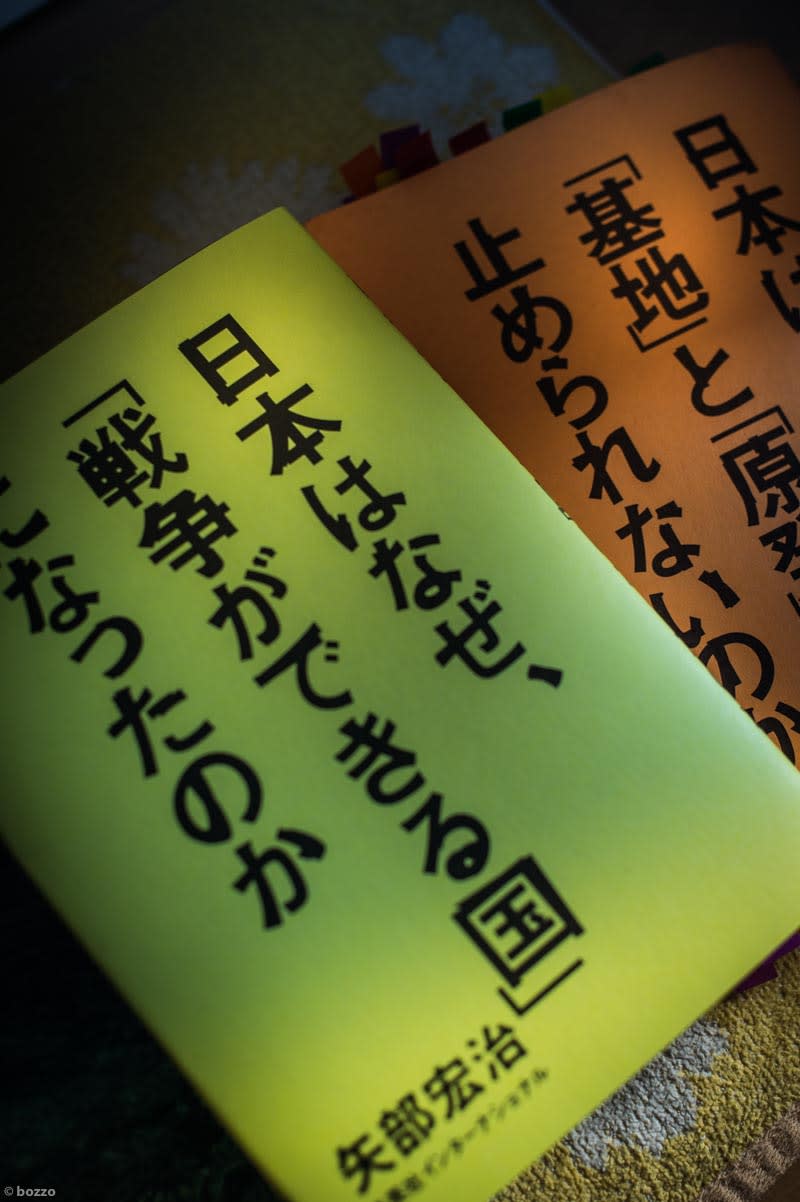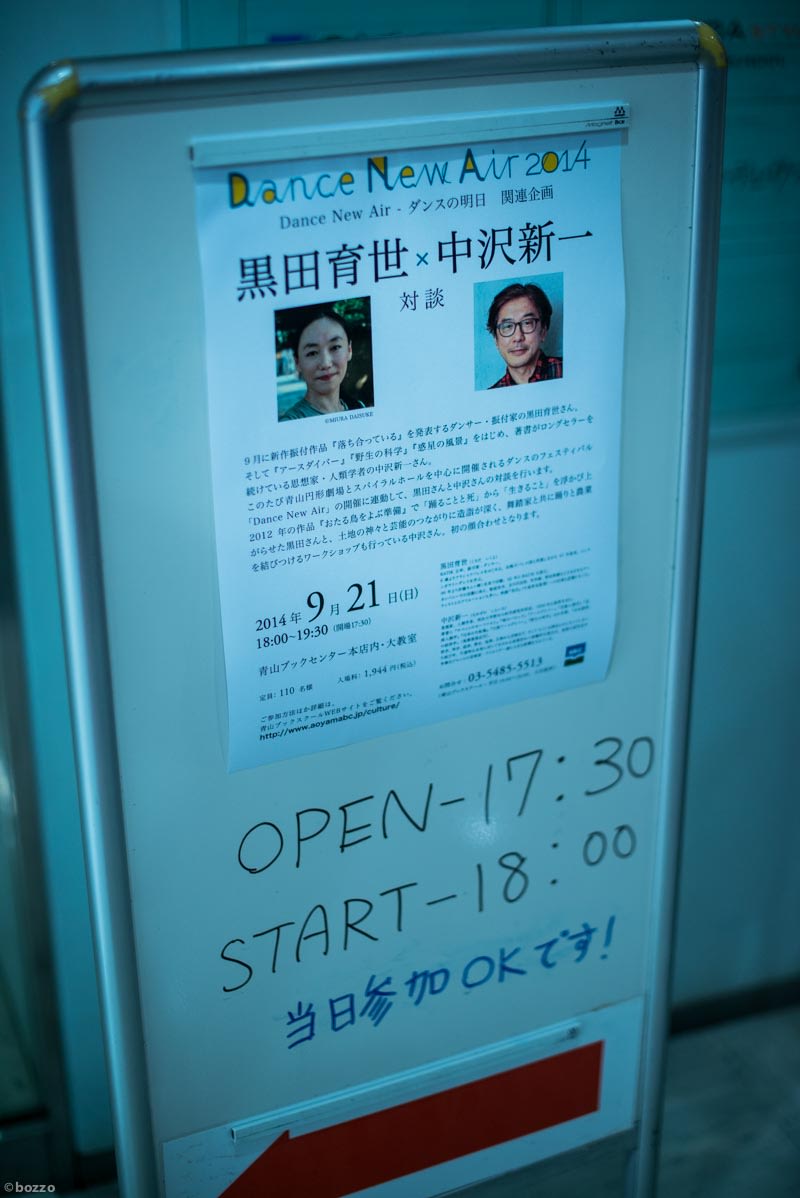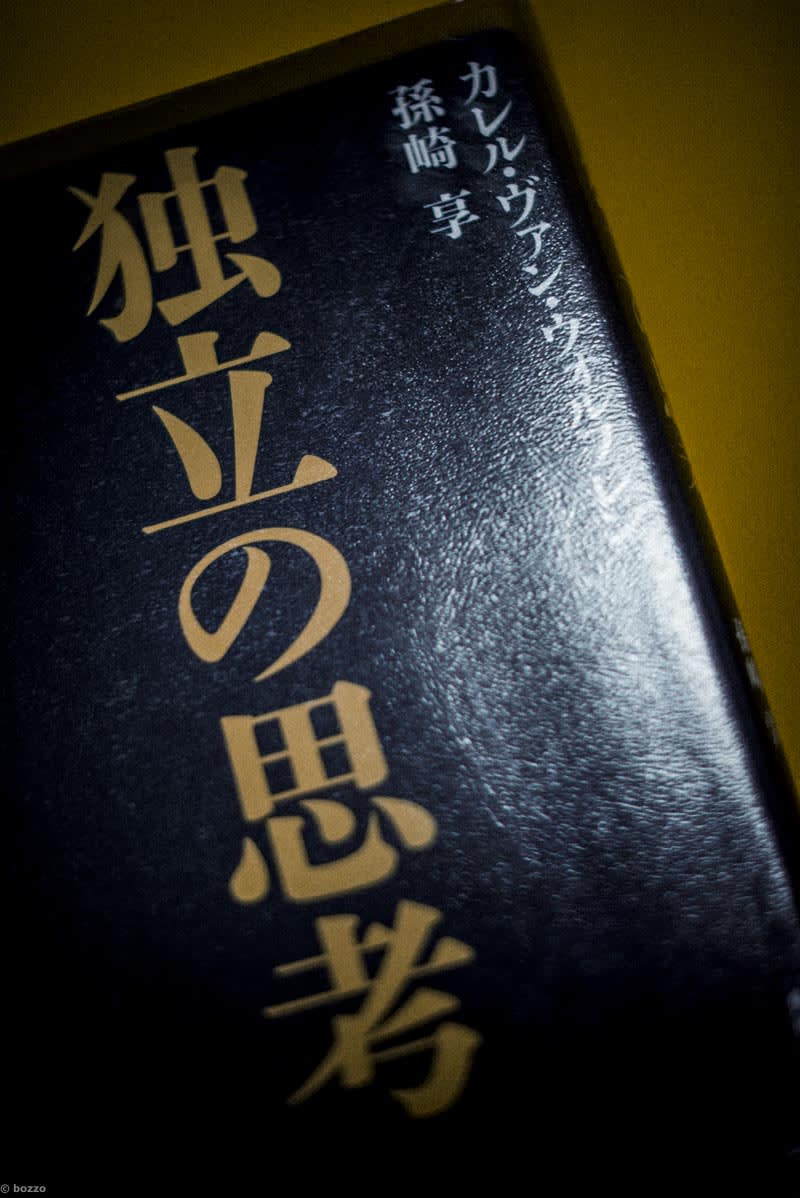死刑廃止を訴える埼玉弁護士会主催の森達也氏の講演に足を運ぶ。
オウム真理教13人の集団処刑から浮き彫りになるこの社会の病巣は何か?
非常に分かりやすく明確なヒントを頂いた。
1995年のオウム事件から始まった“恐怖と不安”を端緒とする【集団化】が
23年経ってより先鋭化しているのが現代社会だと。
【集団化】とはつまり、ポピュリズムであり、
少数排除=『みんな一緒でみんなイイ』の指向で、
そこからはみ出す奴は「敵」であり、
「敵」を設けることで「安心」を得る状態。
鰯のように群れることで己の弱さを隠蔽する行為である。
その同調圧力は外れることを忌み、
結果「こちらとあちら」の二分化を際立たせる。
雑駁としたものを排斥し、理解出来ないモノ、意味不明なモノを全否定する。
大衆がそのように身の回りから潔癖的に異物を排除するから、
メディアはその源である“恐怖と不安”をどんどんつまみ出し、
社会はより先鋭化していくのだと。
そこには「相手を慮る」という行為が徹底的に損なわれている。
元凶は【弱さ】。そこに尽きる。
血のつながりや家族に重心を置く傾向が日に日に顕著なのも、
異物へ思いを馳せることが出来ない顕れだろう。
想像力と創造力が決定的に損なわれた世の中。
免疫不全で、ますます無菌室状態。
その背景には「考える力」の衰退があるわぁ。
“恐怖と不安”におののき、排除していれば、考えなくて良いものねぇ。島国根性。
講演最後に森さんがウランバートルで見た羊の遊牧の話をして、
それがホントに言い得て感服したのだけど、
『羊の遊牧には必ず山羊を一頭混ぜる』って話。
山羊から「山」を取った羊は徹底的に家畜化された生き物なので、
集団を好み自発的な行動をしないそう。
反対に山羊は野性的なので、自由奔放に動き、野草を食むのだと。
山羊が動けば、羊が動く。だから羊の遊牧に山羊は欠かせない。
ああ、これって今の日本であり、世界だわなぁ。
野性の勘を失った島の民は、野性的思考を失ってるので、
羊のように付和雷同で、山羊のような強い者に惹かれてるの。
何事もひとりで引き受け、ひとりで思考し、ひとりで行動しないと、
ますます生きるのしんどくなるわ…と、暗澹とした講演でした。
#photobybozzo
オウム真理教13人の集団処刑から浮き彫りになるこの社会の病巣は何か?
非常に分かりやすく明確なヒントを頂いた。
1995年のオウム事件から始まった“恐怖と不安”を端緒とする【集団化】が
23年経ってより先鋭化しているのが現代社会だと。
【集団化】とはつまり、ポピュリズムであり、
少数排除=『みんな一緒でみんなイイ』の指向で、
そこからはみ出す奴は「敵」であり、
「敵」を設けることで「安心」を得る状態。
鰯のように群れることで己の弱さを隠蔽する行為である。
その同調圧力は外れることを忌み、
結果「こちらとあちら」の二分化を際立たせる。
雑駁としたものを排斥し、理解出来ないモノ、意味不明なモノを全否定する。
大衆がそのように身の回りから潔癖的に異物を排除するから、
メディアはその源である“恐怖と不安”をどんどんつまみ出し、
社会はより先鋭化していくのだと。
そこには「相手を慮る」という行為が徹底的に損なわれている。
元凶は【弱さ】。そこに尽きる。
血のつながりや家族に重心を置く傾向が日に日に顕著なのも、
異物へ思いを馳せることが出来ない顕れだろう。
想像力と創造力が決定的に損なわれた世の中。
免疫不全で、ますます無菌室状態。
その背景には「考える力」の衰退があるわぁ。
“恐怖と不安”におののき、排除していれば、考えなくて良いものねぇ。島国根性。
講演最後に森さんがウランバートルで見た羊の遊牧の話をして、
それがホントに言い得て感服したのだけど、
『羊の遊牧には必ず山羊を一頭混ぜる』って話。
山羊から「山」を取った羊は徹底的に家畜化された生き物なので、
集団を好み自発的な行動をしないそう。
反対に山羊は野性的なので、自由奔放に動き、野草を食むのだと。
山羊が動けば、羊が動く。だから羊の遊牧に山羊は欠かせない。
ああ、これって今の日本であり、世界だわなぁ。
野性の勘を失った島の民は、野性的思考を失ってるので、
羊のように付和雷同で、山羊のような強い者に惹かれてるの。
何事もひとりで引き受け、ひとりで思考し、ひとりで行動しないと、
ますます生きるのしんどくなるわ…と、暗澹とした講演でした。
#photobybozzo