ベルギー・日本戦は、悔しい試合でした。
率直にいって、直接の原因は本田やろ!!!とまず思いました。
最後のベルギーのカウンターがあまりにも素晴らしいので、仕方ないですね、みたいなことを言っている人が多数いるようだけど、あんなことやらしたらいかんという話が先でしょう。
どうしてこうなったのか。心理ゲームみたいだけど、本田はフリーキックのチャンスで、これで決めてやると思ったんだと思う。それ自体は何も問題ではない。そして、実際ホンダのフリーキックは素晴らしかった。しかしベルギーのキーパーも素晴らしいのでそれを防いだ。
それで得られたコーナー。これが問題。ここでも本田△の頭の中ではまだ、これで決めてやる、だったのでは? だから長いキックをしてそこで誰かがヘッドで合わせるという図が頭にあった。が、そのコーナーは、見事にキーパーにダイレクトキャッチされる。
この瞬間、いや正確には、キーパーのクルトワがキャッチの体制の時から既に前を見て選手に、前だ、と言ったのか、イケーと言ったのかしれないけど、そのものの1秒にも至らない間にベルギーの選手は全員意図を理解し走り出す。数的優位なのも多分全員見えたでしょう。きれいなカウンターが決まりました、と。
これはもう、これこそ最もやらせたくない展開。だから、本田△は、ショートコーナーでぐじゃぐじゃやればよかった、と思うわけだが、本人が決めてやる、と思うのも無理はないところもなくはない。いやまぁ少なくとも理解できなくはない。
しかし、そこでやっぱり誰かが、お前の考えてることは危険だ、と声をかけて、すると△が腹を立てるかもしれない、それでもいい。そこで意図を確認して時間を稼いだっていい、と私は考えるが、しかし、多分、ここではチーム全員が、ここで決める、という頭になっていたのかもしれない。一撃必勝みたいな発想はほとんど日本の文化レベルにまで至る思考だから余計そうなのかも。
つまり、守るより攻めに行ったとは一応言える。すると日本の人たちは、攻めて負けたんだから仕方がないわ、みたいな感じで受け取る。
さてしかし、ベルギーは日本と同格ではない。個人的な能力の高い選手がごろごろいるのがベルギー。であればまずは失点を防ぐための防御、阻止、撃退を第一に考えてもよかったんじゃないのかなと私は思う。
2点取ったところで、どうして全力で守りにいかなかったんだろうとかとも思う。そこからもう5人でも6人でも自陣に置いて守りながらチャンスを得る、つまり俗にいう引きこもり+カウンターという戦略もありでしょう。
そういうことを考えると、昨日のロシアのチェルチェソフ監督が戦略を徹底させて、引き込んで、走らせて、とにかく守り切らせたということが、そう簡単でないことがわかるというもの。
どのチームにも力のある人がいて、その人がカッコよく点を取りにいくというのが望ましい展開だと誰だって思うわけだが、それをさせないというのはそう簡単なことではない。
■ 文化的なものかも
そういうことを考えると、上で書いたようにこれはもう文化的な問題なのかもしれない。
守るというのは闘志、ファイティングスピリットがないと守れない。にもかかわらず、日本語環境では、守りに入るというのは一般によろしくないこととされていると思う。
守って、守って、というと全然積極的でないようなニュアンスがある。
しかし、昨日のロシア戦を、元デンマークのレジェンド的なキーパーのシューマイケル(父の方)は、ロシアチームは戦って、戦って、戦った、一秒もおろそかにしなかった云々という言い方で称賛していた。
そう、戦わないと守れない。当たり前のことなんだが、何かが違う文化がここにあるなと思う。
■ 中心でなくなってる
あともう一つ思ったのは、日本の中の評価系がおかしい。これは一体何?
例えば、こんな調子。
激闘見せた日本代表、英紙の採点は軒並み好評価に…乾貴士には「最も危険な男」
英紙の評価がなんだというんだって話。しばしば、イタリア、スペイン紙がこう書いてるああ書いてるという記事もよく出て来る。
だからなんだと押し切れる日本のサッカージャーナリズムが存在していないからこうなんでしょう。
さらには、こんなものまで来る。日本スゴイ運動の一環でしょうか。朝日までやるのかと唖然とするが。
「日本こわかった」「少しの運の差」歓喜のベルギー国内
https://www.asahi.com/articles/ASL7325RBL73UHBI007.html?ref=tw_asahi
終わって数時間もしないうちにこんな動画が複数あがってる。ヘイトは拒否したりできるけど、自己称賛系は批判対象にならないから野放し。
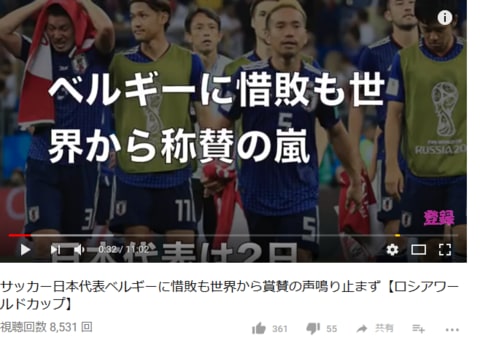
で、中身を見てもなんか適当な話しか載ってない(一応わざわざ流し見してみた)。
そりゃ別に日本を批判しているところはないし、きかれりゃ、頑張ったわねとは言うだろうが、基本的には、日本もいいチームでしたがいやぁベルギー強いですね、あのカウンター大したもんだわという記事がこの件に関しては主流だと思う。そりゃそうでしょ、普通に考えて。
これは別に日本をくさしているんじゃなくて、試合のハイライト的にはそうなるでしょ、という話なのだが、日本の中だけ異常。
私が思うに、Jリーグを作った時サッカー協会の人たちは、こんな日本の状況を期待していたわけではないと思う。
日本に良い選手を連れてきて、強いチーム作って、人々にもっとファンになってもらって、サッカー詳しくなってもらって、それを通して、東アジアで強いサッカーを育てようという意図だったんだと思う。
ところが気がつけば、ベルギーみたいに強いチームなら負けても仕方がない、までならともかく、世界から称賛されているとか、素晴らしいわ、感動したわといった類の報道にくるまれて、それでお話が終わりになるという事態が発生している。
これって一体何なの?
■ 妄想してみる
ふと思うに、欧州のサッカービジネスに食われてしまっている、コントロール奪われちゃったみたいな恰好なのかも。
選手に国際経験を積ませようというのは、日本国内のサッカーをもっと強くするためにあったはずなのだが、いつの間にか、欧州こそ頂点で自分たちのところはまだまだ、本場にはかなわないわ、所詮は育成リーグみたいな認識が滑り込んでいると思う。
自国にさえいればいいってもんではないが、イギリスの代表は確か100%自国リーグの選手、ロシアも90%ぐらいがそう。そして日本は50%弱、という数字が物語るものはあるでしょう。
ではなぜこんなことをしているのか。まぁビジネス界の需要は一つ確実にあったでしょうが、それだけでなく政治的理由もあったのでは?
つまり、日本は欧州の(または欧米の)仲間なのだというアイデンティティを持たせるための一環だったのではなかろうかと想像してみる。サブカル的に気分が結ぶついているだけで、実は怪しいものなのだが、その気にはなる。
これは、70年代の若者がアメリカやイギリスの音楽、映画がカッコいいとあこがれることで、朝鮮戦争、ベトナム戦争、そして日本の場合は基地そのもののせいで現実に存在していた反米(反欧米)意識が薄れたことの二番煎じかもしれない。
どうなるものやら。




























あそこで、延長になってもずたずたにやられる未来がまっていそうです。
だから、決めなくてはならなかったが決められなかった。
そう言う結末におもえます