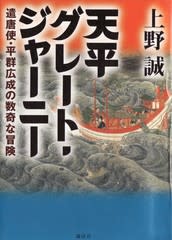 結果において壮大となってしまった旅の物語である。
結果において壮大となってしまった旅の物語である。
天平5年(733年)の遣唐使は数ある遣唐使のなかでも数奇な運命をたどったことで知られる。行きは東シナ海で嵐に遭遇したものの、四隻全てがなんとか蘇州に到着できた。しかし、全員が長安入りは叶わなかった。それでも玄宗皇帝に拝謁でき、多くの人材を招聘することにも成功、留学していた学生・僧ともども帰国の途についたが・・・。
帰国を目指した四隻のうち、第1船だけが種子島に漂着。第2船は流し戻されて帰国は延期。第4船にいたっては、その消息は今日まで杳として知れない。そして第3船。この船は南方の崑崙(現在のベトナム)にまで流され、150人いた乗組員は現地人の襲撃や風土病でほとんどが死亡、生き残ったのは4人だけだったと史書にある!という。その1人が、本書の主人公、遣唐使での役割が判官の平群広成である。
物語の骨格は史実に基づくも細部は作者の創作であるはずだが、全てかくあったと思わせる筆の運びである。各部各章の冒頭には、例えば次の様な文章で始まる2行が置かれる。「諸国の巨木、竊(ひそか)に伐られ、時に平群広成、私に多治比広成の邸を訪ふ」。
かくして、遣唐使の造船の為、近江などで密かに航海の船に適する木が選定され始め、後に大使に任命される多治比広成邸に、平群広成が”私も”と猟官に訪れる第1章の幕が開ける。
判官に任命され、第3船の”船長”となった広成の、漂流とも言うべき帰国ルートを概観して見よう。(地図は本文末に)
⇒が海路、→が陸路・水路である。
蘇州⇒⇒⇒崑崙→⇒欽州⇒⇒蘇州→楚州→洛陽→長安→落陽→登州⇒→鴨緑江→渤海王城→南海府吐号浦⇒出羽吹浦→平城京
蘇州を出発したのが天平6年(734年)10月23日、渤海国公使の大和国訪問一行と共に南海府吐号浦(現在の北朝鮮)を出港したのが天平11年(739年)7月11日。その年の10月27日に漸く平城京に到着。蘇州を出てから5年の、出国から6年もの歳月が流れていた。
遣唐使の一行の航海が並大抵でない事は知っていた。凄まじい暴風雨、船室の狭さ、食事・用便など細部の描写でその困難さを具体的に知ることとなる。外国に赴けば言語や風習の壁がある。ましてや相手は朝貢目的とする唐の国である。謁見の時をただひたすら待たねばならぬ苦痛もあった。菅原道真が遣唐使の停止を奏上したのも、かくなる理由もあるかと思い至るのである。
この困難極まりない旅路を生き抜いた広成の、壮大な旅物語も凄いが、史実からこのような壮大な物語を紡ぎ出した上野誠の筆力恐るべし。著者は学者にして作家。『魂の古代学ーーー問いつづける折口信夫』や『万葉びとの奈良』などの著書多数。オペラ『遣唐使』の脚本も好評とか。
(蘇州を出港後崑崙に漂着し蘇州に帰る着くまで)
(再度蘇州を出港し平城京に帰り着くまで)









