 昨日は第3水曜日。都の、美術関係館は65歳以上無料の日。午前中に恵比寿にある東京都写真美術館へ、午後は江戸東京博物館へと、ハシゴして来た。
昨日は第3水曜日。都の、美術関係館は65歳以上無料の日。午前中に恵比寿にある東京都写真美術館へ、午後は江戸東京博物館へと、ハシゴして来た。
先月、妹夫妻と都写真美術館で「101年目のロバート・キャバ」展を観た折、「黒部と槍」展が、5月6日まで開催されている事を知り、抑えがたいものがあり、11時から開催予定の「文高連総会」への遅刻を承知しつつ、富士前福寿会会長には‘都合で遅れます’と断って出かけたのだった。
シルバーパス利用を心掛けているので、千石→目黒間は三田線を利用し、目黒からJR山手線沿いを歩いた。この辺りは中学時代に自宅から遠出して遊びに来た場所。「日の丸」自動車教習場など懐かしい場所を見ながら行くと、徒歩で15分、10時丁度に到着した。
冠松五郎は、1918(大正7)年、立山から黒部本流に足を踏み入れたのを皮切りに、秘境黒部渓谷を舞台に数々のパイオニア・ワークを果たし、多くの写真と紀行を残し「黒部の主」の異名をとった。秘境十字峡を発見したのが1925(大正14)年。谷は頂上に上るがための登路だという常識を覆し、谷自体の魅力を掘り下げて表現したのだ。
一方、穂刈三寿雄は、1914(大正3)年、初めて槍ヶ岳登山。1926(大正15)年に槍ヶ岳の肩に登山小屋を建て、以来数十年間、夏になるとそこで生活し、山行にはカメラを携えて北アルプスを中心に撮影し、大正末期の積雪期の作品など先駆的な業績を数多く残したとある。
二人併せて137葉もの写真(モノクロ)が展示されていた。 私が登った、穂高・槍・剣などの山々も展示され、懐かしさから見入った写真も幾つかあったが、山や谷に入り、写真撮影をして来た二人の境遇への羨望の思いを抱きながら、写真を見続けた。取分け、黒部の本流や支流が私に迫ってきた。右の写真を見て頂きたい。その谷の深さよ。嶮しさよ。選ばれ、鍛錬を重ねたもののみが見ることが出来る風景がそこにはあった。(右写真:剣の大滝を囲む大岩壁)
私が登った、穂高・槍・剣などの山々も展示され、懐かしさから見入った写真も幾つかあったが、山や谷に入り、写真撮影をして来た二人の境遇への羨望の思いを抱きながら、写真を見続けた。取分け、黒部の本流や支流が私に迫ってきた。右の写真を見て頂きたい。その谷の深さよ。嶮しさよ。選ばれ、鍛錬を重ねたもののみが見ることが出来る風景がそこにはあった。(右写真:剣の大滝を囲む大岩壁)
私は黒部渓谷には憧れを抱きながら、雲の平を訪れた際、結局その源流の地を踏んだだけだった。比較的遡行しやすいと云われている上廊下をも、もはや歩むことはないだろう。
この数年歩いてきた、常念岳や、燕岳から槍へと続く山々は懐かしく観ることが出来た。現在と変わらぬ、大正期の山々がそこにはあった。積雪期の峰が一際美しい。珍しく図録を購入してきて眺めている。(以下図録より)

(柳又沢、魚止の滝)
(「平」の下流。中の谷付近からの眺め)

(好きな山 黒部五郎岳) (早春の槍ヶ岳。燕岳より)

(夏の槍ヶ岳 手前は銀座縦走路) (夏の槍ヶ岳と天狗池、氷河公園より)










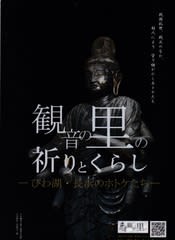 観ていると心が和んでくるホトケさまたちだった。「ようこそいらっしゃいました」と出迎えてくれているような10数体もの、一同に会した観音さまたち。それに導かれるように、ここ東京芸大美術館を訪れた実に多くのヒトたち。
観ていると心が和んでくるホトケさまたちだった。「ようこそいらっしゃいました」と出迎えてくれているような10数体もの、一同に会した観音さまたち。それに導かれるように、ここ東京芸大美術館を訪れた実に多くのヒトたち。

 昨日の4月10日(木)、「こまじいのうち」で『富士神社にまつわるお話』会が開催された。講師は本駒込2丁目在住の平山真理子さん。埼玉で教職。定年
昨日の4月10日(木)、「こまじいのうち」で『富士神社にまつわるお話』会が開催された。講師は本駒込2丁目在住の平山真理子さん。埼玉で教職。定年 某月某日。近隣からラジオ体操時のラジオの音がウルサイとの苦情が入る。そこで音量を小さくし、音が外へ漏れ難い場所にラジオカセを移した。ラジオを囲む輪も今までより小さくなった。それに伴い私も、今までの”外野席”から”内野席”要するにコアの位置に移動した。ラジオの音はよく聞こえ、参加者の様子もよく見える。
某月某日。近隣からラジオ体操時のラジオの音がウルサイとの苦情が入る。そこで音量を小さくし、音が外へ漏れ難い場所にラジオカセを移した。ラジオを囲む輪も今までより小さくなった。それに伴い私も、今までの”外野席”から”内野席”要するにコアの位置に移動した。ラジオの音はよく聞こえ、参加者の様子もよく見える。 4月7日(月)、文京シビック小ホールで石見神楽を観てきた。津和野町の東京事務所が文京区内に開設されたことを記念しての公演で、「400名無料ご招待」に応募し、当選してのご褒美だった。驚いたことに、入場の際に袋入りのお土産が配布された。中身は津和野町地酒の酒粕を用いたカトルカールというケーキと袋入りの豆茶。グーンと津和野町への評価が上がる。単純だが的確な誘致作戦だ。
4月7日(月)、文京シビック小ホールで石見神楽を観てきた。津和野町の東京事務所が文京区内に開設されたことを記念しての公演で、「400名無料ご招待」に応募し、当選してのご褒美だった。驚いたことに、入場の際に袋入りのお土産が配布された。中身は津和野町地酒の酒粕を用いたカトルカールというケーキと袋入りの豆茶。グーンと津和野町への評価が上がる。単純だが的確な誘致作戦だ。 開演に先立ち挨拶が3つ。津和野町観光協会会長・津和野町長・文京区長と続く。会長の話から岩見神樂の謂れと事務所の位置を知る。町長は、文京区からの義捐金への感謝を述べ、津和野に流れる
開演に先立ち挨拶が3つ。津和野町観光協会会長・津和野町長・文京区長と続く。会長の話から岩見神樂の謂れと事務所の位置を知る。町長は、文京区からの義捐金への感謝を述べ、津和野に流れる さて石見神楽。上演された演目は3つ。「鍾馗」「恵比寿」「大蛇」。石見神楽はどれも面白いし、観て実に楽しい。今回の演目は3本の内容が異るという工夫がなされていた。
さて石見神楽。上演された演目は3つ。「鍾馗」「恵比寿」「大蛇」。石見神楽はどれも面白いし、観て実に楽しい。今回の演目は3本の内容が異るという工夫がなされていた。 真打が「八岐の大蛇退治」。何故か八頭ではなく六頭の大蛇がもの凄い絡みを演じたり、すっくと立ち上がったり、蜷局(とぐろ)を巻いたりする。その演技は、熟練して始めて演じられると思える見事さ。須佐之男命が剣で大蛇の頭部を切り取る度ごとに拍車が沸き起こる。メデタシメデタシの後面を取ると、私には、鐘馗を演じた役者と顔が現れたように見えた。
真打が「八岐の大蛇退治」。何故か八頭ではなく六頭の大蛇がもの凄い絡みを演じたり、すっくと立ち上がったり、蜷局(とぐろ)を巻いたりする。その演技は、熟練して始めて演じられると思える見事さ。須佐之男命が剣で大蛇の頭部を切り取る度ごとに拍車が沸き起こる。メデタシメデタシの後面を取ると、私には、鐘馗を演じた役者と顔が現れたように見えた。

