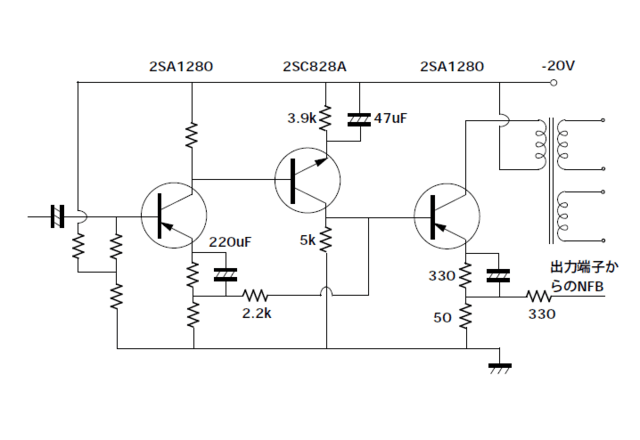今日は次に製作するアンプを検討しようと思い、実験用に使うアンプを整備しました。
元は、2016年頃に製作した、下記写真のVT-25ドライブ300Bシングルアンプでしたが、いまいちな音質で製作後しばらくしてアンプの実験ステーションと化しました。

実験ステーション後の様子。
中身は、いろいろな球で実験などを行っていたため、もうぐちゃぐちゃ。

これをまた別の球で実験するため、きれいに整備します。

さて次のアンプですが、どんな球を使うか、まだ決まっていません。今のところは、UYソケットを使用する出力管を候補にしようかなと思っています。UY型の出力管はいろいろ種類がありますが、相対的に見てあまり人気がないように思います。なにゆえにかというと、オークションの落札価格がそれほど高くならないからです。面白そうな球は結構あるのですが。
例えば、代表的なのは、UY-807で、これは6L6の改良版。ザ・真空管というようなスタイルが見栄え良く、4つ並べたプッシュプルは壮観です。ただ、この球もポピュラーな割にトッププレートだったりしてあまり人気がないようです。807と同じような球で、HY-69という球があります。これはHytronの球ですが、トリタンフィラメントを持った直熱5極管になります。
また、面白いところでは、46という球。これはダブルグリッド管でその名の通りグリッドが2つあります。この2つのグリッドの接続方法で、A級増幅用、B級増幅用と別の特性の球として作用します。あるいは、通常の4極管みたいにG2を一定電圧にした使い方をするのも面白いかもしれません。A級増幅用として動作させた場合、45のような特性とのことですが、本当でしょうか。その辺も確かめられれば。今から25年ぐらい前に一度製作しましたが、結構いい音だったように記憶しています。
あとは、306A、307Aという球があり、807ような外観ですが、こちらも直熱5極管になります。開発はかのWestern Electricのようです。プレートが大きく、いかにも送信管のような感じの球ですが、増幅管としても音は良さそうな印象です。
あと800番代では、814という球があります。この球は、かなり大型でクラスとしては211や845のような球ですが、ソケットはUYとなんだか尻すぼみな球です。3極管接続時の特性は、直線性がよく使ってみたい球の1つです。折角なので以前測定した3結特性図と211との比較写真をUpしておきます。
814(T)の特性曲線です。


フィラメントは、確か211などど同じなので、今回の実験ステーションでの使用は規模的には無理かなと思っています。
その他、47など、6F6の原型といわれている球もありますが、いまいちパッとしない感じのようです。さあどうしようか、悩み中ですがとりあえず何かやってみようかなと思っています。
ということで、また今度。ではまた~。