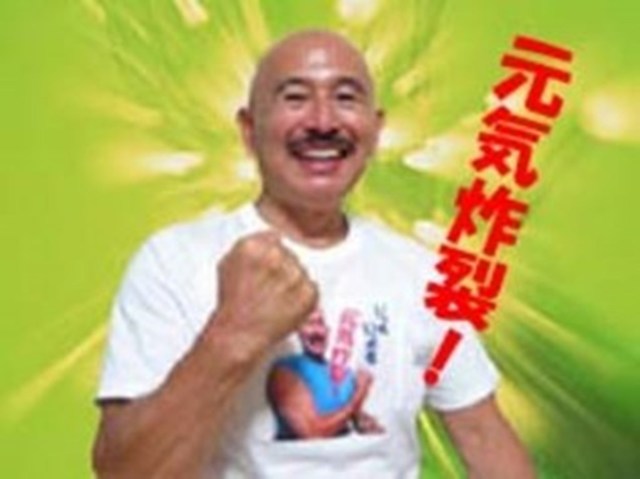先週から2023年度前期の朝ドラ「らんまん」が始まった。
ドラマは日本の植物学者牧野富太郎をモデルにしたものでその名前は
知っていたがその実績、功績などについては知らなかったので
検索してみて日本の植物分類学の基礎を築いた人だとわかり、さらに
人物像などについても興味を持って調べてみるとその人生は興味深く
そのエピソードなども含め、いずれゆっくりと紐解いてみたいと思った。
このドラマを観ながら感じたことや気づいたことがいくつかある。
今日は先ずその1回目を・・・
その①「言葉」
ここの言葉「(土佐弁?高知弁?)が私の出身地の富山弁に似ているのだ。
例えば語尾に「~が」「~がや」とか「~ちゃ」をつけるところなどは
同じ意味で使われているように聞こえる。
ドラマが始まるや否や聞きなれたような言葉が飛び交ったので、
もしや・・と思い、調べると、この物語の舞台は高知県高岡郡佐川町で
あるとわかった。
太平洋側の高知県と日本海側の富山県は500㎞位離れているのに
何故、言葉が似ているのだろう?・・・
高知は関西地方に近いのでアクセント、イントネーションなどは
関西地方の言葉に似ているところがあるのかもしれないと思えるが
富山とは距離もあるのに・・・
以前に富山弁の「だら」という言葉が高知でも使われていると
聞いたことがある。
その時も不思議な気がした。
この「だら」は愛知、静岡、長野、富山、石川、北海道などで、
幅広く、日常的に使われているようだが、富山や石川では「馬鹿、アホ」を
意味する言葉として使われ、関西でも「あほんだら」というように
使われているのは知られているのではないだろうか。
「馬鹿、アホ」などと表現するとけっこうきつい意味に受け取られる
かもしれないが実は、富山で使う方言「だら」には、あまりマイナスの
意味はなく、本当に頭が悪く、救いようがない、と馬鹿にしたり、
叱責するというニュアンスではなく、むしろ、その人の行動や
言動に対する、ちょっとした親しみを込めて、お笑いの突っ込みを
入れるような、愛情を込めた温かみのある意味で使われる場合が多い。
「だら」は、面と向かって厳しく叱りつけるのではなく、
「あほやなあ」と、ちょっと親しみを込めて声をかけるような、
そんな感じで使われる方言だと思う。
静岡や愛知では語尾につけているようで「~だら」は「~ずら」と同じように
「~でしょう?」「~ですよね?」という意味らしい。
北海道の「だら」にはいくつかの意味があるようだがちょっと
検索してみると「あれだら」は「あの人は」という意味のようで
他にもいくつかの使い方があるようだ。
その②「バイカオウレン」
過日ブログ友の記事でヒメイチゲなどを初めて知ったがこの
バイカオウレンの花も名前も初めて知った。
牧野富太郎博士が植物学者になった原点であることを示唆するような
場面にも心を揺さぶられるような感じだった。
あいみょん - 愛の花 / Ai no hana [ 歌詞 Lyrics & Romanized ]